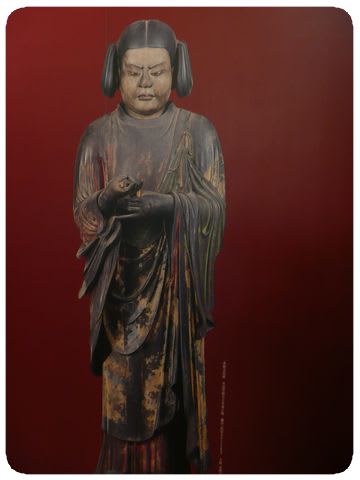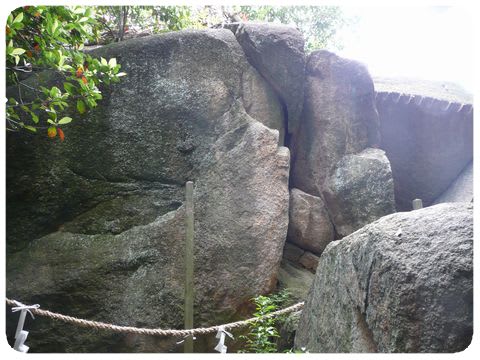プロ野球界に今年チョー快・怪現象が起こっていますネ。
阪神タイガースが優勝でもしようかと思うほど強いのです。
広島から来た3・4番がその原動力なのかも知れません。
お蔭でカープは散々です。
仕事も西宮の中心街に戻ってきているので、こんなタクシーもよく見かけるようになりました。

タイガースカラーのこの手のタクシーが少しあるのは知ってましたが、相手は走ってるので、見つけて、デジカメを探して、ケースから出しているとシャッターチャンスを逃すどころのタイミングではありません。
幸いこの日はちょっと先で停まりよった。
暑いけど、急いで行って撮りました。
尼崎商店街です。
以前はミツバチのイメージだったけど、今回は金魚ですね。
急に応援歌が流れ出したので、動画も撮ってみました。
アーケードを改修したのか、以前と比べると明るくなったような気がします。

タイガースのファンの皆さんはきっと思っていることでしょう。
「このまま行くわけが無い、きっとどっかで躓くでぇ。」
そういう声が聞こえてきそうです。
因みにこの写真を撮ったのが先週の木曜日、以来タイガースは勝っていませんね。

阪神タイガースが優勝でもしようかと思うほど強いのです。
広島から来た3・4番がその原動力なのかも知れません。
お蔭でカープは散々です。
仕事も西宮の中心街に戻ってきているので、こんなタクシーもよく見かけるようになりました。

タイガースカラーのこの手のタクシーが少しあるのは知ってましたが、相手は走ってるので、見つけて、デジカメを探して、ケースから出しているとシャッターチャンスを逃すどころのタイミングではありません。
幸いこの日はちょっと先で停まりよった。
暑いけど、急いで行って撮りました。
尼崎商店街です。
以前はミツバチのイメージだったけど、今回は金魚ですね。
急に応援歌が流れ出したので、動画も撮ってみました。
アーケードを改修したのか、以前と比べると明るくなったような気がします。

タイガースのファンの皆さんはきっと思っていることでしょう。
「このまま行くわけが無い、きっとどっかで躓くでぇ。」
そういう声が聞こえてきそうです。
因みにこの写真を撮ったのが先週の木曜日、以来タイガースは勝っていませんね。