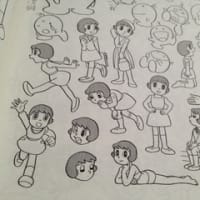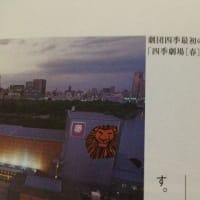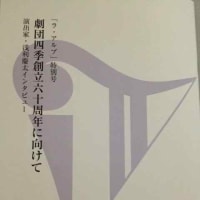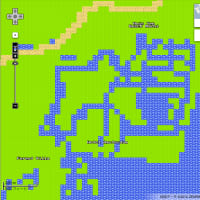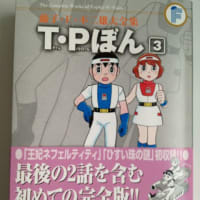前回の記事では、「最終回の予測」というより「最初はこんな最終回が構想されていたけど、結果的にそれが使われなかったために未完となった」という「最終回が描かれなかった理由」を推察してみたのですが、当初はこういう内容の記事にする予定ではありませんでした。本当は、アニメ化されなかった原作について語るつもりだったんです(^^);
そのつもりで完全版の第4巻と、他にアニメ化されなかった作品はなかったか確認するため、第1~3巻をパラパラしているときに、「クローン」というキーワードが目に飛び込んできて、それに先日読み返した「恋人製造法」が組み合わさり、「もしかして」と思ったのです。思ったら、忘れないうちに書いてしまいたかったので(笑)、予定を変更して、こちらを先に記事にすることにしました。
昨日の記事では、F先生の「心境の変化」について、あまり詳しく書けませんでしたので、少し補足しておきます。あくまで「エリクローンがマール星へ行く」というラストを考えておられた、という前提に立って書いていますので、そんなラストをF先生が考えていなかったとすれば、全くの空論になってしまいますけどね(^^);
さて、「チンプイ」連載後半の頃は、「クローン人間」が、だんだん現実味を帯びてきた時代だったと思います。技術的に到底不可能(できても下等生物のみ)という時代であれば、わりと自由に描けた面もあると思いますが、現実に人間のクローンが地球の技術レベルで誕生してしまう可能性が高まると、それに追随するいろんな倫理面の問題も出てきたでしょうし、F先生自身、人間が生命を人工的に生み出してしまうということへの、現実的危機意識も強くなっていったんじゃないでしょうか。「心境の変化」とは、そのあたりを指して書いた言葉です。
F先生が亡くなる直前、1996年7月には、クローン羊のドリーが誕生しています。「ねじ巻き都市冒険記」は、ちょうどその前後に執筆をスタートしていて、直接的にドリーの誕生が作品の構想に影響を与えたかどうかはわかりませんが、作中に「生命のねじ」や「種をまく者」など、ものすごく「生命」というものに対する示唆に富んだ要素が登場しているのです。
その「ねじ巻き」の連載終了後に、「チンプイ」を完結させたいと、F先生が本当に考えておられたとすれば、こうした問題も踏まえた内容にしたのではないかと。つまりエリクローンがマール星へ行って、「ちゃんちゃん!」というような終わり方は、その時点のF先生の作家意識が、おそらく許さなかった気がするのです。
SF短篇「恋人製造法」では、「クローンにも人権がある!」という議論はあっても、クローンを作ること自体に対する賛否には、全く触れられていないのです。他の短篇などでも、わりとクローンは気軽に描かれているフシがあります。「俺と俺と俺」や「有名人販売株式会社」などがそうです。「パーマン」のコピーロボットも、一応はロボットとはいえ、ミツ夫とは独立した人格や意識を持っている点では、ミツ夫とは別個の「生命」だと捉えることも出来ます。ドラえもんだって、しっかり生命を有しているといえるでしょう。
かつてのF作品では「人工的な生命の誕生」という要素を、わりと簡単に描いているところがありました。「死」という現象に対しても、たとえば「モジャ公」で描かれた「自殺フェスティバル」「エッフェル塔からの飛び降り自殺」などのシニカルなギャグもあります。しかしそれも、後の「未来の想い出」や、「雲の王国」で自らの身を挺してタンクに突っ込むドラえもんなどとは、明らかに捉え方が異なっている印象があります。それは、前者では「無機的」な死として描いているのに対して、後者は「有機的」に描いているという違いだと思います。前者は「星新一的」とでも言った方が、わかりやすいかもしれません。
そして、F先生が入院された後は、クローンという存在の描写そのものが激減します。退院された後、はっきりと「クローン」として描かれたのは、「のび太の日本誕生」の、ペガ、グリ、ドラコの3匹が最後だったと思います。F先生のご病気は、はっきりと「死」を意識することもあったと思われる大病だったと聞きます。そうした「死」ひいては「生命」に対する意識の変化と、クローンという存在に対する倫理的な問題が、F先生の作風に何らかの影響を与えたのではないかというのが、私がいう「チンプイには実は最終回として想定していたストーリーがあったけど、それが描かれず封印され、結果未完となった説」(長いね)の根拠なんです。
もちろん言うまでもなく、作者が亡くなった今となっては、実際のところは誰にもわかりません。もっと、わりとあっさりしたラストを考えておられたのかもしれません。「現状維持のまま終わる」ってパターンが一番濃厚な気もします。他にも、マール星が爆発して、ルルロフ殿下たちが「生まれ変わりそうち」によって他の星に生まれ変わって・・・って、それは「バウバウ大臣」(^^); または、マール星の法律が変わり結婚は15歳以上とかになって、ワンダユウが「また3年後にまいります!」とか言ってマール星に帰って行くとか・・・本家の最終回がない以上、いっくらでも考える余地がありますけどね(^^);
ただ、あくまで結果的な話ですが、「チンプイ」は未完になって、ある意味では良かったのかもしれません。「パーマン」や「オバケのQ太郎」は、きちんとした最終回が描かれているものの、「ドラえもん」「エスパー魔美」「T・Pぼん」など、後期の代表作には、きちんとした最終回が描かれていないものも多いのです。それは、いつでも連載を再開できるというような側面もありますが、ファンが自由にラストを想像できるというメリットもあるのです。
実際に数年前「ドラえもんの最終回」としてネット上を広まった作品がありましたよね。あの話は、F先生が書いたものではないことは明確ですし、F先生が描きそうなお話でもありません。だけど単純に「良いお話」だとは思います。それは、あの話を書いた人の「ドラえもん」という作品に対する想いが、強く表れているからではないでしょうか。
「チンプイ」の最終回が、仮に作者の手で描かれていたとしても、必ずしもファン全員が満足できるものになっていたかどうか、わかりません。もともと藤子ファンマガジン的な側面の強い「藤子不二雄ランド」でスタートした連載だったわけですから、F先生も結構気軽に描き始めたのかもしれません。少なくとも「大長編にしよう」というような構想ではなかったでしょう。だから当初はラストも、比較的あっさりした内容を想定していたのかもしれません。クローンであったり、星の爆発であったり、マール星の事情の変化であったり・・・
ところが、この作品は後にアニメ化され、一定の人気も得て、「アニメージュ」などでも取り上げられるに至ったのです。当然、ルルロフの正体や物語のラストへの、興味や憶測も広まりましたし、F先生自身、どんなラストを描いたところで、収拾がつかないような気持ちになっていたんじゃないでしょうか。
だから、「チンプイ」の真のラストは、ファンそれぞれの心の中にあるのです。・・・なんかキレイに決めてしまった(笑)
ということで次回は、本来は昨日書く予定だった「チンプイ」の未アニメ化原作についての記事を書きたいと思います。藤子ネタ、しばらく書いてなかったので、当面続けます(笑)
そのつもりで完全版の第4巻と、他にアニメ化されなかった作品はなかったか確認するため、第1~3巻をパラパラしているときに、「クローン」というキーワードが目に飛び込んできて、それに先日読み返した「恋人製造法」が組み合わさり、「もしかして」と思ったのです。思ったら、忘れないうちに書いてしまいたかったので(笑)、予定を変更して、こちらを先に記事にすることにしました。
昨日の記事では、F先生の「心境の変化」について、あまり詳しく書けませんでしたので、少し補足しておきます。あくまで「エリクローンがマール星へ行く」というラストを考えておられた、という前提に立って書いていますので、そんなラストをF先生が考えていなかったとすれば、全くの空論になってしまいますけどね(^^);
さて、「チンプイ」連載後半の頃は、「クローン人間」が、だんだん現実味を帯びてきた時代だったと思います。技術的に到底不可能(できても下等生物のみ)という時代であれば、わりと自由に描けた面もあると思いますが、現実に人間のクローンが地球の技術レベルで誕生してしまう可能性が高まると、それに追随するいろんな倫理面の問題も出てきたでしょうし、F先生自身、人間が生命を人工的に生み出してしまうということへの、現実的危機意識も強くなっていったんじゃないでしょうか。「心境の変化」とは、そのあたりを指して書いた言葉です。
F先生が亡くなる直前、1996年7月には、クローン羊のドリーが誕生しています。「ねじ巻き都市冒険記」は、ちょうどその前後に執筆をスタートしていて、直接的にドリーの誕生が作品の構想に影響を与えたかどうかはわかりませんが、作中に「生命のねじ」や「種をまく者」など、ものすごく「生命」というものに対する示唆に富んだ要素が登場しているのです。
その「ねじ巻き」の連載終了後に、「チンプイ」を完結させたいと、F先生が本当に考えておられたとすれば、こうした問題も踏まえた内容にしたのではないかと。つまりエリクローンがマール星へ行って、「ちゃんちゃん!」というような終わり方は、その時点のF先生の作家意識が、おそらく許さなかった気がするのです。
SF短篇「恋人製造法」では、「クローンにも人権がある!」という議論はあっても、クローンを作ること自体に対する賛否には、全く触れられていないのです。他の短篇などでも、わりとクローンは気軽に描かれているフシがあります。「俺と俺と俺」や「有名人販売株式会社」などがそうです。「パーマン」のコピーロボットも、一応はロボットとはいえ、ミツ夫とは独立した人格や意識を持っている点では、ミツ夫とは別個の「生命」だと捉えることも出来ます。ドラえもんだって、しっかり生命を有しているといえるでしょう。
かつてのF作品では「人工的な生命の誕生」という要素を、わりと簡単に描いているところがありました。「死」という現象に対しても、たとえば「モジャ公」で描かれた「自殺フェスティバル」「エッフェル塔からの飛び降り自殺」などのシニカルなギャグもあります。しかしそれも、後の「未来の想い出」や、「雲の王国」で自らの身を挺してタンクに突っ込むドラえもんなどとは、明らかに捉え方が異なっている印象があります。それは、前者では「無機的」な死として描いているのに対して、後者は「有機的」に描いているという違いだと思います。前者は「星新一的」とでも言った方が、わかりやすいかもしれません。
そして、F先生が入院された後は、クローンという存在の描写そのものが激減します。退院された後、はっきりと「クローン」として描かれたのは、「のび太の日本誕生」の、ペガ、グリ、ドラコの3匹が最後だったと思います。F先生のご病気は、はっきりと「死」を意識することもあったと思われる大病だったと聞きます。そうした「死」ひいては「生命」に対する意識の変化と、クローンという存在に対する倫理的な問題が、F先生の作風に何らかの影響を与えたのではないかというのが、私がいう「チンプイには実は最終回として想定していたストーリーがあったけど、それが描かれず封印され、結果未完となった説」(長いね)の根拠なんです。
もちろん言うまでもなく、作者が亡くなった今となっては、実際のところは誰にもわかりません。もっと、わりとあっさりしたラストを考えておられたのかもしれません。「現状維持のまま終わる」ってパターンが一番濃厚な気もします。他にも、マール星が爆発して、ルルロフ殿下たちが「生まれ変わりそうち」によって他の星に生まれ変わって・・・って、それは「バウバウ大臣」(^^); または、マール星の法律が変わり結婚は15歳以上とかになって、ワンダユウが「また3年後にまいります!」とか言ってマール星に帰って行くとか・・・本家の最終回がない以上、いっくらでも考える余地がありますけどね(^^);
ただ、あくまで結果的な話ですが、「チンプイ」は未完になって、ある意味では良かったのかもしれません。「パーマン」や「オバケのQ太郎」は、きちんとした最終回が描かれているものの、「ドラえもん」「エスパー魔美」「T・Pぼん」など、後期の代表作には、きちんとした最終回が描かれていないものも多いのです。それは、いつでも連載を再開できるというような側面もありますが、ファンが自由にラストを想像できるというメリットもあるのです。
実際に数年前「ドラえもんの最終回」としてネット上を広まった作品がありましたよね。あの話は、F先生が書いたものではないことは明確ですし、F先生が描きそうなお話でもありません。だけど単純に「良いお話」だとは思います。それは、あの話を書いた人の「ドラえもん」という作品に対する想いが、強く表れているからではないでしょうか。
「チンプイ」の最終回が、仮に作者の手で描かれていたとしても、必ずしもファン全員が満足できるものになっていたかどうか、わかりません。もともと藤子ファンマガジン的な側面の強い「藤子不二雄ランド」でスタートした連載だったわけですから、F先生も結構気軽に描き始めたのかもしれません。少なくとも「大長編にしよう」というような構想ではなかったでしょう。だから当初はラストも、比較的あっさりした内容を想定していたのかもしれません。クローンであったり、星の爆発であったり、マール星の事情の変化であったり・・・
ところが、この作品は後にアニメ化され、一定の人気も得て、「アニメージュ」などでも取り上げられるに至ったのです。当然、ルルロフの正体や物語のラストへの、興味や憶測も広まりましたし、F先生自身、どんなラストを描いたところで、収拾がつかないような気持ちになっていたんじゃないでしょうか。
だから、「チンプイ」の真のラストは、ファンそれぞれの心の中にあるのです。・・・なんかキレイに決めてしまった(笑)
ということで次回は、本来は昨日書く予定だった「チンプイ」の未アニメ化原作についての記事を書きたいと思います。藤子ネタ、しばらく書いてなかったので、当面続けます(笑)