先日の記事で取り上げた第1巻に引き続き、第2巻も読んでみました。
うん、やっぱりこのシリーズって
結構面白いです。少なくとも私の好みには
ピッタリ合った作品です。
ここで
カミングアウト(大げさな)しますが、私は結構「
ファンタジー」や「
SF」という分野は昔から
苦手なんですよ(^^);
ジブリの「
天空の城ラピュタ」や「
千と千尋の神隠し」、あと
藤子SF短篇が好きだとか書きながら、何を言ってるんだと思われそうですが、いわゆる「
ハリーポッター」や「
指輪物語」、それから「
スターウォーズ」など、その系統のお話や映画が苦手なんです。なんだか状況把握がうまく出来ず、どうしても読み続ける&見続けることが出来ないのです。ジブリ映画でも「
ハウルの動く城」は私には全く受け付けられませんでした。
ところが・・・「
不思議なお話」は大好きなんです。ここまで書くと、このブログをご愛読頂いている皆様(笑)には、お分かり頂けるでしょう。・・・そう、私の好きなのは「ファンタジー」でも「サイエンス・フィクション」でもなく、「
少し不思議な物語」なんです。この要素は逆に「ファンタジー」にも「SF」にも備わっているものです。
「
少し=S」「
不思議=F」で「
SF」なんだと提唱したのは、
藤子・F・不二雄先生ですが、小学生の頃、「ドラえもん」のタイムマシンや宇宙などのお話は「SF」と呼ばれていて、これらは大好きなのに、「スターウォーズ」や「ガンダム」のような、同じ「SF」と呼ばれてる作品が好きになれないのは、どうしてなんだろう?という素朴な疑問を解き明かしてくれたのが、この「少し不思議=SF」という概念でした。(言うまでもなく藤子先生は、本来のSF=サイエンスフィクションへの造詣も深い人ですが、これらの要素をかみ砕き、SFというものに何か抵抗のある私のような読者にも「少し不思議」として、わかりやすく与えてくれたのです)
要するに「
日常」という「
地」に足がついていないと、私にはダメなんですね。近未来SFともいえる「
ふたつのスピカ」だって、普通の高校生と何も変わらない日常が繰り広げられているから、入りやすかったんだと思います。他に「
ぼくの地球を守って」という名作も、最初は少し戸惑ったものの、読み進めるうち次第に作品世界が理解でき、そうなると面白くなり始めたりもしました。
~~~~
余談のコーナー
もちろん、ファンタジーやSFが全く駄目というわけではなく、読み進めて作品世界に「入り込む」ことさえ成功すれば、あとはすんなり好きになれることもあります。ゲームになりますけど「
ドラゴンクエスト」シリーズなんて、魔法は使うし魔物も出てくるし、いわば
バリバリのファンタジーなのに、そのストーリーを含めて大好きだったりします。でも「
ファイナルファンタジー」は、いまだに入ることが出来ておりません。つまり、その入り口の「
門」が非常に狭いというわけです。実をいうと「千と千尋」だって、作品世界を理解するには少し時間がかかりました。ところが何度か観ているうち、千尋やカオナシの気持ちなどが、あるとき
ストンと心に落ちたのです。それからは大好きな作品になりました。でも「ハウル」はいまだに、ハウルもソフィーも荒れ地の魔女も理解できておりません(^^);
~~~~~~~~
えー、例によって前置きが長くなりましたが(笑)、この「
天下無敵のお嬢さま!」シリーズは、はっきり言ってしまえば
ファンタジー的な要素を持った作品です。第2巻は突然
SF的な要素まで出てきて、一瞬「
えっ?」と思いましたが、意外に引っかかることもなく、すんなり読破することが出来ました。
おそらく前述したような意味で、私が入り込みやすかった要素がたくさんあったのでしょう。まず舞台が現代の日本という、しっかり
地面に足のついた場所で、物語が展開されること。それから
キャラクターの作り方がとても上手いのです。読んでいるうち、菜奈も芽衣もメリーさんも、登場人物の心情に共感し、すぐに好きになれたのです。
大人になってしまうと、
子どもの世界なんて
一種のファンタジーです。自分もかつて子どもだったくせに、その頃のことは忘れてしまっています。もちろん世代間で流行も学校で教えられる内容も全く違いますから、今の子どもが好きなことを100%理解できないのは当然です。でも、時間が流れても変わらない、
普遍的な子どもの世界というのは、いつの時代にも必ず存在しているはずなんです。
「天下無敵のお嬢さま!」で描かれているのは、
現代の子どもです。携帯電話だって持っているし、主人公の菜奈ちゃんは美少年が好きだし(笑)。だけど、どこか、私たちが子どもの頃に見た
原風景的な懐かしさも感じるのです。これは言ってみれば「
のび太たちの日常」に通じる面があるのかもしれません。
それに加えて、子どもたち、大人たち、それぞれの悩みもきちんと描かれています。
芽衣のお父さんは行方不明だし、お母さんは事故で意識不明のまま長く入院中。それで叔母さん(メリーさん)と暮らしているという、結構
シビアな状況です。実際に登場の頃は、少し影を帯びたところがある女の子でした(それで菜奈が
男の子と間違えて恋をしたわけですけど)。ところが菜奈たちと出会うことで、実は笑い上戸であったりといった本来の性格にも、次第に光が差してくるようになります。
主人公の菜奈も、お金持ちのお嬢さまでありながら、親戚がみんな通っている名門私立ではなく、何故か公立小学校に行っていたりします。弟の玲児は、そんな姉を「
えせお嬢さま」なんて呼んでいて、第1巻の彼女はそんな弟を結構
フワフワとかわしていますけど、第2巻では「
自分なんていなくなっても誰も困らないんじゃないか」とまで思い詰めてしまうなど、普段はモノローグ(お話の語り手が彼女自身)でも、結構
ストイックな子どもなのに、今回は色々な事件を経て、弟に吸い取られてしまった母の愛に飢えるような心情も描かれています。このあたりは、女性作者ならではの「
母親的な温かさ」を感じました。
メリーさんだって、かつては○○○○○ーだったという過去があります(未読の方のために伏せます)。まだ物語では明かされていませんが、何か理由があって、それを引退したのかもしれません。芽衣の母親のお姉さんでもありますが、考えてみると少し不思議な存在でもあります。この後の巻で、彼女自身のことをもっと詳しく描かれていくのか、あくまで子どもたちを見守る立場として一歩引いた存在のままなのかはわかりません。
うーん・・・今回はレビューだか何だかわからない内容になってしまいましたが(笑)、このシリーズは今後も楽しみに読んでいきたいと思います。
私は、児童文学からは長い間離れていましたが、これは別に「子どもの読む本だから」などとバカにしていたわけではなく、単に読む機会がなかっただけです。今回も、たまたま好きな漫画家のこうの史代先生が挿絵を描いていたというキッカケがあって、この作品を知ることが出来たのですが、そうでなかったら、一生作品を知らないままだったと思います。
私は児童漫画の代表格である「ドラえもん」を含め、子ども向けに書かれた作品を読むことに何の抵抗もありませんし、読みもせずに「子ども向けじゃん」とバカにする人には、前から腹を立てたりもしていました(笑)。
もちろん、まだ物語を作る技術も稚拙な「
子どもの書いた話」を読むのはキツいですよ(笑)。だけど、児童文学は「
子ども向けに」書かれているだけであって、書いたのは当然
大人なんです。これはもちろん漫画だって同じです。子ども向けの作品は、大人向けに書くよりも、書き手としては遙かに難しいのです。決して卑下されるいわれはないと考えております。
大人向けに書かれた「
小難しい本」(うちの本棚にある本を母はよくこう呼ぶんです

)だけを読んでいると、なかなか気付くことの出来ないようなことを、ある日子ども向けに書かれた作品を読んで「
ハッ」となることって、確かにあるんですよ。今回取り上げた作品の第2巻で主人公が感じる「
自分なんていなくなっても・・・」という何気ない悩みは、結局これを煎じ詰めていくと、昨今の
子どもの自殺問題にも通じることですからね。菜奈のように、周りに支え合える友だち、親、兄弟、先生などがいれば良いんですが、実際には、そういう存在がいなくて悩む子どもも多いんだろうなと・・・そういうことも考えさせられました。
名作ドラマ「
彼女たちの時代」でも、30歳を数年後に控えた主人公の
深美(深津絵里さんが演じてます)が、冒頭で同様のことをモノローグで呟きます。これは決して、大人だけが感じる寂寞ではなくなってるのが現代社会なんです。自殺しようとする人の根本にあるのは、結局は
自己存在の否定なんです。「
自分がいなくなっても誰も困らない=自分という存在を消しても構わない」という考えに至らせてしまう(特に子どもに)のが大きな問題なんです。「
いじめをなくす」の一言だけで片が付くとも思えません。自殺する人に、誰かが自分を必要としている=
かけがえのない自分の肯定意識が欠落してしまっていること、そうさせてしまう社会の構造に問題があるのではないかと思います。
ちょっと(
かなり)話がズレてしまいましたが、つまり児童文学を読んで、そんなことまで考えを及ばせてしまうこともあるということです(^^);
これからは、何か子ども向けに書かれたお話を、他にも探して読んでみようかなと思いました。自分でもいずれは書いてみたいですしね・・・そう・・・かつては
児童漫画家を志していたこともあったのです。絵が下手で断念しましたけど(笑)。
 |
作: 濱野京子/画: こうの史代
天下無敵のお嬢さま!〈2〉
けやき御殿のふしぎな客人
童心社
詳細 |
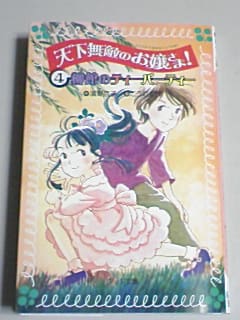
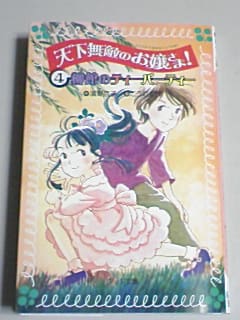










 )だけを読んでいると、なかなか気付くことの出来ないようなことを、ある日子ども向けに書かれた作品を読んで「ハッ」となることって、確かにあるんですよ。今回取り上げた作品の第2巻で主人公が感じる「自分なんていなくなっても・・・」という何気ない悩みは、結局これを煎じ詰めていくと、昨今の子どもの自殺問題にも通じることですからね。菜奈のように、周りに支え合える友だち、親、兄弟、先生などがいれば良いんですが、実際には、そういう存在がいなくて悩む子どもも多いんだろうなと・・・そういうことも考えさせられました。
)だけを読んでいると、なかなか気付くことの出来ないようなことを、ある日子ども向けに書かれた作品を読んで「ハッ」となることって、確かにあるんですよ。今回取り上げた作品の第2巻で主人公が感じる「自分なんていなくなっても・・・」という何気ない悩みは、結局これを煎じ詰めていくと、昨今の子どもの自殺問題にも通じることですからね。菜奈のように、周りに支え合える友だち、親、兄弟、先生などがいれば良いんですが、実際には、そういう存在がいなくて悩む子どもも多いんだろうなと・・・そういうことも考えさせられました。



