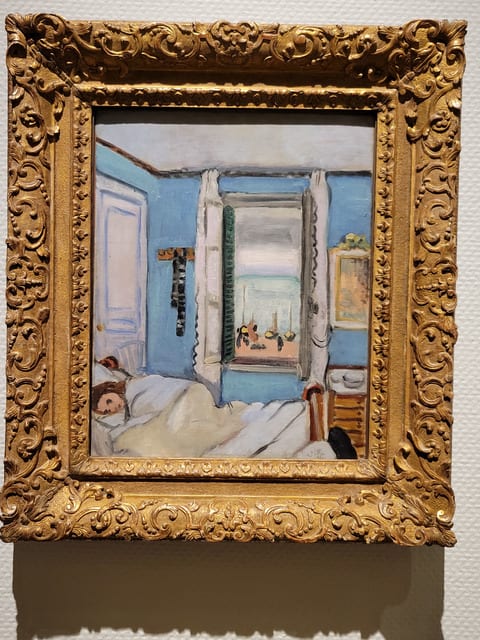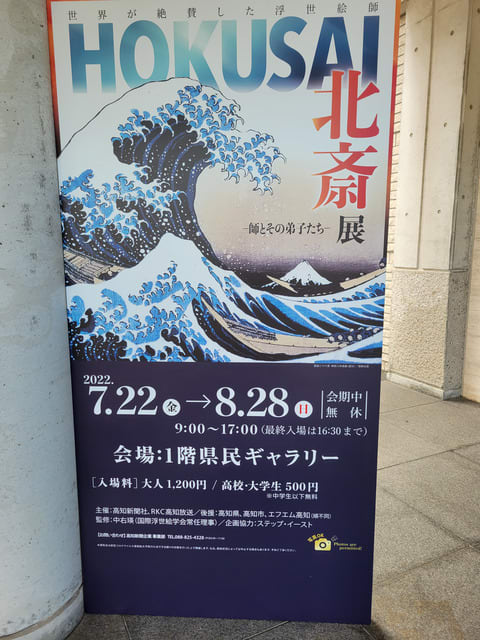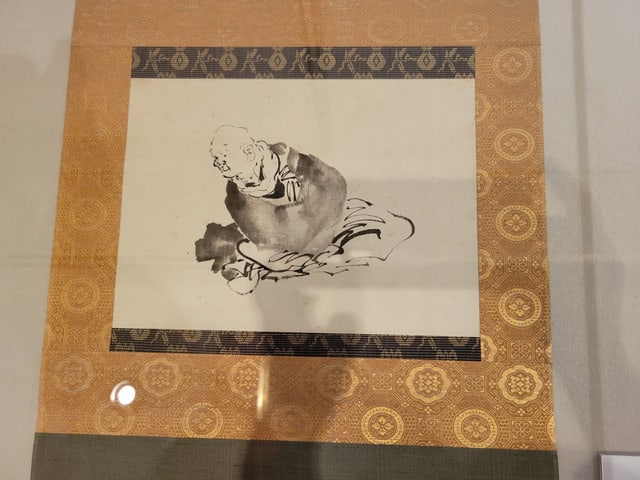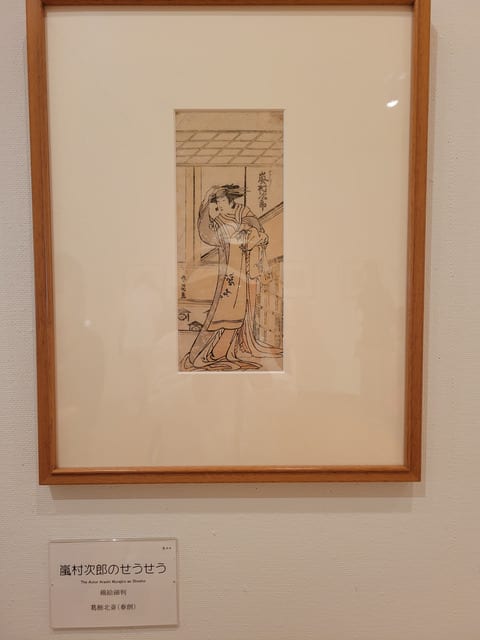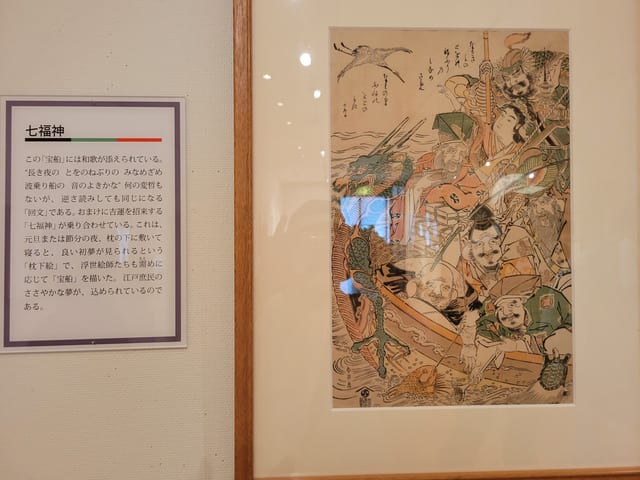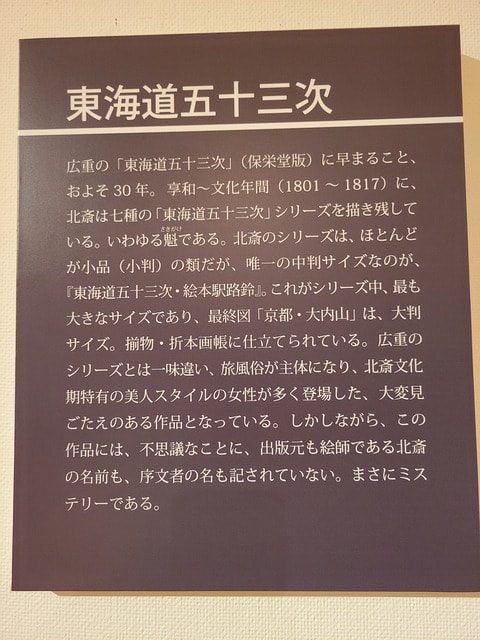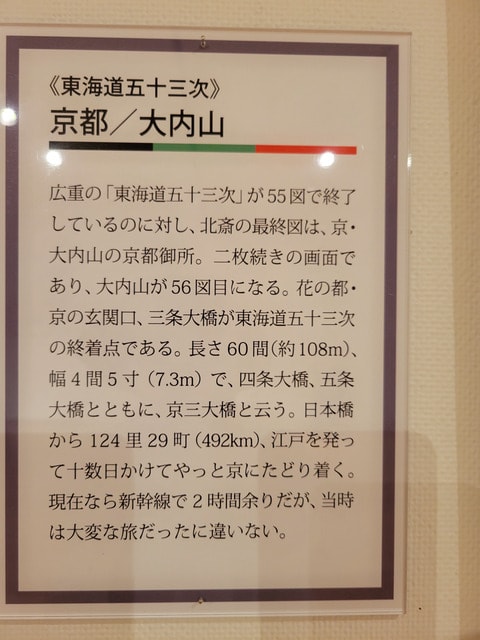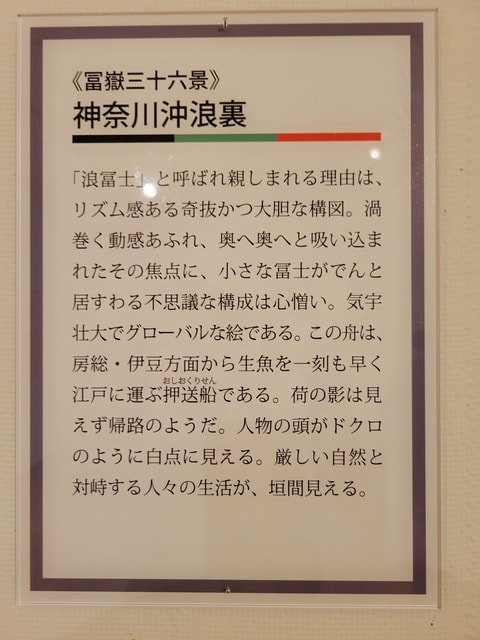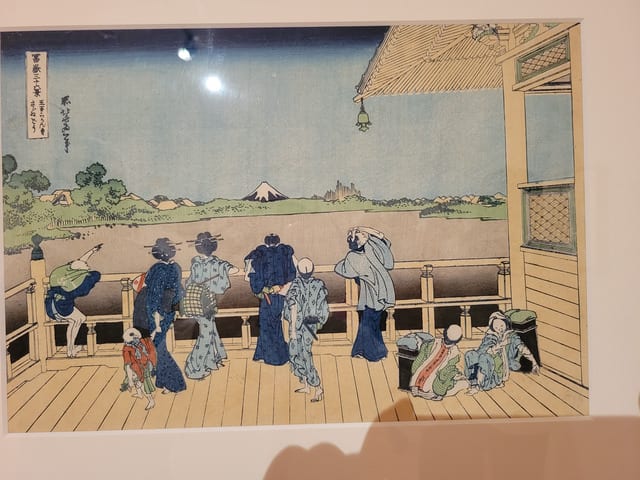曇り時々晴れの高知を
7時30分に出発したのはいいのですが
お仕事を辞めている年金暮らしでは
朝の通勤ラッシュとは関係ない生活をしているので
すっかり念頭から抜け落ちてしまっていて
不覚をとってしまいました。
高知道に乗ったのが8時過ぎで
これでは高松10時14分発の直島へのフェリーに
ギリギリだ~焦る、焦る。
通常の豊浜サービスエリアでの休憩は
おトイレ休憩のみとなって。
何とか直島へのフェリーに乗ることが出来ました。

高松港を離れる四国汽船のフェリー

そう!今日やっと香川県行きが叶った
大学生の孫娘と3人で、秋の開催の瀬戸内国際芸術祭2022に
出かけました。
今までに2回、行く予定を立てていましたが
その2回とも台風に行く手を阻まれて
実現しませんでした。

瀬戸内海は秋の雲はありますが、良いお天気です。
約50分で、直島の宮浦港に着きました。
早速、港で出迎えしてくれたのは

草間彌生さん作の「赤かぼちゃ」

内部はこうなっています。

対岸の方には

藤本 壮介氏作 直島パヴィリオン
「浮島現象」をかたどった浮島感のあるパヴィリオン。

三角形のステンレス製メッシュ約250枚で構成され
内側に入ることができ、夜はナイトアップされます。

宮浦港を出て
安藤 忠雄氏設計の地中美術館を目指しました。
が、入場しようとしたら予約制でアウト。
東京の国立西洋美術館でさえフリーに
なっているのに・・・・残念です。
地中美術館の駐車場に車を置き徒歩で
李 ウファン美術館に向かいます。
そこは海と山に囲まれた谷間に、ひっそりと
佇んでいました。

この美術館も安藤氏の設計によるもので

無限門
遥か遠くに海を臨むところにあります。

コンクリートの打ちっ放しで造られた美術館。
中の作品は絵画と彫刻で、少数精鋭なのか少な目。
写真撮影は禁止でしたので、どのような作品か
見せられずに残念です。
リ・ウファン氏は大韓民国生まれ、
日本大学文学部哲学科を卒業、
1960年代後半から1970年代にかけて現れた
「もの派」と呼ばれる現代美術の動向に
主導的な役割を果たす。

柱の広場

無限門 ステンレスと自然石で造られています。
リ・ウファン美術館を出て
もう少し歩いた所にあるベネッセハウスミュージアムにも
行きたかったのですが、時間の都合で諦めて
戻る途中にあった

三島 喜美代氏作 「もうひとつの再生2005-N]
この巨大なゴミ箱にビックリ!
直島町役場の近くにある
ANDO MUSEUMに向かいます。
そこは見過ごしてしまう程(実際に通り過ぎてしまった)
小さな築100年の木造民家の中にありました。

でも中は、安藤さんらしい
コンクリートの打ちっ放し建築で、中には
安藤 忠雄氏が今まで設計した建物模型、スケッチ
写真等を展示しています。

設計した教会の模型。
ANDO MUSEUMを出て駐車場へと
向かっていると

普通の民家の塀もアートしていました。
題 貝殻に乗るネコたち (勝手に命名)

近くでモデルネコ?を発見!

宮浦港に戻ってきました。
近くで食事ができる所を探します。
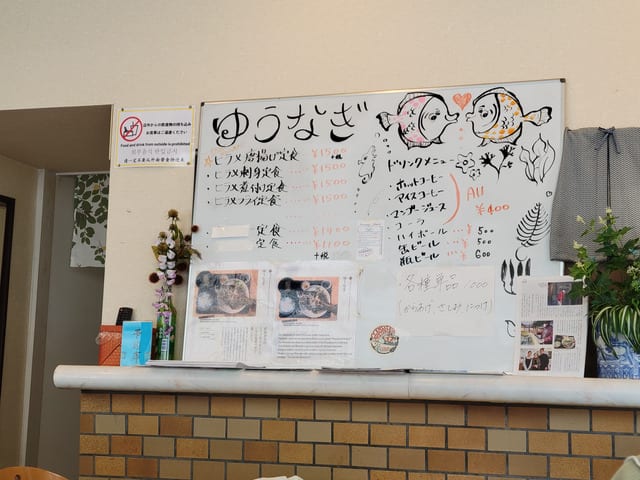
小さな食堂 ゆうなぎ
メニューはヒラメの定食しかないお店。

私はこのヒラメの煮付け定食 1,500円+税

二人はヒラメの唐揚げ定食。お値段は一緒。
腹ごしらえも済んで、この後はお土産を少し買って
14時20分発のフェリーで高松港を目指します。

遥か向こうに微かに見える瀬戸大橋。

高松の街が大都市に見えますよ~
この後、三豊市の
瀬戸内の天空の鏡 父母ヶ浜 に行きました。
それはまた明日ね
今日も来てくださってありがとうございます。