坂上多津夫氏(元津田塾大学職員)に話を聞く会のメモ
(文責、高槻成紀)
2023年7月10日、上水本町地域センター
参加者:大槻史彦、加藤嘉六、黒木由里子、坂上多津夫、高槻成紀、平林俊夫、松山 景二、水口和恵、リー智子
+++ 武蔵野線 +++
<坂上>
私は昭和22(1947)年生まれで、父が津田塾大学の職員であり、当時は職員も教員も学内の宿舎に住んでいたので、津田塾大で育った。コジュケイがいた。長じて自分も昭和50(1975)年から25年ほど津田塾大で勤務した。大雨の時や入試の時の降雪時は排水溝を掃除したり、通学路の雪かきをするのが大変だった。
武蔵野線開通前後の話は父から聞いた。武蔵野線は1964年に全体構想ができ、当初は貨物専用路線だった。1973年に府中本町まで開通し、下河原線(東芝の御用路線)は廃止された。
津田塾大学は1960年代末の買収交渉では教育環境の悪化を理由に買収に応じなかった。東側には日立が住宅を作った。南側の旭ケ丘住宅は菜園付き住宅のふれ込みで都内からインテリ層が引っ越してきた。また当時の経団連会長の石坂泰三氏をはじめ財界の有力者が理事であったことによる影響もあったのか地下化となった*。
ただし、当時は線路が短かったため、電車のゴトゴト音が大きく、視聴覚教室棟の建設に際しては騒音防止対策に苦慮した。
津田塾大は新府中街道には反対しなかった。
*地下化された範囲は新秋津の手前から国分寺の恋ヶ窪のあたりまでであり、地下化の要望は他にもあった可能性がある(リー、水口)。
<高槻>
高度成長期には新しい鉄道路線がつくことは歓迎された訳で、その中で地下化にできたのは特別なことだと思う。それに津田塾大学の要求が反映されて地下化が実現したことを知るのは重要なことだ。
<黒木>
新宿御苑に分断道路の計画があったとき、新宿高校の同窓会にやはり実力者がいて阻止した例もある。
<坂上>
正論を言うだけでは動かないから、現実的方法論として働きかければ動くことはある。状況によっては、トップの裁量で方針転換することもある。まずは水口さんが卒業生の市議として学長と面会することから始めたら良い。
+++ 小平と玉川上水 +++
小平の歴史と文化は玉川上水によって涵養されたと言ってよい。玉川上水は17世紀に標高差92mの平坦地に作った奇跡的な工事。<松山:小平の分水は総延長53kmある。>大学が7つ(津田塾大学、一橋大学、武蔵野美術大学、朝鮮大学校、白梅短大、嘉悦大学他)もあるのは極めて特異。
玉川上水は津田塾大学にとっても重要。礼拝で話した時に、聖書の詩篇にある「流れの脇に植えられた木は強い」*という言葉を紹介した。
*詩篇1篇3節「その人は流れのほとりに植えられた木。時が巡り来れば実を結び、葉もしおれることがない。」新共同訳、
「かかる人は水流のほとりにうゑし樹の期にいたりて實をむすび、葉もまた凋まざるごとく」旧約、
「And he shall be like a tree planted by the rivers of water, that bringeth forth his fruit in his season; his leaf also shall not wither; and whatsoever he doeth shall prosper. Psalm 1:3 (King James Version)」
+++ 津田塾大学 +++
<坂上>
津田塾大学は小平キャンパスのためにアメリカからも含め10万ドル(<高槻>ウィキペディアによれば50万ドル)を集めた。新校舎はセントラルヒーティング、水洗トイレで、文部省から贅沢すぎると言われたほどだった。津田塾大には在野精神とキリスト教精神があった。戦争中も奉安殿を作ることを拒絶したし、陸軍が女子英語塾の看板の上に部隊の看板をかけたことに対して、学生がそれを剥がして玉川上水に投げ捨てた。大学の部品工場(体育館)で兵器の部品作りをしていた時、ラインが止まって部品が届くのを待つ間、将校が学生に「気をつけ」で待つことを強要した時、藤田タキ(第三代学長、元衆議院議員)が「いいから座って休みなさい」と言った。津田梅子は鹿鳴館で会った伊藤博文の人品について批判する日記を書いている。
<高槻>
女子英学塾(津田塾大の前身)は1931年に小平に移ったが、英学塾の歴史を書いた本に空中写真があり、周囲には1軒の家もなかった。秩父おろしで砂嵐になるため、シラカシなどを植林したという記述があった。
<坂上>
シラカシ、スギ、ケヤキなどを明治神宮と同じように100年後、200年後の変化を考えた計画で植林した。
<高槻>
そうであれば、東大林学教授の本多静六であり、大隈重信と対峙した強者だった。
<高槻>
津田塾大にとって玉川上水が重要とのことだが、具体的には学生の通学の問題があると思う。あそこに大道路がつけば問題であろう。
<リー、水口>
反対していると聞いたのですが・・・。
<坂上>
その通りだが、大学は明確な意思表示をしていない*。
<高槻>
学生がどの程度意識しているか不明だが、玉川上水を歩いて通学することが心に与える影響はあるのではないか。
<坂上>
今の玉川上水緑道を通って通うことは大変贅沢なことだと思う。
*<水口>東京都が小平328号線の環境影響評価をしたのは2010年-2012年。私は、当時津田塾大の職員であった利根川氏から、「環境影響評価書案」に対する意見として、津田塾大学が地下化の提案をしたと聞いた。
+++ 地下化 +++
<平林>
328号線計画に反対するとなると小池知事まで届くことになる。そのことを熟慮する必要がある。
<高槻>
シンポジウムでかなりの人が計画自体に反対だとした。しかし我々はそのような理想主義的な主張をして敗北するよりも、現実路線としての地下化を見直すよう説得したい。
<平林>
地下化の場合、住民の土地問題、工事による地下水の動きなど難問もある。
<高槻>
現状で我々は知らないことが多く、これから専門的立場に学びたい。ただはっきりしているのは100年後に「あの時になぜ阻止しなかったのだ」と言われたくないということで、それを思えば課題は多いものの、平面道路に見直しを迫るしかない。
<平林>
地下道の深さは玉川上水の底から5mであり、斜面勾配は5%だから玉川上水から地下道の入り口・出口は水平距離は500m前後になるはず。
<坂上>
50年前に武蔵野線が地下化して現在まで問題が起きていない。しかもその後の土木工学技術の進展は目覚ましい。買収もほぼ済んでいる。地下化した後の土地は緑地公園にすればよい。何も問題はない。
+++ 玉川上水の自然を守ること +++
<坂上>
子供の頃、津田構内の住宅に住んでいたが、夜になると蛍が飛んできたものだ。その光景を思い出すと涙が出そうになる。玉川上水の自然を守り、100年後に良い選択をしたと言われるよう努めるべきだ。
<高槻>
これまで328号線の話し合いをすると、困難であることが認識されて暗い気持ちになることが多かったが、今日は明るい希望が感じられるお話を聞けて大変ありがたかった。















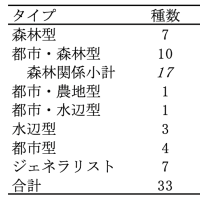



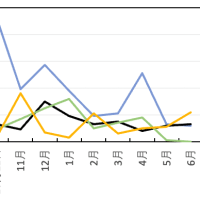






※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます