問い:鎧(よろい)の裏側にある筒のようなものは何? 答えは、文中に。

鎧(よろい)というのは、正面から見るだけで、あまり裏側を見たことはないのではないだろうか。
先日、清洲城に行っていて、ふと鎧の裏を見ると、筒のようなものを目にした。写真では少し分かりづらいかも知れないが、中央の黒い棒のように見えるものである。
実は、これは「受筒」という鎧の一部である。
受筒は、何のために存在するのだろうか。
矢を入れるため? 手が届かない。
刀を入れるため? 筒が細すぎて入らない。
受筒は、指物(旗)を入れるものなのである。
旗は敵味方を区別するものであるから、大事な部分である。その旗を入れる受筒も地味ながら、大事な部分であった。
ところで、この清洲城では、有志が集まって、アルミによる鎧を手作りしていると言う。アルミ缶を溶かして、アルミ板を作り、それをコツコツと木型に合わせ、叩いていく。
完成品は、金箔貼、漆塗りのなかなか豪華なもので、アルミには見えない。
ボランティアの参加者募集中ということなので、興味ある方はいかがであろうか。

このような甲冑を作るのに350MLのアルミ缶が400缶必要とのことである。
清洲城HP
清洲甲冑工房の記事
↓よろしかったら、クリックお願いします。


鎧(よろい)というのは、正面から見るだけで、あまり裏側を見たことはないのではないだろうか。
先日、清洲城に行っていて、ふと鎧の裏を見ると、筒のようなものを目にした。写真では少し分かりづらいかも知れないが、中央の黒い棒のように見えるものである。
実は、これは「受筒」という鎧の一部である。
受筒は、何のために存在するのだろうか。
矢を入れるため? 手が届かない。
刀を入れるため? 筒が細すぎて入らない。
受筒は、指物(旗)を入れるものなのである。
旗は敵味方を区別するものであるから、大事な部分である。その旗を入れる受筒も地味ながら、大事な部分であった。
ところで、この清洲城では、有志が集まって、アルミによる鎧を手作りしていると言う。アルミ缶を溶かして、アルミ板を作り、それをコツコツと木型に合わせ、叩いていく。
完成品は、金箔貼、漆塗りのなかなか豪華なもので、アルミには見えない。
ボランティアの参加者募集中ということなので、興味ある方はいかがであろうか。

このような甲冑を作るのに350MLのアルミ缶が400缶必要とのことである。
清洲城HP
清洲甲冑工房の記事
↓よろしかったら、クリックお願いします。










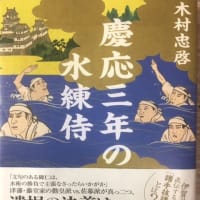
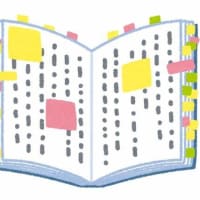
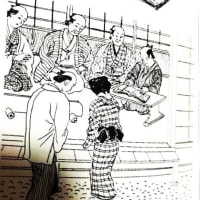
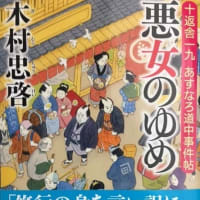
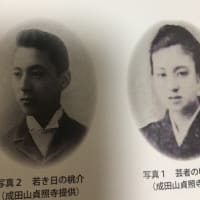

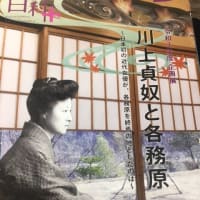
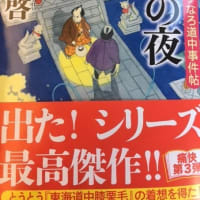
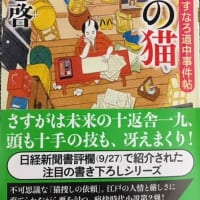
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます