歴史学者の奈良本辰也氏は、徳川家康を「偉大なる平凡人」と表現したが、平凡人どころか、逆境にめげない精神力はずば抜けていると思う。
戦国時代の常とはいえ、天下人となるまでの家康の周囲には死と別離の影が常に漂った。
まず、母・於大の方。
家康3歳のときに、政治的な理由から、離縁されている。ちなみに、そのとき於大はまだ十八であった。
六歳のときには、義理の祖父に裏切られ織田家の人質となる。
不幸は続く。
家康が8歳になると、父・広忠が部下の謀反に遭い、死去。
広忠は、まだ二十四歳の早世である。
この御、しばらくは、身内の死と縁を切ることができたが、試練は家康三十八歳のときに再び訪れる。
長男・信康と、側室・築山殿の殺害を織田信長から命じられたのである。
信康が武田方と内通しているからというのが表の理由。
真実は、信康の妻は、信長の娘・徳姫であったが、夫婦関係、嫁姑関係のこじれから、徳姫が父・信長に中傷誹謗したからだった。
家康は不屈の精神の持ち主とは言い切れない部分もある。
三方ヶ原で武田軍に大敗を喫したとき、天王寺の変を堺で聞いたとき、ともに、「もはやこれまで」と半ば諦めている。
実力だけでは天下取りにはなれないし、もちろん運だけでもなれない。
いろいろな要因が絡み合って徳川家康は天下人となり、徳川幕府が誕生したのだけれど、一番大きな原因は、やはり家康その人の考え方だろう。
堺屋太一は、「家康ほど明確な政治指針を持っていた武将はいない」と言っている。
関ヶ原の戦いで雌雄を決した石田三成なども、明確な指針を持っていたように思うが、もし、三成が戦に勝利して、天下人となっていたら、以後三百年も続く幕府が形成されたかどうかは、疑問が残る。
元和の時代に現代流の政治感覚を持ち込むわけにはいかないが、目標に向かう気持ちや考え方は、現代に通じる。
幼少時代に逆境であったとき、卑屈になるのでもなく、自棄になるのでもなく、前に向かって歩こうとする態度に、何かしら貴重なものを感じるのである。

写真は、清瀧寺にある信康の墓所(静岡県浜松市)
↓よろしかったら、クリックお願いいたします!
 人気ブログランキングへ
人気ブログランキングへ
 にほんブログ村
にほんブログ村
戦国時代の常とはいえ、天下人となるまでの家康の周囲には死と別離の影が常に漂った。
まず、母・於大の方。
家康3歳のときに、政治的な理由から、離縁されている。ちなみに、そのとき於大はまだ十八であった。
六歳のときには、義理の祖父に裏切られ織田家の人質となる。
不幸は続く。
家康が8歳になると、父・広忠が部下の謀反に遭い、死去。
広忠は、まだ二十四歳の早世である。
この御、しばらくは、身内の死と縁を切ることができたが、試練は家康三十八歳のときに再び訪れる。
長男・信康と、側室・築山殿の殺害を織田信長から命じられたのである。
信康が武田方と内通しているからというのが表の理由。
真実は、信康の妻は、信長の娘・徳姫であったが、夫婦関係、嫁姑関係のこじれから、徳姫が父・信長に中傷誹謗したからだった。
家康は不屈の精神の持ち主とは言い切れない部分もある。
三方ヶ原で武田軍に大敗を喫したとき、天王寺の変を堺で聞いたとき、ともに、「もはやこれまで」と半ば諦めている。
実力だけでは天下取りにはなれないし、もちろん運だけでもなれない。
いろいろな要因が絡み合って徳川家康は天下人となり、徳川幕府が誕生したのだけれど、一番大きな原因は、やはり家康その人の考え方だろう。
堺屋太一は、「家康ほど明確な政治指針を持っていた武将はいない」と言っている。
関ヶ原の戦いで雌雄を決した石田三成なども、明確な指針を持っていたように思うが、もし、三成が戦に勝利して、天下人となっていたら、以後三百年も続く幕府が形成されたかどうかは、疑問が残る。
元和の時代に現代流の政治感覚を持ち込むわけにはいかないが、目標に向かう気持ちや考え方は、現代に通じる。
幼少時代に逆境であったとき、卑屈になるのでもなく、自棄になるのでもなく、前に向かって歩こうとする態度に、何かしら貴重なものを感じるのである。

写真は、清瀧寺にある信康の墓所(静岡県浜松市)
↓よろしかったら、クリックお願いいたします!










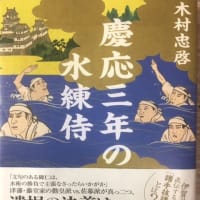
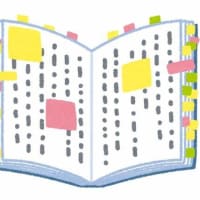
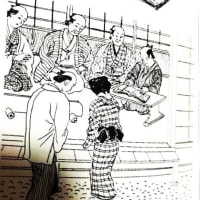
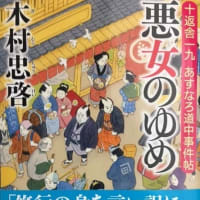
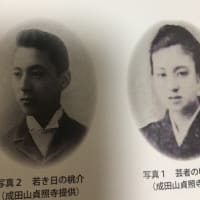

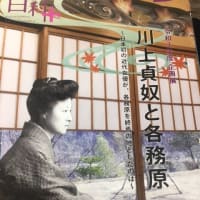
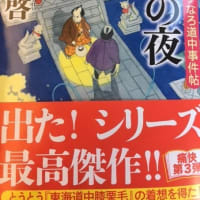
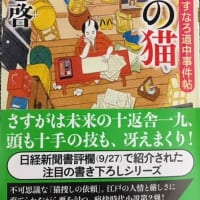
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます