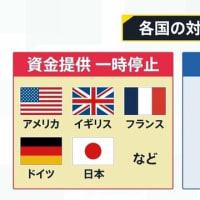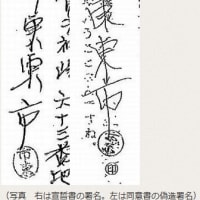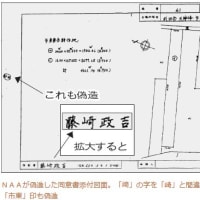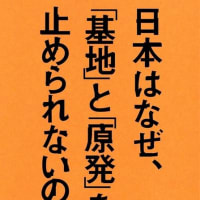室町時代、30年も続いた関東の内戦と七年祭の起源
先日、石橋山を脱出した源頼朝が鷺沼館(やかた)で態勢を建て直し反転攻勢、鎌倉入りを果たし、さらに富士川の戦いに勝つまでのお話をしましたが、その後の、中世の習志野市域はどうなったのか、というお問合せを幾つかいただきました。今日はそのお話をしようと思いますが、はっきり申し上げてこの時代を物語る史料は非常に少なく、よくわからないのが実情です。今回は大胆な想像を交えて、一つのあり得そうな像を作ってみますが、「どこに証拠があるのか」「どの史料からそう言えるのか」と言われても困ります。あくまでも、“夏休みお楽しみ講座”ということで…。また、前提となる話が非常に長くなりますが、「習志野に関係ねぇじゃないか」と言わずにお付き合いください。
鷺沼源太は千葉氏の勢力下にあった
石橋山から安房国(あわのくに)に脱出した頼朝は、千葉氏の庇護を得て鷺沼館に入りました。そのことから、鷺沼源太は千葉氏の勢力下にあったのだろうと思われます。そこでまず、千葉氏がその後、どう展開していったのかを見てみたいと思います。
千葉氏は桓武平氏。やがて千葉氏(下総)と上総氏(上総)に分かれる
千葉氏は桓武平氏(かんむへいし)です。最初、上総国を本拠にしたようですが、千葉常兼(つねかね)の代に下総国へ進出するようになります。その子の常重(つねしげ)の代に下総を拠点とする千葉氏と上総に残った上総氏の2つに分かれ、千葉氏は現在の千葉市中央区亥鼻(いのはな)付近に館を築いたとされます。県庁の裏に現在、鉄筋コンクリートの模造天守閣が見えますが(もちろん常重の時代にそんなものはありません)、あの高台です。
また、千葉氏の当主は代々「千葉介」(ちばのすけ)を、上総氏は「上総介」(かずさのすけ)を名乗ります。そして常重の子、常胤(つねたね)の代の治承4年(1180)、石橋山の戦いで敗れた頼朝が安房国に逃げてくるのです。頼朝は上総介広常と千葉介常胤に加勢を頼み起死回生、鎌倉を押え平家打倒に成功する、というのは「鷺沼から頼朝が出陣!」の回でお話したところです。
上総氏が謀反の疑いで滅ぼされ、上総国も千葉市の勢力下に
鎌倉幕府の下で千葉氏は下総国の守護とされ、また上総氏が、謀叛の疑いを受けて頼朝に滅ぼされてしまうと、上総国も千葉氏の勢力下に入りました。なお、平家が滅び幕府が出来ても血みどろの権力抗争は収まらず、平家打倒に功のあった源義経、源範頼(のりより)が粛清されてしまった他、三浦、和田、畠山といった有力武将が次々と滅亡していったこと、また将軍家自体が3代将軍実朝(さねとも)の暗殺で絶えてしまい、結局、頼朝の妻政子の実家であった北条氏が覇権を握ったことなど、この際、思い出していただくことにしましょう。
千葉六党
千葉氏を支えた一門として重要なのは、相馬、武石、大須賀(おおすが)、国分(こくぶう又はこくぶ)、東(とう)の諸氏です。千葉宗家(そうけ)にこの5氏を加えて千葉六党(ちばりくとう)と呼ばれます。
相馬氏は平将門の子・将国(まさくに)が相馬小次郎を称したことに始まるとされます。千葉常胤の二男・師常(もろつね)がこの相馬氏に養子に入り、千葉氏の一門となります。
武石氏は千葉常胤の三男・胤盛(たねもり)が、下総国千葉郡武石郷を領したもの。現在の千葉市花見川区武石で、真蔵院という寺が武石城の跡とされています。
大須賀氏は本来、上総氏の一門でしたが、先ほど見たように上総氏は頼朝によって滅ぼされます。そこで千葉常胤の四男・多部田胤信(たねのぶ)が大須賀家を相続したものです。先日、幕張が江戸北町奉行所の与力給地で、そこを治めていたのが大須賀代官だった、というお話をしたのを覚えているでしょうか?もちろん、大須賀氏の末裔です。
国分氏は、千葉常胤の五男・胤通(たねみち)が、下総国葛飾郡国分寺を領したもの。現在の市川市国分です。最後に東氏は、千葉常胤の六男・胤頼(たねより)が、下総国東庄(とうのしょう)を領したもの。現在の香取郡東庄町です。

室町時代は戦乱の世
時代はやがて、南北朝の争乱を経て室町時代を迎えます。
室町時代というと、日本史の授業では大正時代と並んで、先生もつい手抜きしてしまう時代です。室町時代を扱ったNHK大河ドラマは「太平記」「花の乱」がありましたが、視聴率はイマイチだったようです。室町時代、というと金閣寺・銀閣寺だ、能・狂言だと、何か平和な時代であったかのように錯覚してしまう方もいると思いますが、実は戦乱に明け暮れていた時代でした。前半は、南北朝の混乱が続いています。応仁の乱から後半は、いわゆる戦国時代でした。その中間期も、決して平和な時代ではなかったのです。
戦国時代の始まりは、「応仁の乱」(1467〜)ではなく、関東での「享徳の乱」(1454〜)?
関東では享徳(きょうとく)の乱という戦乱が、何と約30年間(1454~82)に及びます。京都・室町(上京区室町通)に幕府を開いた足利氏は、関東の支配は前の時代に引き続き、鎌倉で行うこととしました。京都に公方(くぼう、将軍のこと)がいて管領(かんれい)が補佐しているのと同様に、鎌倉には鎌倉公方を置き関東管領が補佐をするという体制が作られましたが、やがて関東管領の上杉氏が宗家の山内上杉(やまのうちうえすぎ)氏と分家の扇谷上杉(おおぎがやつうえすぎ)氏に分裂します。
享徳3年(1454)、鎌倉公方足利成氏(しげうじ)が,関東管領の上杉氏と対立、上杉憲忠(のりただ)を殺してしまったことから戦乱が始まります。京都にいる将軍は成氏を追放しますが、成氏は下総の古河(こが)に移って引き続き関東を支配しようとします。
幕府は8代将軍義政の兄・政知(まさとも)を関東に派遣し、鎌倉公方の職を取り上げようとしますが、政知は鎌倉には入れず、伊豆国堀越を拠点とします。古河にいる成氏の方を古河公方、伊豆にいる政知の方を堀越公方というのですが、要するに鎌倉公方の座が分裂してしまったことになります。
古河公方vs.堀越公方、山内上杉氏vs.扇谷上杉氏。この抗争が複雑に絡み合い、東国武士もそれぞれを支持したもので、とうとう大戦乱になってしまったのです。応仁の乱(1467~)に先立つこと13年。そこで戦国時代の始まりを応仁の乱ではなく、この享徳の乱に求める学者も少なくありません。そしてこの享徳の乱が、習志野市域にも影を落としていたはずなのです。
乱が始まった2年目、康正(こうしょう)元年(1455)のこと。千葉氏の内部でも分裂が起ります。下総国の守護であった千葉氏の下には、幕府方と古河公方方それぞれから支援要請が来ました。宗家の当主、千葉胤直(たねなお)は幕府に味方して古河公方討伐に乗り出そうとしますが、甥の千葉康胤(やすたね)は古河公方方に付くことを主張して対立します。また、千葉家の重臣筆頭の地位をめぐっては、原氏と円城寺氏が対立していましたから、胤直vs. 康胤、原vs.円城寺の対立が組み合わさって、分裂抗争が始まりました。原胤房は亥鼻城に攻め込みます。宗家の千葉胤直・胤宣(たねのぶ)父子は千田庄(現在の香取郡多古町付近)に逃げ込みましたが、千葉康胤も叛旗をひるがえし、千田庄に立てこもる胤直父子を攻め滅ぼしてしまいました。胤直の甥・千葉実胤(さねたね)、自胤(よりたね)らは後に武蔵国に逃れ、千葉氏宗家は康胤が継ぐことになります。この千葉康胤ですが、千葉郡馬加村(現在の千葉市花見川区幕張町)に城を構えていたことから馬加を名乗り、馬加康胤(まくはり やすたね)とも呼ばれます。なお馬加城はJR幕張駅北方、現在「幕張ハウス」という大きなマンションが立っている山にありました。

8代将軍足利義政というと、銀閣寺に籠って東山文化を愛していた文弱な将軍のように思われていますが、この千葉氏の内紛を聞くと大変怒り、鎮圧の兵を向かわせます。千葉氏の一族で、美濃国郡上(ぐじょう)郡の城主だった東常縁(とう つねより)の軍が馬加城に攻め寄せました。馬加康胤の嫡子胤持(たねもち)は討ち取られ、康胤は城を落ちのびましたが、康正2年(1456)、上総国八幡(現在の市原市八幡宿)の村田川で討ち死にしたとされています。また、幕張の堂の山(幕張町1丁目)には現在も「康胤の首塚」という五輪塔が残されています。

この後、下総国には、幕府の命を受けた扇谷上杉氏の家老、太田道灌が攻め込んで古河公方の勢力を駆逐しようとします(太田道灌と言えば江戸城を作ったことで知られていますが、そもそも江戸城は康正3年(1457)、この下総国の混乱に対処する前線基地として築城されたものでした)。対する原氏は馬加康胤の庶子輔胤(すけたね)を奉じ、古河公方の支援を受けて抵抗を続けます。一方、武蔵国に逃れていた千葉実胤は石浜城(現在の浅草周辺)、その弟・自胤は赤塚城(板橋区)に籠って、反攻の機会をうかがっており、室町幕府は千葉氏宗家の当主として自胤を擁立しました。結局、千葉輔胤が宗家の地位を確保し、文明年間には本佐倉城(もとさくらじょう。酒々井町)を築いて従来の亥鼻城から本拠地を移しました。しかし、双方がそれぞれ、我こそは千葉氏の正統と称して争っている内に、名門千葉氏はどんどん衰退の一途をたどることになったのです。
さらに戦国時代に入ると千葉氏は、常陸国の佐竹氏や小弓公方足利義明(古河公方の分家、下総国千葉郡小弓城(おゆみじょう。現在の千葉市中央区生実、緑区おゆみ野の一帯)を本拠地とした)、また安房国の里見氏から侵攻を受けるようになります。これに対して千葉氏は、小田原の北条氏康と姻戚関係を結ぶことで所領を守ろうとしました。しかし天正18年(1590)、豊臣秀吉の小田原征伐で北条氏が滅亡したことにより、千葉氏の当主千葉重胤(しげたね)も所領没収となり、滅亡したのでした。
(ここまでの千葉氏の歴史が下記のサイトにまとめられています)
郷土博物館_千葉氏の歴史
ここまで読んで、「習志野はいつ出てくるんだ」と思われた方と、馬加康胤の名前に「おや?」と思われた方がいると思います。馬加康胤の名は、習志野市史でもよく見かけますね。それは「七年祭」です。
「七年祭」の話に入る前に、それぞれがたどった運命を見てみると
まず扇谷上杉氏ですが、文明18年(1486)、家老である太田道灌の力を恐れた主君・扇谷上杉定正は、道灌をだまし打ちにしてしまいます。風呂場で入浴中に襲われた道灌は「当方滅亡」、自分がいなくなれば扇谷上杉氏に未来はないと言い残したといいます。その言葉どおり、天文15年(1546)のいわゆる河越夜戦(北条方の拠点、武蔵国川越城の攻略に失敗)で扇谷上杉氏は滅亡しています。
一方の山内上杉氏は永禄4年(1561)、越後国の守護代(しゅごだい)・長尾景虎を養子とし、家督と関東管領職を継承させます。この景虎こそ上杉謙信です。甲斐の武田氏との抗争ばかり有名ですが、上杉謙信は越後から度々関東に攻め入っており、関東管領の後継者だという意識が強かったものと思われます。
堀越公方は明応2年(1493)、駿河の今川氏の軍勢を率いた伊勢新九郎という者に滅ぼされます。新九郎はそのまま堀越に近い韮山(にらやま)に留まり、続いて明応4年(1495)、相模国に攻め入って小田原城を奪取します。この伊勢新九郎が北条早雲を名乗ります。その後、豊臣秀吉に滅ぼされるまで5代にわたり関東を制圧したわけですが、鎌倉幕府の北条氏と区別して小田原北条氏とか後北条氏と呼ばれます。鎌倉の北条氏が伊豆国韮山から起って、相模国から天下を支配したのにあやかって、韮山から相模に入った早雲も北条の後継者を名乗ったのだとされています。また関東では、この早雲の小田原城奪取をもって戦国時代の始まりと考えられてきました。
一方の古河公方は、本文にも述べたように古河公方と小弓公方に分れて争いましたが、天正18年(1590)に小田原を落として関東を平定した豊臣秀吉は、小弓公方の子孫に古河公方の娘を娶(めと)らせた上、下野国喜連川(きつれがわ)に5千石の所領を与えました。この喜連川氏は江戸時代には、喜連川公方として大名並の格式を与えられています。
七年祭は、千葉(馬加)康胤が4つの神社への安産祈願で男子に恵まれたのが起源、とされているが…
七年祭は丑年と未年に、船橋・千葉・八千代・習志野市の4市域にわたって開催される大きなお祭です。「下総三山の七年祭」として千葉県の無形民俗文化財にも指定されています。
その起源として、馬加城主の千葉康胤が二宮神社、子安神社、子守(こまもり)神社、三代王(さんだいおう)神社の神主に馬加村の浜辺で安産祈願をさせたところ、無事奥方が嫡子を出産したことに由来するとされます。文安2年(1445)に最初の祭が行われるようになったということです。なお、昔の人はゼロの概念がありませんから、年は1から数えます。丑・寅・卯・辰・巳・午・未で7年、未・申・酉・戌・亥・子・丑で7年と、七年に一度の祭ということで「七年祭」と呼ばれているわけです。
祭の年の11月に行われる大祭の初日は、9つの神社の神輿が船橋市三山の二宮神社に勢ぞろいし「安産御礼大祭」を行います。これが嫡子の誕生を祝って親族が詰めかけた姿であるとされます。9つの神社とは、二宮神社(船橋市三山)、子安神社(千葉市花見川区畑町)、子守神社(同区幕張町)、三代王神社(同区武石町)、菊田神社(習志野市津田沼)、大原大宮神社(同市実籾)、時平神社(八千代市萱田町・大和田)、高津比咩(たかつひめ)神社(同市高津)、八王子神社(船橋市古和釜町)です。それぞれに役割があり、二宮神社は父、子安神社は母、子守神社は子守、三代王神社は産婆、菊田神社は叔父、大原大宮神社は叔母、時平神社は長男、高津比咩神社は娘、八王子神社は末息子、ということになっています。この9社の神輿(みこし)が勢ぞろいする姿は壮観で、祭のクライマックスとなっています。
しかし祭礼には二日目があり、二宮神社(父)、子安神社(母)、子守神社(子守)、三代王神社(産婆)の4社の神輿は、千葉市幕張海岸の磯出御旅所で「磯出祭」を行います。これは、馬加康胤が浜辺で安産祈願をさせた再現だとされます。しかし、伝説のとおりであれば、まず浜辺での安産祈願があり、その後、無事出産した御礼があるわけですから、初日と二日目が逆転しています。このため、「三山の祭は後が先」という言い習わしがあります。
このように、馬加康胤と嫡子胤持にまつわる祭が、馬加氏滅亡後も600年近く続いているということは注意しなければならないことでしょう。領主が末永く栄え、領民がこれをことほいで、祭が永年続いてきたというよくあるパターンではないのです。
なぜ神輿は馬加城でなく、菅原道真の祟りで死んだ藤原時平を合祀した二宮神社に集まる?
しかし、9つの神社を見てみると、不思議がいくつも浮かんできます。馬加城の世継ぎが生まれた祝いなのに、なぜ神輿は馬加城に集るのではなく二宮神社に集るのでしょう。ここで、頼朝の回でもご紹介した、一つの伝説が浮かび上ってきます。
菊田神社には、治承5年(1181)、平家打倒の陰謀に加わった疑いで流罪となり、船で相模から安房を目指した藤原師経(もろつね)を、鷺沼源太光則が久々田浦で迎えた。菊田神社は弘仁年間(810~824)に創建されているが、この時、師経の祖先・藤原時平(ときひら)を合祀したのだ、という伝承がありました。もとより伝承なので、直ちに史実と考えるわけには行きませんが、この伝承はさらに次のように広がって行きます。
師経は菊田神社から菊田川を遡行し、三山に住み着いた。そこで、三山の地に弘仁年間(810~824)に創建されていた二宮神社に、祖先の藤原時平を合祀した(二宮神社)
菅原道真を追放した祟りで死んだ藤原時平の妻と第五息女の高津姫は、東下りをして下総の久々田に漂流した時、舟が石となった。姫は三山からさらに当地に落ち着き、都を偲び亡父を慕いながら当地で一生を終えた。姫の守り本尊であった十一面観音を祀ったのが高津観音寺で、姫は高津比咩神社(たかつひめじんじゃ)に祀られた(高津比咩神社)
八千代市内には時平神社が4つあるが、いずれも由緒や情報に乏しい。大和田は慶長15年(1610)、萱田は元和元年(1615)と、いずれも江戸初期に創建されているが、なぜこの地域に4社もの時平神社が集中しているのか、また室町時代に起源があるとされる七年祭になぜ関わるようになったのかは不明(時平神社)
七年祭は、高津姫の故事と馬加の浜辺での安産祈願が一緒になったもの?
このように見てくると、七年祭は馬加氏の世継ぎ誕生の神事と、時平の末裔を称する人々の神事が混淆していると見るべきなのではないでしょうか。つまり、祭の初日は馬加城の祝儀の再現であり、二日目は藤原師経あるいは高津姫の故事の再現と、馬加の浜辺での安産祈願が一緒になったと考えれば「三山の祭は後が先」なのも何となく理解できるような気がします。特に二日目の祭は、最後に二宮神社の神輿だけが「神の台」と呼ばれる場所(習志野市津田沼)で神事を行ってすべて終了します。この「神の台」は、藤原師経が嵐に遭遇してこの地に流れ着いた際に、見失った姉の船に合図ののろしを上げた場所とも、鷺沼源太光則が一行を出迎えた場所だとも言われます。
千葉市の市章は千葉氏の家紋、月星紋(妙見菩薩)から作られた。そして高津比咩神社も妙見菩薩を合祀
ここで想像を逞しくするならば、元々古代からこの地にいた勢力(鷺沼源太)、新たに入植してきた時平の末裔を称する勢力、そして馬加城から現在9つの神社がある地域を支配した馬加康胤が手を組んで、中世の周辺社会が成り立っていたということなのではないかと思われます。例えば高津比咩神社は、千葉氏の守護神である妙見(みょうけん)菩薩(道教の北極星、北斗七星信仰と仏教の菩薩信仰が習合したもの。千葉氏は家紋も「月星」や「七曜」を用いる)も合祀しており、馬加城との関係を暗示しています。
七年祭、それは非業の死をとげた祖先への鎮魂のための祭りではないか?
なお藤原時平ですが、ご存知のように菅原道真を陥れたため、道真の死後、その祟りを受け、謎の熱病に冒され、両耳からは黒い蛇が這い出し、発狂して死んだとされています。一方で馬加康胤・胤持父子も、非業の死を遂げています。安産を祝われた胤持は討ち死にした際23歳、その首は京都へ運ばれたといいます。盛大な七年祭ですが、本当はこうした非業の死を遂げた祖先への、鎮魂のための祭なのではないだろうかという気もしないではありません。
昭和10年代に、七年祭の地域を合体させた「習志野市」構想があった
ところで、この七年祭を基盤とした繋がりは、後に意外なところに顔を出します。太平洋戦争後の町村合併ブームが起きるさらに以前、昭和10年代に時の津田沼町長は「大習志野市構想」を打ち上げたといいます。津田沼町と幕張町、犢橋(こてはし)村、大和田町、睦(むつみ)村、豊富村、二宮町が合併して「習志野市」を作ろうというものでしたが、その地域は言うまでもなく七年祭の地域と重なっています。元々、中世の頃からの深い地縁・結束があったわけなのでしょう。紆余曲折あって結局この大習志野市構想は実らず、幕張町と犢橋村は千葉市と、二宮町と豊富村は船橋市と合併し、大和田町と睦村は合併して八千代市となり、津田沼町だけが習志野市を名乗ることとなりました。しかし、もしこれら7町村が合併し、市役所を幕張に置いて「馬加市」とでも名乗っていれば、歴史的にも根拠のあるものになっていたのかも知れません。
https://www.city.narashino.lg.jp/smph/citysales/shizen/walk/sansaku/h16/sansaku072.html
閑話休題
➀謎の多い武石氏
ここで、千葉六党の内、馬加城に最も近い位置にいた武石氏はどうなったのかを見ておきましょう。実は武石氏は謎が多く、頼朝が千葉常胤に庇護された際、既に武石城もあったはずなのに、頼朝がそちらではなく鷺沼館に入ったというのも一つの謎ですね。しかし、常胤が頼朝を自分の勢力の及ばない館に宿営させるはずはないので、鷺沼源太も千葉氏に服していたのでしょう。その常胤の三男・武石胤盛は頼朝に従い、木曽義仲や平家、さらに奥州藤原氏の軍勢と戦っています。
また、康正元年(1455)に馬加康胤が、千葉氏宗家の千葉胤直・胤宣父子を滅亡させた際に、同族で、しかも馬加に隣接する領地を持っていた武石城がどういう立場を取ったのかも、よくわかっていません。なお、この後述べる第一次国府台合戦(1538)の際、小弓公方に従った武石胤親(たねちか)は討ち死にし、武石氏は滅亡しています。
➁実籾城跡に千葉氏ゆかりの妙見神社
よくわかっていないものと言えば、鷺沼城と並んで習志野市域に残るもう一つの城、実籾城の存在があります。実籾本郷の台地上に、確かに山城の郭を思わせるものが存在するのですが、いつ頃、誰が作った城なのか、詳細がわかりません。しかし、主郭と思われる場所には現在も妙見神社が建っています。
http://www.komainu.org/chiba/narasino/MyoukenMomihongo/myoken.html

妙見菩薩は千葉氏の守護神であり、千葉氏の勢力下にあった城であることは間違いないのです。実籾城の南東500mほどには長胤寺があり、武石胤盛の曾孫・武石長胤(ながたね)の館跡とされていますが、これと実籾城の関係もよくわかっていません。
里見側についた鷺沼源太が国府台合戦で討ち死に
それでは今日の最後に、戦国時代、鷺沼源太が討ち死にしたと伝わる国府台合戦の経過を見て、その中で習志野市域がどうなったのかを推理してみることにしましょう。
市川市国府台付近には、国府台城がありました。文明10年(1478)に太田道灌が千葉孝胤を攻める際、この地に陣を置いたのが始まりとされます。千葉氏と古河公方の連携を断つための要衝となりました。
やがて戦国時代に入り、この地に小田原の北条氏が進出してきます。一方、古河公方には内紛が起ります。古河公方足利政氏の子・義明が下総国千葉郡小弓城に入って「小弓公方(おゆみくぼう)」を称し、北条氏と結んだ古河公方や千葉氏とは敵対するようになりました。天文7年(1538)、安房国の里見氏の援軍を得た小弓公方は国府台城を占拠しますが、江戸川を渡ってきた北条氏綱の大軍に敗れて討ち死にします。この結果、北条氏の勢力は下総国にまで浸透する事になりました。一方、小弓公方の勢力がいなくなった上総国の南部には、安房国から里見義堯(よしたか)が進出してきます。この戦いを第一次国府台合戦と呼んでいます。
それから25年後、再度国府台で大きな合戦が起ります。鷺沼源太が討ち死にしたというのはこの時のことです。
永禄6年(1563)、有名な川中島の合戦から2年後のことです。武田信玄は北条氏康と共に、上杉方の武蔵国松山城(埼玉県比企郡)を攻撃します。そこで謙信は、安房の里見氏に救援を要請しました。里見義堯は子の義弘を北上させ松山城救援に向かわせますが、北条氏はこれを国府台で阻止しました。国府台は北条vs.里見の決戦場の様相を呈してきます。ちょうどこの頃、北条方となっていた江戸城の太田康資(やすすけ。道灌の曽孫)が上杉方に寝返り、逃亡します。謙信は里見義弘に康資の救出を依頼してきます。翌永禄7年(1564)正月、義弘は房総の諸将を率いて出陣し、1月4日に国府台城を落としました。北条軍2万は、直ちに城の奪還を図りましたが、1月7日、北条方の先鋒は城奪還に失敗してしまいます。これに油断した義弘は、兵士らに正月の祝い酒を振舞います。しかし北条方は、里見方のこの油断を見落としませんでした。翌8日未明、江戸川を渡って夜襲をかけたため、酒に酔って寝ていた里見方は大混乱に陥ったといいます。伝説ではこの時、コウノトリが舞い降りて北条方に江戸川の浅瀬を教えてくれたのだそうです。里見方に加わっていた鷺沼源太が討ち死にしたというのは、この時のことですね。
義弘はやっとのことで脱出したものの、この戦いの後、北条方は一気に上総国まで進出してしまいました。
以上が国府台合戦の経過ですが、鷺沼源太は里見方にいて北条氏に敵対していたことがわかります。本佐倉城の千葉胤富(たねとみ)は北条方に付いていますから、こちらとも敵対していたことになります。鷺沼源太敗死後のこともわかりませんが、習志野市域はおそらく北条氏の占領下に入り、秀吉の小田原攻めと家康の江戸入府、そして天領・旗本領への編入という流れで江戸時代を迎えたのだろうと思われます。
習志野市域支配地図の移り変わりを見る
今日のお話から中世の習志野市域を推測してみれば、
鎌倉時代は、頼朝に付いた千葉氏宗家の下にあった
この時期、藤原時平の末裔を称する人々の入植があった
室町時代に入り、時平の末裔を称する村々と共に、馬加康胤の支配下に入った
村々は馬加氏が滅び去った後も、七年祭を続けてきた
戦国時代に入って太田道灌や北条氏の勢力が迫ってきたが、これには従わず、むしろ里見方に付いた
第二次国府台合戦で鷺沼氏が滅び、北条氏の占領下に入った
間もなく豊臣秀吉の小田原攻めで北条氏が滅び、江戸に徳川家康が入って江戸時代を迎えた
といった流れだったのだろうと思うのです。
(ニート太公望)
コメントをお寄せください。
<パソコンの場合>
このブログの右下「コメント」をクリック⇒「コメントを投稿する」をクリック⇒名前(ニックネームでも可)、タイトル、コメントを入力し、下に表示された4桁の数字を下の枠に入力⇒「コメントを投稿する」をクリック
<スマホの場合>
このブログの下の方「コメントする」を押す⇒名前(ニックネームでも可)、コメントを入力⇒「私はロボットではありません」の左の四角を押す⇒表示された項目に該当する画像を選択し、右下の「確認」を押す⇒「投稿する」を押す