| マッチメイク | ||
|---|---|---|
 |
読了日 | 2016/01/07 |
| 著 者 | 不知火京介 | |
| 出版社 | 講談社 | |
| 形 態 | 単行本 | |
| ページ数 | 385 | |
| 発行日 | 2003/08/07 | |
| ISBN | 4-06-212001-1 | |
 昨日(23日金曜日)、処方されていた血圧降下剤が切れたので、病院に行ってきた。慌て者の僕はかかりつけの医師の診察日をうっかり間違えて、その日の診察は午前中だけだったのに、のんびりと午後になってから出かけていったのだ。
昨日(23日金曜日)、処方されていた血圧降下剤が切れたので、病院に行ってきた。慌て者の僕はかかりつけの医師の診察日をうっかり間違えて、その日の診察は午前中だけだったのに、のんびりと午後になってから出かけていったのだ。
受付で、診察券と血圧管理表を渡したら、「今日は診察は午前中だけですよ。」と言われ、しまった間違えた! と言ったら、受付嬢、「でも先生が2時半ごろ見えるので、お待ちいただければ、多分診てもらえると思います。」と言うので、2時半まで待つことにした。病院はいつも待ち時間が長いので、そのために持ち込んだ文庫本をゆっくりと読むことにする。 薬を変えたりして飲み続けてはいるが、どうしたことか一向に数値が安定しない。全く自覚症状はないから、さほど心配はしてないが、それでも血圧が高いことは良いことではない。ストレスをため込まないよう気を付けて、過ごすことを心がけてはいるのだが・・・・。

2時半からのドクターの診察では、いつものように簡単な問診だけだが、1週間後の29日金曜日に循環器内科の診察を改めて受けることを勧められて、予約を取った。そのため今回の降圧剤は6日分だけの処方となった。
今年で僕も喜寿となるから、押しも押されもしない年寄りだ。少しそれらしく食事なども気を付けなければいけないのかな。とは思うが、貧乏暮らしの僕は贅沢な食事をしているわけでも、偏った食生活を送っているわけでもない。食事やその他についても、ごくごく普通の暮らしをしているので、血圧の高い要因はとんと見当がつかないのだ。
植木等氏の歌の文句ではないが、そのうち何とかなるだろう。

 近のことだって記憶はあいまいなのに、この本を手に入れたのはかなり前のことだから、どのような状況で僕の手元にあるのかは全く覚えていない。多分江戸川乱歩賞の受賞作を集中して読んだ時期があったから、そうした時期だったのだろう。近頃長い間積ン読だった蔵書を、思い出したように読んでいる中で、底の方から引っ張り出して読んだ。その昔、僕も近所の子たちと同様に、テレビのある家にお邪魔して、夢中になってプロレスを見たものだ。
近のことだって記憶はあいまいなのに、この本を手に入れたのはかなり前のことだから、どのような状況で僕の手元にあるのかは全く覚えていない。多分江戸川乱歩賞の受賞作を集中して読んだ時期があったから、そうした時期だったのだろう。近頃長い間積ン読だった蔵書を、思い出したように読んでいる中で、底の方から引っ張り出して読んだ。その昔、僕も近所の子たちと同様に、テレビのある家にお邪魔して、夢中になってプロレスを見たものだ。
余談になるが、その当時はテレビもまだまだ一般に普及しておらず、テレビのある家は近所に2-3軒しかなかった。しかもそうした家には近所から大勢の子供が、押しかけて見せてもらっていた。
そうした家の人たちは子どもたちばかりでなく、大人でも快く受け入れて、一緒にテレビを楽しんでいた。今の時代では考えられないほど、そんな地域の繋がりが生きていた古き良き時代だったと、思わせるものがあった。

僕も今でこそ興味が他に移って、プロレスを見ることもなくなったが、その当時はテレビの珍しさや、花形スター・力道山の雄姿は、何物にも代えがたい魅力をもって僕たち子どもの心をとらえて離さなかったのだ。
否、子供ばかりではない、大人も老人も国民的スターに魅了されていた。今、そんな誰しもが興味を惹かれる物事があるだろうか?一億総中流化と言われた時代を経て、多様化の時代になった現在は、それぞれが独自の価値観を持つから、昔のようなことが再び蘇ることは、もう望んでもないのだろう。
プロレスは全盛時代から、八百長だという話があった。子供の頃はそうした話を半信半疑でとらえていたが、この本によれば、そう本書はプロレスの世界を舞台としたミステリーなのだ。そんなことは断らなくとも、表紙のイラストを見ればすぐにわかることだが、プロレスも演劇と同様に、脚本家がいてその脚本通りに試合運びが行われるということなのだ。
その脚本家をマッチメイカー、脚本を練ることをマッチメイクと言うのだそうだ。演劇と違って100%マッチメイク通りにいかないこともままあるようだが、おおよその試合はマッチメイクに沿って行われるということだ。 だから八百長と言うのとは少し違う。八百長は特に試合が賭け事に用いられるときに行われて、人気のある方のレスラーに、大半の掛け金が偏ったとき、わざと負け戦をするといったようなことだ。
脚本によって試合運びが行われることは、先述の通り演劇と同様にその試合のプロセスを観客に楽しんでもらうという寸法なのだ。

 書では、関西を拠点とするチームの主宰者―彼もまたプロレスラーの一人で、しかも国会議員である―が、毒殺?されるというところから、ストーリーが始まる。
書では、関西を拠点とするチームの主宰者―彼もまたプロレスラーの一人で、しかも国会議員である―が、毒殺?されるというところから、ストーリーが始まる。
実在の人物を思わせるようなところもあるが、多数のプロレスラー志願者の中で、厳しい訓練を耐えて生き残 った新人プロレスラーの視点で、ストーリーの展開が語られていく。試合運びや下働きの様子も描写しながら、プロレスと言う格闘技の内幕も、判りやすく描かれる。
そして、第2の事件が引き起こされる。果たして連続殺人か?謎解きの興味もあることはあるが、プロレス業界の複雑な人間関係などが、僕にはミステリーへの関心を薄めているような気がするのは、やはり今の時代とマッチしていないからか?ちょっと残念。
にほんブログ村 |













 者の本は2012年10月に「享年0.1歳」を読んだのが最後だから、もう足掛け4年も前のこととなる。この読書記録を始めたころ、僕はサイコサスペンスに夢中になって、最初に読んだ「心理分析官」で、ファンとなって作品を読み継いできた。それにしても、前回から随分間が空いた。
者の本は2012年10月に「享年0.1歳」を読んだのが最後だから、もう足掛け4年も前のこととなる。この読書記録を始めたころ、僕はサイコサスペンスに夢中になって、最初に読んだ「心理分析官」で、ファンとなって作品を読み継いできた。それにしても、前回から随分間が空いた。
 版元のNHK出版と言えば、以前は「日本放送出版協会」ではなかったかと、ネットで検索したらその通りで、2010年に今のNHK出版に名称が変更されたということだった。僕がなぜこの出版社に関心があるかと言えば、鈴木栄氏の著作「生きよわが子たち」、「生きよ仲間たち」、「光はバスに乗って」などが、その日本放送出版協会から刊行されていたことを思い出したからだ。
版元のNHK出版と言えば、以前は「日本放送出版協会」ではなかったかと、ネットで検索したらその通りで、2010年に今のNHK出版に名称が変更されたということだった。僕がなぜこの出版社に関心があるかと言えば、鈴木栄氏の著作「生きよわが子たち」、「生きよ仲間たち」、「光はバスに乗って」などが、その日本放送出版協会から刊行されていたことを思い出したからだ。 れない劇団員・加納慎策は、たまたま現役の総理大臣に似ていることから、前座の出し物として、総理の形態模写を演じていた。次第に彼の模写はそこそこの評判になっていったが、彼とすれば本番の出し物での出番のないことに苛立ちを感じていた。そんな彼はある日マンションを出たとたん、待ち構えていたとみられる二人の男に両脇から挟まれて、拉致されたのだ。
れない劇団員・加納慎策は、たまたま現役の総理大臣に似ていることから、前座の出し物として、総理の形態模写を演じていた。次第に彼の模写はそこそこの評判になっていったが、彼とすれば本番の出し物での出番のないことに苛立ちを感じていた。そんな彼はある日マンションを出たとたん、待ち構えていたとみられる二人の男に両脇から挟まれて、拉致されたのだ。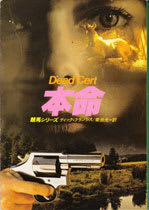
 々回コーヒーについて書いたが、忘れていたことを一つ思い出した。10月4日に行われた天羽支部会(社会福祉法人薄光会の施設利用者の保護者・家族で構成されるいくつかある団体の一つで、ケアホームの利用者の保護者・家族の会が年に数回開催する会合)の折に、以前から親しくしている薄光会役員のM.Kさんから、瓶入りのインスタントコーヒーを頂戴した。彼女は息子さんのために、薄光会の通所施設の一つである湊ひかり学園を利用した後、息子さんを豊岡光生園へと入所させた。
々回コーヒーについて書いたが、忘れていたことを一つ思い出した。10月4日に行われた天羽支部会(社会福祉法人薄光会の施設利用者の保護者・家族で構成されるいくつかある団体の一つで、ケアホームの利用者の保護者・家族の会が年に数回開催する会合)の折に、以前から親しくしている薄光会役員のM.Kさんから、瓶入りのインスタントコーヒーを頂戴した。彼女は息子さんのために、薄光会の通所施設の一つである湊ひかり学園を利用した後、息子さんを豊岡光生園へと入所させた。
 み始めると関心があるとかないとか言ったこととは関わりなく、ストーリーに引き込まれる。小説として、ミステリーとしての魅力が、ぐいぐいと物語に引き込むのだ。やはり多くの読者に迎へ入れられた作品は、競馬の好き嫌いに関係なく、面白く読ませる力がある。
み始めると関心があるとかないとか言ったこととは関わりなく、ストーリーに引き込まれる。小説として、ミステリーとしての魅力が、ぐいぐいと物語に引き込むのだ。やはり多くの読者に迎へ入れられた作品は、競馬の好き嫌いに関係なく、面白く読ませる力がある。
 NHK BSプレミアムで放送されている、「刑事フォイル」という英国のドラマでは、大戦中の英国を舞台として様々なエピソードが語られる。
NHK BSプレミアムで放送されている、「刑事フォイル」という英国のドラマでは、大戦中の英国を舞台として様々なエピソードが語られる。
 陰矢の如しなどと引き合いに出すまでもなく、毎年、月日の経つ速さを実感する季節が近づいてきた。
陰矢の如しなどと引き合いに出すまでもなく、毎年、月日の経つ速さを実感する季節が近づいてきた。 頃はあまり聞かなくなったが、シャーロキアンは今でも世界各地で、活動が活発なのだろうか?
頃はあまり聞かなくなったが、シャーロキアンは今でも世界各地で、活動が活発なのだろうか?
 010年、「このミステリーがすごい!」大賞を受賞してデビューした中山七里氏の作品は、今年までの5年間で18冊を読んだことになる。彼はこの他にも何冊かの作品を世に出しているから、その執筆活動は驚異的ともいえるだろう。
010年、「このミステリーがすごい!」大賞を受賞してデビューした中山七里氏の作品は、今年までの5年間で18冊を読んだことになる。彼はこの他にも何冊かの作品を世に出しているから、その執筆活動は驚異的ともいえるだろう。 ステリーの題材として、双生児が登場するのは古今東西変わらぬことのようだ。表紙のイラストでもわかるように、本書にも双子の美人姉妹が登場して、ミステリーの種を振りまくのだ。
ステリーの題材として、双生児が登場するのは古今東西変わらぬことのようだ。表紙のイラストでもわかるように、本書にも双子の美人姉妹が登場して、ミステリーの種を振りまくのだ。
 田よしき氏の作品はアンソロジーの短編をいくつか読んではいるが、長編は横溝正史賞を受賞した「RIKO-女神の永遠-」しか読んでいない。あまり目に留まらなかったというか、もしかしたら「RIKO-女神の永遠-」があまり印象に残っていなかったのか?
田よしき氏の作品はアンソロジーの短編をいくつか読んではいるが、長編は横溝正史賞を受賞した「RIKO-女神の永遠-」しか読んでいない。あまり目に留まらなかったというか、もしかしたら「RIKO-女神の永遠-」があまり印象に残っていなかったのか? まりいい思い出のない学校生活であったが、僕が通っていた県立大多喜高校の3年D組のクラス会(昭和33年卒業から33会と名付けている)は、今でも毎年行われており、出来るだけ参加するようにしている。
まりいい思い出のない学校生活であったが、僕が通っていた県立大多喜高校の3年D組のクラス会(昭和33年卒業から33会と名付けている)は、今でも毎年行われており、出来るだけ参加するようにしている。
 譜によれば、この作品は昭和39年(1964年)2月に塔晶夫の名で、講談社から刊行されたという。この文庫はその10年後に同社から出ているから、その間10年を要しているという勘定だ。これを買ったのはそれほど前ではないが、それでも買ってから数年は経つだろう。なんでそんなに間が空いたかと言えば、これと言って理由はない。いつもの気まぐれだ。一部のミステリーマニアの間では名作?の誉れ高いタイトルなので、いつかは読んでおこうと買っておいたのだった。
譜によれば、この作品は昭和39年(1964年)2月に塔晶夫の名で、講談社から刊行されたという。この文庫はその10年後に同社から出ているから、その間10年を要しているという勘定だ。これを買ったのはそれほど前ではないが、それでも買ってから数年は経つだろう。なんでそんなに間が空いたかと言えば、これと言って理由はない。いつもの気まぐれだ。一部のミステリーマニアの間では名作?の誉れ高いタイトルなので、いつかは読んでおこうと買っておいたのだった。 戸川乱歩氏をはじめ、古今、内外のミステリー作家や、その作品が比喩として現れるところも面白く、途中までユーモア・ミステリーかと思えるようなところもあるが、終盤に至るまでには、重厚さを表しながらミステリーとしての展開を見せ始める。
戸川乱歩氏をはじめ、古今、内外のミステリー作家や、その作品が比喩として現れるところも面白く、途中までユーモア・ミステリーかと思えるようなところもあるが、終盤に至るまでには、重厚さを表しながらミステリーとしての展開を見せ始める。
 来読んできた著者の作品とは一味違う内容だ。タイトルで分かるように、相撲の力士を題材にとっていて、一時期世間をにぎわせた八百長問題なども絡ませた、ミステリーだ。
来読んできた著者の作品とは一味違う内容だ。タイトルで分かるように、相撲の力士を題材にとっていて、一時期世間をにぎわせた八百長問題なども絡ませた、ミステリーだ。 うしたこととは別に、横尾弁護士は殺人罪で服役している滝本という男が、冤罪であることを信じて、事務所で働く小宮冬子を伴って、滝本と面会するのだが、彼はかたくなに自分がやったのだという。
うしたこととは別に、横尾弁護士は殺人罪で服役している滝本という男が、冤罪であることを信じて、事務所で働く小宮冬子を伴って、滝本と面会するのだが、彼はかたくなに自分がやったのだという。
 トーリーは2部構成で、一部で語られるエピソードの中に、後の話の重要な部分が隠されているのだ。
トーリーは2部構成で、一部で語られるエピソードの中に、後の話の重要な部分が隠されているのだ。
 雨の影響で川の氾濫による堤防決壊が、大きな被害をもたらした茨城県、宮城県、あるいは栃木県など、被災者の皆さんに心からお見舞い申し上げます。日がたつとともに東日本大震災を彷彿させる被害の状況が明らかになって、一日も早い復興を望むばかりだ。
雨の影響で川の氾濫による堤防決壊が、大きな被害をもたらした茨城県、宮城県、あるいは栃木県など、被災者の皆さんに心からお見舞い申し上げます。日がたつとともに東日本大震災を彷彿させる被害の状況が明らかになって、一日も早い復興を望むばかりだ。 の作品では、SFのようにタイム・スリップとかタイム・トラベルの話ではないのだが、僕がそういう感覚を覚えたということである。
の作品では、SFのようにタイム・スリップとかタイム・トラベルの話ではないのだが、僕がそういう感覚を覚えたということである。
 つの台風による雨風の被害が、関東・東北に甚大な被害をもたらした。テレビの画像が被害の痛ましさを何度も流して、心が痛む。被害を受けた地方の方々には心からお見舞いを申し上げたい。当地方では何日が続いた涼しい日がおわり、再び夏が戻ってきたようだ。朝から暑い日差しが降り注いでいる。
つの台風による雨風の被害が、関東・東北に甚大な被害をもたらした。テレビの画像が被害の痛ましさを何度も流して、心が痛む。被害を受けた地方の方々には心からお見舞いを申し上げたい。当地方では何日が続いた涼しい日がおわり、再び夏が戻ってきたようだ。朝から暑い日差しが降り注いでいる。 くからパソコンに携わってきた僕を、こうしたストーリーは興奮させるに十分だ。
くからパソコンに携わってきた僕を、こうしたストーリーは興奮させるに十分だ。
 ビュー作の「六番目の小夜子」を始めとして、不思議な感覚をもたらす環境設定は、著者の独特の感性によって紡ぎだされる物語舞台だ。好きな作家のストーリーが好みの展開を見せて進むとき、僕が幸せを感じる時なのだ。
ビュー作の「六番目の小夜子」を始めとして、不思議な感覚をもたらす環境設定は、著者の独特の感性によって紡ぎだされる物語舞台だ。好きな作家のストーリーが好みの展開を見せて進むとき、僕が幸せを感じる時なのだ。
 はいっても問題が発生した、あるいはトラブルが起こったような場合は、医療機関を訪れて保険者の病状を確認したりすることも業務の一部となる。
はいっても問題が発生した、あるいはトラブルが起こったような場合は、医療機関を訪れて保険者の病状を確認したりすることも業務の一部となる。