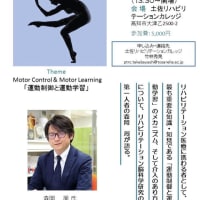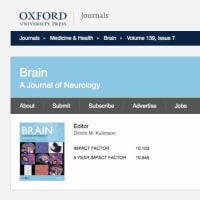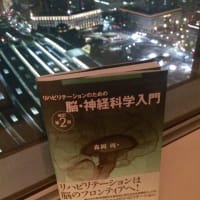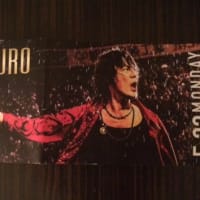昨日は13時より21時まで大学院の中間発表会でした.
実に8時間連続であり,事務が鬼に見えましたが,
院生,教授陣もよく耐えました.
金子研究科長,森研究所長,
そして,学者として尊敬しています山本教授,坂田教授もほぼ全部いていただき,
時には厳しい意見をいただき,院生も感謝している次第です.
ほほえましかったのは,いろんな意見をすべて受容せずに,
自分の研究の意図を主張する点が数名の院生でいましたので,
それがうれしかったです.
それは単にわがままな主張でなく,
そこで意見を出し合うことで新たな発見がある場合があるのです.
畿央大学は私立大学で,知名度も大きくはないのですが,
こうした教授陣がいることで,ソフトの充実さがあるため,
有意義な研究生活がおくれると思います.
あとは現役教授陣,准教授陣が管理や授業だけに忙殺されず,
世界に発信できる研究をし続けることが,
院生の研究水準を上げるのだと思います.
院生の研究はまだ粗削りですが,
削りようによっては,国際ジャーナルに十分通用する研究がいくつもありました.
ただ残念なのは,意義を自分自身が見いだせていない点です.
ただデータをとっているという感もみえたので,
何のためにやっているのか,
そして自らの研究のリミテーションは,
そのようなことを意識しながら,プレゼンしているものと,
そうでないものがいて,ここに差を感じました.
進捗状況には一長一短あれど,
そこに冷静さをもっていないといけません.
情熱も大事ですが,研究者としてもっとも重要なのは,
冷静さです.
そして,自らの観察眼にバイアスをもたないことです.
メソドロジーに没頭しているセラピストは,知らないうちにバイアスがかっています.
それが時に自らの科学心に潜在的に邪魔しているときが多々あります.
あとは,先行研究では,と,先行研究から考察している場合がほとんどで,
それもしないといけないのですが,
自前のデータですべてが説明できるよう,
自分のデータから言えることを探し続ける方が重要です.
所詮,先行研究との文献考察は「こじつけ」です.
これは症例報告も同じで,
ほとんどの症例報告は,その症例の現象と現象の考察でなく,
基礎実験との照合で,知らぬ前にこじつけをしています.
だから,どのような症例であっても最終的には考察が一緒になってしまうのです.
これは大きな問題です.
科学的とは程遠く,結果よりも解釈を優先してしまう脳です.
文献で頭でっかちになると,そのきらいが強く出ます.
実験の場合は,自分のデータをくまなく見る.
それにつきます.
魚でいうと骨の髄までしゃぶる,という感じです.
まだ自分のデータに身がいっぱい残っている状態です.
理学療法士や作業療法士はこのデータを隅々まで眺めるというプロセスが,
どこかで欠陥があるように思えます.
これが業界全体に蔓延していつように感じます.
学会が議論にならないのも,文献考察ばかりだからのようにも思えてきます.
ただ,理念で考察していないので,そこは救いです.
他の医療職の学会に昔は出たりした時もあるのですが,
ここではいえませんが,閉口してしまうものはいっぱいあります.
理念は自分の研究室まででとどめ,
議論は冷静に進めていく,これが鉄則です.
情熱は自分の心にとどめ,公には冷静に展開する.
クールなヘッドが研究者には必要なのです.
しかし,ここ数日は,この発表に間に合わすために,
時には怒号もとび,時には椅子を蹴り飛ばし,時には机をたたき,
院生も負の情動が多々,生まれたと思いますが,
何はともあれ,無事に終了し,まずまずの評価であったと思います.
喜びは苦しさに比例して得られると思います.
苦しさで逃げるか逃げないか,
すなわち,それを認知せず,逃げるか接近するかで接してしまうと,
爬虫類脳でしかないのです.
研究を不快と思うのも快と思うのも,
ある心の持ち得ようで変化します.
いやな仕事が「美しく」なることはありません.
原点は,それを愛することです.
私は院生の研究の現状レベルでも満足していません.
国際的に活躍できるように,そしてリハビリテーション領域だけでなく,
他の基礎科学と対等,それ以上に研究室のメンバーが研究展開できる,
そのようなレベルを前向きに意識しています.
今年度入試もすぐそこです.
そうした院生が数多く入り,研究室の垣根を越え,研究が展開できていくことが,
最終的には畿央大学が生き残る戦略になると思っています.
ブランドなき,大学は消滅していく運命です.
これは病院,そしてリハビリテーション科にもいえると思います.
自分たちのブランドを作る,これが認知されていく手続きなのです.
最終的には自分自身がブランド商品になっていかないといけません.
明治製菓のお菓子みたいなものなのです.
おかげさまで,大学院全体では前期入試の出願も好調なようです.
実に8時間連続であり,事務が鬼に見えましたが,
院生,教授陣もよく耐えました.
金子研究科長,森研究所長,
そして,学者として尊敬しています山本教授,坂田教授もほぼ全部いていただき,
時には厳しい意見をいただき,院生も感謝している次第です.
ほほえましかったのは,いろんな意見をすべて受容せずに,
自分の研究の意図を主張する点が数名の院生でいましたので,
それがうれしかったです.
それは単にわがままな主張でなく,
そこで意見を出し合うことで新たな発見がある場合があるのです.
畿央大学は私立大学で,知名度も大きくはないのですが,
こうした教授陣がいることで,ソフトの充実さがあるため,
有意義な研究生活がおくれると思います.
あとは現役教授陣,准教授陣が管理や授業だけに忙殺されず,
世界に発信できる研究をし続けることが,
院生の研究水準を上げるのだと思います.
院生の研究はまだ粗削りですが,
削りようによっては,国際ジャーナルに十分通用する研究がいくつもありました.
ただ残念なのは,意義を自分自身が見いだせていない点です.
ただデータをとっているという感もみえたので,
何のためにやっているのか,
そして自らの研究のリミテーションは,
そのようなことを意識しながら,プレゼンしているものと,
そうでないものがいて,ここに差を感じました.
進捗状況には一長一短あれど,
そこに冷静さをもっていないといけません.
情熱も大事ですが,研究者としてもっとも重要なのは,
冷静さです.
そして,自らの観察眼にバイアスをもたないことです.
メソドロジーに没頭しているセラピストは,知らないうちにバイアスがかっています.
それが時に自らの科学心に潜在的に邪魔しているときが多々あります.
あとは,先行研究では,と,先行研究から考察している場合がほとんどで,
それもしないといけないのですが,
自前のデータですべてが説明できるよう,
自分のデータから言えることを探し続ける方が重要です.
所詮,先行研究との文献考察は「こじつけ」です.
これは症例報告も同じで,
ほとんどの症例報告は,その症例の現象と現象の考察でなく,
基礎実験との照合で,知らぬ前にこじつけをしています.
だから,どのような症例であっても最終的には考察が一緒になってしまうのです.
これは大きな問題です.
科学的とは程遠く,結果よりも解釈を優先してしまう脳です.
文献で頭でっかちになると,そのきらいが強く出ます.
実験の場合は,自分のデータをくまなく見る.
それにつきます.
魚でいうと骨の髄までしゃぶる,という感じです.
まだ自分のデータに身がいっぱい残っている状態です.
理学療法士や作業療法士はこのデータを隅々まで眺めるというプロセスが,
どこかで欠陥があるように思えます.
これが業界全体に蔓延していつように感じます.
学会が議論にならないのも,文献考察ばかりだからのようにも思えてきます.
ただ,理念で考察していないので,そこは救いです.
他の医療職の学会に昔は出たりした時もあるのですが,
ここではいえませんが,閉口してしまうものはいっぱいあります.
理念は自分の研究室まででとどめ,
議論は冷静に進めていく,これが鉄則です.
情熱は自分の心にとどめ,公には冷静に展開する.
クールなヘッドが研究者には必要なのです.
しかし,ここ数日は,この発表に間に合わすために,
時には怒号もとび,時には椅子を蹴り飛ばし,時には机をたたき,
院生も負の情動が多々,生まれたと思いますが,
何はともあれ,無事に終了し,まずまずの評価であったと思います.
喜びは苦しさに比例して得られると思います.
苦しさで逃げるか逃げないか,
すなわち,それを認知せず,逃げるか接近するかで接してしまうと,
爬虫類脳でしかないのです.
研究を不快と思うのも快と思うのも,
ある心の持ち得ようで変化します.
いやな仕事が「美しく」なることはありません.
原点は,それを愛することです.
私は院生の研究の現状レベルでも満足していません.
国際的に活躍できるように,そしてリハビリテーション領域だけでなく,
他の基礎科学と対等,それ以上に研究室のメンバーが研究展開できる,
そのようなレベルを前向きに意識しています.
今年度入試もすぐそこです.
そうした院生が数多く入り,研究室の垣根を越え,研究が展開できていくことが,
最終的には畿央大学が生き残る戦略になると思っています.
ブランドなき,大学は消滅していく運命です.
これは病院,そしてリハビリテーション科にもいえると思います.
自分たちのブランドを作る,これが認知されていく手続きなのです.
最終的には自分自身がブランド商品になっていかないといけません.
明治製菓のお菓子みたいなものなのです.
おかげさまで,大学院全体では前期入試の出願も好調なようです.