
(つづき)
30日の記事ということで福岡市早良区の「三十田橋」(さんじゅうだばし)を取り上げてみる。
「三十田橋」バス停は、「橋」を挟んで北側に上り(写真)、南側に下りのバス停があり、両者はやや距離が離れている。
下りバス停は地下鉄七隈線「賀茂駅」に距離的に近いことから、駅の最寄バス停として扱われているが、上りバス停まではやや距離がある。
そこで、七隈線開業時に上りのみ「次郎丸中学校前」のバス停が新設され、上りについてはこちらが駅への最寄バス停となった。
このため、地下鉄賀茂駅への最寄バス停は、上りと下りでは異なるという状態になっており、「地下鉄開業は我々とは全く関係ない話なので、従来の枠組みは変えませんよ」とでも言っている感じである。
本来なら、上りの「次郎丸中学校前」と下りの「三十田橋」を、それぞれ「賀茂駅入口」などに改称するのがスマートのような気がするのだが…。
なお、「三十田橋」の南に位置する「田隈新町」についても、上りのみ「田隈新町第二」というバス停が存在する。
この付近は、上りと下りでは停車停留所数が2つも違う(上りのほうが2つ多い)という事態が生じている。
田隈新町交差点北側に、上りのみ存在する「田隈新町第二」は、もともとは「本家」の「田隈新町」であった。
「209番」が運行を開始した際、田隈新町交差点の南側に、「田隈新町」の「209番」上り専用乗り場ができ、その後そのバス停に「209番」だけでなく「2番」「201番」なども停車するようになった。
その際、交差点南側の乗り場が「本家」の「田隈新町」となり、北側の乗り場は「田隈新町高石公園前」という「分家」扱いとなり、その後「田隈新町第二」に改称され現在に至っている。
私が幼い頃は、この「三十田橋」バス停がある三十田橋北詰交差点~講倫館南口(かつての西高南口)交差点間の道路はまだなく、今から30年くらい前に、暫定供用の砂利道を車で通った記憶がある。
道路供用開始後は、まず「2番」の田隈経由がここを通るようになった(1980年頃ではないかと思う)。
路線開通前、この「三十田橋」や「平田」のバス停に黒ビニールがかかっているのをワクワクしながら見に行った思い出がある。
なお、その後しばらくして、「三十田橋」バス停が電照式となり、はじめて英字表記が付いた際には「MITODABASHI」と表示されていた。
小さな頃からこういう例をいろいろと目にしてきたので、西鉄のバス停の英字表記に対して、「間違っていて当たり前」「正しい表記を期待するのは酷」という寛容さ(?)が自然と身についてきたのかもしれない(笑)。
(つづく)
30日の記事ということで福岡市早良区の「三十田橋」(さんじゅうだばし)を取り上げてみる。
「三十田橋」バス停は、「橋」を挟んで北側に上り(写真)、南側に下りのバス停があり、両者はやや距離が離れている。
下りバス停は地下鉄七隈線「賀茂駅」に距離的に近いことから、駅の最寄バス停として扱われているが、上りバス停まではやや距離がある。
そこで、七隈線開業時に上りのみ「次郎丸中学校前」のバス停が新設され、上りについてはこちらが駅への最寄バス停となった。
このため、地下鉄賀茂駅への最寄バス停は、上りと下りでは異なるという状態になっており、「地下鉄開業は我々とは全く関係ない話なので、従来の枠組みは変えませんよ」とでも言っている感じである。
本来なら、上りの「次郎丸中学校前」と下りの「三十田橋」を、それぞれ「賀茂駅入口」などに改称するのがスマートのような気がするのだが…。
なお、「三十田橋」の南に位置する「田隈新町」についても、上りのみ「田隈新町第二」というバス停が存在する。
この付近は、上りと下りでは停車停留所数が2つも違う(上りのほうが2つ多い)という事態が生じている。
田隈新町交差点北側に、上りのみ存在する「田隈新町第二」は、もともとは「本家」の「田隈新町」であった。
「209番」が運行を開始した際、田隈新町交差点の南側に、「田隈新町」の「209番」上り専用乗り場ができ、その後そのバス停に「209番」だけでなく「2番」「201番」なども停車するようになった。
その際、交差点南側の乗り場が「本家」の「田隈新町」となり、北側の乗り場は「田隈新町高石公園前」という「分家」扱いとなり、その後「田隈新町第二」に改称され現在に至っている。
私が幼い頃は、この「三十田橋」バス停がある三十田橋北詰交差点~講倫館南口(かつての西高南口)交差点間の道路はまだなく、今から30年くらい前に、暫定供用の砂利道を車で通った記憶がある。
道路供用開始後は、まず「2番」の田隈経由がここを通るようになった(1980年頃ではないかと思う)。
路線開通前、この「三十田橋」や「平田」のバス停に黒ビニールがかかっているのをワクワクしながら見に行った思い出がある。
なお、その後しばらくして、「三十田橋」バス停が電照式となり、はじめて英字表記が付いた際には「MITODABASHI」と表示されていた。
小さな頃からこういう例をいろいろと目にしてきたので、西鉄のバス停の英字表記に対して、「間違っていて当たり前」「正しい表記を期待するのは酷」という寛容さ(?)が自然と身についてきたのかもしれない(笑)。
(つづく)










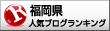





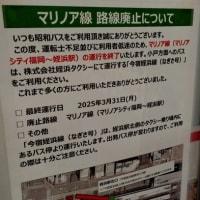















































また、公式時刻表では読みもあまり信用できませんね。碓井交番の読みが「うすいゆうびんきょく」らしいですので(^_^;)
果たして本当に通勤利用者はそういう形態を求めているのでしょうか?
確かに、朝の方が混雑が激しいので、そういうのも良く分かりますが…
まだ子どもだった頃、中学生くらいのことか。
「五十川は、『ごじっかわ』って読むったいねぇ、知らんやった~!」と父に言ったところ、父は、
「当たり前たい!『いそがわ』とでも思うとったとか?」と言われてしまいました。
思い込みは、困ったものです。そんな時、バス停にふり仮名またはローマ字がついていると助かります。しかしそれまでも間違っていると、何が正しいのか、わからなくなってしまいます。
ところで、「五十川」バス停にローマ字表記があったとして、どう表記されているのか、気になってしまいます。
最も正しいのは、「Gojikkawa」でしょうねぇ。
「Gojukkawa」となっているとすると、カナの促音表記を誤っていることになると思いますし、もしも「Gojyukkawa」となっているとすると、カナ表記に加えて、ローマ字のヘボン式表記も間違っていることになります。
>また、公式時刻表では読みもあまり信用できませんね。碓井交番の読みが「うすいゆうびんきょく」らしいですので(^_^;)
たしかに。
サイトの検索に表示されるものが正式、と思いたいところですが、実際には「本当にそうか?」という例も多いですね。
濁点を付けるか付けないか、入口か口か、前を付けるか付けないか…など。
それまで紙ベースで管理していたものをコンピュータのデータに移管する際に、いろんな漏れや付け足しが起こったのかもしれませんね。
都市高502さん、こんにちは。
>上りと下りで停留所数が違うというのは、朝の上りが本数が多く、なおかつ快速・急行も朝の上りしか運行されないものが多いというのと同じく、「上りの方を速達性を高める」という思想に基づいているのだと思います。
なるほど、そういう解釈もできるのかもしれませんね。
私は「たまたまそうなっただけ」と思っておりました(笑)。
明治通りだと逆に下りのほうが停留所が多いですね(荒戸一丁目と西新一丁目)。
Tokyo Chikushiさん、こんにちは。
たしかに、耳で読みを実際に確認しないと、「思い込み」で勝手に決めつけてしまうケースが多くなりますね。
ちなみに私は、少し前まで「ごじっかわ」ではなく「ごじゅっかわ」だと思っていました(今でも頭の中では「ごじゅっかわ」と認識している気がします)。
他にも京阪電鉄には「樟葉(くずは)」という駅がありますけど、この周囲には樟葉と楠葉と両方の名前が付く小学校や中学校が点在していますし、佐賀県の江北町にも八丁(はっちょう)というバス停がありますが、あの辺の住所は「八町」だったりします。
福岡でも、…簑島と美野島、唐人と当仁、草香江と草ケ江、筥崎と箱崎、苅屋と仮屋など、そういう例は結構ありますね。
古い地名はもともとは「音」のほうが優位であり、その後に「字」をあてたというパターンが多いため、いろんな表記が出てくるのは自然の流れなのでしょうが、駅や施設名でいろんな表記が使われていると、混乱のもとにはなりますね。
ただ、いろんな表記があること、それ自体が「文化」(分化?)なのかもしれませんが。