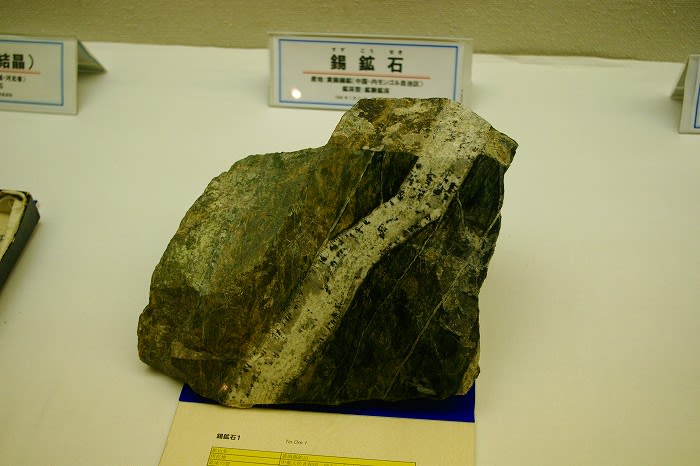水神の碑から上流へ行きます。

乙女月の県道横に、がっくい井戸があります。

がっくい井戸。昔、殿様が休んだ時、乙女が汲んだ井戸水があまりにもおいしく、殿様は満足したそうです。

そば茶屋「吹上庵」から川のほうへ行くと、大蛇ケ淵の看板があります。ここから川へ下りますが、最近通る人はいないようで、道は荒れています。
男岩・女岩に参拝すると子宝に恵まれるそうです。

男岩と大蛇ケ淵が見えてきました。

大蛇ケ淵。大蛇が住むという伝説があるそうです。

右岸にそびえるのが男岩です。

男岩の向かいにある岩。これが女岩でしょうか。

それとも、男岩の下流右岸にあるこの岩が女岩でしょうか。

新赤仁田橋から上流を望む。

前の写真の旧道の橋から上流を望む。稲刈り作業中でした。

さらに上流へ行くと、ボックスの橋があります。

前の橋から上流を望む。

さらに進むと、棚田があります。伊作川は棚田の向こうを流れています。

上の道から上与倉の棚田を見たものです。棚田の上流の谷が伊作川源流です。
下の道へ下ります。

下から見た上与倉の棚田。

さらに進んだところから見る。

棚田の横を流れる伊作川。

最上段の棚田を横から見たものです。

上から見た棚田。

棚田の少し上流の伊作川です。
これ以上遡上するのが難しくなりました。伊作川源流の旅はここまでとします。