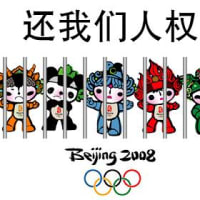秦暉:『田園詩と狂詩曲』(パストラルとラプソディー)韓国語版序文(2000年)
我あるが故に我思う、そこに「問題」あり。我思う故に我あり、そこに「主義」あり。「五四」運動以降ずっと中国知識人は「主義」と「問題」の二つを苦労して探求してきた。「五四」運動自体は、大きくて意味不明な概念の「文化」運動というよりは、(知識人を代表とする)中国人が率直に「主義」を語り、「問題」を直視した運動だったというべきだろう。当時胡適と李大の間に「問題」か、それとも「主義」かの論争があったが、実際は、胡、李を含めた「五四」エリートの大部分が「主義」も語り、「問題」も語っていた。違いは「主義」が同じでないことと、「問題」に対する認識と回答が同じでないことだけだった。
80年が経過し、世紀の移り変わり、ミレニアムの中国は依然として大変革のさなかにあり、やはり率直に「主義」を語り、「問題」を直視する精神が必要とされている。確かに「問題」を避けた「主義」の説教は空疎な学問であり、「主義」を欠いた「問題」研究は贅言の学問と言うべきだろう。空疎な学問と贅言の学問は今後もこれまで同様存在し続けるだろうが、空疎化と贅言化を抜け出す「問題と主義」の討論は疑いもなく中国思想界の希望である。
私は15歳の時に文革で学業を離れ、農村に「下放」され9年間農民をした。その「早稲田大学」(日本の大学と混同しないように!)で、私は「農民学」との縁ができた。24歳の時「早稲田」から田植えをしない大学に研究生として編入したときに、「土地制度と農民戦争史」を研究方向と定めてから、農民問題はずっと私の関心の中心である。理論と実践の探求によって私は、中国のいわゆる農民問題は過去も現在もpeasants(農民)問題であり、farmers(農業経営者)問題ではないことを知った。それはずっと、単に農耕者に関わるだけでなく、本質的には「早稲田」の中の問題でもなかった。とりわけ1949年以降、中国は僅かに存在したcitizen(市民)も徐々に消滅させられ、「都会人」は「田舎の人」よりさらにpeasantization(農民化)(もしくはnon-citizenization(非市民化))した。そのため1978年以降もやはり田舎の人が都会人にどうやってcitizenになるかを教えていた――少なくとも経済的にはそうだった〔農村からの収奪による都市の育成を言っている〕。
9年の農業生活で私は農村と密接な関係を結び、多くの農民の友達ができて、農耕者の問題は「彼らの問題」ではなく私自身の問題となった。そのため狭義の農民問題研究、過去の農民戦争史や土地制度史、農業経済学や農村社会学から今の改革の中で直面しているいわゆる三農(農業・農村・農民)問題まで、どれも私は注目してきた。だが、これらの狭義の農民学研究のほかに、peasantology(農民学)にはより広義な内容がある。すなわち農民国家・農業文明・伝統社会の研究であり、とりわけそれらの改革と近代化、すなわちいかに市民国家・工業文明・現代社会に転換するかの研究である。それが関係するのは決して農耕者のいわゆる「三農」問題だけではない。9年間の農村生活で私は農耕者の感情を持つようになったが、それだからといって私は毛沢東が言ったように都会人は農民の「再教育」を受けることが「非常に必要である」とは感じなかったし、「深刻な問題は農民教育だ」(これも毛の言葉)などとはさらさら信じられなかった。それが私に感じさせたのは都会人と農民が同じように不自由であり、同様に「共同体の付属物」だということだった。もし両者に違いがあるとしても、それは都会人が田舎の人より共同体の保護をより多く受けていること(「三年困難時期」〔1959年~61年、大躍進政策がもたらした大飢饉〕に餓死したのは田舎の人だけだった。私達都会人の「上山下郷」は一種の不幸とみなされたが、いわゆる「下放青年待遇」を受けられたので村民の羨望の対象だった)、そしてより多く共同体の束縛(政治的統制から「単位」〔配属機関:役所や会社などで、生活のすべてを管理した〕の制約、私達の選択の余地のない「生産隊への編入」を含めて。)を受けていることだけである。だから共同体の束縛から自由になった改革時代には、田舎の人はより簡単に束縛を脱し、「保護」を失うコストもより少なかった。
だが煎じつめると、改革は私たちの都市と農村の社会にいずれにとっても再編である。都市と農村の人々はみな改革の中でpeasantsからcitizenになる。すなわち従属的な共同体構成員から個性ある自由人になる過程である。よって現代中国では、狭義の農民学と広義の農民学の結合は極めて重要な意義がある。もしすでにpeasantsがおらずfarmersだけの先進国なら、人々は農場の最適規模を中心概念としてミクロ農業経済学を構築し、農産物の価格=供給反応を中心概念としてマクロ農業経済学を構築できる。だが私たちのところでは農業について語る「農業経済学」はあまり意義がない。前近代の中国では、専制国家と社会の矛盾は一貫して農村内部の地主小作、貧富の矛盾より重要だった(多く発生した「農民戦争」はその全てが反役人反朝廷であり、反地主ではなかった)。
今日の中国ではまた「農民に問題はあるが、それは『農民問題』ではない」という説がある。私は以前「中国問題の実質は農民問題」だと言ったが、これはむしろ逆転させて、農民問題の実質は中国問題だというべきである。要するに、今日の農民研究は狭義の農民学と広義の農民学を結合しなければならない。狭義の農民学は農耕者すなわち「農」を生業とする「民」に関連する人文社会問題、例えば土地制度・農民運動・農村社会・コミュニティ組織・農民負担・農村文化・農民人口移動などに注目するものであり、広義の農民学は伝統社会・前工業社会・前近代社会・前市民社会ないし未開発社会(以前よく「封建社会」と言われたがこの言葉は正確ではない)の理論、とりわけその種の社会の近代化の理論を研究するものである。その種の社会は通常農業を主とするが、その基本的特徴はその職業性にあるのではなく、その問題も農耕者の問題に限られるものではない。言い換えれば、狭義の農民学は一種の「問題」の学であり、広義の農民学は一種の「主義」の学である。前者が欠ければ、農民研究は空疎に流れ、後者が欠ければ、農民研究は贅言に流れる。
私は「問題」と「主義」の結合、狭義の農民学と広義の農民学の結合という意図をもって本書を書いた。本書の前半は「関中モデル」〔関中とは陝西省秦嶺北麓の渭河沖積平野地域〕の研究で「問題」の検討と実証に重点をおき、後半は「前近代社会」の研究で理論もしくは「主義」に重点を置いている。原書は1988年に書き、当時私は陝西師範大学で教べんをとっていたので、本書の「問題」は「関中モデル」からとっており、「主義」は80年代の新啓蒙運動の特徴を帯びている。だが、1989年の中国の政治文化気候の急変〔天安門事件を指す〕で出版社がすでに印刷に付していた本書の出版を取り下げてしまった。そして、1996年にわたしが北京の清華大学に転じてから私が編集責任者となった『農民学双書』の1冊としてやっと北京で出版することができた。私が本書を書いた80年代後期の「問題」と「主義」に対する見方は今でも成り立っている。
また、私が最近新たに展開している観点は以下の数点である。伝統社会の共同体本位という基本的特徴に加えて、中国の伝統の大共同体本位と西側の小共同体本位の違いを指摘した。西側は近代化の初期に「市民と王権の同盟」すなわち個人と大共同体が連携してまず小共同体の人権に対する桎梏を打破する段階を経験した。一方中国のこの段階は個人と小共同体の同盟の代わりに、まず大共同体の束縛を打破した。近代中国農村の多くの現象、末期清朝の宗族自治から現代の郷鎮企業まで、このように解釈する方が、簡単に「封建の氾濫」とけなしたり「伝統の活力」とほめあげたりするより合理的である。90年代、「保守的文化決定論」が「批判的文化決定論」に取って代わり一時流行したが、私はそのどちらも拒絶し、「文化決定論の貧困」を指摘し、価値観の上での普遍主義と進歩主義、歴史観の上での非決定論(歴史決定論にも文化決定論にも反対)を主張し、「自分で自分に責任を持つ歴史観」を提示した。
私はかつて伝統共同体を解消し個性化した市民社会を確立する改革のプロセスを古い大家族の「分家」に喩えたことがある。その場合「分家すべきかどうか」は重要問題であるが、分家が完了してから新しい自由な小家族が直面する冷淡・孤立・危険などもまた重要な問題である。だがこの両者の間では、「どう分家するか」・どのように公平に分家するかこそが最も重要な問題である。なぜなら経済が私たちに示すのは、私たちに古い大家族が危機に陥った時最も起こりそうな矛盾とは分家するかどうかではなく、どう分家するかの争いだからだ。それは分家の過程でもめるかどうかにかかわるだけでなく、分家後に一体どうなるかにもかかわる。公平な分家の後に「実の兄弟も、明朗会計」の良性パターン・理性的な取引の中でむつまじい関係を維持するのか、それとも分家が不公正であったために禍根を残し、その後際限のない紛争が続き「分家後の問題」をいっそう深刻にするのか? さらにそれはすでに問題でなくなったはずの「分家すべきかどうかの争い」が再び問題になる事態も引き起こすかもしれない。不公正な分家に怒った人々が再び新しい大家長を求め、混乱の中で旧式の大家族を再建し、再び苦しい歴史のサイクルを繰り返すのではないか?
だから、「どう分家するか」もしくは分家における公正の問題は極めて重要である。それは分家過程自体についてだけでなく、我が国と人類が六道輪廻の悪循環を抜け出して、新しいミレニアムに新しい文明を築けるかどうかに関わってくる。古い家父長制の弊害を除去したいと心から願う全ての人、新しい現代病を本当に憂うる全ての人は、必ずそれを直視しなければならない。残念なことにいま本当に「どう分家するか」という問題を直視している人は多くない。その原因はたぶん、第一に、「どう分家するか」という問題は非常に具体的で、「分家すべきか否か」という類の問題のように形而上で「理論的」でないからだろう。第二に、この問題を語ることが歓迎されないのだろう。「家産」を盗み侵奪した人はもちろん「公平な分家」を議論するのを嫌がるし、しかも彼らは家の中で最も勢力の強い人々だから、彼らを怒らせたら自分たちの身が危なくなる。外の人は「分家」後の新しい世帯主と商売をしたいだけなので、ほとんど誰も「分家」の公平さに興味を示さない。また外の人は長いこと新しい小家族で暮らしていてその冷たさと孤独に嫌気がさしているので、同じような不満を聞くことは好きだが、「分家の不公正」の苦しみは理解できない。そこでこの国の人たちは二つのことに没頭する。どんな結果になるか構わず分家の利点を並べたて、実施的な「家産」の窃盗や侵奪にまで正当化の理由を提供すること、そして、ひたすら新しい自由な小家族の冷たさと孤独を攻撃し、実質的には古い大家長を称揚することである。そして往々にして家産侵奪者と古い大家長は同一人物なので、私たちはその二つの声を合わせた「左右同源」の声を聞く。
その議論に全く道理がないとは言えない。たしかに分家の利点と小家族の冷たさや孤独はどちらも事実である。だが「どう分家するか」を離れた選択により、それらの議論の価値は少なくとも大幅に値引きされる。そこで「公平な分家」すなわち公正な改革の呼びかけが私が関心を寄せる中心問題となる。1989年にさかのぼるが、私が本を書いた時――その頃はまだ「分家すべきかどうかの争い」が本当の中心問題だった――私たちは歴史上の「アテネ路線」と「マケドニア路線」、「アメリカ路線」と「プロイセン路線」の研究の中で「改革路線の選択は改革の是非の争いよりも重要である」という命題を提出した。1992年私たちは公正な改革を呼びかけ、「管理人の共有財産不正配分」を防止しなければならないし、「管理人の共有財産侵奪」はなおさら許されるべきことではないと訴えた。1994年から私は続けて5回「公正の至上」を論じる文章を書いた。そして歴史事例と現実問題の分析という二つの角度から現代化・改革の中の公正の問題の各領域での現れを検討した。それには農村、農民問題も含まれる。
1997年末に「自由主義と新左派」の争いが国内で「水面に浮かび上がった」。実際はそれ以前からこの種の論争は海外ですでに始まっており、国内では「問題」の争いという形で「水面」下で行われていた。私はどちらにも参加した。私は80年代の「文化ブーム」から90年代の「主義ブーム」で思想解放が一歩前進したと考える。「文化ブーム」のとこはまだ「問題」を直視し、「主義」を率直に語る雰囲気はなかった。当時人々は「文化討論」の形式で隠喩的に思想を戦わすしかなく、何でも孔子や「文化的伝統」に結び付けて、本来明晰に伝えることのできる問題を訳の分からないおしゃべりにしてしまっていた。今「主義」を議論する空間があることは、大進歩だ。だが足りないのは、今は「問題」のタブーが「主義」のタブーより多い――これは「どう分家するか」が「分家すべきかどうか」より突出しており、利益衝突が「信念の衝突」より突出しているという社会動向の思想界における反映である――ことでこの「主義」の議論がかなりの程度「思想資源」のレベルに留まってしまっていることだ。一方はハイエク、ロナルド・コース、もう一方は「ポスト学」、「ネオマルクス主義」と、まるで外国人の論争のようだ。「資源」の争いは確かに大いに意義があるが、もし現実の「問題意識」から離れたら、「資源」はむしろ「思想」を覆い隠してしまうだろう。なぜならどんなに深刻な「主義」も現実の「問題意識」から離れて学術伝承の脈絡の中だけで発展することはできないからだ。
ある人はハイエクとミュルダールの思想は調和しないと考えている。だがある種の「問題」の前で、ハイエクとミュルダールばかりか、同じく極端な自由主義の名声をもつハイエクとミーゼスでさえ調和しない。だが別の「問題」の前では、ハイエクとミュルダールと言わず、ハイエクとマルクスでさえ同じ立場に立っている――現在の我が国にハイエクの理念から容認し得ないだけでなく、マルクスの理念によっても容認し得ないことは少なくないでしょう? 帝政ロシアの一時期、社会民主派(マルクス主義者)は「アメリカ路線」を追求し、自由主義派は「合法的マルクス主義者」を自称した。そしてこの両者と寡頭主義、ナロードニキ主義〔もしくは人民主義〕との闘争こそが水と油の闘いだった。だが後のストルイピン時代には、一部の社会民主派がナロードニキ化し、一部の自由主義派は寡頭主義化して、両者の衝突が先鋭化して寡頭主義とナロードニキ主義の風潮は日増しに盛んになった。そしてついに「不公正な分家」に根差す社会不安から自由主義と社会民主主義は共倒れになり、むしろナロードニキ主義と寡頭主義が最も極端な形で結びついてロシアを長い夜に引き込んだ。
今日の中国の「主義ブーム」の中で当時の歴史を回顧するとき、学ぶべき教訓は多い。今日の「主義ブーム」の各アクターはみな現代の西側から「思想資源」と記号資源を汲み取っているが、自由秩序が確立して久しい西側に比し、いま私たちが直面している「問題状況」は実は自由秩序が確立する前の帝政ロシアにむしろ近い。そのような状況下では、自由の欠乏は社会民主が多すぎるからではなく、社会民主の欠乏も自由が多すぎるからではない。だから当時の社会民主派は自由競争の民主国家である「アメリカ路線」に憧れ、ビスマルク式の社会保障制度を持つ独裁国家である「プロイセン路線」を敵視したのだった。そして自由主義反対派はむしろ積極的な自由の視点からマルクスを称賛し、トーリー党〔イギリスの保守党〕式の(エドマンド・バーク式ではない)保守主義に反対した。似たように、中国の現実の「問題状況」を見れば、私たちには現在自由主義が多すぎるわけでも社会民主主義が多すぎるわけでもなく、寡頭主義とポピュリズム〔もしくは人民主義〕が多すぎるのだ。だから自由主義の立場から出発して寡頭主義を批判し、社会民主主義の立場から出発してポピュリズムを批判することは、どちらも非常に必要なことだ。私はまさに同時に「二つの戦線」で「主義の争い」に参加している。
こう聞く人もいるだろう「君は一体自由主義の立場に立っているのかね、それとも社会民主主義の立場かね?」。私の答えは、自由秩序が構築される前はこの二つの立場の価値観の重なる部分は非常に広く、自由秩序の構築に伴い両者の価値の重なり面が縮小してゆき価値観の対立が目立ってくるにすぎないということだ(だが現代国家ではこの両者はまた重なりつつある)。だから中国の現在の「問題」背景の下では、私が堅持するのは自由主義と社会民主主義のどちらもが肯定する価値であり、反対するのは自由主義と社会民主主義がともに否定する価値である。自由主義が肯定し社会主義が否定するようなもの(例えば「純粋市場経済」)、および自由主義が否定し社会民主主義が肯定するもの(例えば「強大すぎる」労働組合)は私たちの中国にはどちらもまだ存在しない。それらが存在するようになってから自分の立場を選択しても遅くはない。
私のこの態度はいわゆる「第三の道」だろうか? そうかもしれないが、「第一と第二の道の重なり」(二つの道の中間でもなく、二つの道以外でもない)という方が正確であろう。いずれにせよ、中国の現在の問題は「自由が多すぎて平等を妨げている」のでもなければ「平等が多すぎて自由を妨げている」のでもない。よって、私たちが追求すべきはより多くの自由とより多くの平等という「第三の道」であり、自由でもなく平等でもない「第三の道」でも、「半自由半平等」とか「自由と平等の間の折衷」の「第三の道」でもない。
ヒトラーはかつて「アングロサクソン式民主」と「ソビエト式民主」を超越する「ゲルマン式民主」を主張していた。これこそ自由でもなく平等でもない「第三の道」の例であり、私たちはもちろんその真似をすることはできない。一方、今日のブレアが主張している「第三の道」は「福祉国家でもなく、自由放任でもない」道で、それは彼らの福祉国家と自由放任がかつて多すぎたためだ。だが私たちの大多数の人口(農民身分)が全く社会保障を受けられず、また自由も非常に少ない(あちこちの「農民工整理」の状況を見よ!)ような国で、「より多く福祉国家、より多く自由放任」の路線を選ぶべきではないと言うことができるだろうか? だからブレアの模索は確かに貴重だが、我々は真似をしてはならない。要するに、我々が進むべきは決して反自由、反社会民主の路線ではなく、また親自由で反社会民主もしくは親社会民主で反自由の道でもなく、いわんや「自由と社会民主の中間の」道でもなく、自由と社会民主の二者の重なりあう基本的価値の追求路線以外にない。
この種の基本的価値は他の国ではすでに実現しているので、彼らは自由主義とか社会民主主義というそれぞれの価値観で、左や右もしくは中間の立場を選択できる。だが私たちのところでは、上述の基本的価値を実現のために奮闘している段階であり、実際は二つの立場の対立しかない。すなわち人道と反人道の立場、ハイエクとマルクスの立場対ヒトラーとスターリンの立場だ。今海外で「自由主義左派は自由主義右派に反対する」という命題が提出されている。よその国ではこれは真の命題かもしれない。なぜなら彼らのところでは「自由主義右派」の他に自由主義左派にとって反対すべき対象がなく、逆もまた同様だからだ。だが私たちのところでは、「自由主義右派」だけに反対する人や「自由主義右派」を最大の敵とみなす人は決して「自由主義左派」ではなく、(帝政ロシア時代の社会民主党員の言葉を借りれば)「警察ポピュリスト」である。一方、「自由主義左派」だけに反対したり、社会民主主義の原則だけに反対する人も「自由主義右派」などではなく、「警察寡頭主義派」だ。――そしてプレハーノフたちが当時指摘したように、警察ポピュリストは警察寡頭主義派に簡単に転化するので、自由主義者と社会民主主義者はお互い対立するのではなく、「別個に進んで共に撃つ」という関係に立つべきである。そして、自由主義派と社会民主派の関係さえそうなのに「自由主義左派は自由主義右派に反対する」などという説が一体なぜ出せるのだろう? だから私は「主義」問題で自由主義と社会民主主義が共有する基本的価値の立場、私の別の文章の中でのいい方だと「自由が主義に優先する」立場に立つ。この立場は西側では多分いかにも「中庸」に見えるだろう。左でも右でもなく、もっと正確にいえば左でもあり右でもある。だが中国ではこの立場は「過激な中庸」――経済的には、大家長が〔社会主義〕大家族を防衛したり復興したりすること(これには一部の「左派」が賛成している)に不利であり、大家長が家産を独占して子供たち〔=労働者〕を家から叩き出すこと(これには一部の「右派」が賛成している)に不利である。政治的には、それは擁護することだけを許す政府に反対し、反対することを許す政府を擁護する。ゆえにそれはもっぱら「擁護することだけを許す政府」を擁護する「保守主義者」の攻撃を受け、またもっぱら「反対することを許す政府」に反対する「急進主義者」の攻撃を受けることになる。この後二者の「急進か保守か」の論争は見ていて全く滑稽である。
間違いなく、これらの立場は現代の先進国では珍しいことではないが、今日の中国ではこの種の立場の前提が、大方の見るところ、全く欠如している。それなら、我々の努力は成果を得られるだろうか? 私はそれは問題にならないと思う。私は文化決定論に反対する。私が思うに、歴史には因果関係がある(だからこそ歴史は解釈できる)、だが歴史の主体としての人には主体性があるから、歴史の中の因果は確率的因果であり、必然的因果ではない。いかなる1以外の確率も何度も掛け続けて行けば0に近づくから、長期的にみると人々は自分で責任を負わなくてはならない。例えば、もし事件Aが事件Bを引き起こす確率が80%、事件Bが事件Cを引き起こす確率が60%、事件Cが事件Dを引き起こす確率が70%だとすると、事件Aが事件Dを引き起こす確率は33.6%に過ぎない。よって「原因の原因の原因は、原因ではない」。だからもし明日の中国がうまくいかないとしても、孔子を責めることはできないし、マルクスを責めることもできず、私たち自身を責めるしかないのだ。私たちが努力すれば必ずや成果を得られると、私は確信している。
原文出典:http://www.boxun.com/hero/qinhui/83_2.shtml
中国語版『田園詩与狂想曲』は現在品切れだが一部が下記サイトで読める。
http://book.ifeng.com/lianzai/detail_2010_01/23/298295_0.shtml
2010年1月漢語版重版出来。
(転載自由、要出典明記)
関連記事
ポピュリズムもエリート主義もいらない
http://blog.goo.ne.jp/sinpenzakki/e/1a15fdf1512d9962d910527f8f18cb08
「第三の道」か、それとも共通のベースラインか?(一)
http://blog.goo.ne.jp/sinpenzakki/e/bd1140500e12d6b11b18e0415cbd2096
「第三の道」か、それとも共通のベースラインか?(二、三)
http://blog.goo.ne.jp/sinpenzakki/e/d37c8bfb2fbc29bbdb71d3ac45643a24
我あるが故に我思う、そこに「問題」あり。我思う故に我あり、そこに「主義」あり。「五四」運動以降ずっと中国知識人は「主義」と「問題」の二つを苦労して探求してきた。「五四」運動自体は、大きくて意味不明な概念の「文化」運動というよりは、(知識人を代表とする)中国人が率直に「主義」を語り、「問題」を直視した運動だったというべきだろう。当時胡適と李大の間に「問題」か、それとも「主義」かの論争があったが、実際は、胡、李を含めた「五四」エリートの大部分が「主義」も語り、「問題」も語っていた。違いは「主義」が同じでないことと、「問題」に対する認識と回答が同じでないことだけだった。
80年が経過し、世紀の移り変わり、ミレニアムの中国は依然として大変革のさなかにあり、やはり率直に「主義」を語り、「問題」を直視する精神が必要とされている。確かに「問題」を避けた「主義」の説教は空疎な学問であり、「主義」を欠いた「問題」研究は贅言の学問と言うべきだろう。空疎な学問と贅言の学問は今後もこれまで同様存在し続けるだろうが、空疎化と贅言化を抜け出す「問題と主義」の討論は疑いもなく中国思想界の希望である。
私は15歳の時に文革で学業を離れ、農村に「下放」され9年間農民をした。その「早稲田大学」(日本の大学と混同しないように!)で、私は「農民学」との縁ができた。24歳の時「早稲田」から田植えをしない大学に研究生として編入したときに、「土地制度と農民戦争史」を研究方向と定めてから、農民問題はずっと私の関心の中心である。理論と実践の探求によって私は、中国のいわゆる農民問題は過去も現在もpeasants(農民)問題であり、farmers(農業経営者)問題ではないことを知った。それはずっと、単に農耕者に関わるだけでなく、本質的には「早稲田」の中の問題でもなかった。とりわけ1949年以降、中国は僅かに存在したcitizen(市民)も徐々に消滅させられ、「都会人」は「田舎の人」よりさらにpeasantization(農民化)(もしくはnon-citizenization(非市民化))した。そのため1978年以降もやはり田舎の人が都会人にどうやってcitizenになるかを教えていた――少なくとも経済的にはそうだった〔農村からの収奪による都市の育成を言っている〕。
9年の農業生活で私は農村と密接な関係を結び、多くの農民の友達ができて、農耕者の問題は「彼らの問題」ではなく私自身の問題となった。そのため狭義の農民問題研究、過去の農民戦争史や土地制度史、農業経済学や農村社会学から今の改革の中で直面しているいわゆる三農(農業・農村・農民)問題まで、どれも私は注目してきた。だが、これらの狭義の農民学研究のほかに、peasantology(農民学)にはより広義な内容がある。すなわち農民国家・農業文明・伝統社会の研究であり、とりわけそれらの改革と近代化、すなわちいかに市民国家・工業文明・現代社会に転換するかの研究である。それが関係するのは決して農耕者のいわゆる「三農」問題だけではない。9年間の農村生活で私は農耕者の感情を持つようになったが、それだからといって私は毛沢東が言ったように都会人は農民の「再教育」を受けることが「非常に必要である」とは感じなかったし、「深刻な問題は農民教育だ」(これも毛の言葉)などとはさらさら信じられなかった。それが私に感じさせたのは都会人と農民が同じように不自由であり、同様に「共同体の付属物」だということだった。もし両者に違いがあるとしても、それは都会人が田舎の人より共同体の保護をより多く受けていること(「三年困難時期」〔1959年~61年、大躍進政策がもたらした大飢饉〕に餓死したのは田舎の人だけだった。私達都会人の「上山下郷」は一種の不幸とみなされたが、いわゆる「下放青年待遇」を受けられたので村民の羨望の対象だった)、そしてより多く共同体の束縛(政治的統制から「単位」〔配属機関:役所や会社などで、生活のすべてを管理した〕の制約、私達の選択の余地のない「生産隊への編入」を含めて。)を受けていることだけである。だから共同体の束縛から自由になった改革時代には、田舎の人はより簡単に束縛を脱し、「保護」を失うコストもより少なかった。
だが煎じつめると、改革は私たちの都市と農村の社会にいずれにとっても再編である。都市と農村の人々はみな改革の中でpeasantsからcitizenになる。すなわち従属的な共同体構成員から個性ある自由人になる過程である。よって現代中国では、狭義の農民学と広義の農民学の結合は極めて重要な意義がある。もしすでにpeasantsがおらずfarmersだけの先進国なら、人々は農場の最適規模を中心概念としてミクロ農業経済学を構築し、農産物の価格=供給反応を中心概念としてマクロ農業経済学を構築できる。だが私たちのところでは農業について語る「農業経済学」はあまり意義がない。前近代の中国では、専制国家と社会の矛盾は一貫して農村内部の地主小作、貧富の矛盾より重要だった(多く発生した「農民戦争」はその全てが反役人反朝廷であり、反地主ではなかった)。
今日の中国ではまた「農民に問題はあるが、それは『農民問題』ではない」という説がある。私は以前「中国問題の実質は農民問題」だと言ったが、これはむしろ逆転させて、農民問題の実質は中国問題だというべきである。要するに、今日の農民研究は狭義の農民学と広義の農民学を結合しなければならない。狭義の農民学は農耕者すなわち「農」を生業とする「民」に関連する人文社会問題、例えば土地制度・農民運動・農村社会・コミュニティ組織・農民負担・農村文化・農民人口移動などに注目するものであり、広義の農民学は伝統社会・前工業社会・前近代社会・前市民社会ないし未開発社会(以前よく「封建社会」と言われたがこの言葉は正確ではない)の理論、とりわけその種の社会の近代化の理論を研究するものである。その種の社会は通常農業を主とするが、その基本的特徴はその職業性にあるのではなく、その問題も農耕者の問題に限られるものではない。言い換えれば、狭義の農民学は一種の「問題」の学であり、広義の農民学は一種の「主義」の学である。前者が欠ければ、農民研究は空疎に流れ、後者が欠ければ、農民研究は贅言に流れる。
私は「問題」と「主義」の結合、狭義の農民学と広義の農民学の結合という意図をもって本書を書いた。本書の前半は「関中モデル」〔関中とは陝西省秦嶺北麓の渭河沖積平野地域〕の研究で「問題」の検討と実証に重点をおき、後半は「前近代社会」の研究で理論もしくは「主義」に重点を置いている。原書は1988年に書き、当時私は陝西師範大学で教べんをとっていたので、本書の「問題」は「関中モデル」からとっており、「主義」は80年代の新啓蒙運動の特徴を帯びている。だが、1989年の中国の政治文化気候の急変〔天安門事件を指す〕で出版社がすでに印刷に付していた本書の出版を取り下げてしまった。そして、1996年にわたしが北京の清華大学に転じてから私が編集責任者となった『農民学双書』の1冊としてやっと北京で出版することができた。私が本書を書いた80年代後期の「問題」と「主義」に対する見方は今でも成り立っている。
また、私が最近新たに展開している観点は以下の数点である。伝統社会の共同体本位という基本的特徴に加えて、中国の伝統の大共同体本位と西側の小共同体本位の違いを指摘した。西側は近代化の初期に「市民と王権の同盟」すなわち個人と大共同体が連携してまず小共同体の人権に対する桎梏を打破する段階を経験した。一方中国のこの段階は個人と小共同体の同盟の代わりに、まず大共同体の束縛を打破した。近代中国農村の多くの現象、末期清朝の宗族自治から現代の郷鎮企業まで、このように解釈する方が、簡単に「封建の氾濫」とけなしたり「伝統の活力」とほめあげたりするより合理的である。90年代、「保守的文化決定論」が「批判的文化決定論」に取って代わり一時流行したが、私はそのどちらも拒絶し、「文化決定論の貧困」を指摘し、価値観の上での普遍主義と進歩主義、歴史観の上での非決定論(歴史決定論にも文化決定論にも反対)を主張し、「自分で自分に責任を持つ歴史観」を提示した。
私はかつて伝統共同体を解消し個性化した市民社会を確立する改革のプロセスを古い大家族の「分家」に喩えたことがある。その場合「分家すべきかどうか」は重要問題であるが、分家が完了してから新しい自由な小家族が直面する冷淡・孤立・危険などもまた重要な問題である。だがこの両者の間では、「どう分家するか」・どのように公平に分家するかこそが最も重要な問題である。なぜなら経済が私たちに示すのは、私たちに古い大家族が危機に陥った時最も起こりそうな矛盾とは分家するかどうかではなく、どう分家するかの争いだからだ。それは分家の過程でもめるかどうかにかかわるだけでなく、分家後に一体どうなるかにもかかわる。公平な分家の後に「実の兄弟も、明朗会計」の良性パターン・理性的な取引の中でむつまじい関係を維持するのか、それとも分家が不公正であったために禍根を残し、その後際限のない紛争が続き「分家後の問題」をいっそう深刻にするのか? さらにそれはすでに問題でなくなったはずの「分家すべきかどうかの争い」が再び問題になる事態も引き起こすかもしれない。不公正な分家に怒った人々が再び新しい大家長を求め、混乱の中で旧式の大家族を再建し、再び苦しい歴史のサイクルを繰り返すのではないか?
だから、「どう分家するか」もしくは分家における公正の問題は極めて重要である。それは分家過程自体についてだけでなく、我が国と人類が六道輪廻の悪循環を抜け出して、新しいミレニアムに新しい文明を築けるかどうかに関わってくる。古い家父長制の弊害を除去したいと心から願う全ての人、新しい現代病を本当に憂うる全ての人は、必ずそれを直視しなければならない。残念なことにいま本当に「どう分家するか」という問題を直視している人は多くない。その原因はたぶん、第一に、「どう分家するか」という問題は非常に具体的で、「分家すべきか否か」という類の問題のように形而上で「理論的」でないからだろう。第二に、この問題を語ることが歓迎されないのだろう。「家産」を盗み侵奪した人はもちろん「公平な分家」を議論するのを嫌がるし、しかも彼らは家の中で最も勢力の強い人々だから、彼らを怒らせたら自分たちの身が危なくなる。外の人は「分家」後の新しい世帯主と商売をしたいだけなので、ほとんど誰も「分家」の公平さに興味を示さない。また外の人は長いこと新しい小家族で暮らしていてその冷たさと孤独に嫌気がさしているので、同じような不満を聞くことは好きだが、「分家の不公正」の苦しみは理解できない。そこでこの国の人たちは二つのことに没頭する。どんな結果になるか構わず分家の利点を並べたて、実施的な「家産」の窃盗や侵奪にまで正当化の理由を提供すること、そして、ひたすら新しい自由な小家族の冷たさと孤独を攻撃し、実質的には古い大家長を称揚することである。そして往々にして家産侵奪者と古い大家長は同一人物なので、私たちはその二つの声を合わせた「左右同源」の声を聞く。
その議論に全く道理がないとは言えない。たしかに分家の利点と小家族の冷たさや孤独はどちらも事実である。だが「どう分家するか」を離れた選択により、それらの議論の価値は少なくとも大幅に値引きされる。そこで「公平な分家」すなわち公正な改革の呼びかけが私が関心を寄せる中心問題となる。1989年にさかのぼるが、私が本を書いた時――その頃はまだ「分家すべきかどうかの争い」が本当の中心問題だった――私たちは歴史上の「アテネ路線」と「マケドニア路線」、「アメリカ路線」と「プロイセン路線」の研究の中で「改革路線の選択は改革の是非の争いよりも重要である」という命題を提出した。1992年私たちは公正な改革を呼びかけ、「管理人の共有財産不正配分」を防止しなければならないし、「管理人の共有財産侵奪」はなおさら許されるべきことではないと訴えた。1994年から私は続けて5回「公正の至上」を論じる文章を書いた。そして歴史事例と現実問題の分析という二つの角度から現代化・改革の中の公正の問題の各領域での現れを検討した。それには農村、農民問題も含まれる。
1997年末に「自由主義と新左派」の争いが国内で「水面に浮かび上がった」。実際はそれ以前からこの種の論争は海外ですでに始まっており、国内では「問題」の争いという形で「水面」下で行われていた。私はどちらにも参加した。私は80年代の「文化ブーム」から90年代の「主義ブーム」で思想解放が一歩前進したと考える。「文化ブーム」のとこはまだ「問題」を直視し、「主義」を率直に語る雰囲気はなかった。当時人々は「文化討論」の形式で隠喩的に思想を戦わすしかなく、何でも孔子や「文化的伝統」に結び付けて、本来明晰に伝えることのできる問題を訳の分からないおしゃべりにしてしまっていた。今「主義」を議論する空間があることは、大進歩だ。だが足りないのは、今は「問題」のタブーが「主義」のタブーより多い――これは「どう分家するか」が「分家すべきかどうか」より突出しており、利益衝突が「信念の衝突」より突出しているという社会動向の思想界における反映である――ことでこの「主義」の議論がかなりの程度「思想資源」のレベルに留まってしまっていることだ。一方はハイエク、ロナルド・コース、もう一方は「ポスト学」、「ネオマルクス主義」と、まるで外国人の論争のようだ。「資源」の争いは確かに大いに意義があるが、もし現実の「問題意識」から離れたら、「資源」はむしろ「思想」を覆い隠してしまうだろう。なぜならどんなに深刻な「主義」も現実の「問題意識」から離れて学術伝承の脈絡の中だけで発展することはできないからだ。
ある人はハイエクとミュルダールの思想は調和しないと考えている。だがある種の「問題」の前で、ハイエクとミュルダールばかりか、同じく極端な自由主義の名声をもつハイエクとミーゼスでさえ調和しない。だが別の「問題」の前では、ハイエクとミュルダールと言わず、ハイエクとマルクスでさえ同じ立場に立っている――現在の我が国にハイエクの理念から容認し得ないだけでなく、マルクスの理念によっても容認し得ないことは少なくないでしょう? 帝政ロシアの一時期、社会民主派(マルクス主義者)は「アメリカ路線」を追求し、自由主義派は「合法的マルクス主義者」を自称した。そしてこの両者と寡頭主義、ナロードニキ主義〔もしくは人民主義〕との闘争こそが水と油の闘いだった。だが後のストルイピン時代には、一部の社会民主派がナロードニキ化し、一部の自由主義派は寡頭主義化して、両者の衝突が先鋭化して寡頭主義とナロードニキ主義の風潮は日増しに盛んになった。そしてついに「不公正な分家」に根差す社会不安から自由主義と社会民主主義は共倒れになり、むしろナロードニキ主義と寡頭主義が最も極端な形で結びついてロシアを長い夜に引き込んだ。
今日の中国の「主義ブーム」の中で当時の歴史を回顧するとき、学ぶべき教訓は多い。今日の「主義ブーム」の各アクターはみな現代の西側から「思想資源」と記号資源を汲み取っているが、自由秩序が確立して久しい西側に比し、いま私たちが直面している「問題状況」は実は自由秩序が確立する前の帝政ロシアにむしろ近い。そのような状況下では、自由の欠乏は社会民主が多すぎるからではなく、社会民主の欠乏も自由が多すぎるからではない。だから当時の社会民主派は自由競争の民主国家である「アメリカ路線」に憧れ、ビスマルク式の社会保障制度を持つ独裁国家である「プロイセン路線」を敵視したのだった。そして自由主義反対派はむしろ積極的な自由の視点からマルクスを称賛し、トーリー党〔イギリスの保守党〕式の(エドマンド・バーク式ではない)保守主義に反対した。似たように、中国の現実の「問題状況」を見れば、私たちには現在自由主義が多すぎるわけでも社会民主主義が多すぎるわけでもなく、寡頭主義とポピュリズム〔もしくは人民主義〕が多すぎるのだ。だから自由主義の立場から出発して寡頭主義を批判し、社会民主主義の立場から出発してポピュリズムを批判することは、どちらも非常に必要なことだ。私はまさに同時に「二つの戦線」で「主義の争い」に参加している。
こう聞く人もいるだろう「君は一体自由主義の立場に立っているのかね、それとも社会民主主義の立場かね?」。私の答えは、自由秩序が構築される前はこの二つの立場の価値観の重なる部分は非常に広く、自由秩序の構築に伴い両者の価値の重なり面が縮小してゆき価値観の対立が目立ってくるにすぎないということだ(だが現代国家ではこの両者はまた重なりつつある)。だから中国の現在の「問題」背景の下では、私が堅持するのは自由主義と社会民主主義のどちらもが肯定する価値であり、反対するのは自由主義と社会民主主義がともに否定する価値である。自由主義が肯定し社会主義が否定するようなもの(例えば「純粋市場経済」)、および自由主義が否定し社会民主主義が肯定するもの(例えば「強大すぎる」労働組合)は私たちの中国にはどちらもまだ存在しない。それらが存在するようになってから自分の立場を選択しても遅くはない。
私のこの態度はいわゆる「第三の道」だろうか? そうかもしれないが、「第一と第二の道の重なり」(二つの道の中間でもなく、二つの道以外でもない)という方が正確であろう。いずれにせよ、中国の現在の問題は「自由が多すぎて平等を妨げている」のでもなければ「平等が多すぎて自由を妨げている」のでもない。よって、私たちが追求すべきはより多くの自由とより多くの平等という「第三の道」であり、自由でもなく平等でもない「第三の道」でも、「半自由半平等」とか「自由と平等の間の折衷」の「第三の道」でもない。
ヒトラーはかつて「アングロサクソン式民主」と「ソビエト式民主」を超越する「ゲルマン式民主」を主張していた。これこそ自由でもなく平等でもない「第三の道」の例であり、私たちはもちろんその真似をすることはできない。一方、今日のブレアが主張している「第三の道」は「福祉国家でもなく、自由放任でもない」道で、それは彼らの福祉国家と自由放任がかつて多すぎたためだ。だが私たちの大多数の人口(農民身分)が全く社会保障を受けられず、また自由も非常に少ない(あちこちの「農民工整理」の状況を見よ!)ような国で、「より多く福祉国家、より多く自由放任」の路線を選ぶべきではないと言うことができるだろうか? だからブレアの模索は確かに貴重だが、我々は真似をしてはならない。要するに、我々が進むべきは決して反自由、反社会民主の路線ではなく、また親自由で反社会民主もしくは親社会民主で反自由の道でもなく、いわんや「自由と社会民主の中間の」道でもなく、自由と社会民主の二者の重なりあう基本的価値の追求路線以外にない。
この種の基本的価値は他の国ではすでに実現しているので、彼らは自由主義とか社会民主主義というそれぞれの価値観で、左や右もしくは中間の立場を選択できる。だが私たちのところでは、上述の基本的価値を実現のために奮闘している段階であり、実際は二つの立場の対立しかない。すなわち人道と反人道の立場、ハイエクとマルクスの立場対ヒトラーとスターリンの立場だ。今海外で「自由主義左派は自由主義右派に反対する」という命題が提出されている。よその国ではこれは真の命題かもしれない。なぜなら彼らのところでは「自由主義右派」の他に自由主義左派にとって反対すべき対象がなく、逆もまた同様だからだ。だが私たちのところでは、「自由主義右派」だけに反対する人や「自由主義右派」を最大の敵とみなす人は決して「自由主義左派」ではなく、(帝政ロシア時代の社会民主党員の言葉を借りれば)「警察ポピュリスト」である。一方、「自由主義左派」だけに反対したり、社会民主主義の原則だけに反対する人も「自由主義右派」などではなく、「警察寡頭主義派」だ。――そしてプレハーノフたちが当時指摘したように、警察ポピュリストは警察寡頭主義派に簡単に転化するので、自由主義者と社会民主主義者はお互い対立するのではなく、「別個に進んで共に撃つ」という関係に立つべきである。そして、自由主義派と社会民主派の関係さえそうなのに「自由主義左派は自由主義右派に反対する」などという説が一体なぜ出せるのだろう? だから私は「主義」問題で自由主義と社会民主主義が共有する基本的価値の立場、私の別の文章の中でのいい方だと「自由が主義に優先する」立場に立つ。この立場は西側では多分いかにも「中庸」に見えるだろう。左でも右でもなく、もっと正確にいえば左でもあり右でもある。だが中国ではこの立場は「過激な中庸」――経済的には、大家長が〔社会主義〕大家族を防衛したり復興したりすること(これには一部の「左派」が賛成している)に不利であり、大家長が家産を独占して子供たち〔=労働者〕を家から叩き出すこと(これには一部の「右派」が賛成している)に不利である。政治的には、それは擁護することだけを許す政府に反対し、反対することを許す政府を擁護する。ゆえにそれはもっぱら「擁護することだけを許す政府」を擁護する「保守主義者」の攻撃を受け、またもっぱら「反対することを許す政府」に反対する「急進主義者」の攻撃を受けることになる。この後二者の「急進か保守か」の論争は見ていて全く滑稽である。
間違いなく、これらの立場は現代の先進国では珍しいことではないが、今日の中国ではこの種の立場の前提が、大方の見るところ、全く欠如している。それなら、我々の努力は成果を得られるだろうか? 私はそれは問題にならないと思う。私は文化決定論に反対する。私が思うに、歴史には因果関係がある(だからこそ歴史は解釈できる)、だが歴史の主体としての人には主体性があるから、歴史の中の因果は確率的因果であり、必然的因果ではない。いかなる1以外の確率も何度も掛け続けて行けば0に近づくから、長期的にみると人々は自分で責任を負わなくてはならない。例えば、もし事件Aが事件Bを引き起こす確率が80%、事件Bが事件Cを引き起こす確率が60%、事件Cが事件Dを引き起こす確率が70%だとすると、事件Aが事件Dを引き起こす確率は33.6%に過ぎない。よって「原因の原因の原因は、原因ではない」。だからもし明日の中国がうまくいかないとしても、孔子を責めることはできないし、マルクスを責めることもできず、私たち自身を責めるしかないのだ。私たちが努力すれば必ずや成果を得られると、私は確信している。
原文出典:http://www.boxun.com/hero/qinhui/83_2.shtml
中国語版『田園詩与狂想曲』は現在品切れだが一部が下記サイトで読める。
http://book.ifeng.com/lianzai/detail_2010_01/23/298295_0.shtml
2010年1月漢語版重版出来。
(転載自由、要出典明記)
関連記事
ポピュリズムもエリート主義もいらない
http://blog.goo.ne.jp/sinpenzakki/e/1a15fdf1512d9962d910527f8f18cb08
「第三の道」か、それとも共通のベースラインか?(一)
http://blog.goo.ne.jp/sinpenzakki/e/bd1140500e12d6b11b18e0415cbd2096
「第三の道」か、それとも共通のベースラインか?(二、三)
http://blog.goo.ne.jp/sinpenzakki/e/d37c8bfb2fbc29bbdb71d3ac45643a24