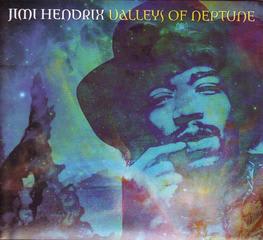このブログには「アクセス解析」機能がありまして、
「ページごとの閲覧数」をたまに見るんですが、
最近は「ユニクロUJ」の閲覧数が多いですね。
■驚きと自己発見
で、今更言うまでもないことかもしれませんが、
ファスト商品(特にファッション)隆盛の本質は、
不況による生活者の先行き不透明感(=不安)による、
節約・倹約意識によるニーズを掘り起こした、ということだけではなく、
生活者に「驚き」と「発見」をもたらしたことだ、
と私は考えます。
言うなれば「自己発見」ということでしょうか。
「賢い自分」「マスマーケティングの餌食にならない自分」。
もちろん、「ユニクロ」にもマーケティング戦略があり、
生活者もそのことをわかっているでしょう。
しかし、自分が心地よく納得できる“モノ”“コト”であれば、
「自分が踊らされている」というネガティブな感情は起きません。
この辺りの心の機微については、「欲望」ということになりますか。
ネットショッピングを始めたことによって、
書籍の購入量が増えたという精神分析の専門家、斎藤環氏の言説を借りますと、
「僕たちの欲望は『欲しい物』、つまり目標が存在するから生まれるんじゃない。『欲しい物を金で(ネットで)買える』という可能性こそが、僕たちの欲望を生み出しているんだ」 (『生き延びるためのラカン』102ページより)

という我々の「欲望」ですね。
所謂、「ヒット」する商品の場合、
商品そのものの価値よりも、
実は、パッケージの形状の新奇さや、
購入そのものの「快楽」というものが本質だったんだよね?
という事例は沢山あるはずです。
生活の「スタイル」ということで。
「商品」を「購入」する快楽と、「使用」する快楽は別物である、
ということを理解されていることが前提ですけど。
やはり数ヶ月前、この書籍(↓)を読んで、
改めてそのことを再確認しました。

■記号消費は消滅したのか?
ところで、佐々木俊尚氏の著作『電子書籍の衝撃』が売れているようです。
私も5月に読んで、多くものを得ました。

前半の電子書籍プットフォームの動向よりも、
中盤のセルフ・パブリッシングの方法論と、
後半の出版業界の歴史と構造のほうが、
マーケティング論として面白かったです。
ただ、経済・社会・文化の変遷によって、
「マス感性」(みんなで一つの感性を共有)が行き詰った、
という論はいいんですが (同書169ページ)、
「マス感性」と「記号消費」をイコールとされていることに対しては、
自分は違うんじゃないかな? と思います。
これは、「記号消費」の定義の違いでしかないんですが、
佐々木氏の場合、「記号消費」を、80年代後半から90年代初頭までの、
「バブル」消費のイメージに縛られているんじゃないかなと。
「顕示的消費」=「記号消費」であると。
自分の場合、もっと広義に考えます。
極端に言うと、
「消費しない」というのも消費態度であり、
「シンプル族」的な消費も、「記号消費」に違いないと思うのです。
特に「関係性」を重視する女性の場合にね。
■追記-ユニクロのソーシャルビジネス(社会事業)
本題とは異なる追記です。
一部の「マーケター」や「経済人」は、
「ユニクロ」に代表されるファストファッション業態を、
“デフレの元凶”のように眼の敵にしてますが、
ファストリさんは、ソーシャルビジネスも展開する先進的な企業です。
『日本経済新聞』7月19日朝刊9面の「経営の視点」は、
「社会事業、ユニクロの布石 貧困層40億人開拓へ一歩」。
(編集委員 井本省吾氏)
ファストリさんが、バングラディッシュで貧困層向けの融資を手掛ける
グラミン銀行と提携されたとのこと。
この提携は単なる“善意” からだけではありません。
「貧困層の人口は世界で40億人。バングラディッシュだけで1億5千万人を超す。貧困層の社会的課題が改善されて経済成長が進む時、潜在市場の開花は大きい。『服を変え、常識を変え、世界を変える』を目指すファストリにとって貧困市場の開拓は長期的に重要なテーマなのだ」(井本編集委員)
「経済の語源は世を治め、苦しみを救うという『経世済民』で、社会事業の意味合いを含んでいる。そこに視点を定めた企業が長期的に幅広い顧客を獲得する」(同)
こういうのを「企業戦略」って言うんですけど、
とにかく、資本主義とは(最高かどうかわからないものの)、
現時点では、エクセレントな“システム”ですね。
中途半端な「良心」「理想主義」や、
能天気な性善説に基づいた「共産主義」の悲喜劇とは対照的に。
かつて、貧困層の宗教を利用し、敵陣営との戦いに組織化し、
使い捨てた挙句、最大の「敵」にしてしまい、
「テロ」られて、泥沼の戦争に巻き込まれた、
(ベトナムでの教訓から学んでいない!!!)
グローバリズムとやらを、独りよがりに標榜する、
某国の「資本主義」は別ですけど。。。
**************************************************************************
お読み頂き有難うございます。
(↓)クリックの程、宜しくお願い申し上げます。

「ページごとの閲覧数」をたまに見るんですが、
最近は「ユニクロUJ」の閲覧数が多いですね。
■驚きと自己発見
で、今更言うまでもないことかもしれませんが、
ファスト商品(特にファッション)隆盛の本質は、
不況による生活者の先行き不透明感(=不安)による、
節約・倹約意識によるニーズを掘り起こした、ということだけではなく、
生活者に「驚き」と「発見」をもたらしたことだ、
と私は考えます。
言うなれば「自己発見」ということでしょうか。
「賢い自分」「マスマーケティングの餌食にならない自分」。
もちろん、「ユニクロ」にもマーケティング戦略があり、
生活者もそのことをわかっているでしょう。
しかし、自分が心地よく納得できる“モノ”“コト”であれば、
「自分が踊らされている」というネガティブな感情は起きません。
この辺りの心の機微については、「欲望」ということになりますか。
ネットショッピングを始めたことによって、
書籍の購入量が増えたという精神分析の専門家、斎藤環氏の言説を借りますと、
「僕たちの欲望は『欲しい物』、つまり目標が存在するから生まれるんじゃない。『欲しい物を金で(ネットで)買える』という可能性こそが、僕たちの欲望を生み出しているんだ」 (『生き延びるためのラカン』102ページより)

という我々の「欲望」ですね。
所謂、「ヒット」する商品の場合、
商品そのものの価値よりも、
実は、パッケージの形状の新奇さや、
購入そのものの「快楽」というものが本質だったんだよね?
という事例は沢山あるはずです。
生活の「スタイル」ということで。
「商品」を「購入」する快楽と、「使用」する快楽は別物である、
ということを理解されていることが前提ですけど。
やはり数ヶ月前、この書籍(↓)を読んで、
改めてそのことを再確認しました。

■記号消費は消滅したのか?
ところで、佐々木俊尚氏の著作『電子書籍の衝撃』が売れているようです。
私も5月に読んで、多くものを得ました。

前半の電子書籍プットフォームの動向よりも、
中盤のセルフ・パブリッシングの方法論と、
後半の出版業界の歴史と構造のほうが、
マーケティング論として面白かったです。
ただ、経済・社会・文化の変遷によって、
「マス感性」(みんなで一つの感性を共有)が行き詰った、
という論はいいんですが (同書169ページ)、
「マス感性」と「記号消費」をイコールとされていることに対しては、
自分は違うんじゃないかな? と思います。
これは、「記号消費」の定義の違いでしかないんですが、
佐々木氏の場合、「記号消費」を、80年代後半から90年代初頭までの、
「バブル」消費のイメージに縛られているんじゃないかなと。
「顕示的消費」=「記号消費」であると。
自分の場合、もっと広義に考えます。
極端に言うと、
「消費しない」というのも消費態度であり、
「シンプル族」的な消費も、「記号消費」に違いないと思うのです。
特に「関係性」を重視する女性の場合にね。
■追記-ユニクロのソーシャルビジネス(社会事業)
本題とは異なる追記です。
一部の「マーケター」や「経済人」は、
「ユニクロ」に代表されるファストファッション業態を、
“デフレの元凶”のように眼の敵にしてますが、
ファストリさんは、ソーシャルビジネスも展開する先進的な企業です。
『日本経済新聞』7月19日朝刊9面の「経営の視点」は、
「社会事業、ユニクロの布石 貧困層40億人開拓へ一歩」。
(編集委員 井本省吾氏)
ファストリさんが、バングラディッシュで貧困層向けの融資を手掛ける
グラミン銀行と提携されたとのこと。
この提携は単なる“善意” からだけではありません。
「貧困層の人口は世界で40億人。バングラディッシュだけで1億5千万人を超す。貧困層の社会的課題が改善されて経済成長が進む時、潜在市場の開花は大きい。『服を変え、常識を変え、世界を変える』を目指すファストリにとって貧困市場の開拓は長期的に重要なテーマなのだ」(井本編集委員)
「経済の語源は世を治め、苦しみを救うという『経世済民』で、社会事業の意味合いを含んでいる。そこに視点を定めた企業が長期的に幅広い顧客を獲得する」(同)
こういうのを「企業戦略」って言うんですけど、
とにかく、資本主義とは(最高かどうかわからないものの)、
現時点では、エクセレントな“システム”ですね。
中途半端な「良心」「理想主義」や、
能天気な性善説に基づいた「共産主義」の悲喜劇とは対照的に。
かつて、貧困層の宗教を利用し、敵陣営との戦いに組織化し、
使い捨てた挙句、最大の「敵」にしてしまい、
「テロ」られて、泥沼の戦争に巻き込まれた、
(ベトナムでの教訓から学んでいない!!!)
グローバリズムとやらを、独りよがりに標榜する、
某国の「資本主義」は別ですけど。。。
**************************************************************************
お読み頂き有難うございます。
(↓)クリックの程、宜しくお願い申し上げます。