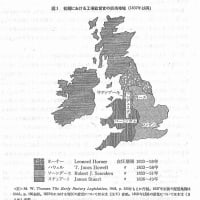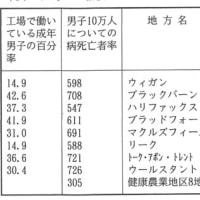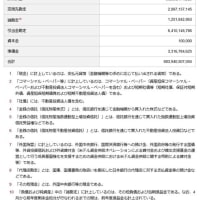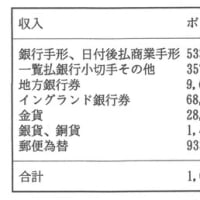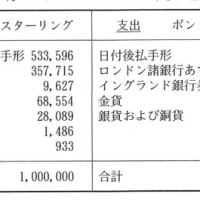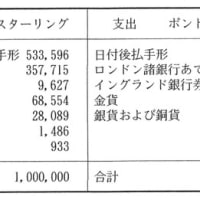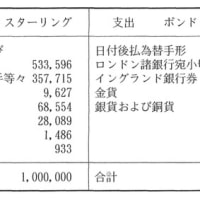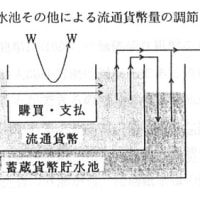『資本論』学習資料No.31(通算第81回)(5)
◎第24パラグラフ(不変資本の概念は、その諸成分の価値革命をけっして排除するものではない)
【24】〈(イ)不変資本の概念は、その諸成分の価値革命をけっして排除するものではない。(ロ)1ポンドの綿花が今日は6ぺンスであるが、明日は綿花収穫の不足のために1シリングに上がると仮定しよう。(ハ)引き続き加工される古い綿花は、6ペンスという価値で買われたものであるが、今では生産物に1シリングという価値部分をつけ加える。(ニ)そして、すでに紡がれた、おそらくすでに糸になって市場で流通している綿花も、やはりその元の価値の二倍を生産物につけ加える。(ホ)しかし、明らかに、この価値変動は、紡績過程そのものでの綿花の価値増殖にはかかわりがない。(ヘ)もし古い綿花がまだ全然労働過程にはいっていないならば、それを今では6ペンスではなく1シリングでもう一度売ることもできるであろう。(ト)それどころか、それが労働過程を通っていることが少なければ少ないほど、いっそうこの結果は確実なのである。(チ)それだから、このような価値革命にさいしては、最も少なく加工された形態にある原料に賭けるのが、つまり、織物よりはむしろ糸に、糸よりはむしろ綿花そのものに賭けるのが、投機の法則なのである。(リ)価値変化はここでは綿花を生産する過程で生ずるのであって、綿花が生産手段として、したがってまた不変資本として機能する過程で生ずるのではない。(ヌ)一商品の価値は、その商品に含まれている労働の量によって規定されてはいるが、しかしこの量そのものは社会的に規定されている。(ル)もしその商品の生産に社会的に必要な労働時間が変化したならば--たとえば同じ量の綿花でも不作のときには豊作のときよりも大きい量の労働を表わす--、前からある商品への反作用が生ずるのであって、この商品はいつでもただその商品種類の個別的な見本としか認められず(26)、その価値は、つねに、社会的に必要な、したがってまたつねに現在の社会的諸条件のもとで必要な労働によって、計られるのである。〉
(イ)(ロ)(ハ)(ニ) 不変資本の概念は、その諸成分の価値革命をけっして排除するものではありません。1ポンドの綿花が今日は6ぺンスであるが、明日は綿花収穫の不足のために1シリングに上がると仮定しましょう。引き続き加工される古い綿花は、6ペンスという価値で買われたものですが、今では生産物に1シリングという価値部分をつけ加えます。そして、すでに紡がれた、おそらくすでに糸になって市場で流通している綿花も、やはりその元の価値の二倍を生産物につけ加えることになるのです。
不変資本というから、その価値は生産過程では変化しないのかというと必ずしもそうではないのです。例えば1ポンドの綿花が今日は6ペンスであったのが、不作のために1シリングに上がった場合、すでに生産過程にあり6ペンスで仕入れた綿花の価値も1シリングになり、だから1シリングの価値を糸に再現することになります。あるいはすでに糸に転化してしまってすでに流通している綿花もそれ自体としては6ペンスで仕入れたもので、糸には6ペンスの価値を移転したのですが、しかしそれがいまだ最終的に売られていない場合、綿花が1シリングに値上がりした時点で、糸に転換された綿花の価値も1シリングに上がり、糸の価値もそれだけ大きくなるわけです。
(ホ)(ヘ)(ト)(チ) しかし、明らかに、この価値変動は、紡績過程そのものでの綿花の価値増殖にはかかわりがありません。もし古い綿花がまだ全然労働過程に入っていないのでしたら、それを今では6ペンスではなく1シリングでもう一度売ることもできるでしょう。それどころか、それが労働過程を通っていることが少なければ少ないほど、いっそうこの結果は確実なのです。それだから、このような価値革命にさいしては、最も少なく加工された形態にある原料に賭けるのが、つまり、織物よりはむしろ糸に、糸よりはむしろ綿花そのものに賭けるのが、投機の法則なのです。
しかしこうした不変資本としての綿花の価値の変化は、紡績過程そのものにおける変化ではありません。それは紡績過程とは違った別の綿花の生産過程の諸条件の変化による変化なのです。だから綿花が生産手段として参加する生産過程そのものにおいてその価値を変化させるわけではないという点では不変資本の概念から外れているわけではないのです。こうした生産過程の外での価値革命は、だから古い綿花がまだ全然生産過程に入っていない段階では明確にその価格の変化として現われてきます。それがすでに生産過程に入ったり、あるいはすでに生産過程を通って新たな生産物に転化してしまえばしまうほど、その価値革命の現われ方はさまざまな諸条件から不確実になるでしょう。すでに糸になったものを原料である綿花の価値が上がったからといって、そのまま糸の価格の引き上げとして反映できるかどうかはさまざまな市場の条件なども加わって不確実になるからです。だから価格の変動を見越して投機に走る人たちは、できるだけ川上に近いもの、織物よりも糸に、糸よりも綿花そのものに賭けるのが常道なのです。だから先物取引の市場では石油や金や銀や銅、あるいは穀物などの諸原料を扱うのが一般的なのです。
(リ)(ヌ)(ル) 価値変化はここでは綿花を生産する過程で生ずるのであって、綿花が生産手段として、したがってまた不変資本として機能する過程で生ずるのではありません。一商品の価値は、その商品に含まれている労働の量によって規定されてはいますが、しかしこの量そのものは社会的に規定されているのです。もしその商品の生産に社会的に必要な労働時間が変化したならば--たとえば同じ量の綿花でも不作のときには豊作のときよりも大きい量の労働を表わします--、前からある商品への反作用が生ずるのです。だから商品はいつでもただその商品種類の個別的な見本としか認められません。そしてその価値は、つねに、社会的に必要な、したがってまたつねに現在の社会的諸条件のもとで必要な労働によって、計られるのです。
綿花の価値の変化は、綿花を生産する諸条件の変化から生じるのであって、綿花が生産手段として入っていく、すなわち不変資本として機能する生産過程(紡績過程)で生じるのではありません。
一商品の価値は、その商品に含まれている労働の量によって規定されていますが、その量そのものは社会的に規定されているのです。すなわちその商品の生産に社会的に必要な労働時間がその商品の価値を規定しています。だからその社会的条件が変化して社会的に必要な労働時間が変化すれば--例えば同じ量の綿花でも不作のときには豊作のときよりも大きな量の労働時間をあらわします--その価値は変化しますが、それはすでに前に商品として生産されていて、今は流通にあるか在庫として停滞している商品についても、あるいはすでに別の生産過程にある商品についても、その価値の変化は反作用して変化させるのです。
だから商品は常に同じ商品種類の個別の見本としてしか認められないのです。つまりある一商品の生産に社会的に必要な労働時間というのは、その商品種類全体を生産するに社会的に必要な労働時間総量の一加除部分として考えられるということです。だからその商品種類の生産に社会的に必要な労働時間の変化は、同じ商品種類の個別の商品全体に行き渡るということです。そしてその社会的に必要な労働時間というのは、今その時点における生産の諸条件における社会的に必要な労働時間であって、だからそれは今その時点では、すでにその前に生産されたがいまだその価値存在を失っていないものにも影響するということなのです。生産手段(原料)としてある商品(綿花)の価値は、資本家(紡績業者)によって購入されることによってその商品としての価値は実現されますが、しかし資本としての価値は失いません。それは依然として資本の一機能(生産手段)を担うものとして価値(不変資本価値)を維持しているからです。だからこうした価値存在を維持しているものには、商品価値の変化は及ぶということです。だから綿花はすでに糸に転化してしまってその使用価値は存在していないのに、その価値は依然して綿花のその時点の価値の変化を反映して、糸の価値部分の変化として現われてくるわけです。
◎原注26
【原注26】〈26 「同じ種類の生産物の全体が本来はただ一つのかたまりをなしているのであって、このかたまりの価格は一般的に、そしていちいちの事情にかかわることなく、決定されるのである。」(ル・トローヌ『社会的利益について』、893べージ。)〉
これは〈この商品はいつでもただその商品種類の個別的な見本としか認められず(26)〉という本文に付けられた原注です。
ここではトローヌは同じ種類の生産物は一つのかたまりとして存在していて、そのかたまりの価格が個々別々の事情にかかわりなく決まってくることを述べています。その意味では本文の主旨をそのまま述べているものとして原注に採用されているといえます。ル・トローヌについては第4章「貨幣の資本への転化」の原注17と19、20等々、いろいろと出てきました。原注17の解説のところでは『資本論辞典』から紹介しましたので、もう一度それを再録しておきましょう。
〈ル・トローヌ・Guillaume Francois Le Trosne(1728-1780) フランスの経済学者.はじめ自然法学研究に従事したが,やがてケネーの影響をうけて経済学研究に入り.重農主義学説のもっとも有能な説明者の一人となった.……彼は価値の基礎を効用にだけおくコンディヤックに反対し,価値の発生を交換にもとめ,価値決定の原因を交換関係における効用・生産費・稀少怯・競争の共同作用によると説明した.つまりル・トローヌは一方に欲望にもとづく効用を認め他方に生産費を認めて主客折衷の価値説を示したが.コンディヤック批判では,彼の説に使用価値と交換価値の混同があることを指摘し得たのではなく,彼自身交換価値の本質については理解できず,使用価値と交換価値とを混同していた.マルクスはル・ローヌにたいして積極的には論評を加えていないが.『資本論』第1巻第1篇および第2篇で,重農主義の価値論を代表するものとして上記主著からしばしば引用し,彼が交換価値を異なる種類の使用価値の交換における量的関係すなわち比率として相対的なものと理解していること(KI-40;青木1・116;岩波1-74).また彼が商品交換は等価物間の交換であって,価値増殖の手段でないことを明示し(KⅠ-166;青木2・301-302;岩波2-30),コンディヤックの相互余剰交換説をきわめて正当に批判していること(KI-I86;青木2-3日3-304;岩波2-32)などを指摘している.〉(500頁)
◎第25パラグラフ(原料と同様、すでに生産過程で役だっている労働手段(機械など)の価値も、したがってまたそれらが生産物に引き渡す価値部分も、変動することがある)
【25】〈(イ)原料の価値と同じように、すでに生産過程で役だっている労働手段すなわち機械その他の価値も、したがってまたそれらが生産物に引き渡す価値部分も、変動することがある。(ロ)たとえば、もし新たな発明によって同じ種類の機械がより少ない労働支出で再生産されるならば、古い機械は多かれ少なかれ減価し、したがってまた、それに比例してより少ない価値を生産物に移すことになる。(ハ)しかし、この場合にも価値変動は、その機械が生産手段として機能する生産過程の外で生ずる。(ニ)この過程では、その機械は、それがこの過程にかかわりなくもっているよりも多くの価値を引き渡すことはけっしてないのである。〉
(イ) 原料の価値と同じように、すでに生産過程で役だっている労働手段すなわち機械その他の価値も、したがってまたそれらが生産物に引き渡す価値部分も、変動することがあります。
先には不変資本としての原料(綿花)の価値の変化の可能性を見ましたが、同じ不変資本である労働手段の場合にもやはりその価値が変化することがあるのです。だからその価値の変化とともにそれが生産物に引き渡す価値部分も変化することになります。しかしこの場合もやはり不変資本という概念から外れるようなことではないのです。
(ロ) たとえば、もし新たな発明によって同じ種類の機械がより少ない労働支出で再生産されるならば、古い機械は多かれ少なかれ減価します。だからまた、それに比例してより少ない価値を生産物に移すことになるわけです。
例えば、今、新しい発明によって同じ種類の機械がより少ない労働時間で生産されることになれば、当然その価値は減少します。そうするとすでに生産過程にある同じ機械の価値も同じように減価し、だから当然、それが生産物に引き渡す価値もそれに比例して減少することになるのです。
(ハ)(ニ) しかし、この場合にも価値変動は、その機械が生産手段として機能する生産過程の外で生じています。この過程のなかでは、その機械は、それがこの過程にかかわりなくもっているよりも多くの価値を引き渡すことはけっしてないのです。
すでに述べましたように、こうした場合も機械が不変資本としての概念からはずれているとは言えません。機械の価値の変動は、その機械が生産手段として機能している生産過程によって生じるのではなく、それとは別の機械そのものを生産する過程の変化によって生じたものです。だから機械が生産手段として機能している過程においては、その過程の外で決まった価値であっても、やはりその価値をそのまま生産物に移転するということは依然として変わらないのです。つまり不変資本の概念に合致しているのです。
◎第26パラグラフ(生産手段の価値の変動は、不変資本と可変資本との量的割合を変化させても、不変と可変との区別の相違には影響しない)
【26】〈(イ)生産手段の価値の変動は、たとえその生産手段がすでに過程にはいってから反作用的に生じても、不変資本としてのその性格を変えるものではないが、同様にまた、不変資本と可変資本との割合の変動も、それらの機能上の相違に影響するものではない。(ロ)労働過程の技術的な諸条件が改造されて、例えば、以前は1O人の労働者がわずかな価値の1O個の道具で比較的少量の原料に加工していたのに、今では1人の労働者が1台の高価な機械で百倍の原料に加工するようになるとしよう。(ハ)この場合には、不変資本、すなわち充用される生産手段の価値量は非常に増大し、労働力に前貸しされる可変資本部分は非常に減少するであろう。(ニ)しかし、この変動は、不変資本と可変資本との量的関係、すなわち、総資本が不変成分と可変成分とに分かれる割合だけを変えるたけで、不変と可変との区別の相違には影響しないのである。〉
(イ) 生産手段の価値の変動は、たとえその生産手段がすでに過程にはいってから反作用的に生じても、不変資本としてのその性格を変えるものではないが、同様にまた、不変資本と可変資本との割合の変動も、それらの機能上の相違に影響するものではありません。
すでに検討しましたように、生産手段(原料や労働手段)の価値の変動が、すでに生産過程にある生産手段の価値に反作用してその価値の変動をもたらしても、その不変資本としての性格を変えるものではないことが確認されました。
同じことは、不変資本と可変資本との割合が変化しても、それらの機能上の区別そのものには何の影響もないと言うこともできます。不変資本の価値が変化すれば、当然、不変資本と可変資本との割合は変化するでしょう。しかし不変資本の価値が変化しても不変資本でないことにはならないのですから、両者の区別もまた依然とし存在していることは当然なことです。
(ロ)(ハ)(ニ) 労働過程の技術的な諸条件が改造されて、例えば、以前は1O人の労働者がわずかな価値の1O個の道具で比較的少量の原料に加工していたのに、今では1人の労働者が1台の高価な機械で百倍の原料に加工するようになったとしましょう。この場合には、不変資本、すなわち充用される生産手段の価値量は非常に増大し、労働力に前貸しされる可変資本部分は非常に減少するでしょう。しかし、この変動は、不変資本と可変資本との量的関係、すなわち、総資本が不変成分と可変成分とに分かれる割合だけを変えるたけで、不変と可変との区別の相違には影響しないのです。
例えば具体的に見て行きましょう。労働過程の技術的な諸条件が変化して、以前は10人の労働者が、わずかな価値の10個の道具で比較的少量の原料を加工していたのに、今では1人の労働者が1台の高価な機械を使って以前の百倍の原料を加工したとします。この場合には、不変資本はわずかな価値の道具から、高価な1台の機械に置き換わったのですから、その価値部分は飛躍的に増大するでしょう。それに比して、可変資本、すなわち労働力に投じられる資本部分は、10人から1人になったのですから、1/10に減ったことになります。しかしこの変動は、総資本を不変資本と可変資本とに分けて投下する場合の量的割合を変化させますが、そのことは一方が不変資本で他方が可変資本だという資本の機能上の区別そのものには何の影響もしないということは明らかです。
(付属資料1に続く。)