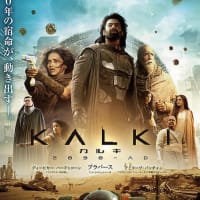※第3章「後期フッサール 時間・身体・相互主観性・生世界」C「相互主観性」21「構成する相互主観性」
※ダン・ザハヴィ『フッサールの現象学』(初刊2003)、工藤和男・中村拓也訳、晃洋書房(2017年新装版)
(31)「客観的妥当性」についての私の経験は、「異他的な主観性(他者or他我)の超越(と接近不可能性)を私が経験する」ことによって可能になる!
★「『客観性』と『超越』は相互主観的に構成され、したがってこの(『客観性』と『超越』の)構成の解明は、『超越論的相互主観性』の分析を、もっと具体的には『別の主観についての私の経験』の吟味を必要とする」とフッサールは主張する。(174-175頁)
★しかしながら「なぜ『主観』(※超越論的主観性)は『他者(他我)』を経験した後でしか『客観性』を構成することができないのか?」(175頁)
☆「なぜ『他者(他我)』は、『私が客観的世界を経験する』可能性の必要条件なのか?」(175頁)
☆「なぜ『対象』についての私の経験は、私が『異他的な主観性』を経験するときに根底的に変化するのか?」(175頁)
★基本的にフッサールのテーゼはこうである。「客観的妥当性」についての私の経験は、「異他的な主観性の超越(と接近不可能性)を私が経験する」ことによって可能になる。(175頁)
☆「最初の実在的他性」として、ならびに「すべての実在的超越の源泉」としてフッサールが明示する「この超越(異他的な主観性の超越)」が世界に「客観的妥当性」を付与する。(Hua 14/277『間主観性の現象学』, 15/560『間主観性の現象学』, 1/173『デカルト的省察』)(175頁)
☆「ここに《唯一本来的にそう呼ばれるべき超越》があり、《客観的世界のようにその他になお超越と呼ばれるすべてのもの》は、《異他的な主観性(※他我)の超越》に依拠している」(Hua 8/495『Erste Philosophie』)(175頁)
(31)-2 「他者(他我)についての《後に続く経験》」は、「客観性と超越のカテゴリー」を「構成する」ことをもはや可能にせず、むしろ「客観性と超越のカテゴリー」を「充実する」!
★さて普通、私は「《他者によって経験されるもの》として同時に経験している」のではないけれども、「ひとりで超越的、客観的、実在的なものとして経験しているもの」(Ex. いま使っているコンピューター)を経験する。(176-177頁)
☆これはどういうことか?「他者(他我)についての《最初の経験》」と「他者(他我)についての《後に続く経験》」は「客観性、実在、超越の構成」への寄与が異なるのだ。(177頁)
☆「他者(他我)についての《後に続く経験》」は、「客観性と超越のカテゴリー」を「構成する」ことをもはや可能にせず、むしろ「客観性と超越のカテゴリー」を「充実する」。(177頁)
☆すなわち上述のように「例えばコンピュータについての私の単独の経験」は、コンピュータを「実在的で客観的なものとして経験すること」であったが、「(客観的)妥当性」のこうした成素は、最初は「表意的」(※意味的)にだけ与えられるにすぎない。(177頁)
☆「他者が事実それを経験してもいる」ということを「私が経験したとき」にだけ、それは「直観的に、すなわち明証的に充実された私の経験」についての「妥当性-主張」なのである。(177頁)
《参考》たとえ「空虚な表意的(※意味的)志向」と「直観」(「直観的」志向)とが、同じ「志向的本質」(「対象」)をもっていようとも、「直観」は「対象」の「直観的充実」(Fülle)を加えるのである。(45頁)
※ダン・ザハヴィ『フッサールの現象学』(初刊2003)、工藤和男・中村拓也訳、晃洋書房(2017年新装版)
(31)「客観的妥当性」についての私の経験は、「異他的な主観性(他者or他我)の超越(と接近不可能性)を私が経験する」ことによって可能になる!
★「『客観性』と『超越』は相互主観的に構成され、したがってこの(『客観性』と『超越』の)構成の解明は、『超越論的相互主観性』の分析を、もっと具体的には『別の主観についての私の経験』の吟味を必要とする」とフッサールは主張する。(174-175頁)
★しかしながら「なぜ『主観』(※超越論的主観性)は『他者(他我)』を経験した後でしか『客観性』を構成することができないのか?」(175頁)
☆「なぜ『他者(他我)』は、『私が客観的世界を経験する』可能性の必要条件なのか?」(175頁)
☆「なぜ『対象』についての私の経験は、私が『異他的な主観性』を経験するときに根底的に変化するのか?」(175頁)
★基本的にフッサールのテーゼはこうである。「客観的妥当性」についての私の経験は、「異他的な主観性の超越(と接近不可能性)を私が経験する」ことによって可能になる。(175頁)
☆「最初の実在的他性」として、ならびに「すべての実在的超越の源泉」としてフッサールが明示する「この超越(異他的な主観性の超越)」が世界に「客観的妥当性」を付与する。(Hua 14/277『間主観性の現象学』, 15/560『間主観性の現象学』, 1/173『デカルト的省察』)(175頁)
☆「ここに《唯一本来的にそう呼ばれるべき超越》があり、《客観的世界のようにその他になお超越と呼ばれるすべてのもの》は、《異他的な主観性(※他我)の超越》に依拠している」(Hua 8/495『Erste Philosophie』)(175頁)
(31)-2 「他者(他我)についての《後に続く経験》」は、「客観性と超越のカテゴリー」を「構成する」ことをもはや可能にせず、むしろ「客観性と超越のカテゴリー」を「充実する」!
★さて普通、私は「《他者によって経験されるもの》として同時に経験している」のではないけれども、「ひとりで超越的、客観的、実在的なものとして経験しているもの」(Ex. いま使っているコンピューター)を経験する。(176-177頁)
☆これはどういうことか?「他者(他我)についての《最初の経験》」と「他者(他我)についての《後に続く経験》」は「客観性、実在、超越の構成」への寄与が異なるのだ。(177頁)
☆「他者(他我)についての《後に続く経験》」は、「客観性と超越のカテゴリー」を「構成する」ことをもはや可能にせず、むしろ「客観性と超越のカテゴリー」を「充実する」。(177頁)
☆すなわち上述のように「例えばコンピュータについての私の単独の経験」は、コンピュータを「実在的で客観的なものとして経験すること」であったが、「(客観的)妥当性」のこうした成素は、最初は「表意的」(※意味的)にだけ与えられるにすぎない。(177頁)
☆「他者が事実それを経験してもいる」ということを「私が経験したとき」にだけ、それは「直観的に、すなわち明証的に充実された私の経験」についての「妥当性-主張」なのである。(177頁)
《参考》たとえ「空虚な表意的(※意味的)志向」と「直観」(「直観的」志向)とが、同じ「志向的本質」(「対象」)をもっていようとも、「直観」は「対象」の「直観的充実」(Fülle)を加えるのである。(45頁)