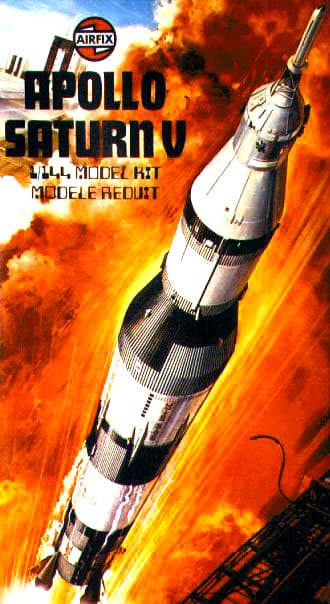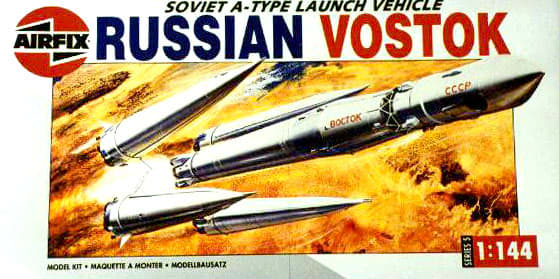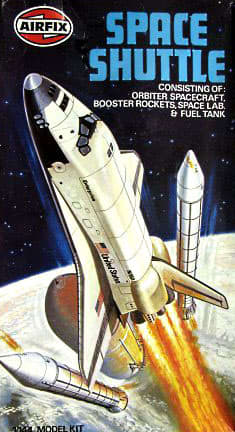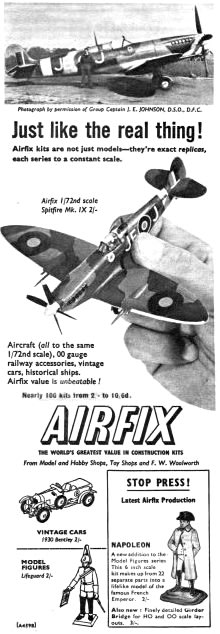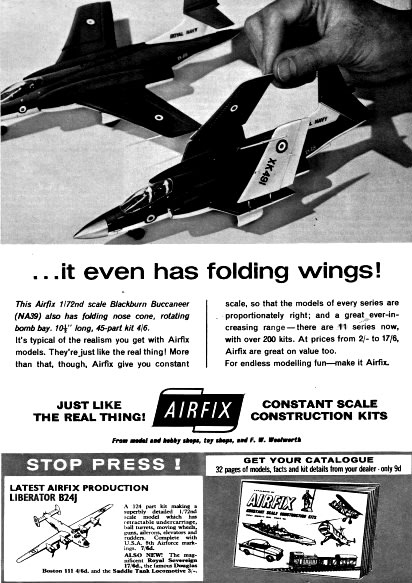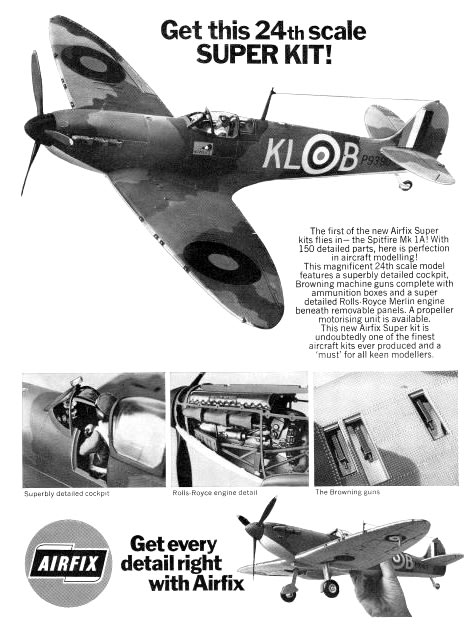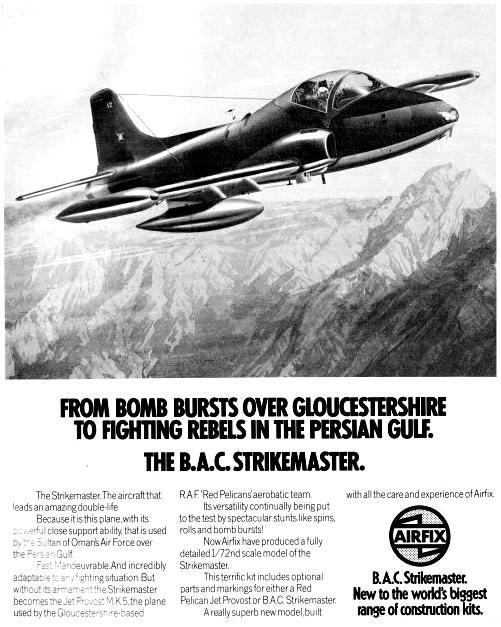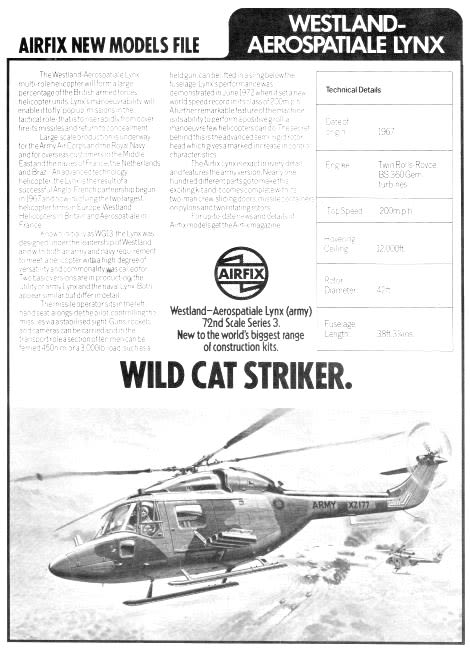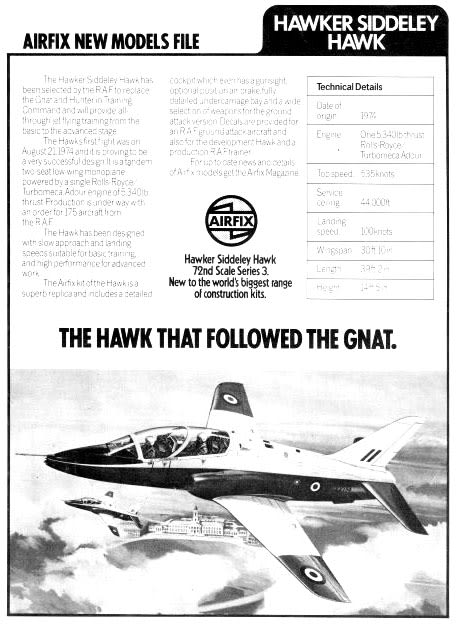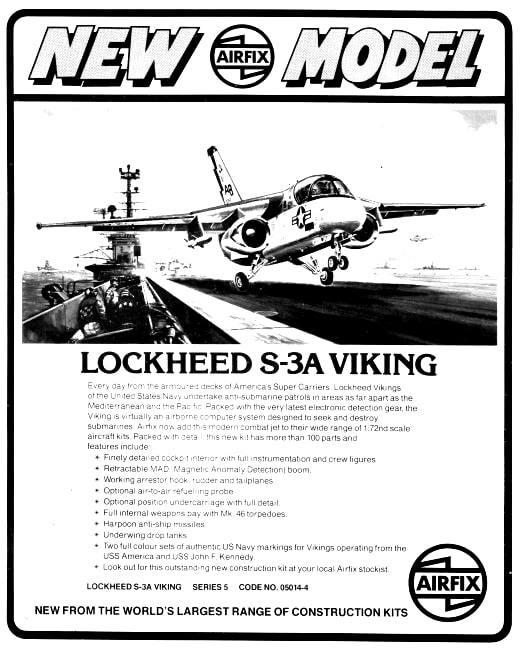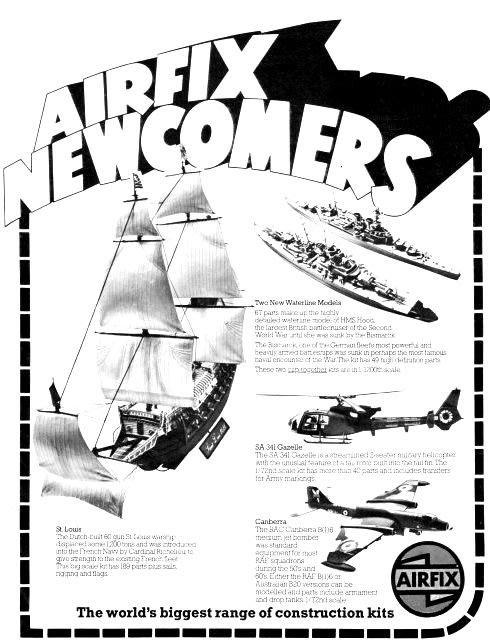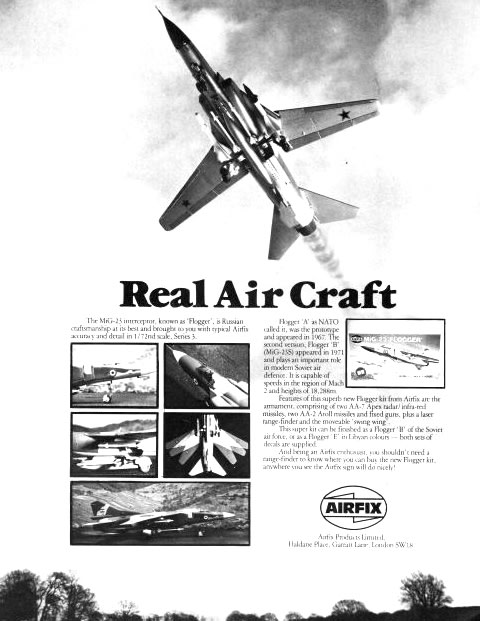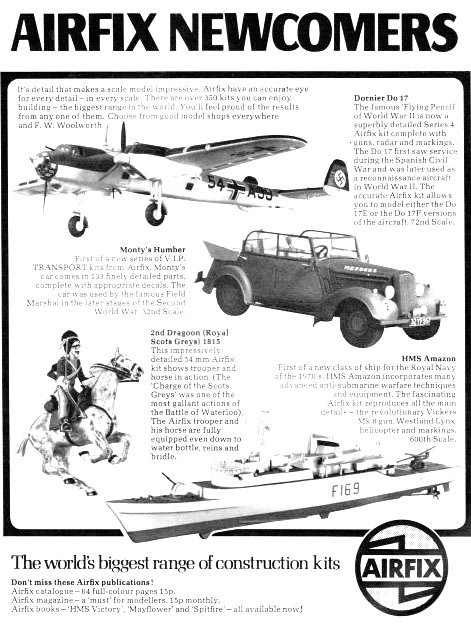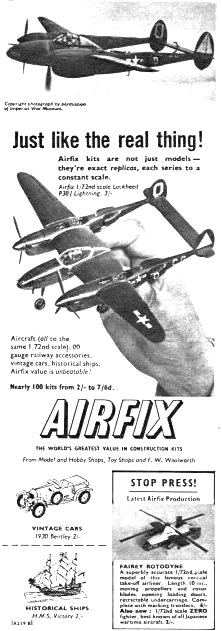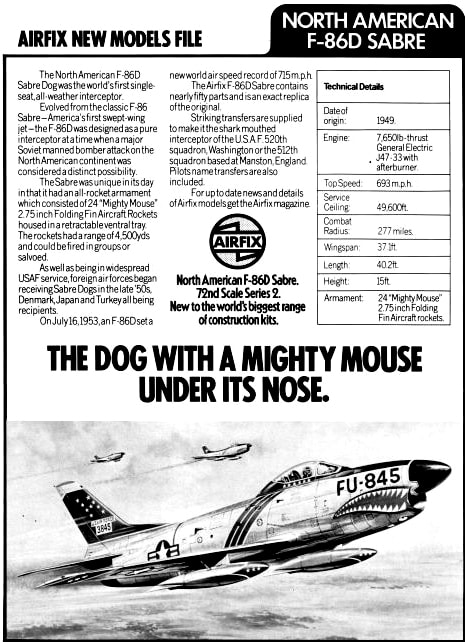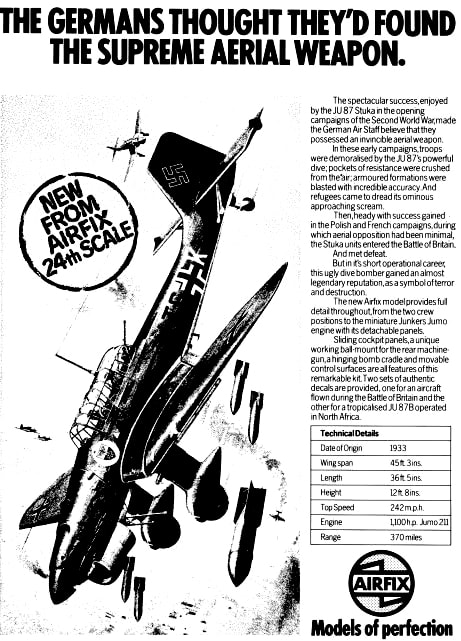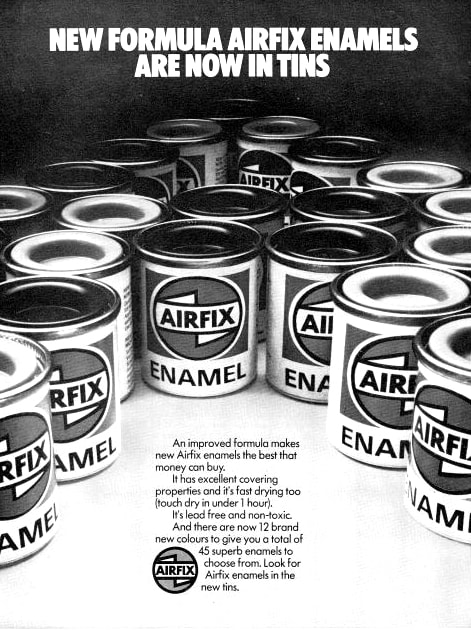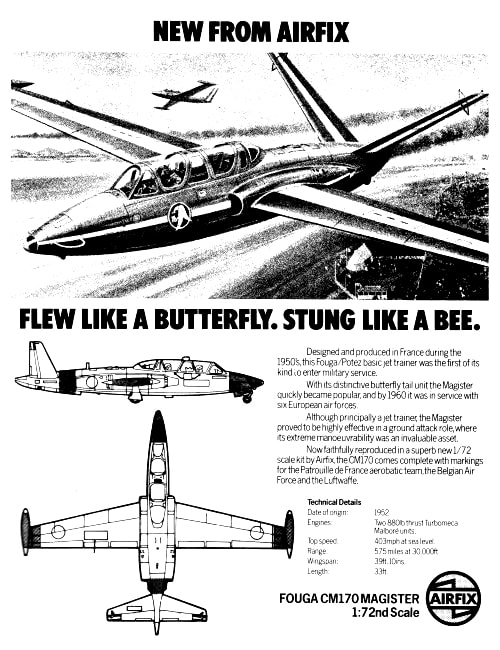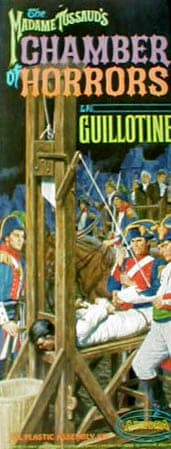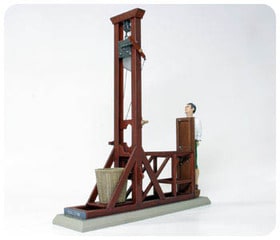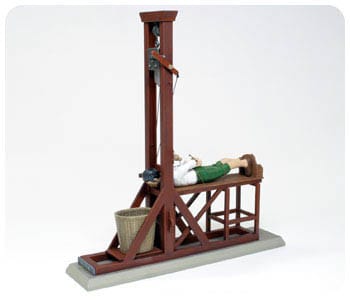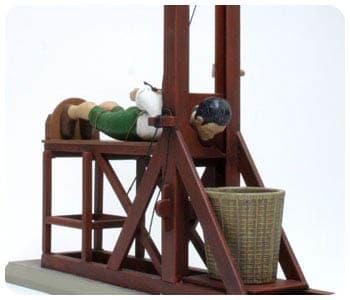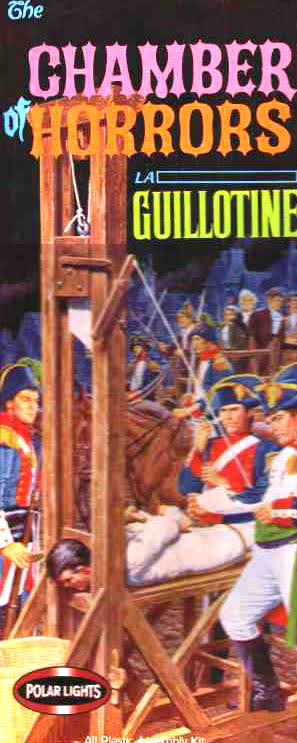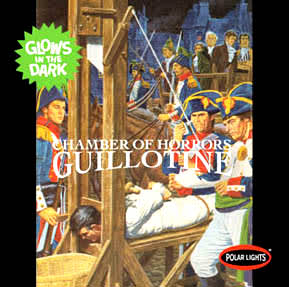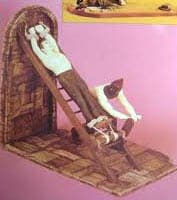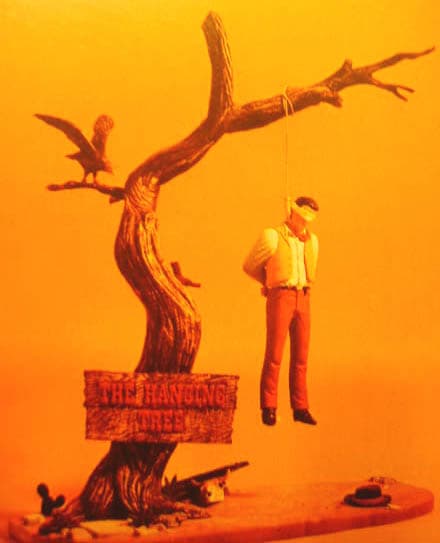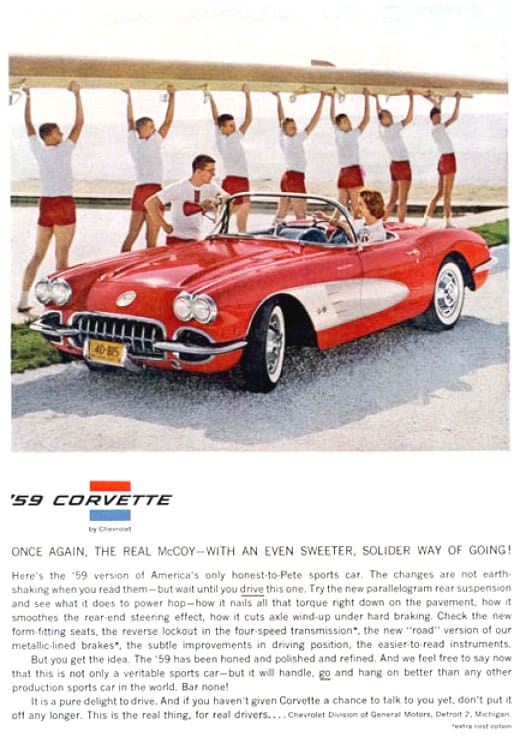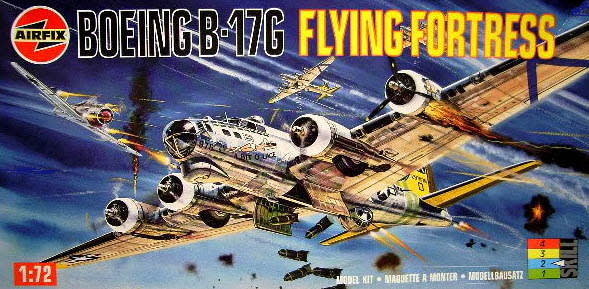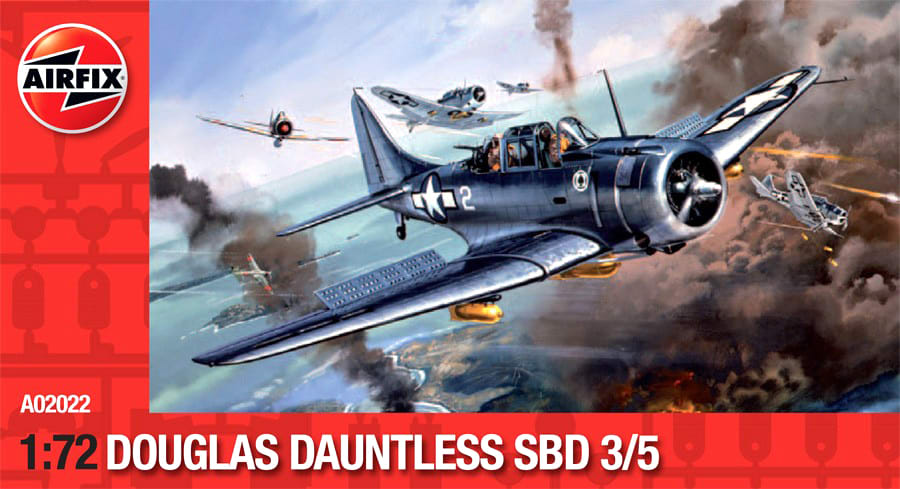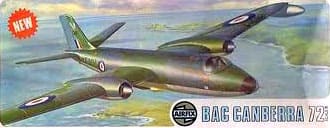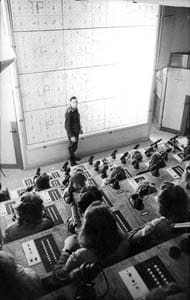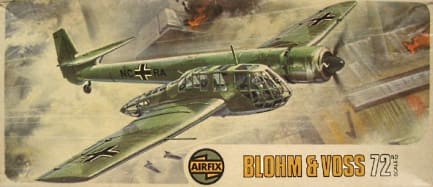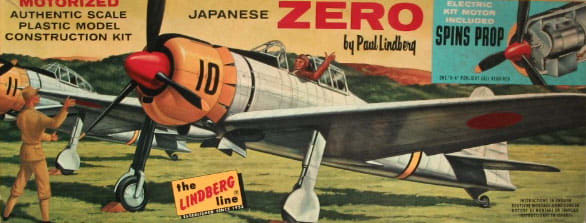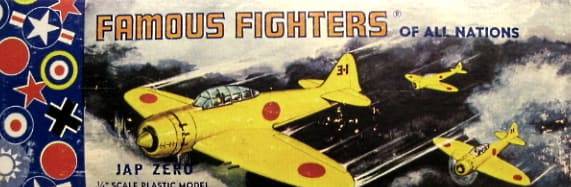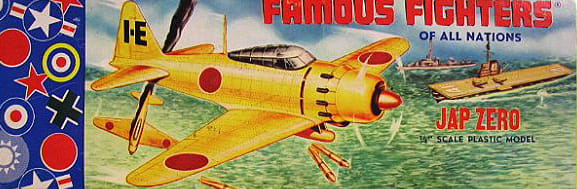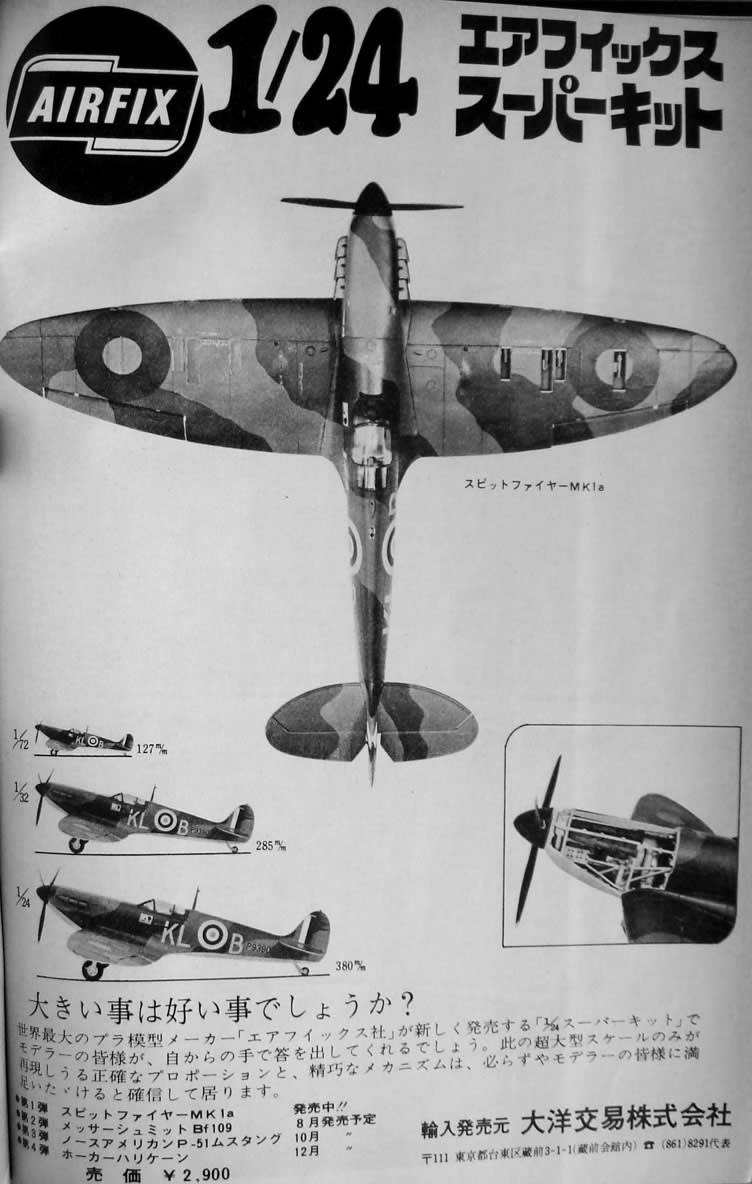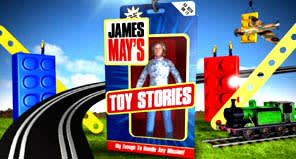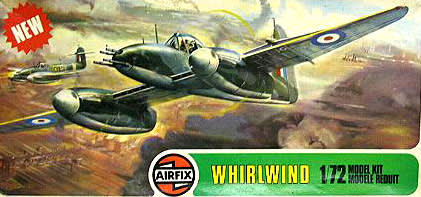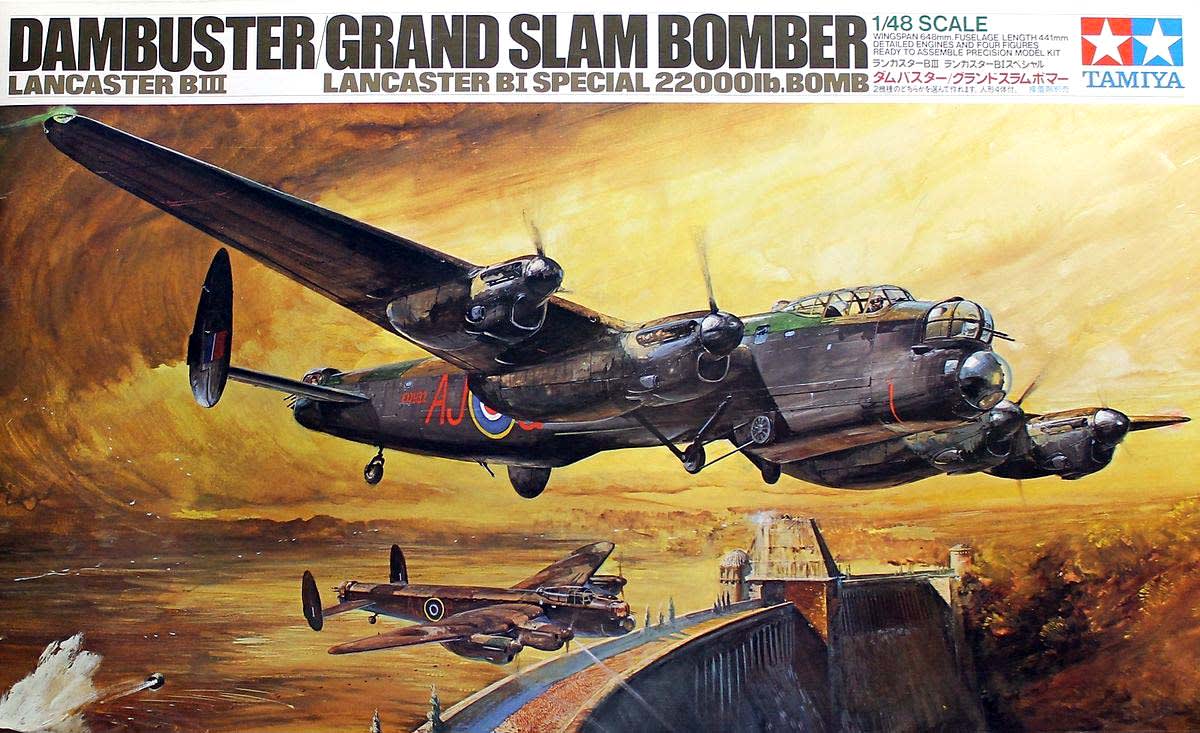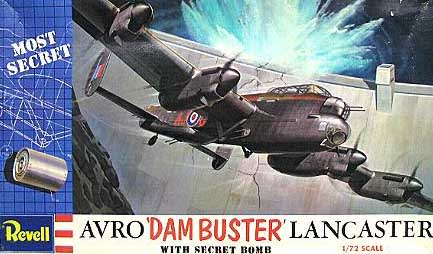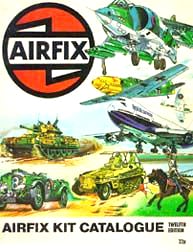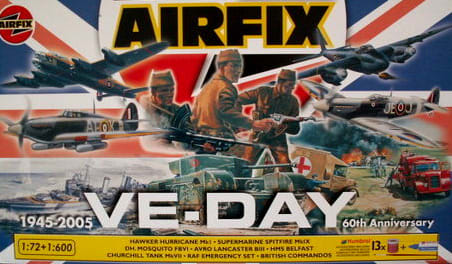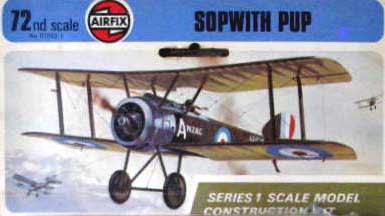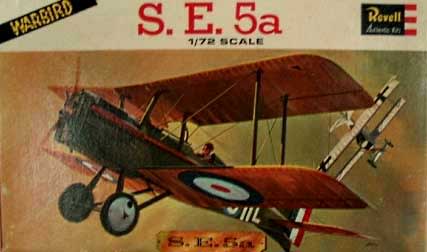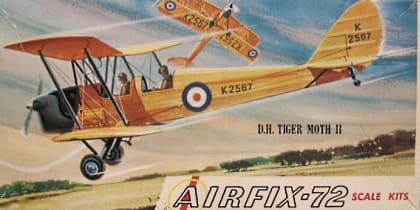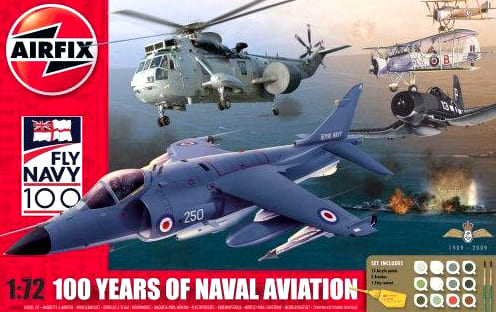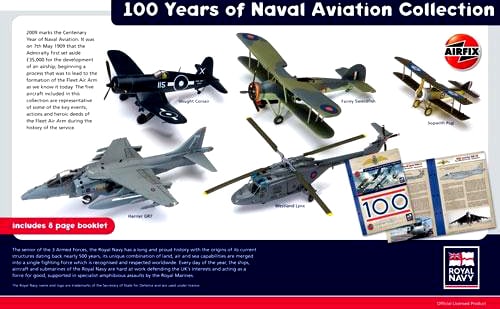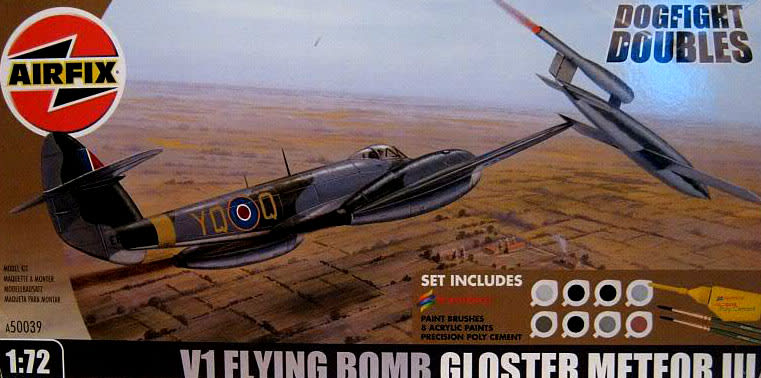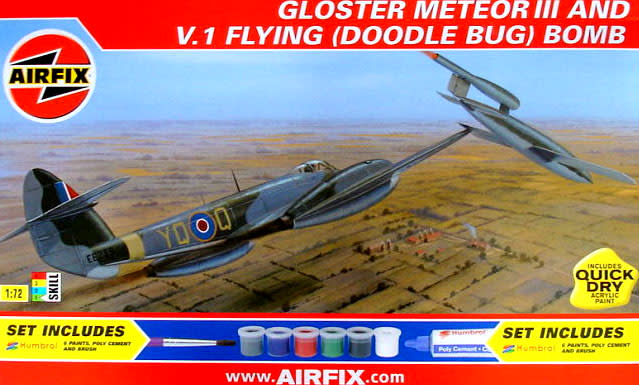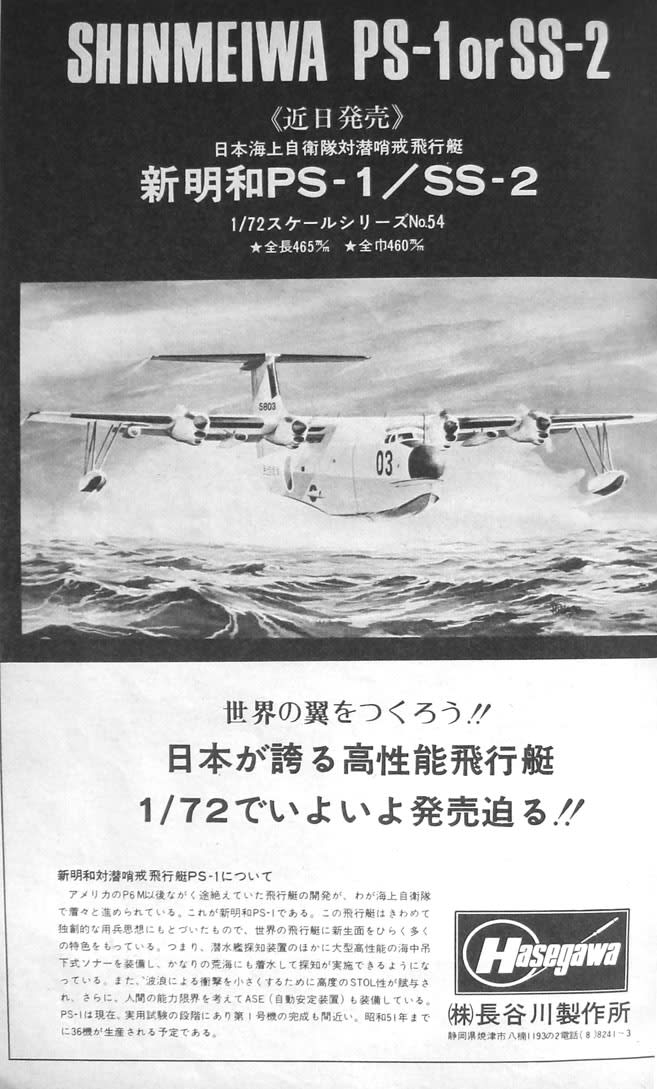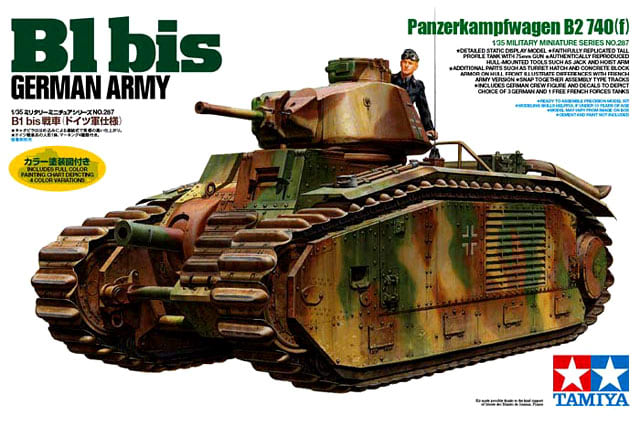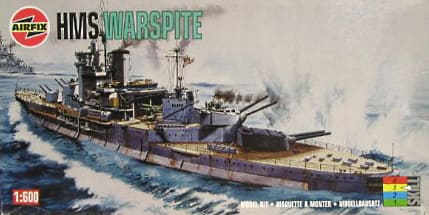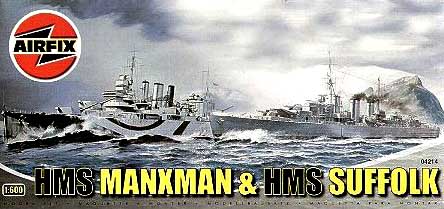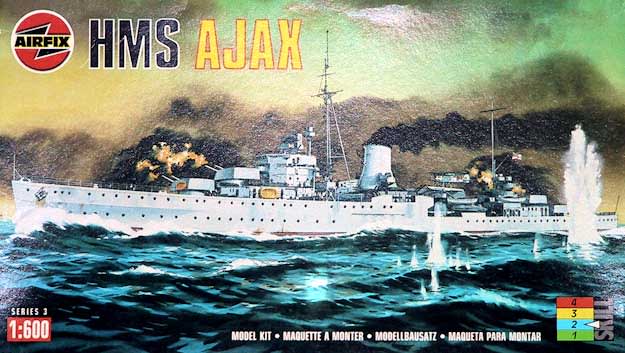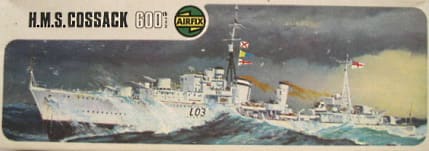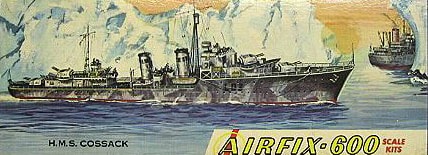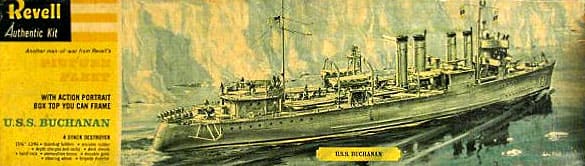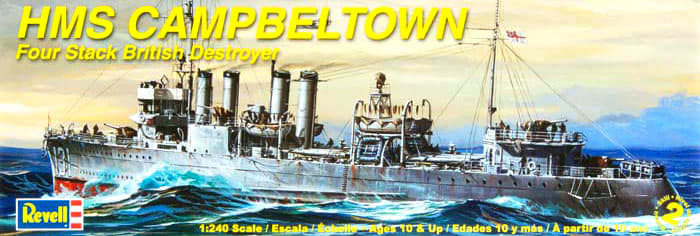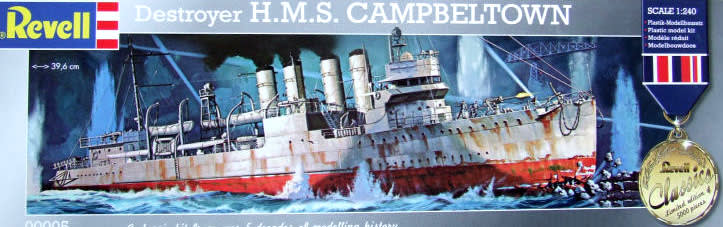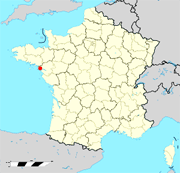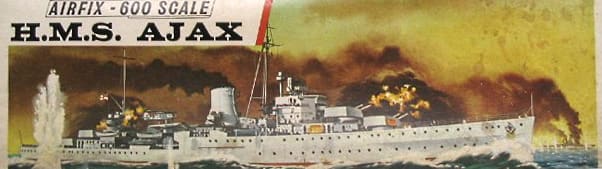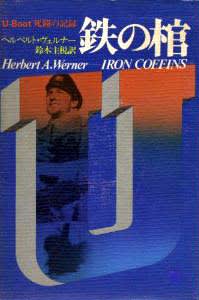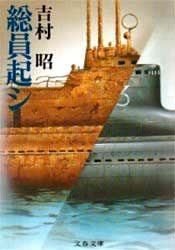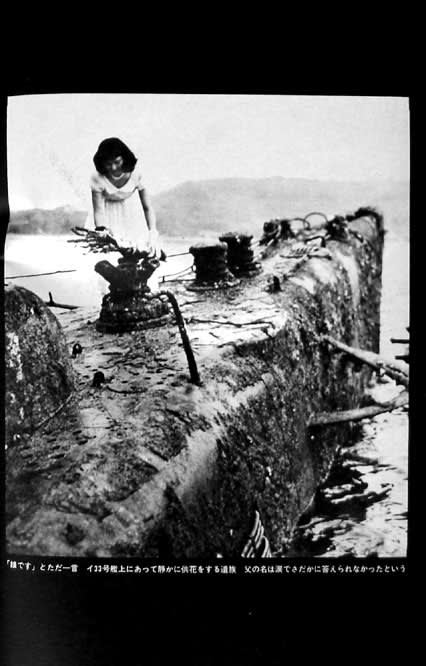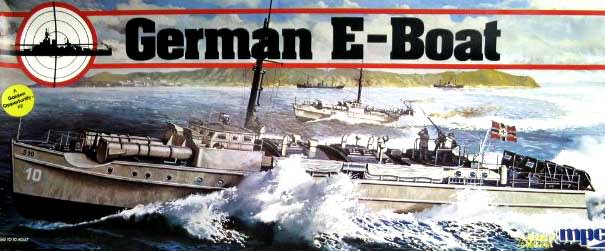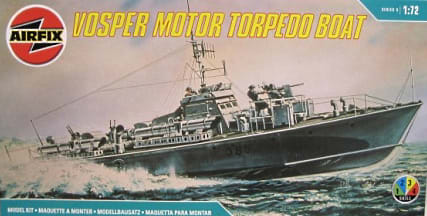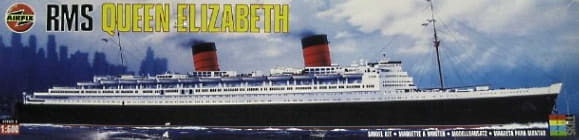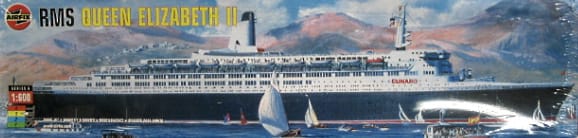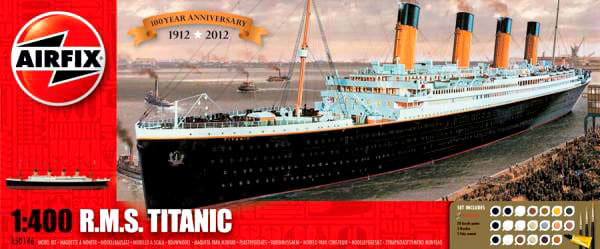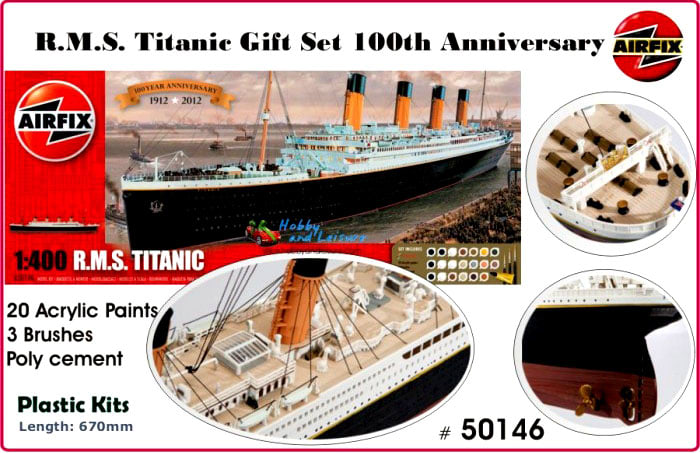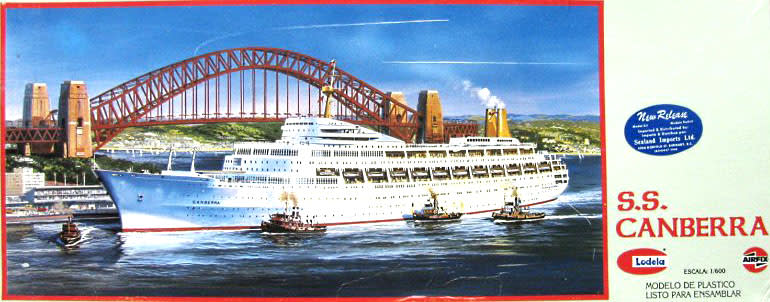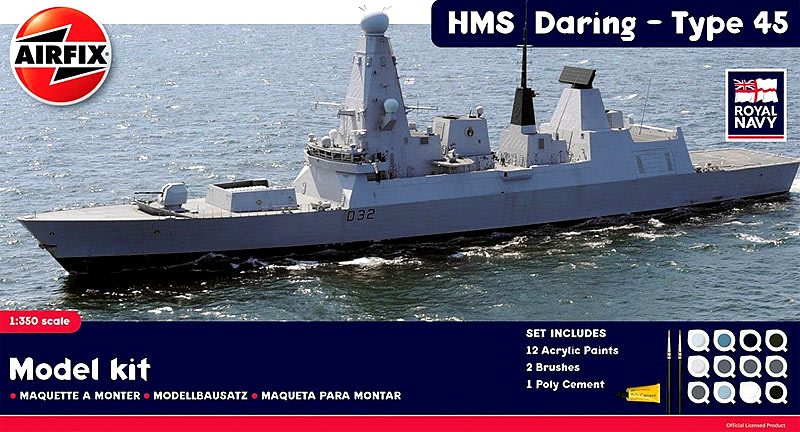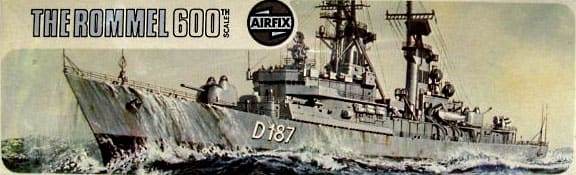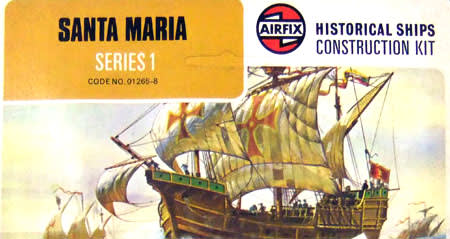アメリカ軍によるボックスアート奪還大作戦
アメリカ軍によるボックスアート奪還大作戦 今回はお休みです
今回はお休みです テレビドラマに見る
テレビドラマに見る
アメ車
 あれこれ
あれこれ


特設美術館

じゃじゃ馬たちは
オールズモビルに乗って
やってきた!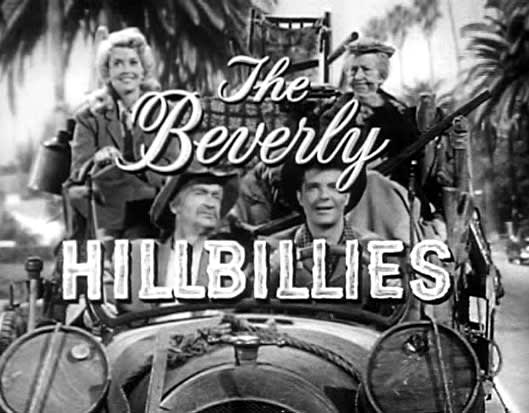
Wikipedia
エリー(ドナ・ダグラス) グラニー(アイリーン・ライアン)
ジェド・クランペット(バディ・イブセン) ジェスロ(マックス・ベア)
ある日自分の土地から石油が出て、一夜にして億万長者になった
クランペット家。いままで住んでいた山奥から、ビバリーヒルズという超高級住宅地に
引っ越してきたのだが、日々の生活は西部開拓時代とまるで変わらない。
場所にそぐわないトンチンカンな行動で、毎回とんでもない騒動を引き起こすという
コメディーが、この『じゃじゃ馬億万長者』だ。
放送当時地方の人間をバカにしているという批判もあったようだが、CBSで1962年から
1971年まで放送されるという大長寿番組となった。
日本ではモノクロバージョンが1963年の毎週火曜午後7時から午後7時30分まで
日本テレビで放送された。
その後、カラーバージョンが1968年から1969年にかけて毎週日曜の午前10時から
午前10時30分までフジテレビで放送された。
『じゃじゃ馬億万長者』というと、こちらのカラーバージョンを見た方が多いのではないかと思う。
YouTube
『じゃじゃ馬億万長者』のオープニングおよびエンディング。
モノクロバージョン。
https://www.youtube.com/watch?v=QtvTE3m5jpM
『じゃじゃ馬億万長者』のオープニング・カラーバージョン。
http://www.youtube.com/watch?v=NwzaxUF0k18
『じゃじゃ馬億万長者』の第一回目エピソード。
http://www.youtube.com/watch?v=sBmYkXVteaU
YouTube
大量の家財道具満載で車種がわかりにくいが、
オールズモビル・ロードスター1921年型のように思える。
YouTube
YouTube
YouTube
YouTube
モノクロバージョンとカラーバージョンとではクルマの搭載品が
微妙に異なっている。
Wikipedia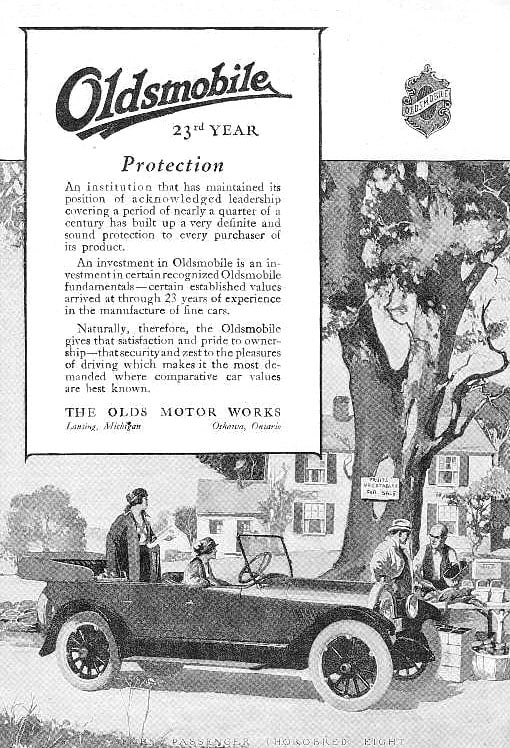
Oldsmobile1920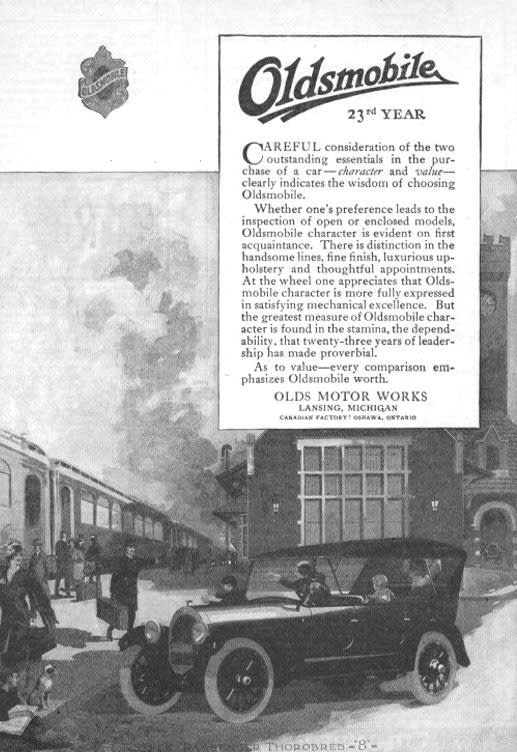
Oldsmobile1921
Oldsmobile1923

Oldsmobile1923
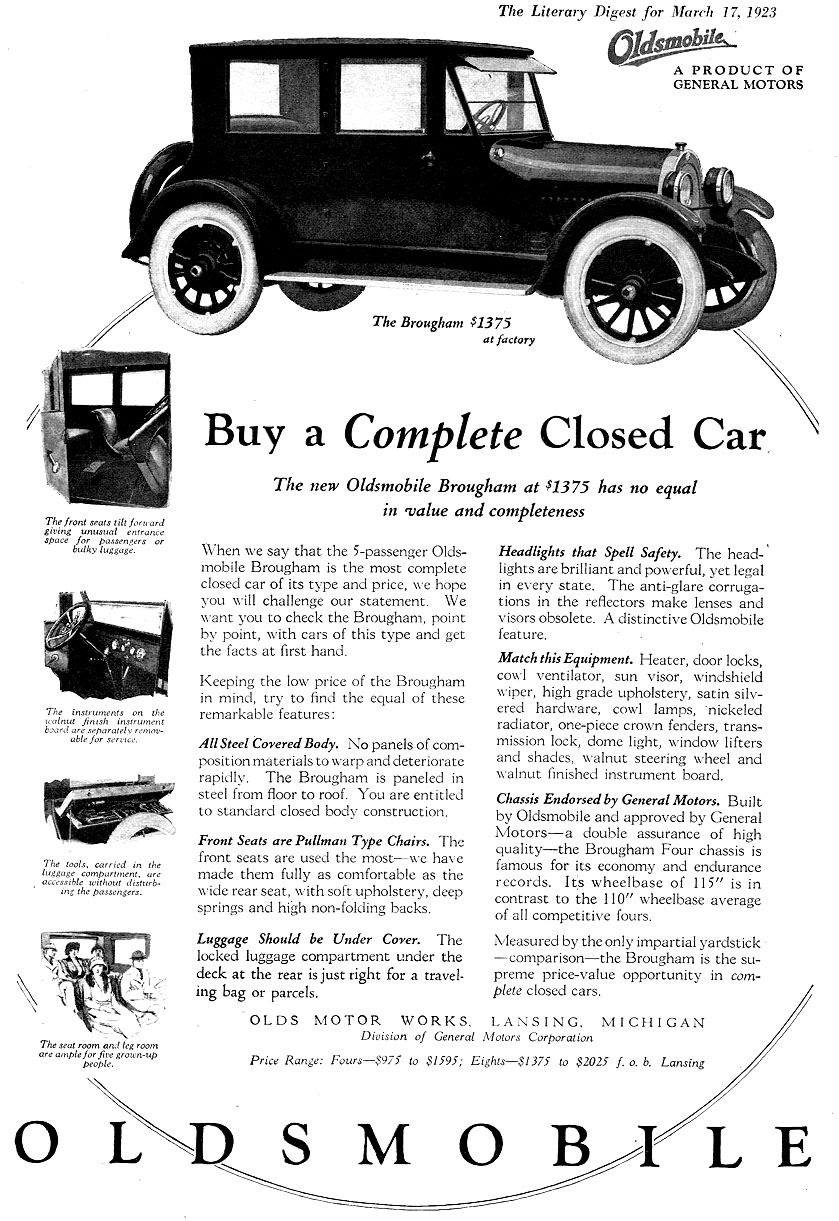
Oldsmobile1923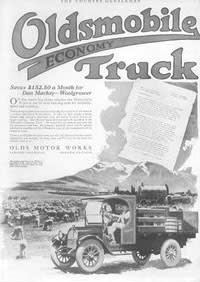
Oldsmobile1921
1900年代のオールズモビル広告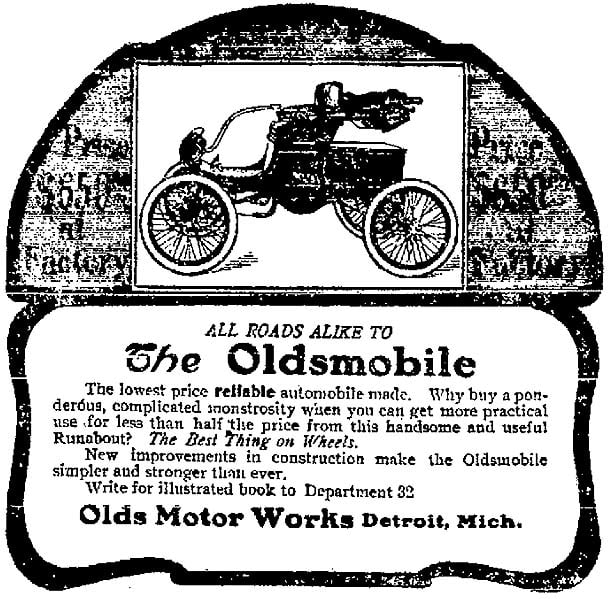
Wikipedia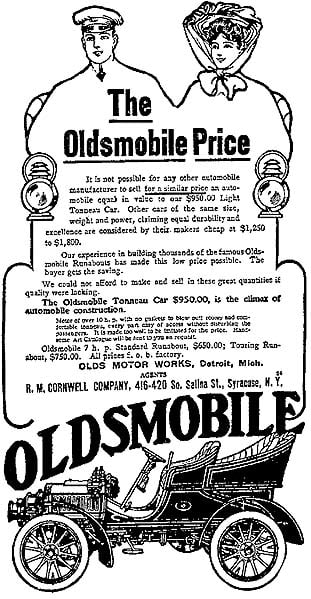
Wikipedia
Wikipedia
Wikipedia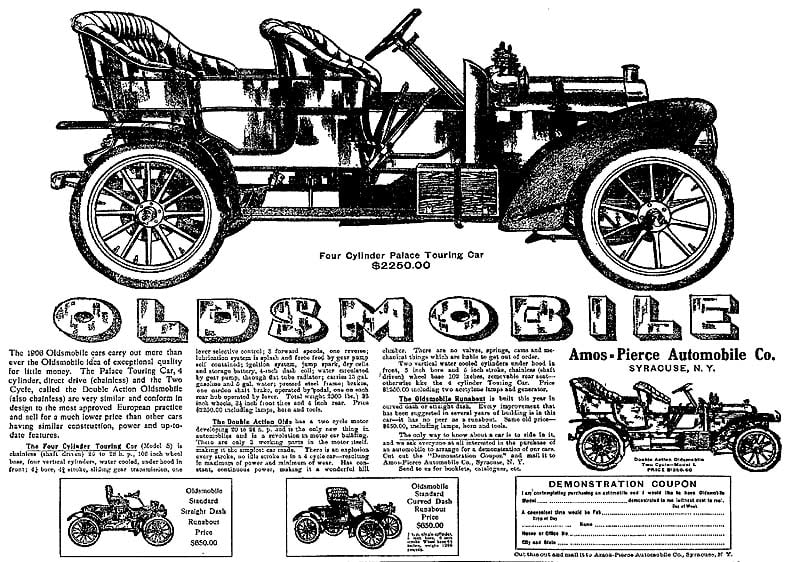
Wikipedia
Wikipedia
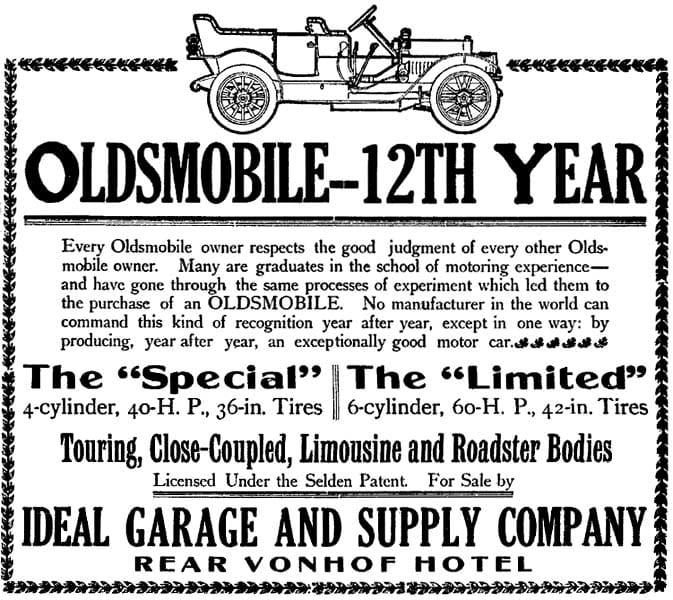
Wikipedia
Wikipedia
いまではやる物好きもいないだろうが、
かつて流行した汽車ポッポとのスピード競争。
クルマにある程度の信頼性がでてくると、
当時高速交通機関の代表であった鉄道への
挑戦を企てる者が出てくる。
強力なパワーをもつ陸の王者蒸気機関車に
勝利することが、ある種のステイタスだった
時代の話である。 トヨペット・SA型
トヨペット・SA型
Wikipedia
日本でも蒸気機関車とのスピード競争が行われている。
1948年8月7日にトヨタの販売促進イベントとしてSA型と呼ばれる
小型乗用車が、東海道本線の急行列車(当時は蒸気機関車が
引っ張っていた)に挑戦し勝利している。
名古屋駅を同時に出発し、大阪駅をめざしたが
トヨタ車が46分早く目的地に到着したという。
トヨタ自動車75年史というホームページに
SA型と蒸気機関車の競争を撮影した
画像が掲載されている。
https://www.toyota.co.jp/jpn/company/history/75years/text/taking_
on_the_automotive_business/chapter2/section8/item1_d.html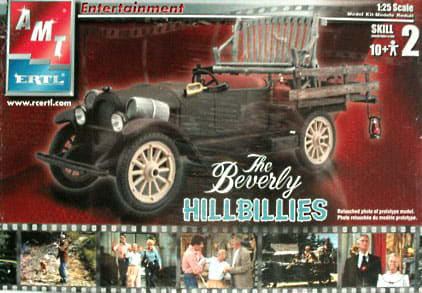
家財道具などの搭載品がないので、じゃじゃ馬自動車
最大の特徴たる後部フロア特設木製座席の
様子がわかり興味深い。
じゃじゃ馬関連クルマは
オールズモビルばかりではないゾ!
YouTube
YouTube
銀行頭取(左)のドライスデール(レイモンド・ベイリー)と
秘書のハサウェイ(ナンシー・クルプ)。
頭取さんはクランペット家が預金を解約してしまうのを非常に
恐れている(いったいどれほどの預金額なのだろうか?)。
解約されそうになると、いろいろな策を講じるのだが、
自らドロをかぶるようなことはやらず、みな秘書に
丸投げ。そんな訳で、秘書は頭取さんの尻ぬぐいに
奔走することになる。
ところで、秘書は赤のダッジ・コンバーチブルを
日常業務の足としていつも颯爽と乗り回している。
番組のシーズンによってクルマの変更があるが、
ダッジ・コンバーチブルであることは変わりがない。
これは私の勝手な想像なのだが、秘書は実のところ
頭取の愛人であり頭取は銀行のカネで秘書がお気に入り
のクルマを買い与えていたのではないだろうか。
それは日頃の自分の尻ぬぐいに走り回る秘書への
感謝の念であったかもしれない。
秘書の愛車 ダッジ・ポラーラ・コンバーチブル1963年型
YouTube
YouTube
YouTube
ダッジ1963年型各種広告
CHRYSLER
CHRYSLER
CHRYSLER
CHRYSLER
CHRYSLER
CHRYSLER
CHRYSLER
CHRYSLER
CHRYSLER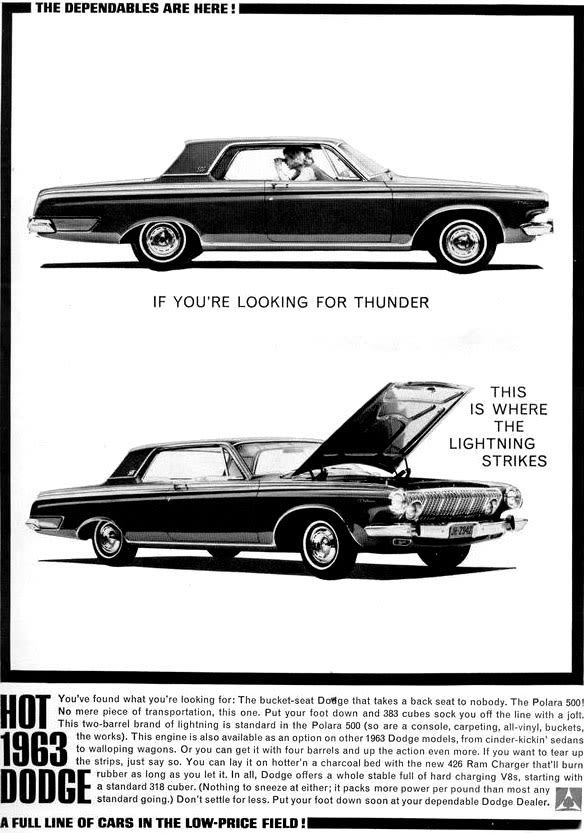
CHRYSLER
CHRYSLER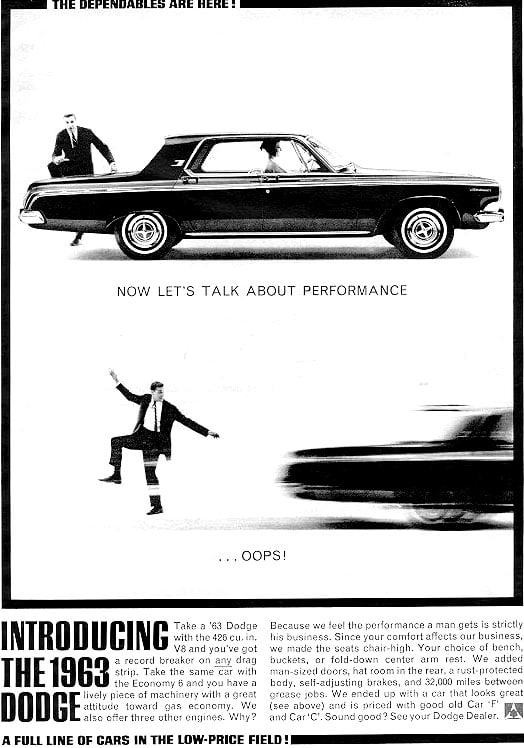
CHRYSLER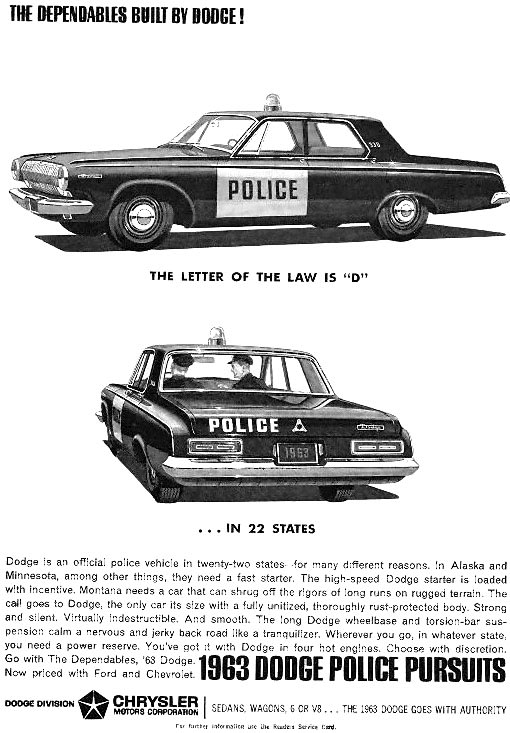
CHRYSLER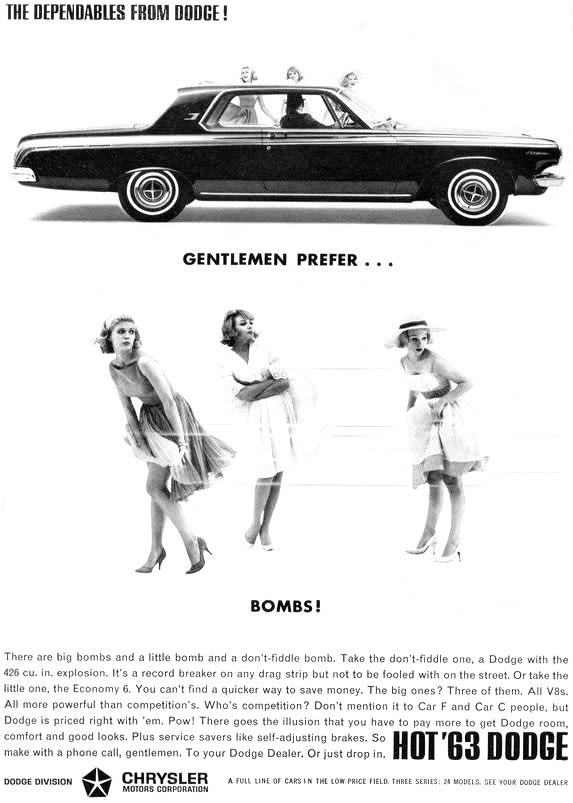
CHRYSLER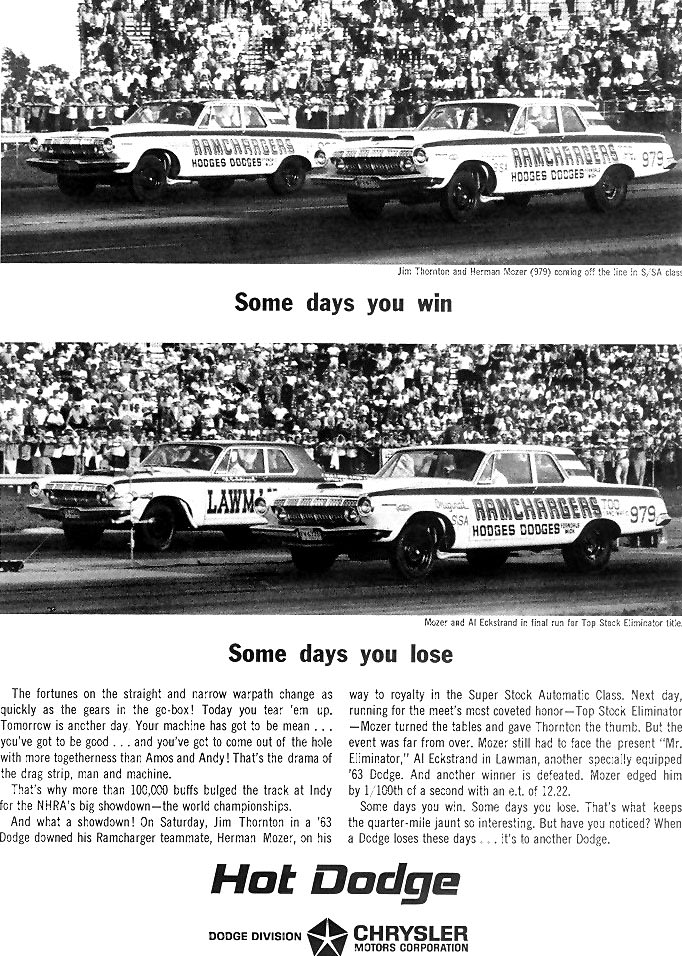
CHRYSLER
CHRYSLER
秘書の愛車 ダッジ・ポラーラ・コンバーチブル1963年型登場
https://www.youtube.com/watch?v=80RUI7MDXQo
秘書の愛車 ダッジ・コロネット・コンバーチブル1965年型
YouTube
YouTube
YouTube
YouTube
YouTube
ダッジ1965年型各種広告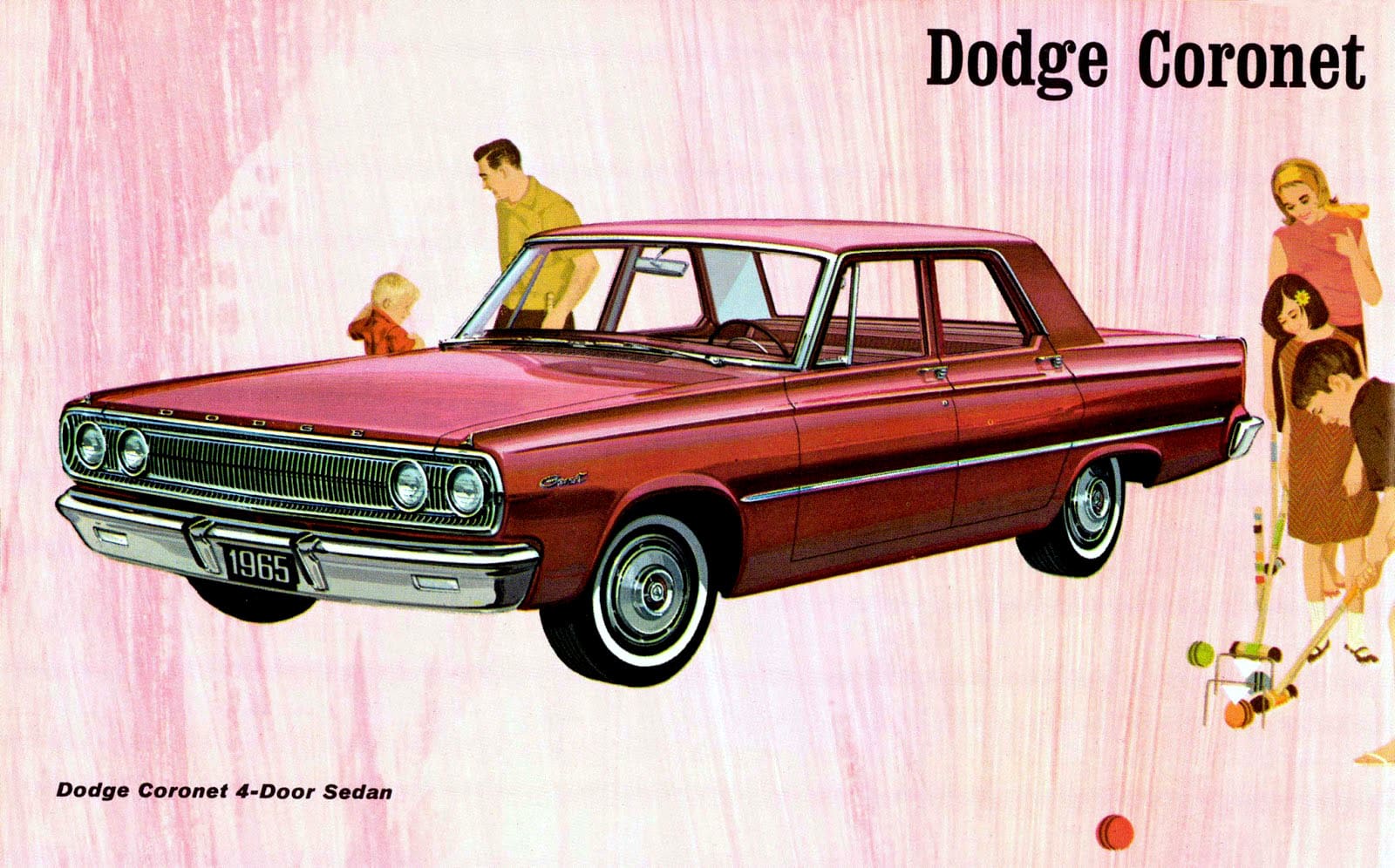
CHRYSLER
CHRYSLER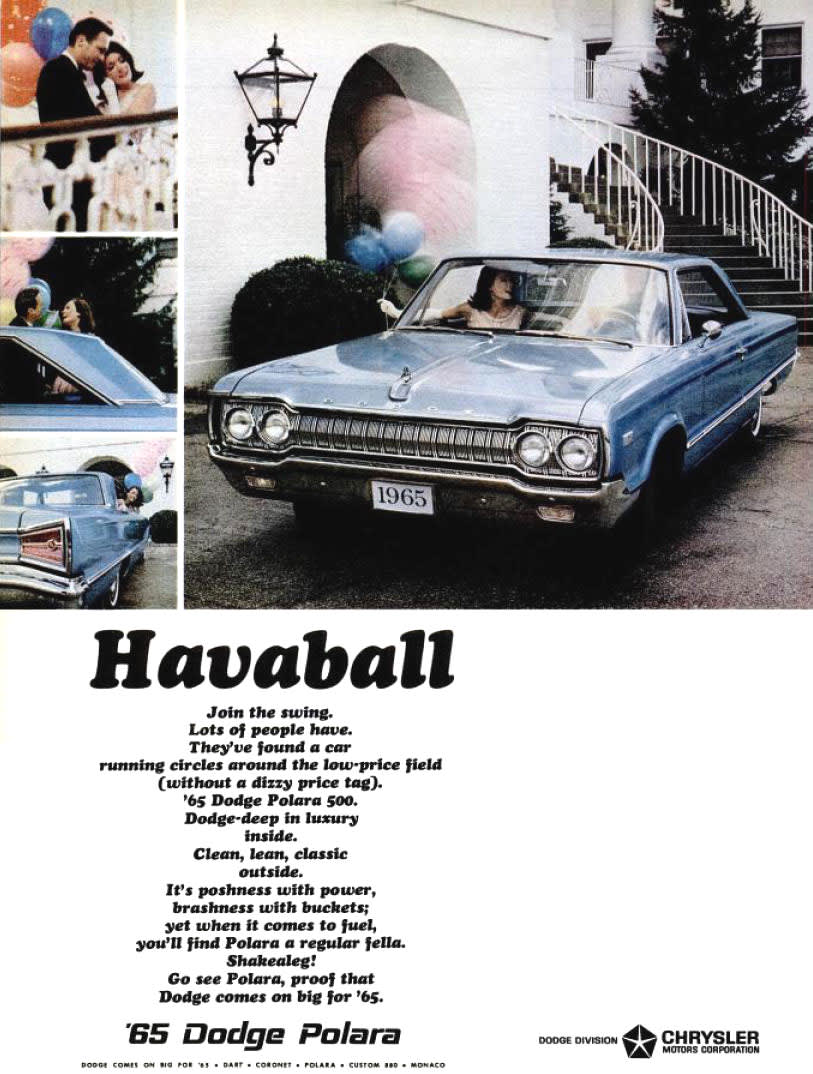
CHRYSLER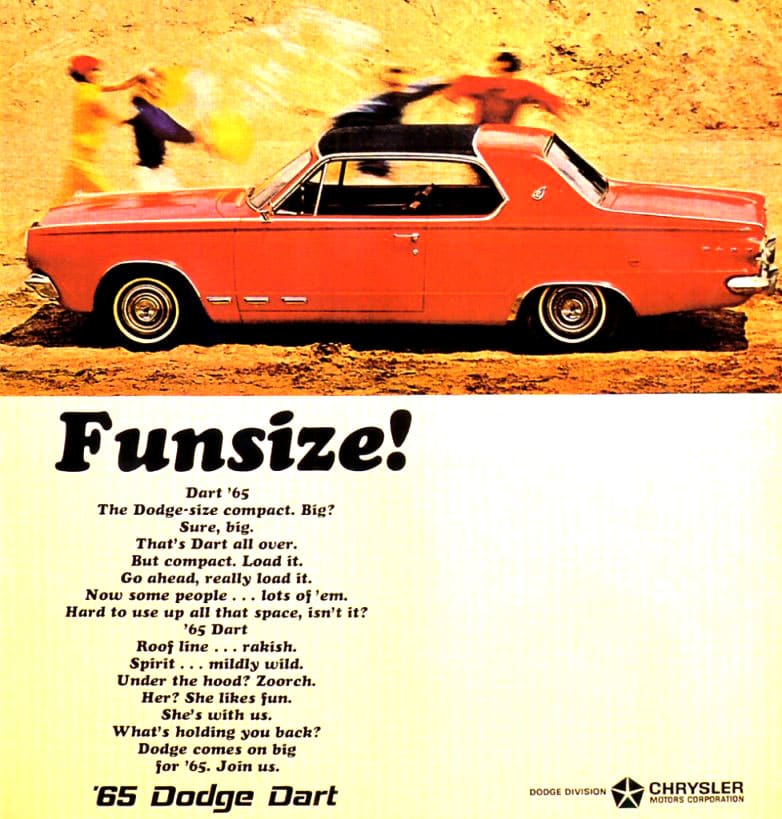
CHRYSLER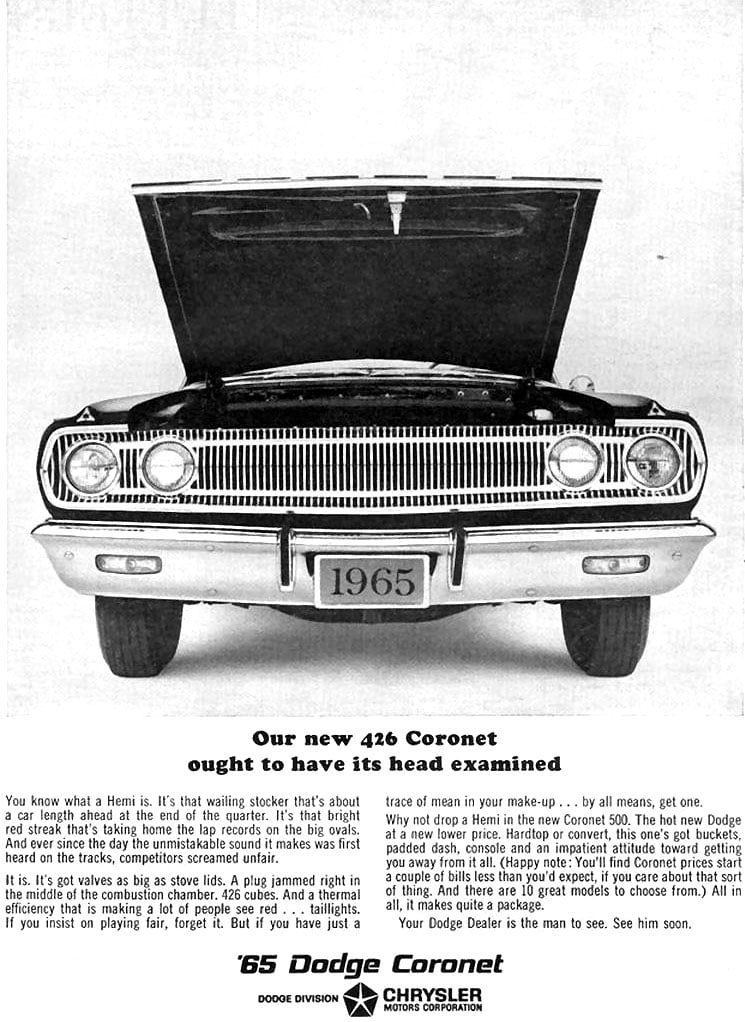
CHRYSLER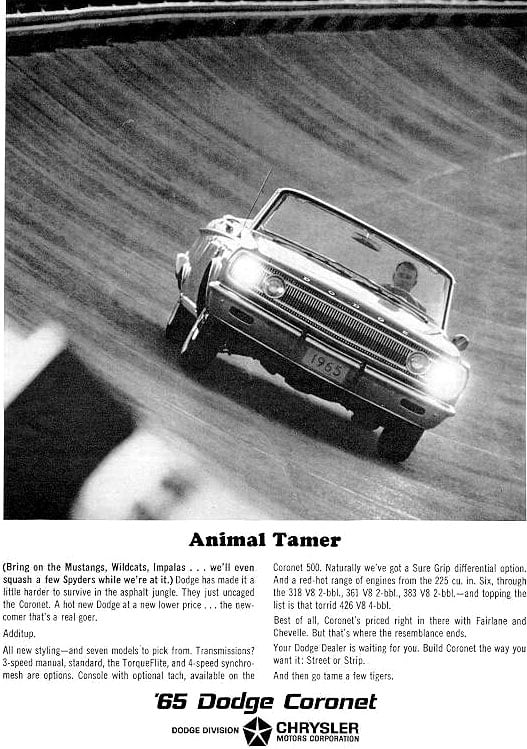
CHRYSLER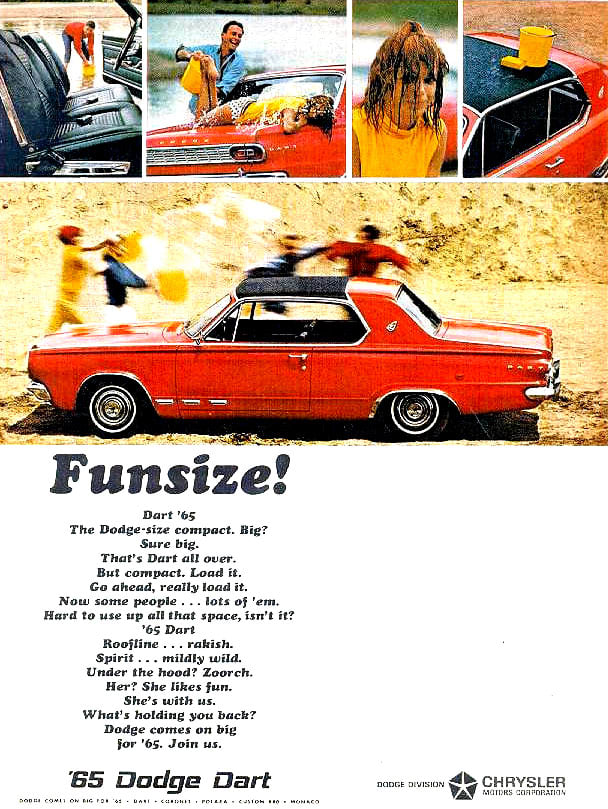
CHRYSLER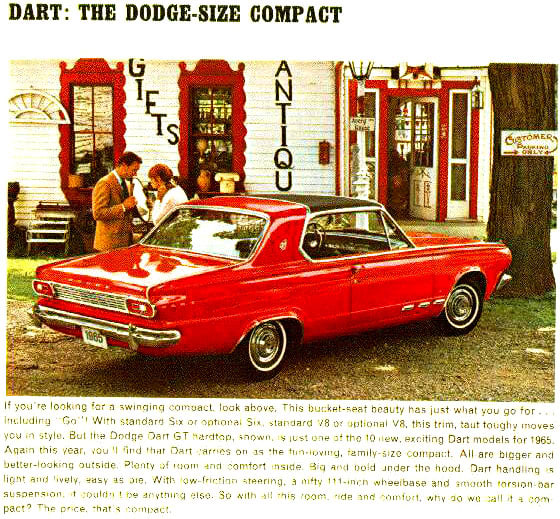
CHRYSLER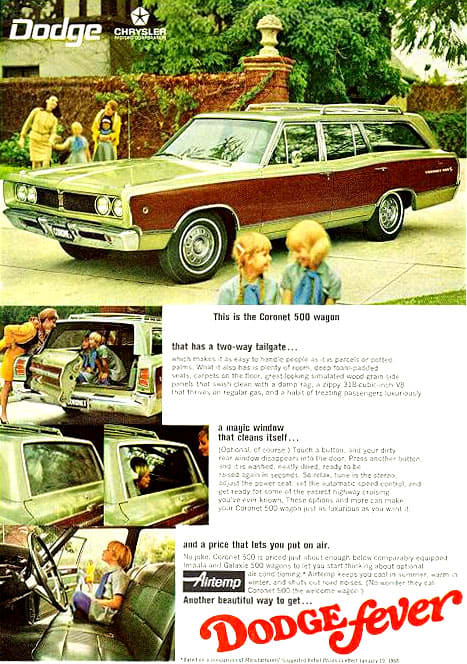
CHRYSLER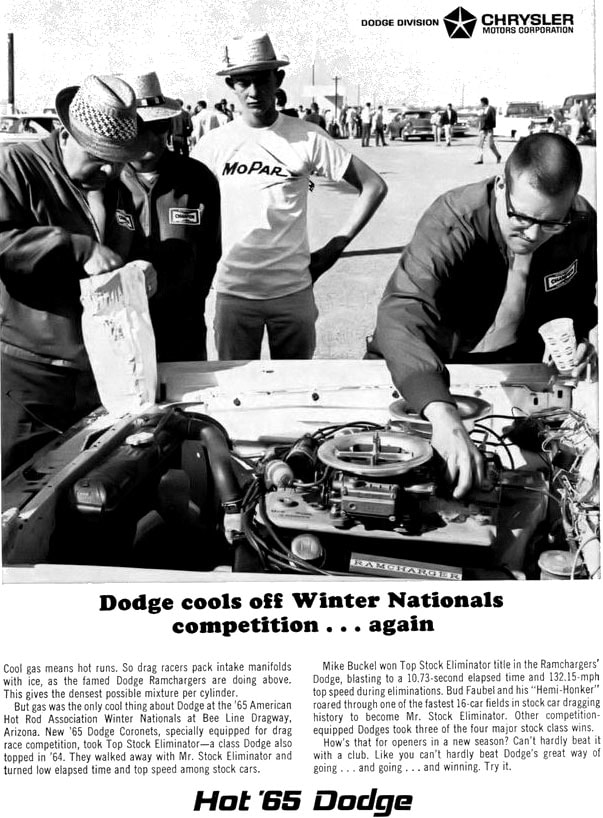
CHRYSLER
CHRYSLER
秘書の愛車 ダッジ・コロネット・コンバーチブル1965年型登場(モノクロ)
https://www.youtube.com/watch?v=dA4EJ1Nw0yg
秘書の愛車 ダッジ・コロネット・コンバーチブル1965年型登場(カラー)
https://www.youtube.com/watch?v=DsqY-HAOVW0
秘書の愛車 ダッジ・チャレンジャー・コンバーチブル
1971年型
YouTube
ダッジ1971年型各種広告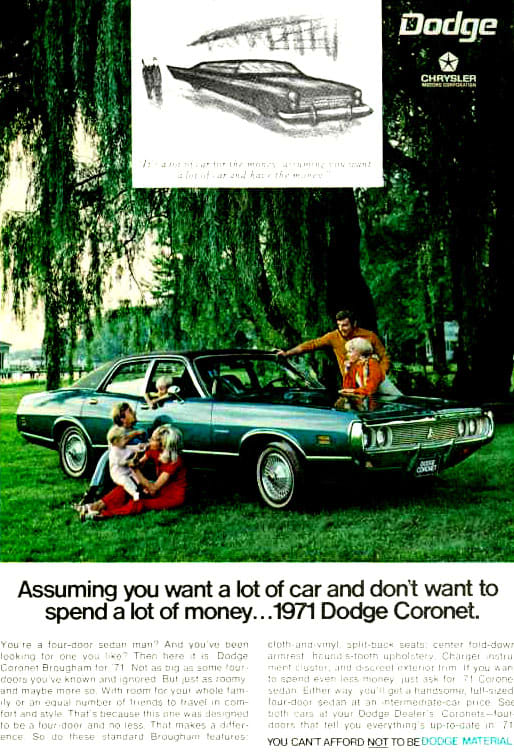
CHRYSLER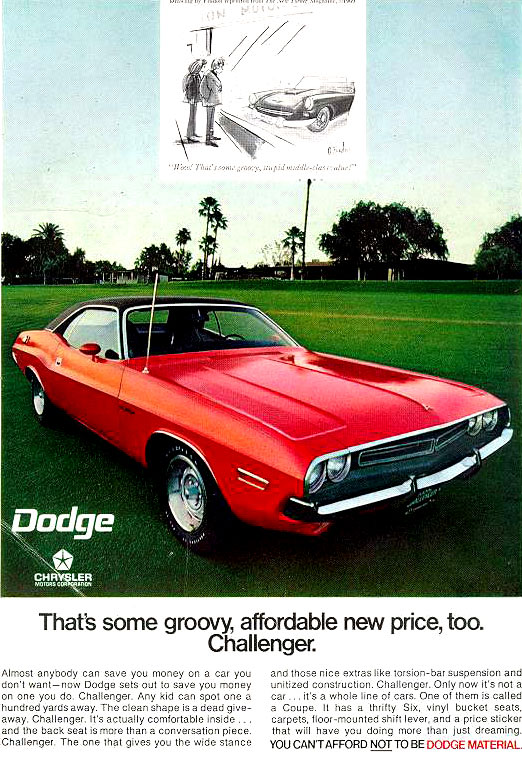
CHRYSLER
CHRYSLER
CHRYSLER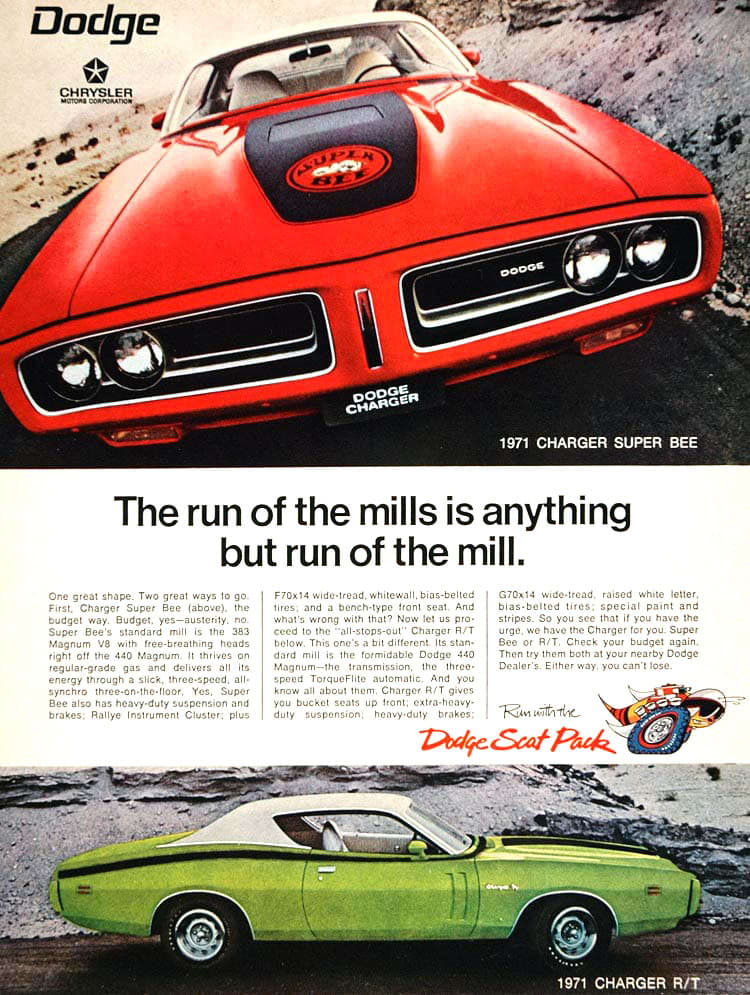
CHRYSLER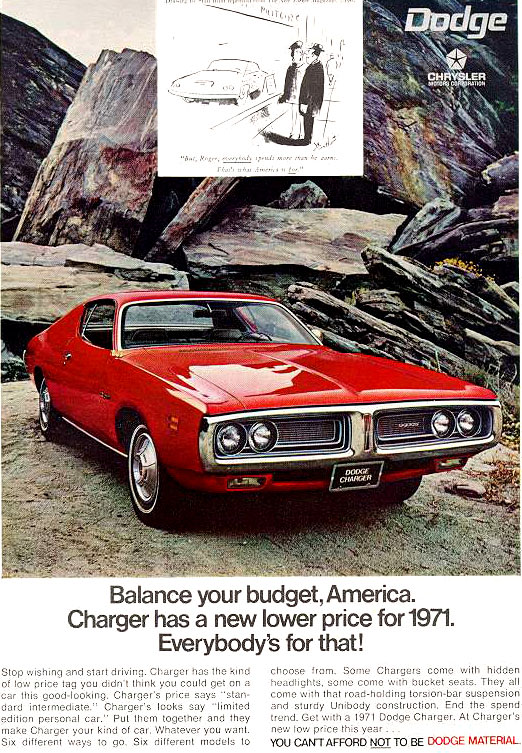
CHRYSLER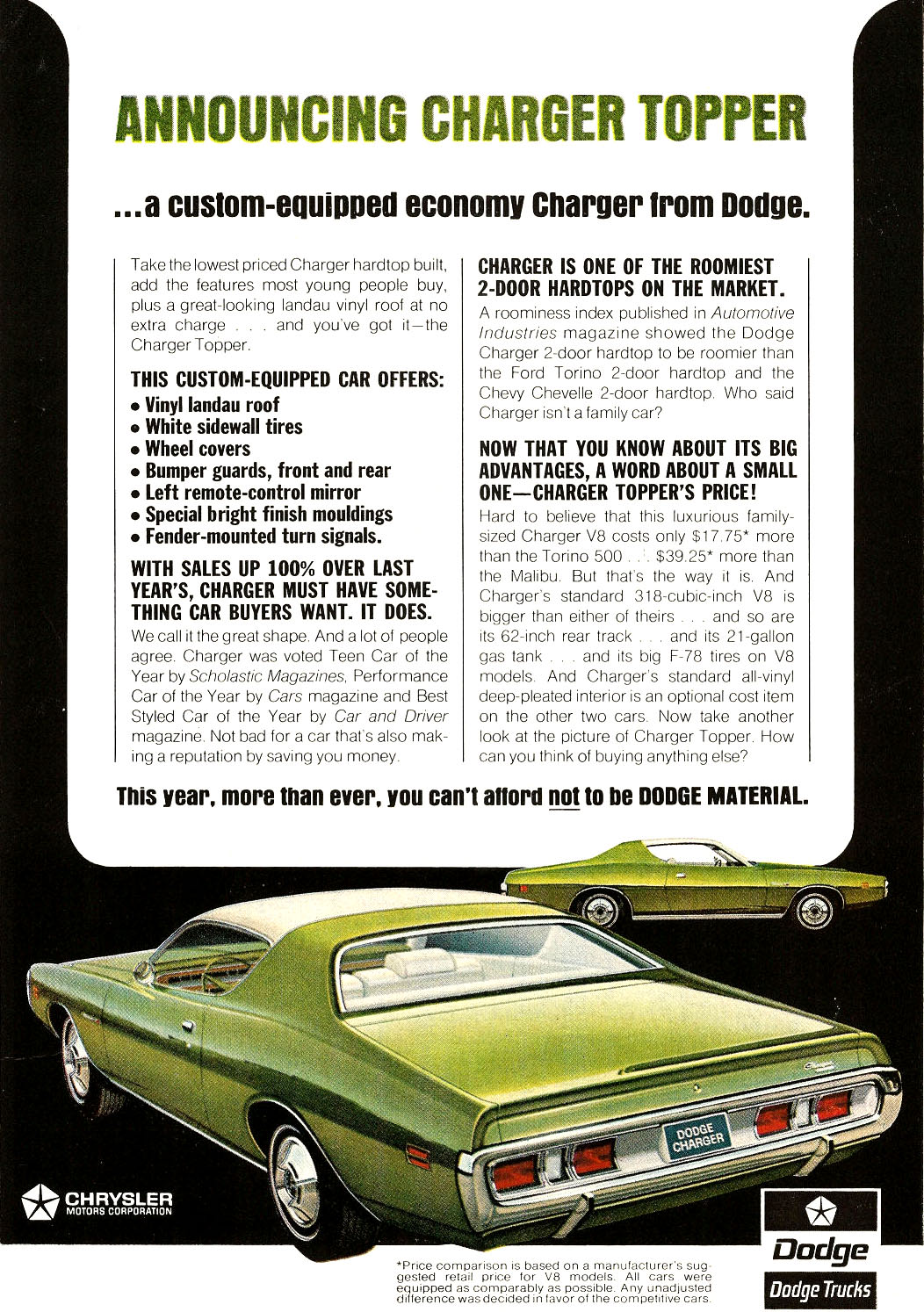
CHRYSLER
CHRYSLER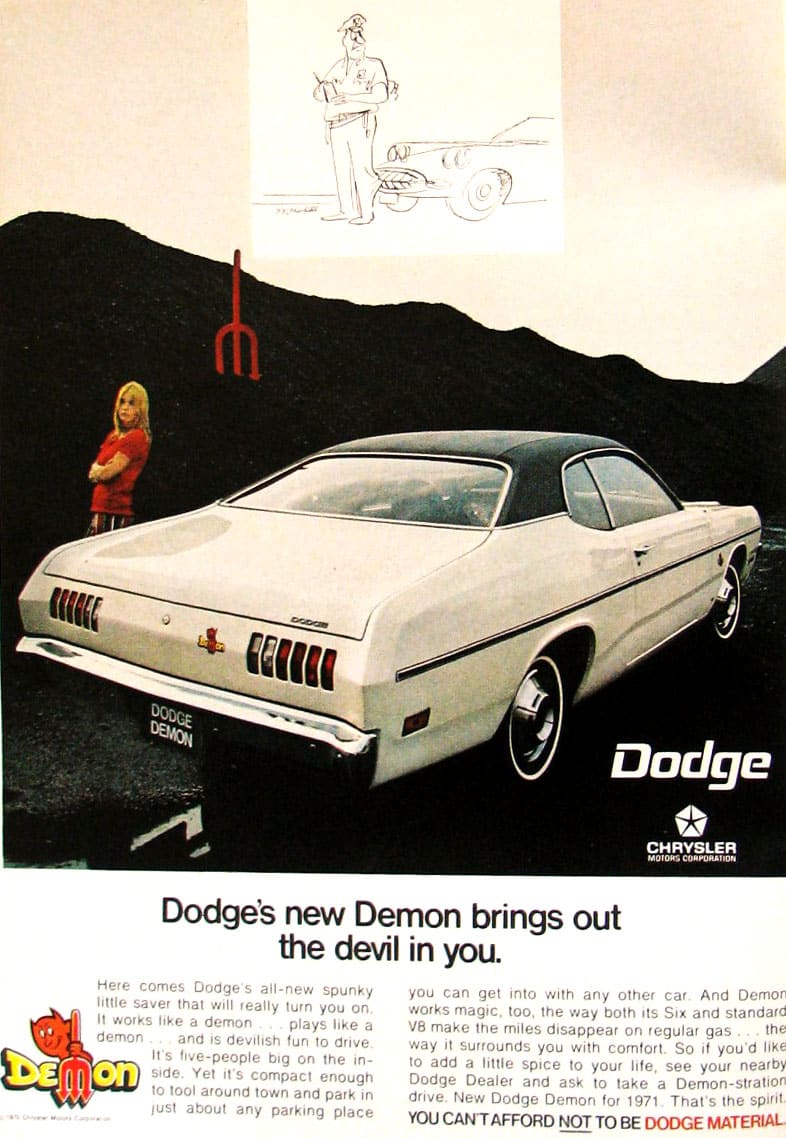
CHRYSLER
CHRYSLER
Wikipedia

秘書の愛車 ダッジ・チャレンジャー・コンバーチブル
1971年型登場エピソード
https://www.youtube.com/watch?v=IHNe7UO9Hpc
頭取さんの愛車 インペリアル・クラウン1962年型
YouTube
頭取のドライスデール氏が乗るクルマは、クライスラーの
最高級車インペリアル・クラウン1962年型。
やはりお偉いさんが乗るクルマは違う。
YouTube

YouTube
YouTube
クランペット家と頭取さんのクルマが登場。
http://www.youtube.com/watch?v=Q8bNdFfWVtk
YouTube
YouTube
最高級車なので雨漏りなど絶対に許されない(安いクルマなら
雨漏りしてもいいという話ではないが‥‥)。そのため徹底した
水密テストが行われる。
インペリアル・クラウン1962年型プロモーション・フィルム
http://www.youtube.com/watch?v=GGqDzW3Z8-w
インペリアル・クラウン1962年型各種広告
CHRYSLER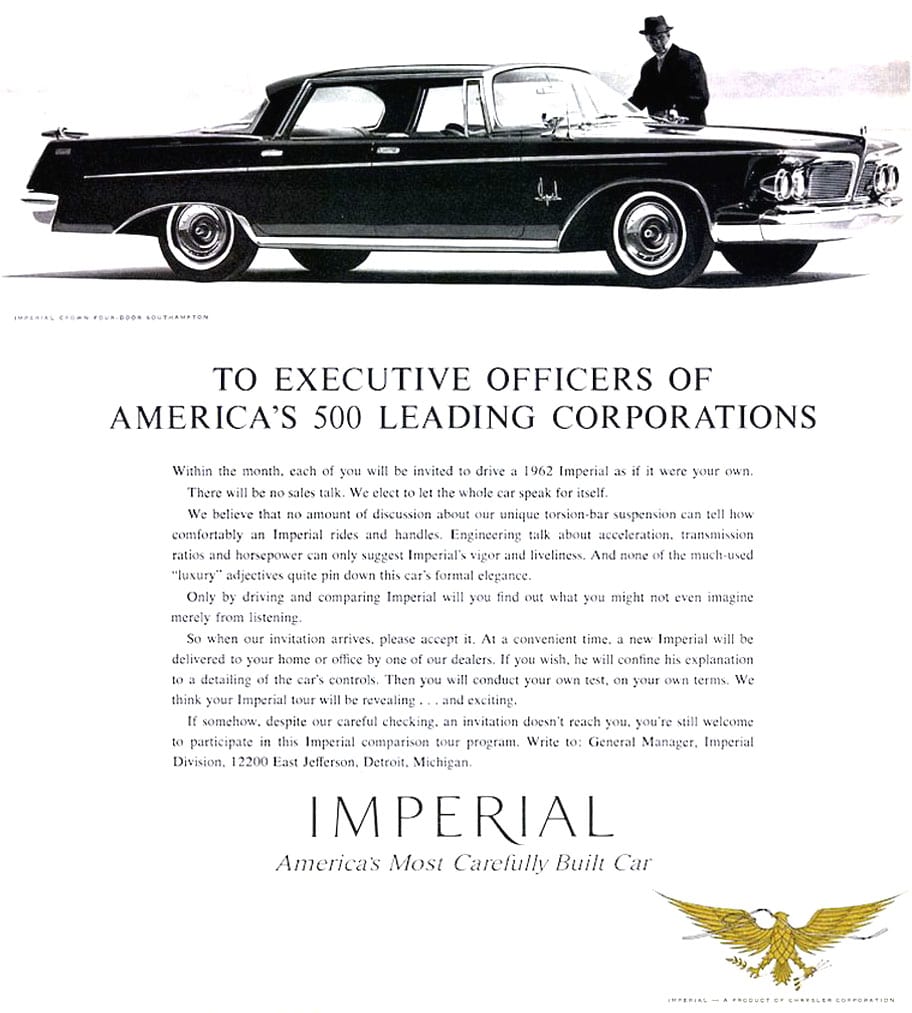
CHRYSLER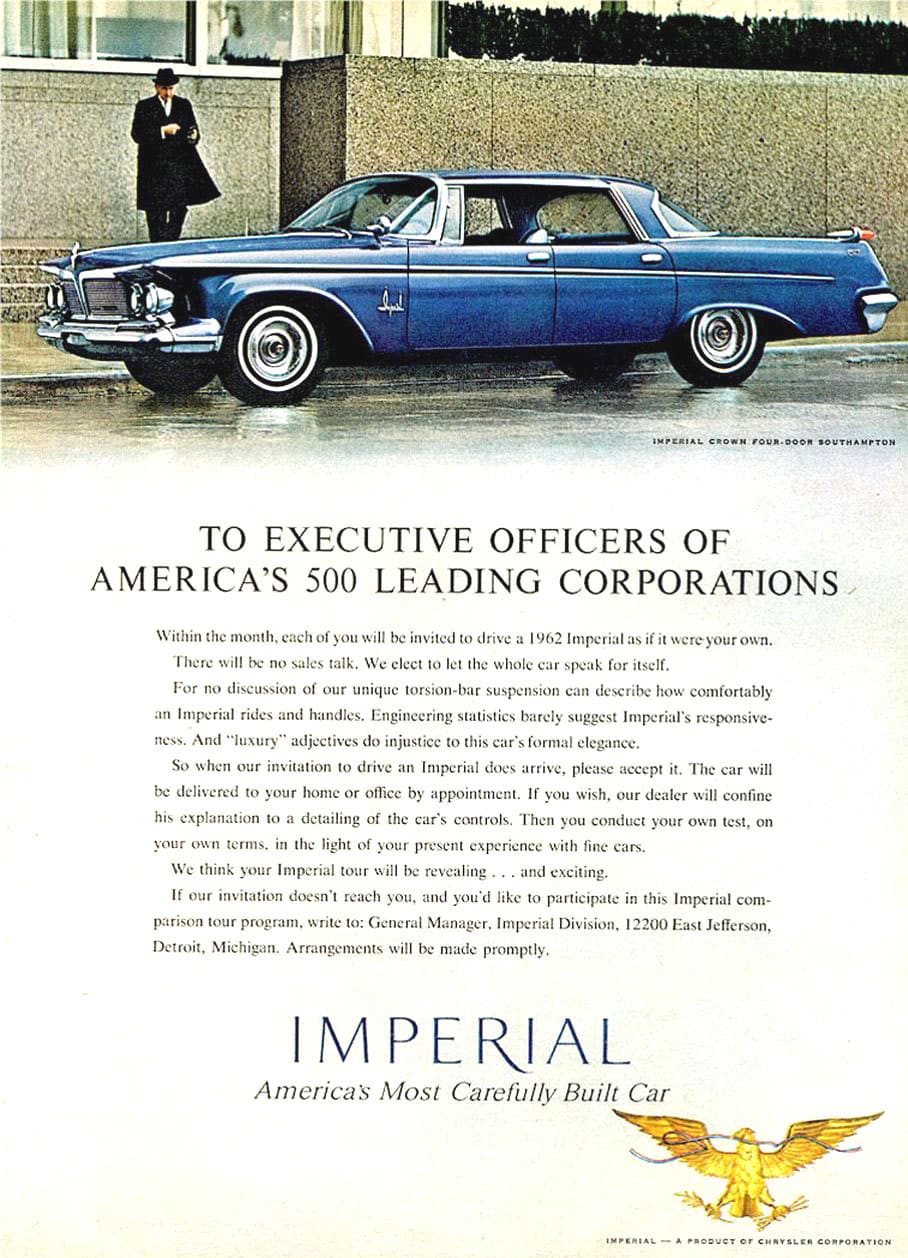
CHRYSLER
CHRYSLER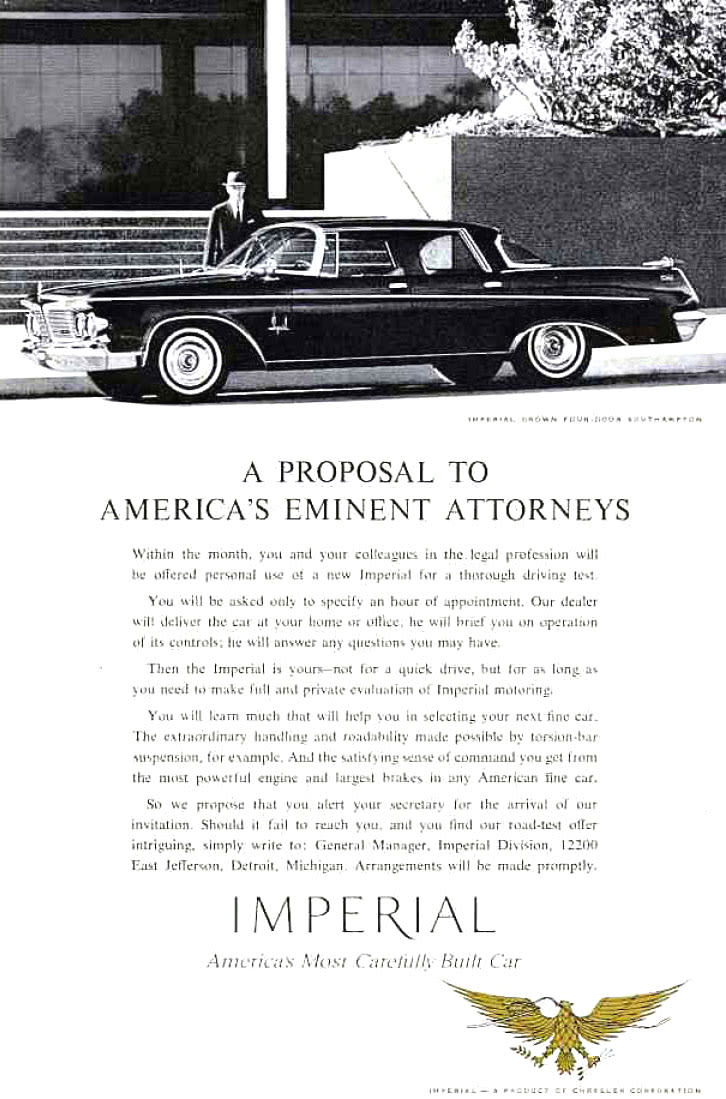
CHRYSLER
CHRYSLER
CHRYSLER
CHRYSLER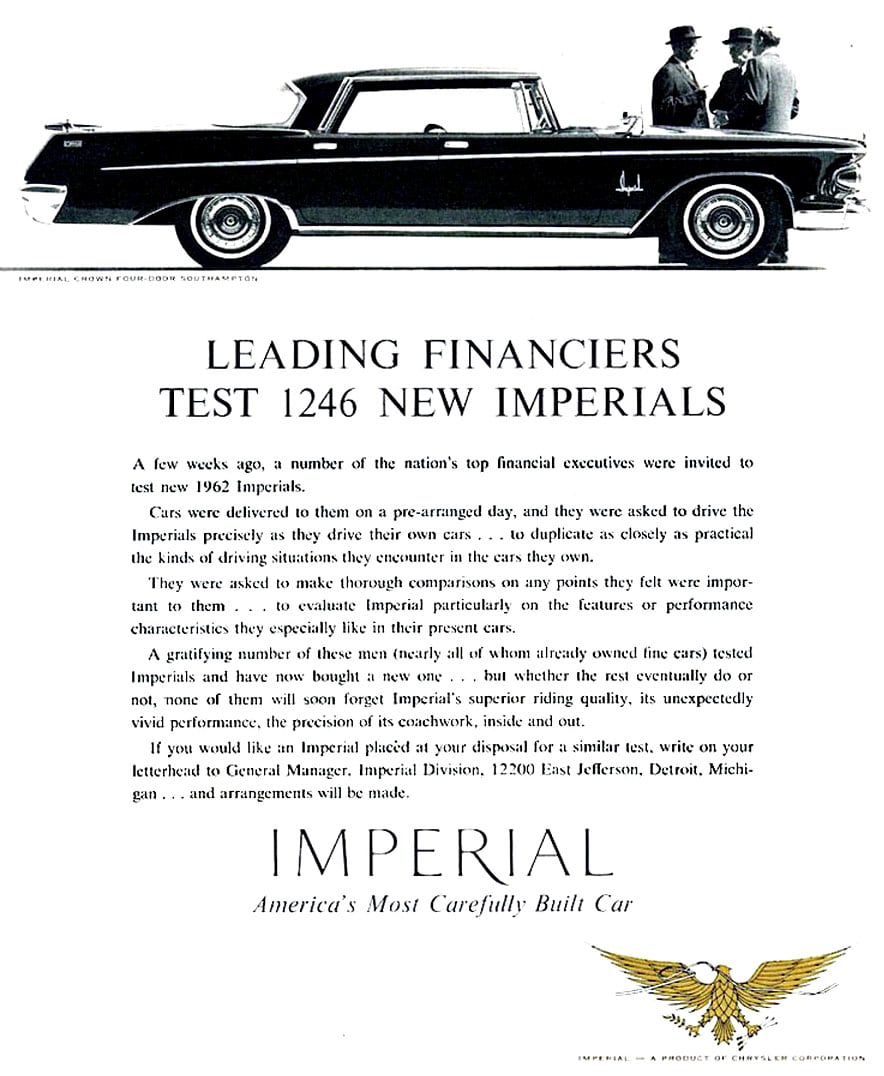
CHRYSLER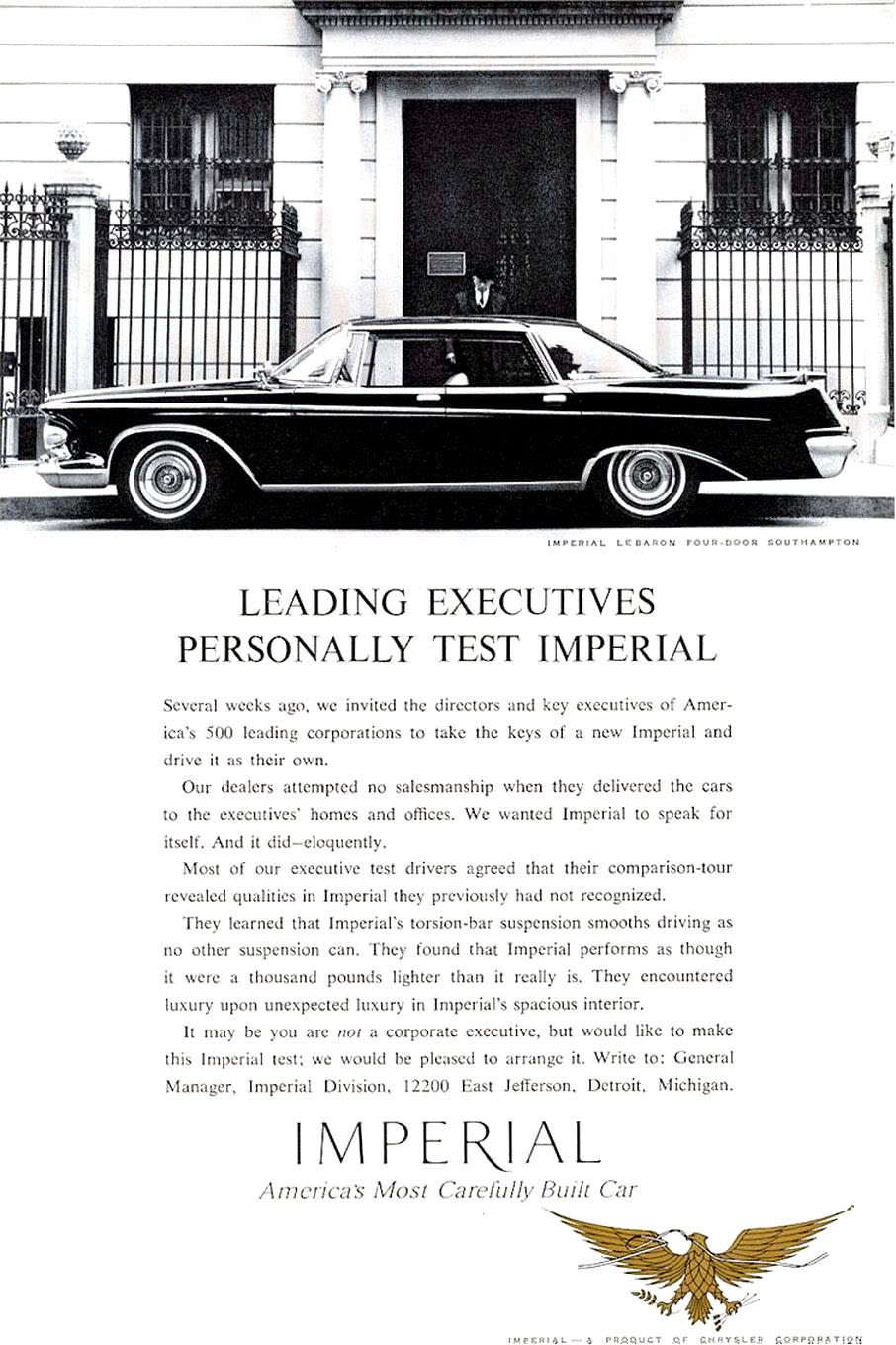
CHRYSLER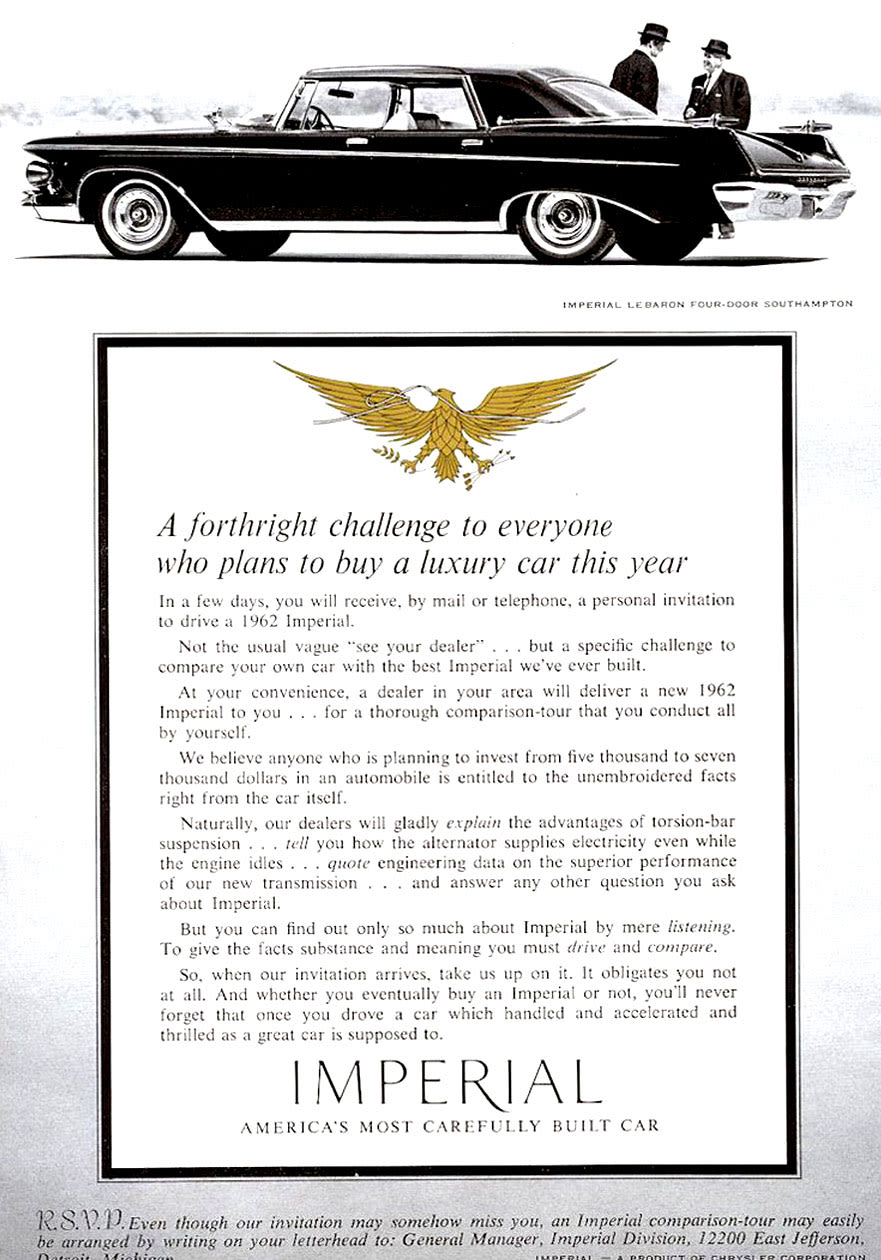
CHRYSLER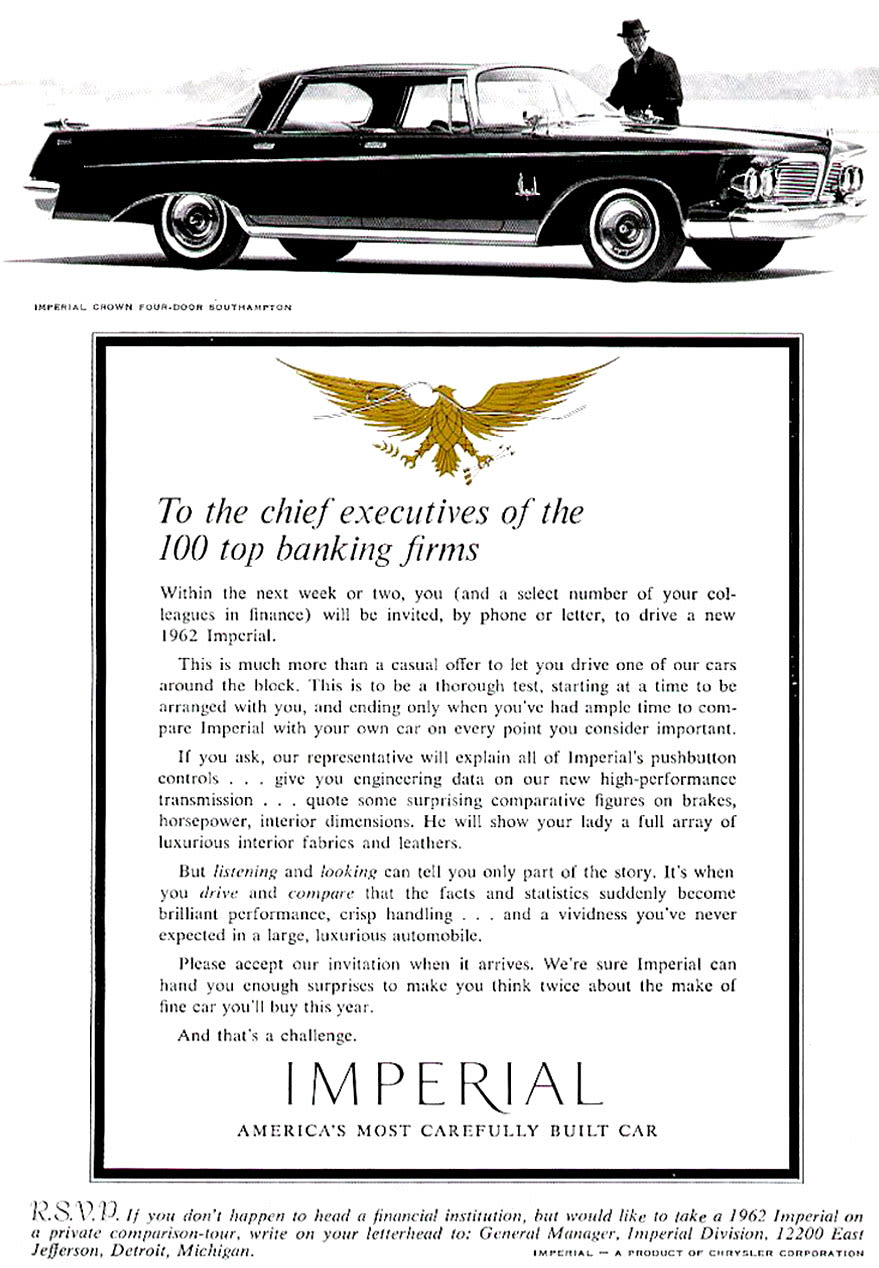
CHRYSLER
CHRYSLER
ところで…
銀行のお偉いさんと秘書といえば、『ザ・ルーシー・ショー』も
忘れられない。副頭取のムーニー(ゲール・ゴードン)と秘書の
ルーシー(ルシル・ボール)が繰り広げるドタバタ騒動が
なんとも傑作だった。
なお、秘書のおバカ度ではルーシーがダントツだと思うが
いかがだろうか。
YouTube
ロンドンへ旅行することになったルーシー。
搭乗した旅客機で出張するムーニーさんと
一緒になってしまう。
困惑するムーニーさんなど眼中にないルーシーだが、
慣れない空の旅でとんだ騒ぎが…
http://www.youtube.com/watch?v=eI8BaL7vreI
じゃじゃ馬屋敷、今と昔…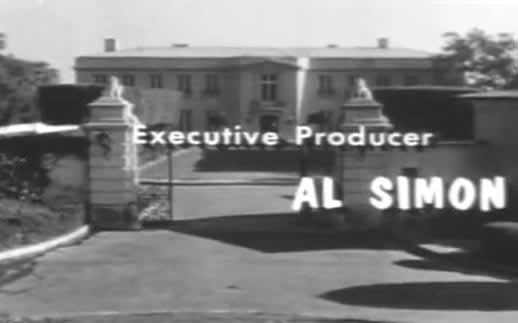
YouTube
ドラマ放送当時のクランペット邸。
Google Earth
現在のクランペット邸。
建物は放送当時となんら変わっていない。
変化といえば塀に植物がからまり、生垣風に
なったことくらいか。
この邸宅はドラマ用のセットではなく、
個人の住宅(!)というからスゴい。
Arnold Kirkeby(1901~1962)という
アメリカのホテル経営者の邸宅で、
『じゃじゃ馬億万長者』以外にも多くの
ドラマや映画のロケに使われている。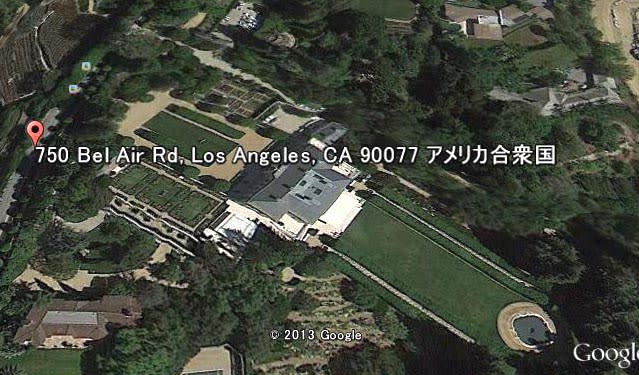
Google Earth
クランペット邸はビバリーヒルズにあるというドラマ設定だったが、
実際の所在地はビバリーヒルズ近隣のベル・エア地区。
もちろん、この地も高級住宅地。
住所 750 Bel Air Road, Los Angeles, CA, United States
YouTube
クランペット邸(Kirkeby邸)空撮映像。
屋敷の広大さがよ~くわかる。
https://www.youtube.com/watch?v=Xcot7ZvxIog
おやっ?
YouTube
芸者さんが登場するエピソード。
肩もみで癒され、ジェドも心からご満悦。
https://www.youtube.com/watch?v=4vj0SnP9X9A
YouTube
オマケ
ウルトラ警備隊の出動車は
インペリアルだった!
YouTube
YouTube
YouTube
YouTube
YouTube
YouTube
初期のウルトラマンシリーズに登場したクルマで
もっともカッコいいクルマといえば、ウルトラ警備隊
御用達のポインターではないだろうか。
Wikipedia
インペリアル1957年型
本車はポインターのベースになったことで知られているが
あまりの変わり様に驚いてしまう。
それだけ番組制作者のヤル気というか熱意の表れという
ことができようか。
1957年型ではないが参考まで…
インペリアル・クラウン1957年型各種広告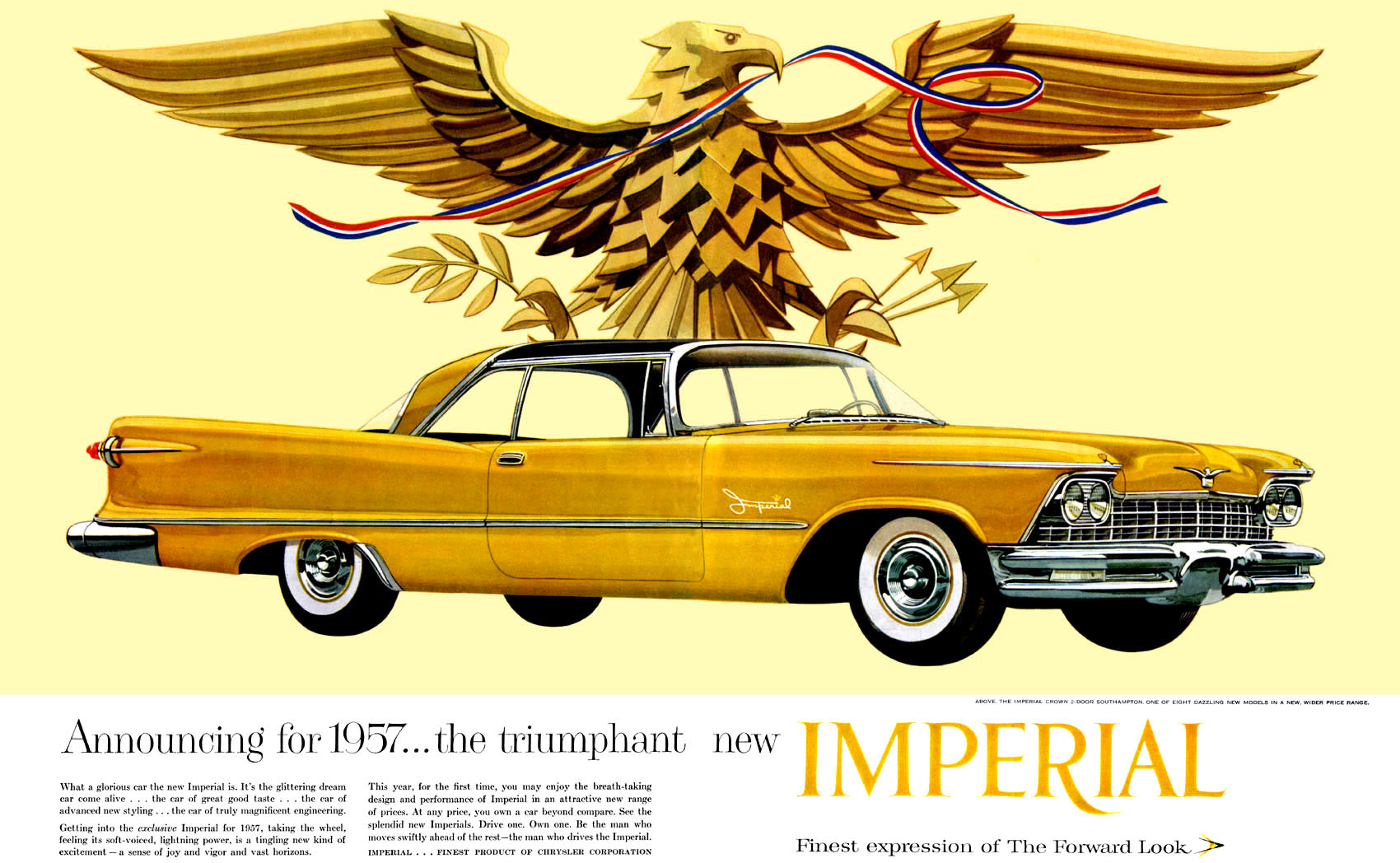
CHRYSLER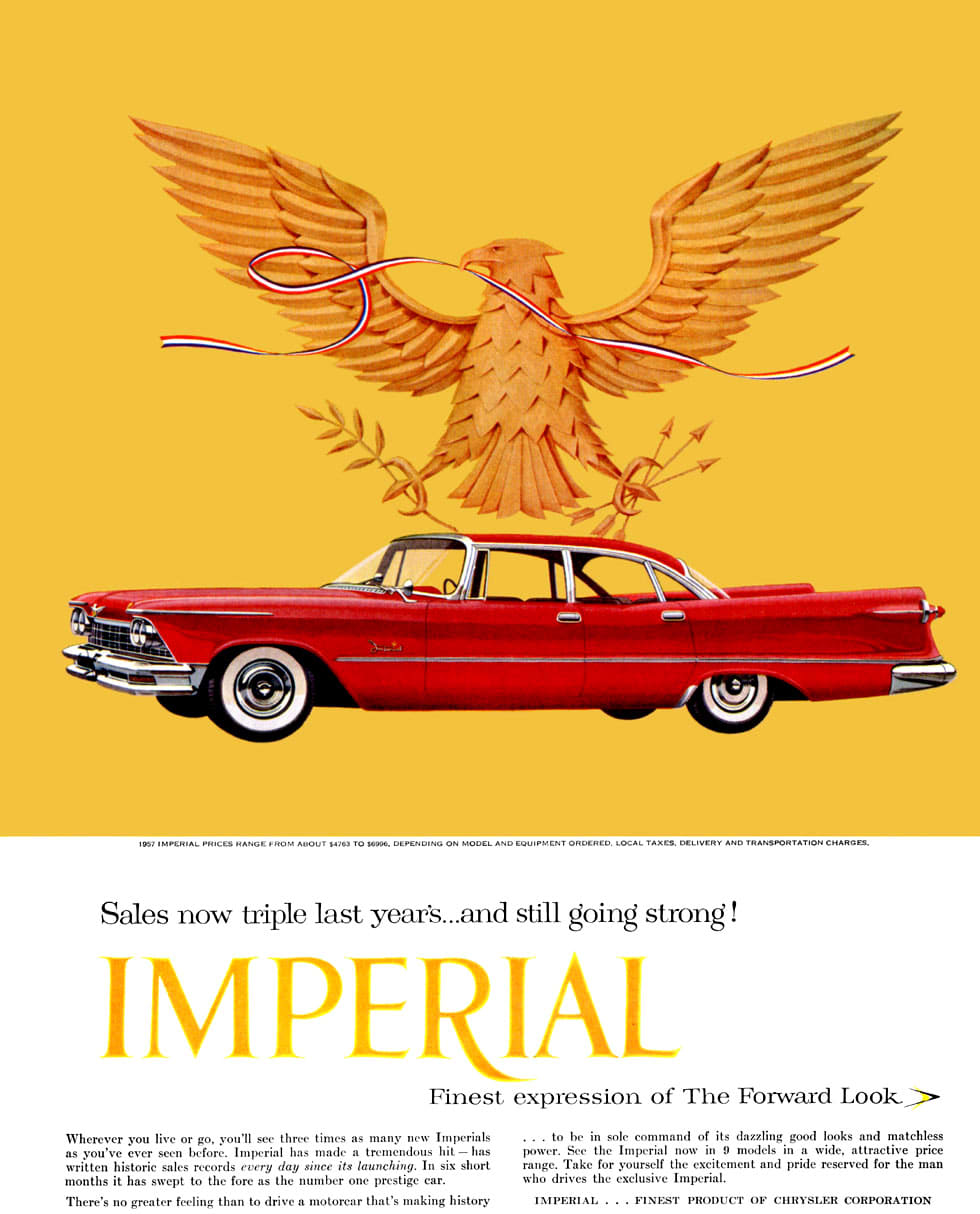
CHRYSLER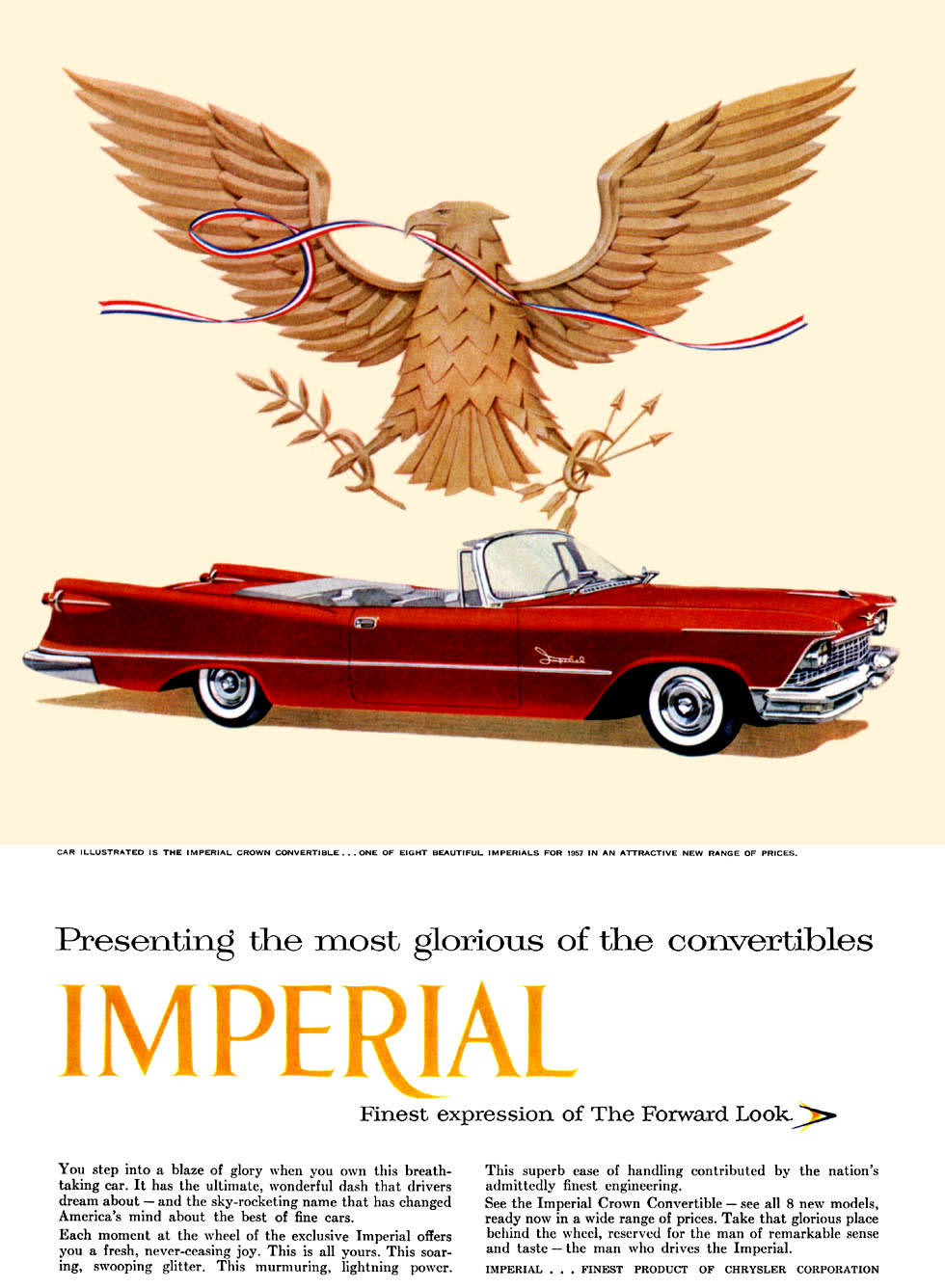
CHRYSLER
CHRYSLER
CHRYSLER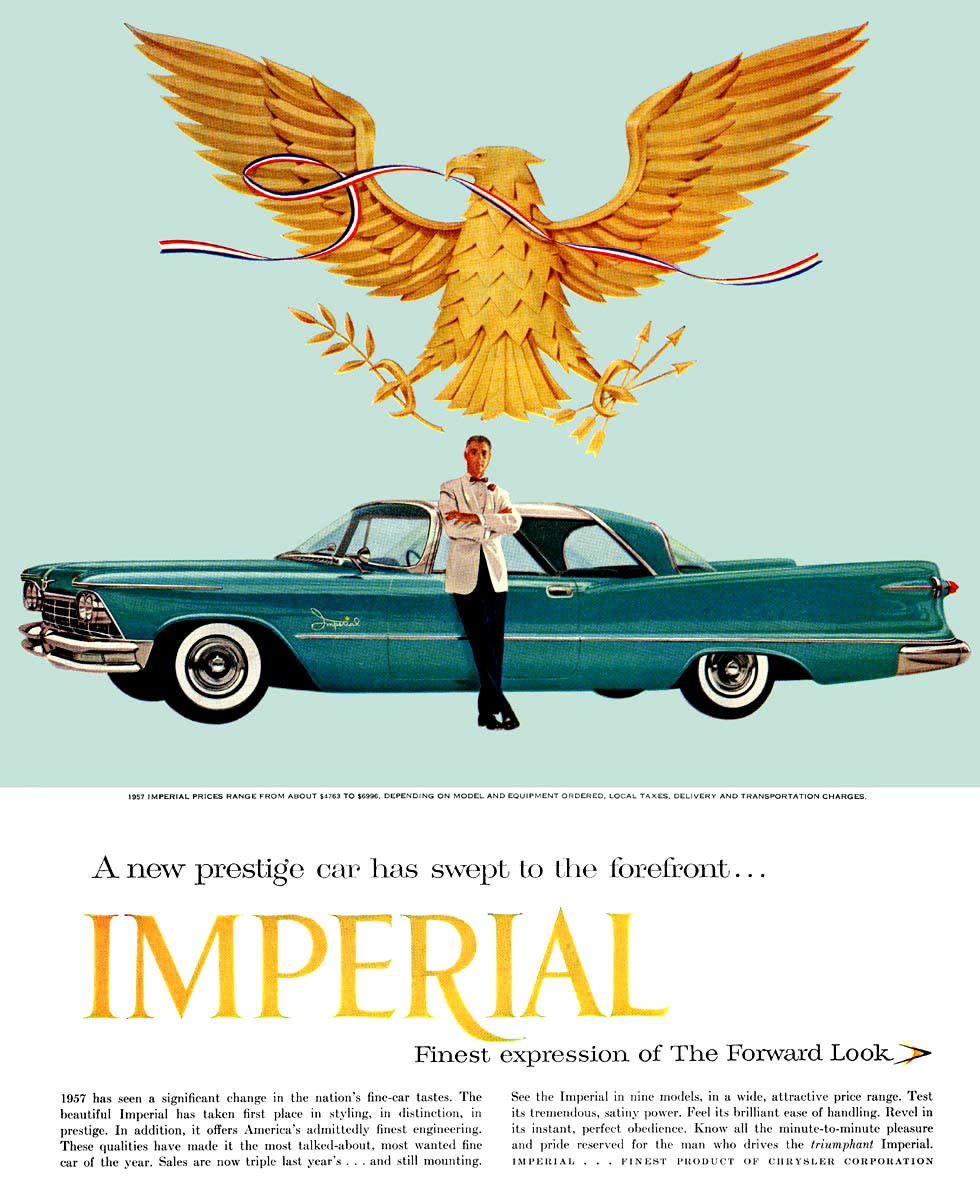
CHRYSLER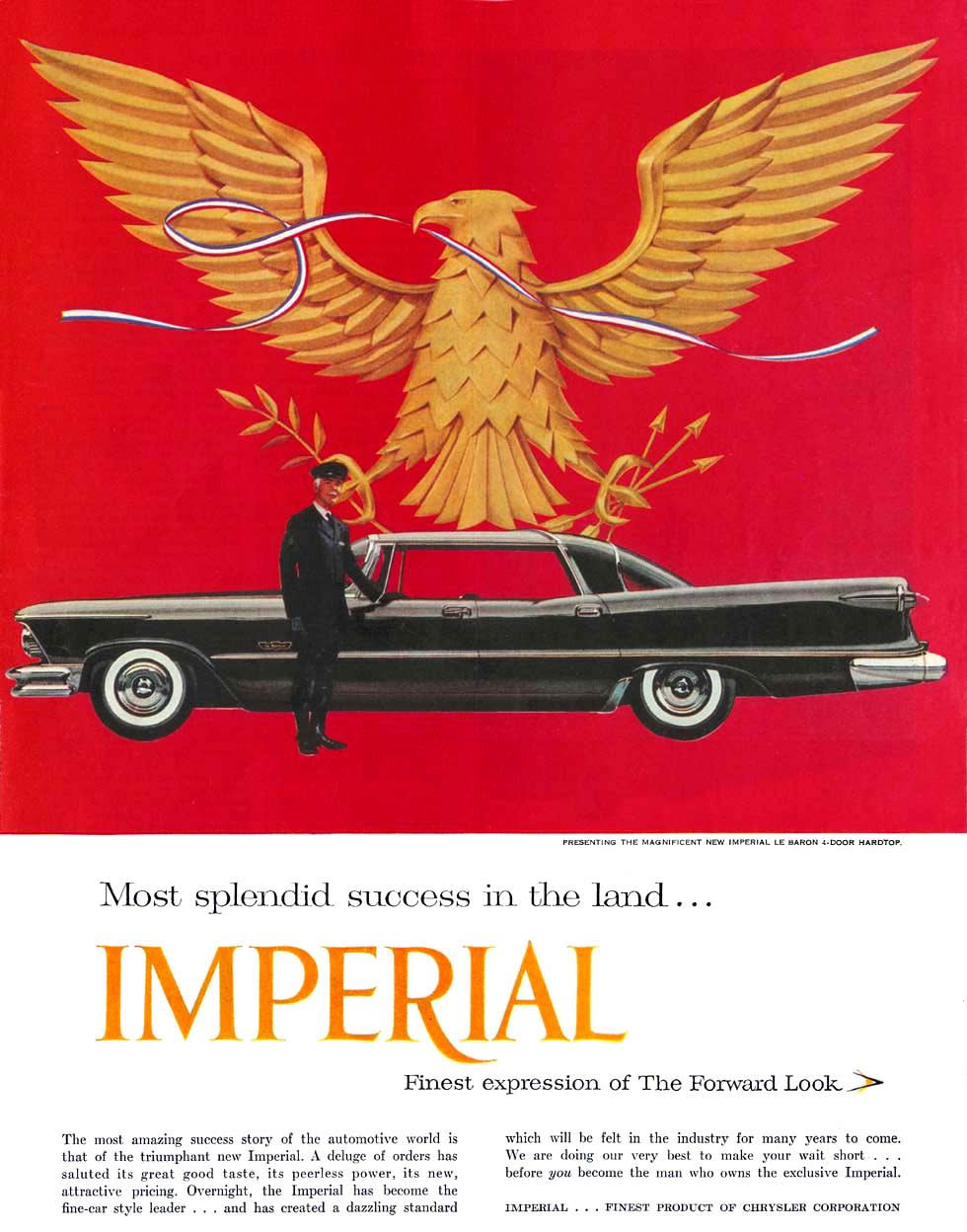
CHRYSLER
CHRYSLER
上2枚の広告画像にはお抱え運転手が描かれており、社会的に成功した人物が
乗るクルマであることを強くアピールしている。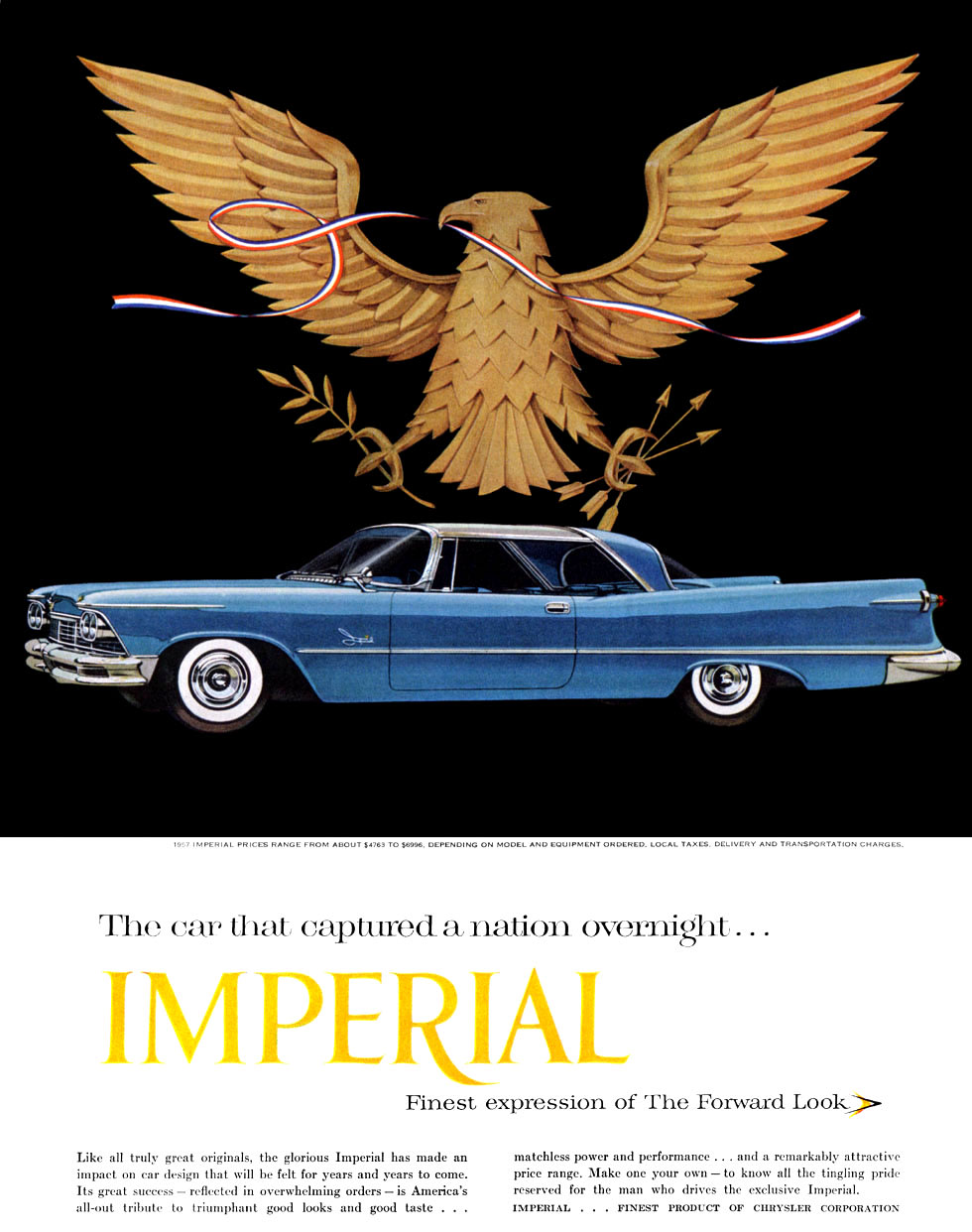
CHRYSLER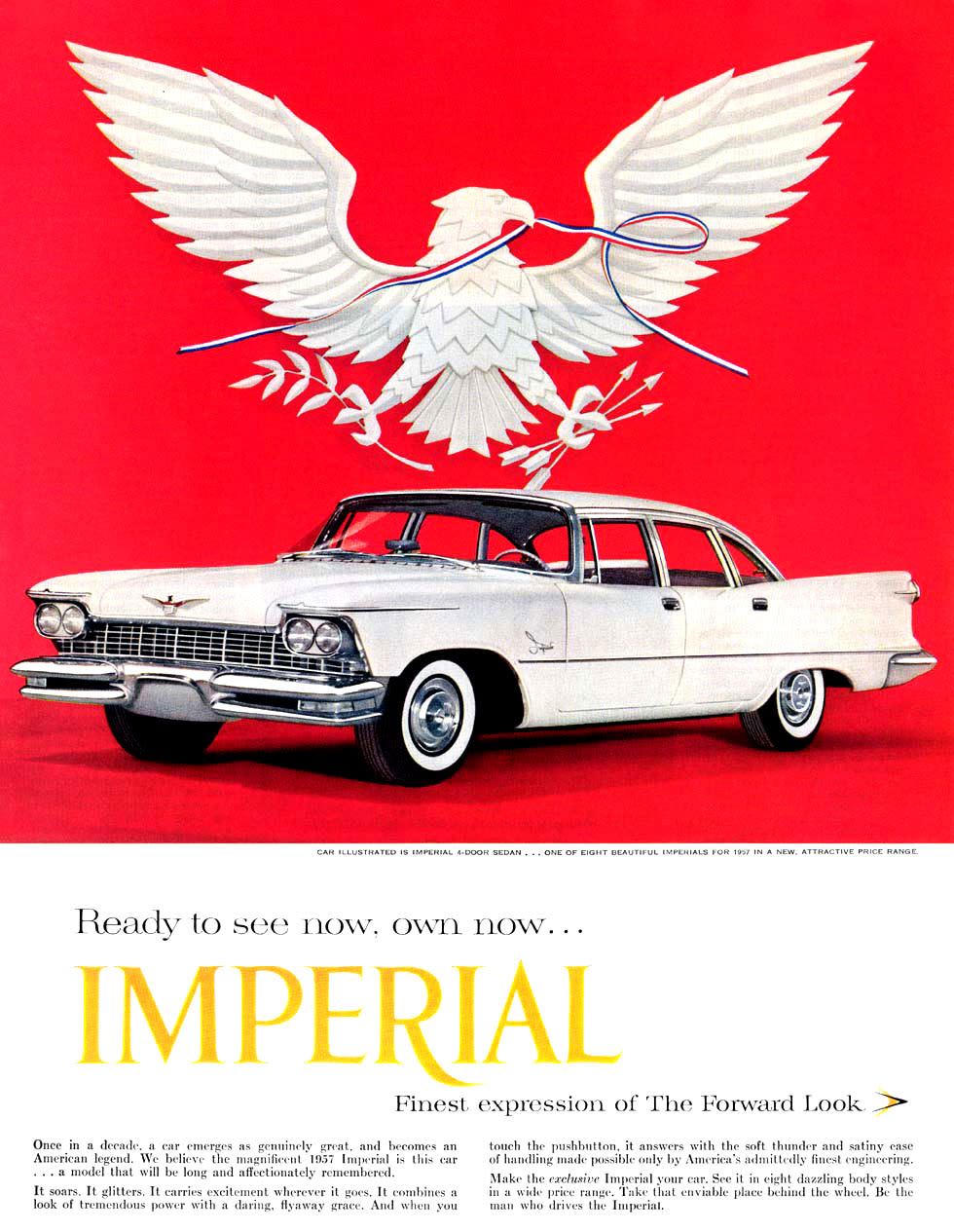
CHRYSLER
CHRYSLER
CHRYSLER
CHRYSLER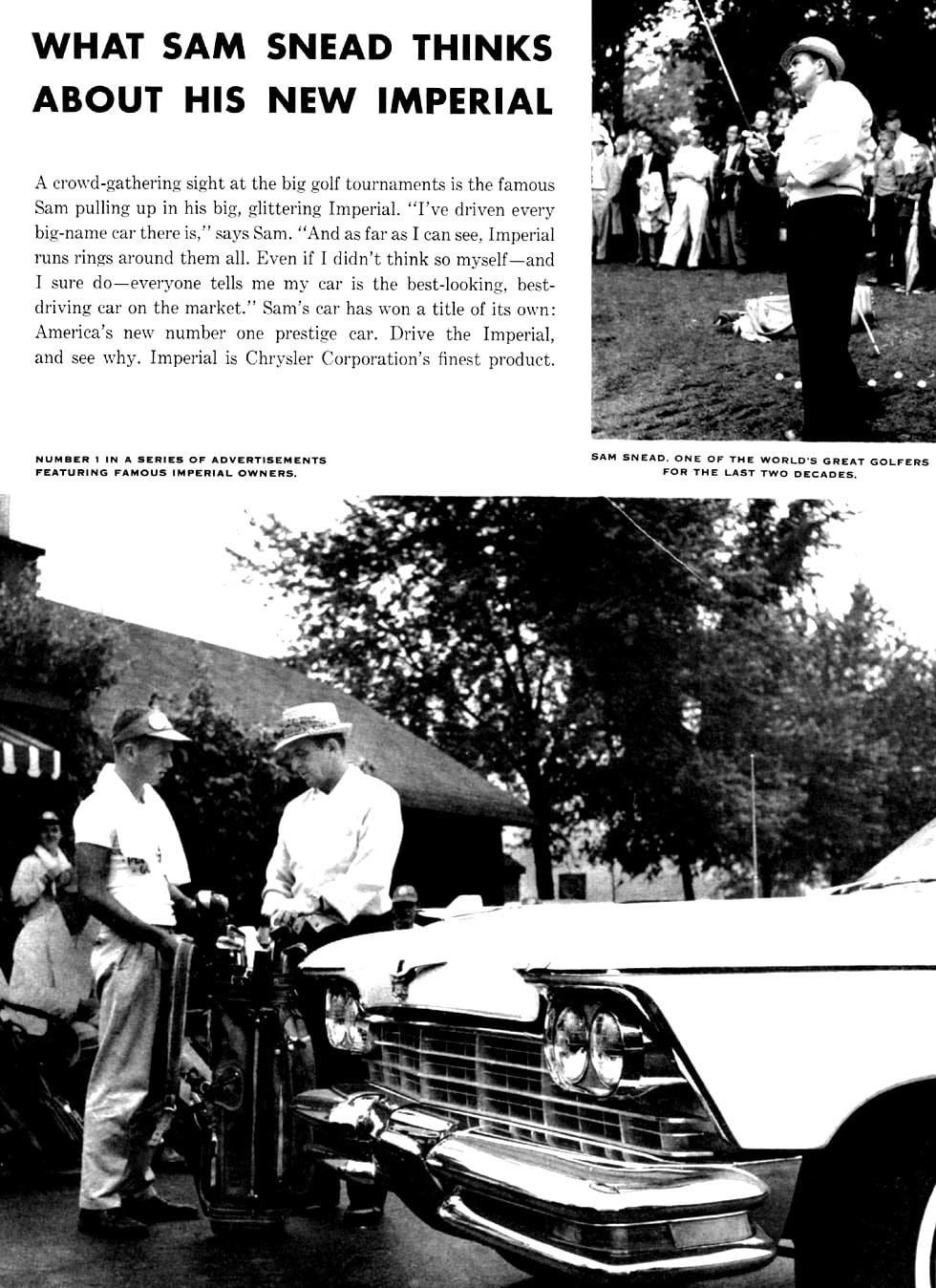
CHRYSLER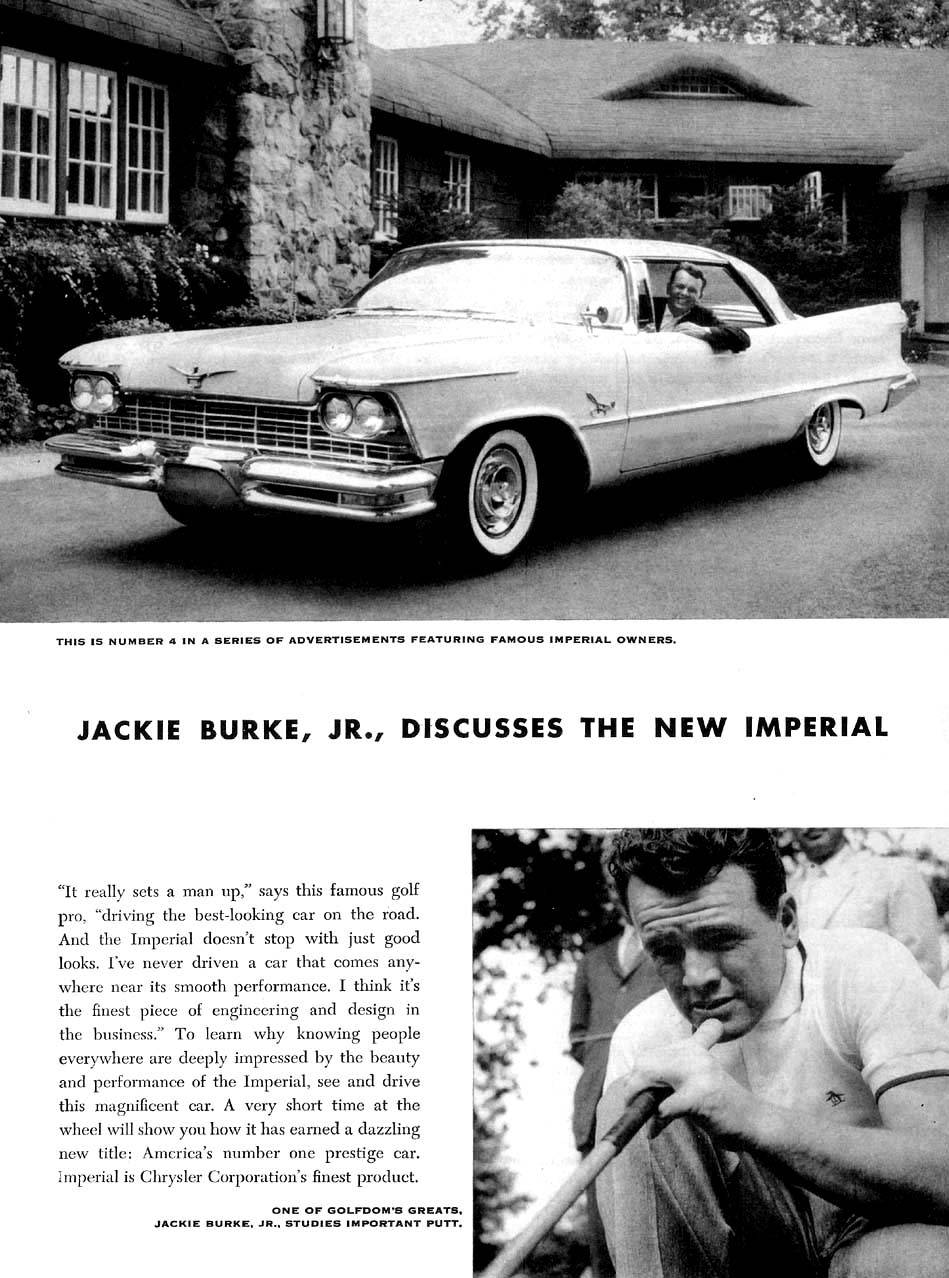
CHRYSLER
ポインター走行映像。
カーグラフィックTV風のオープニングがオモシロい。
http://www.youtube.com/watch?v=HUpFb6XZgUQ
オマケのオマケ
その他1957年型クライスラー車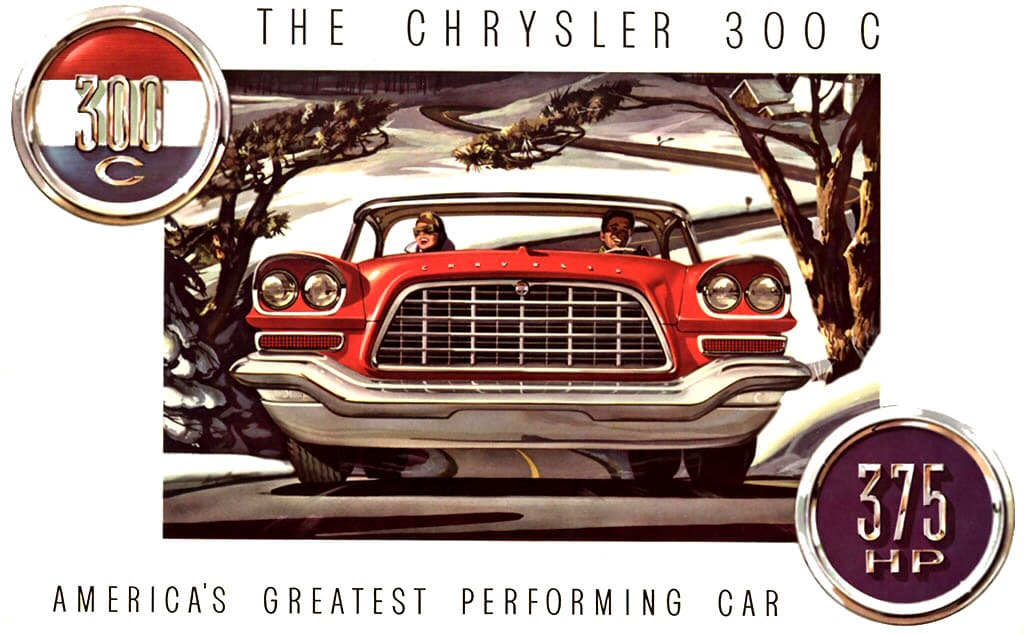
CHRYSLER
CHRYSLER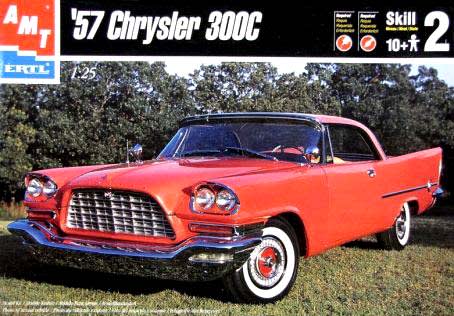
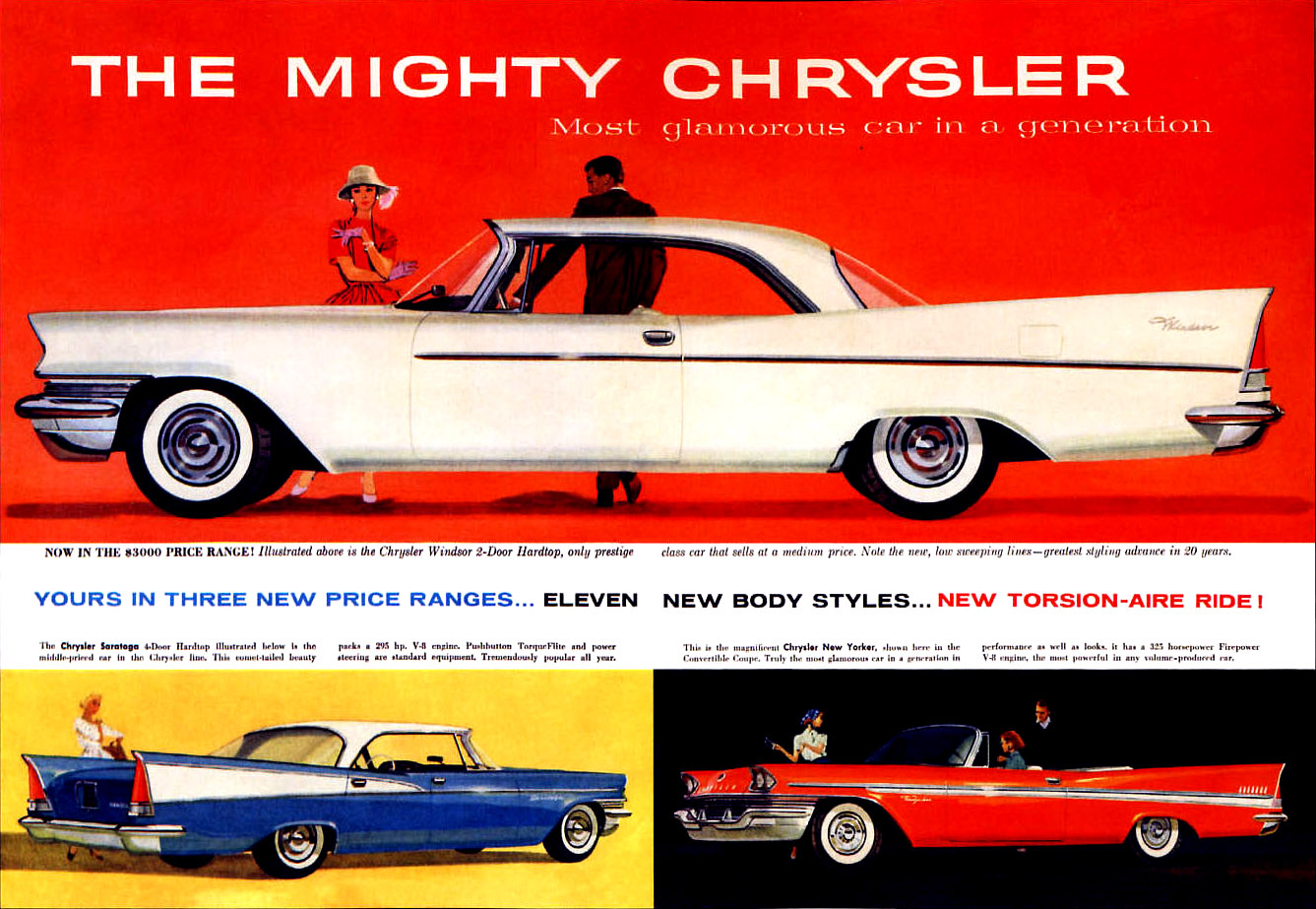
CHRYSLER
CHRYSLER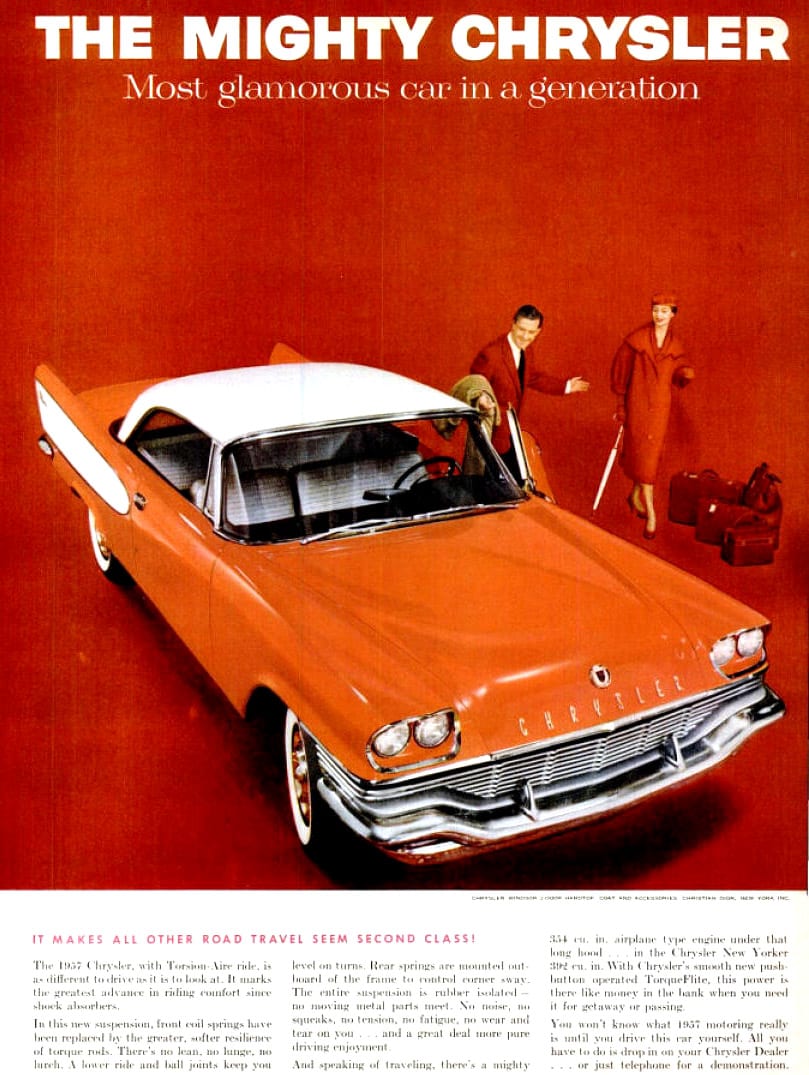
CHRYSLER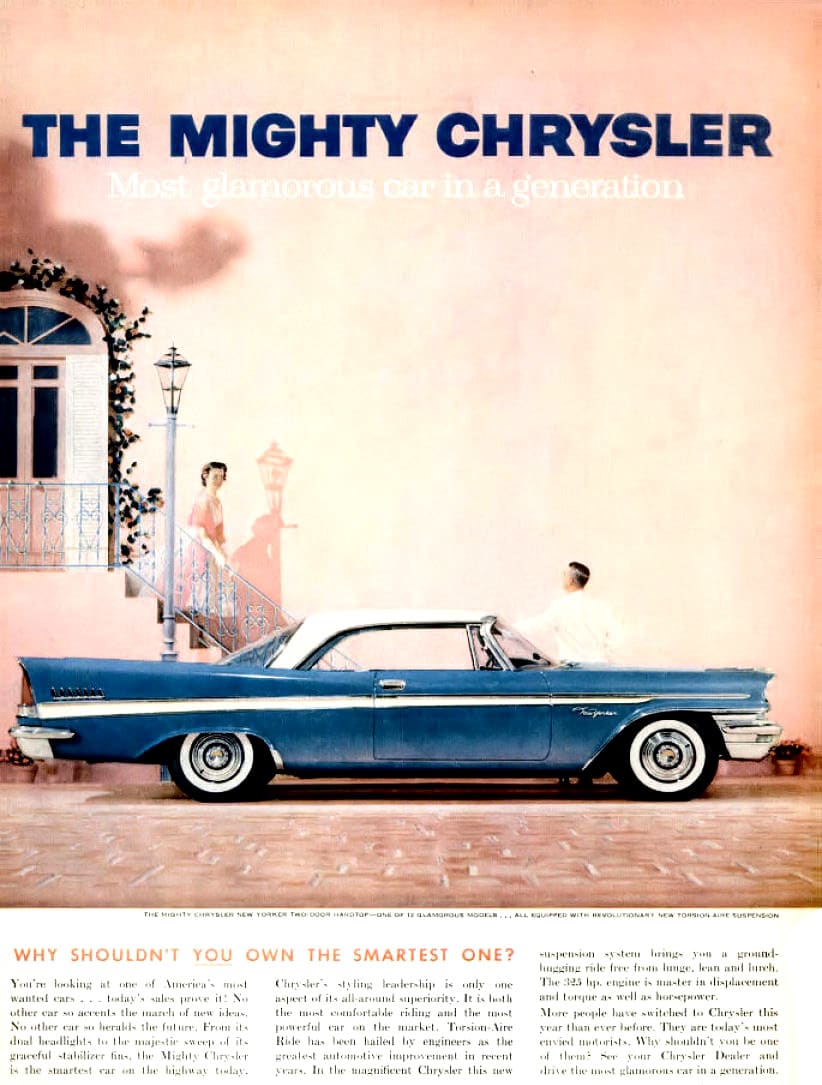
CHRYSLER
CHRYSLER
CHRYSLER
CHRYSLER
次回の更新は5月31日夜の予定です。
















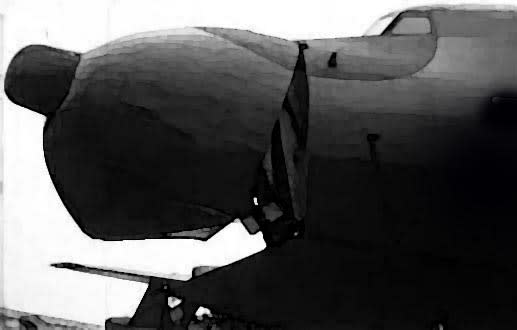




 つづく
つづく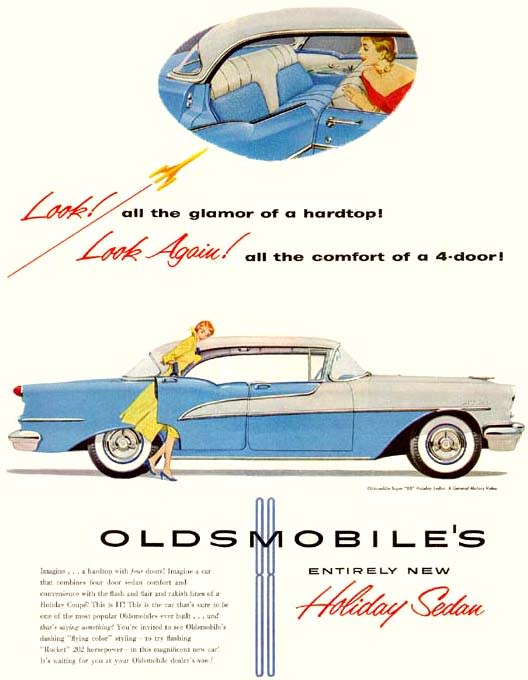
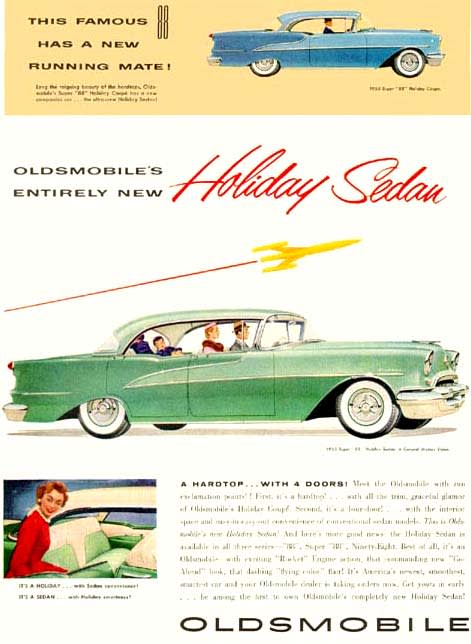

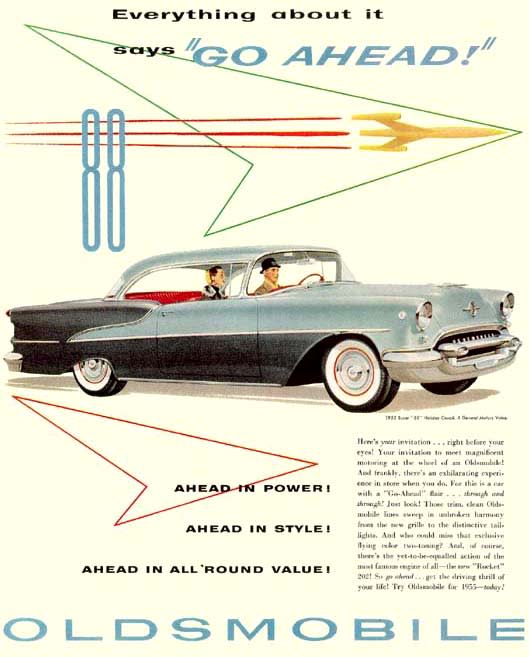
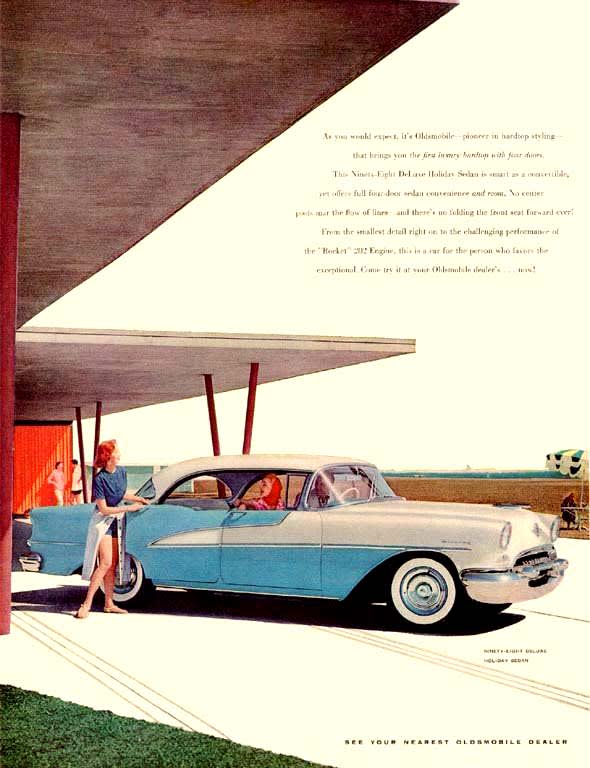

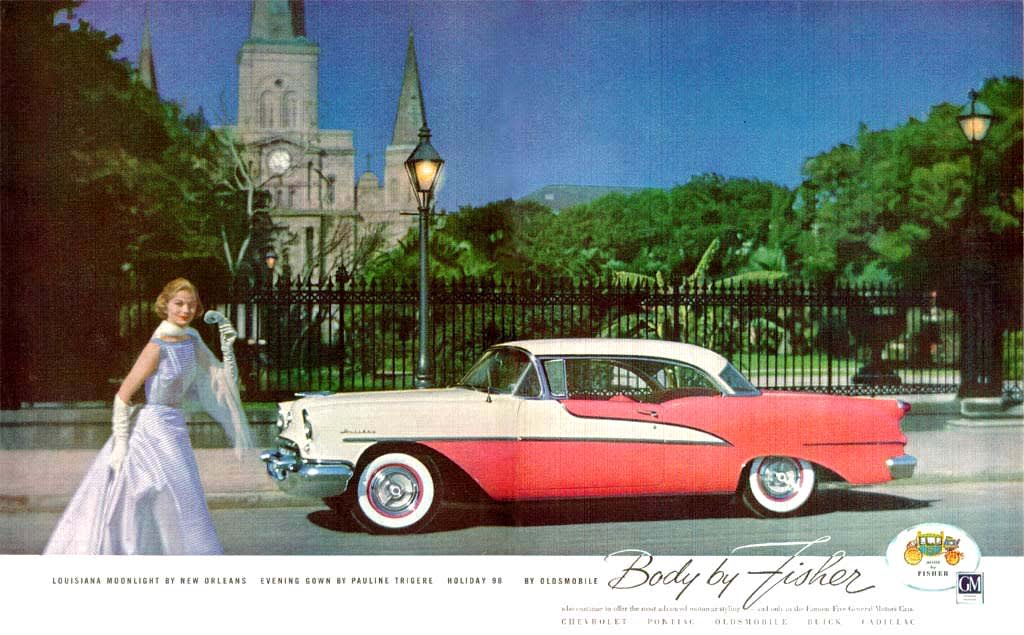
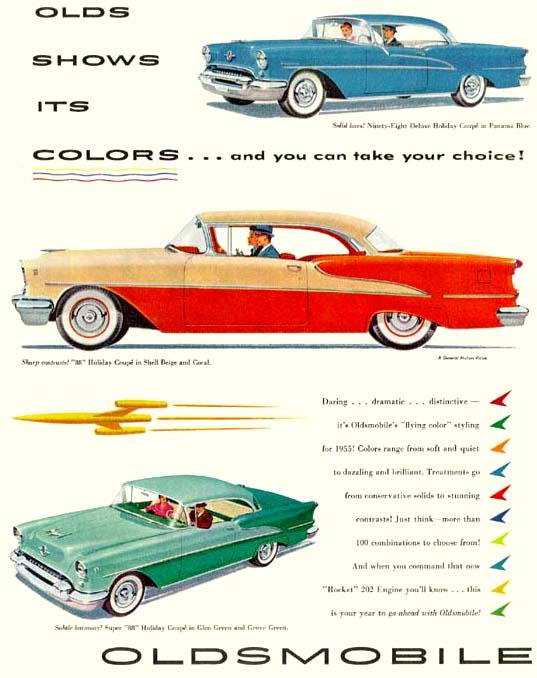









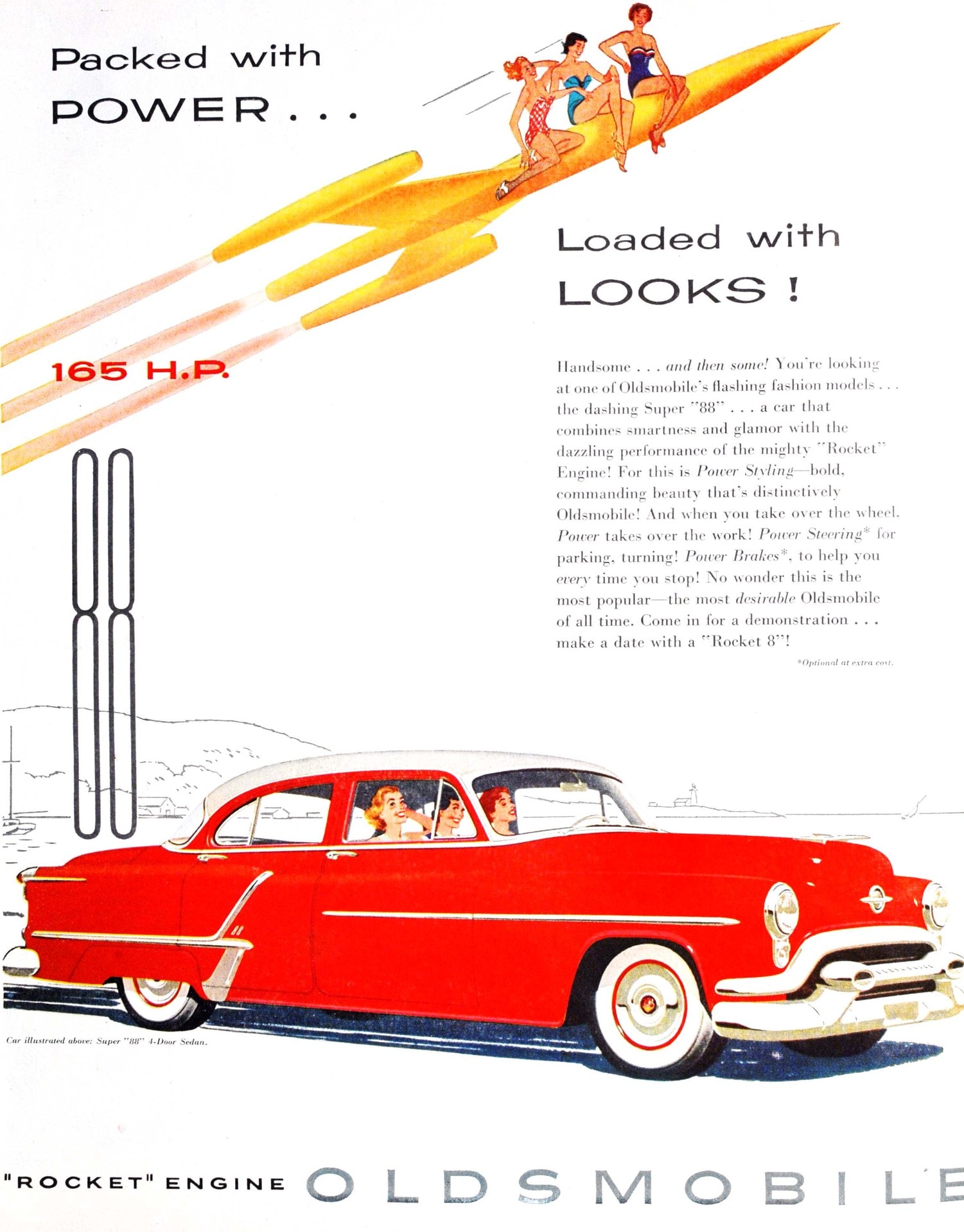

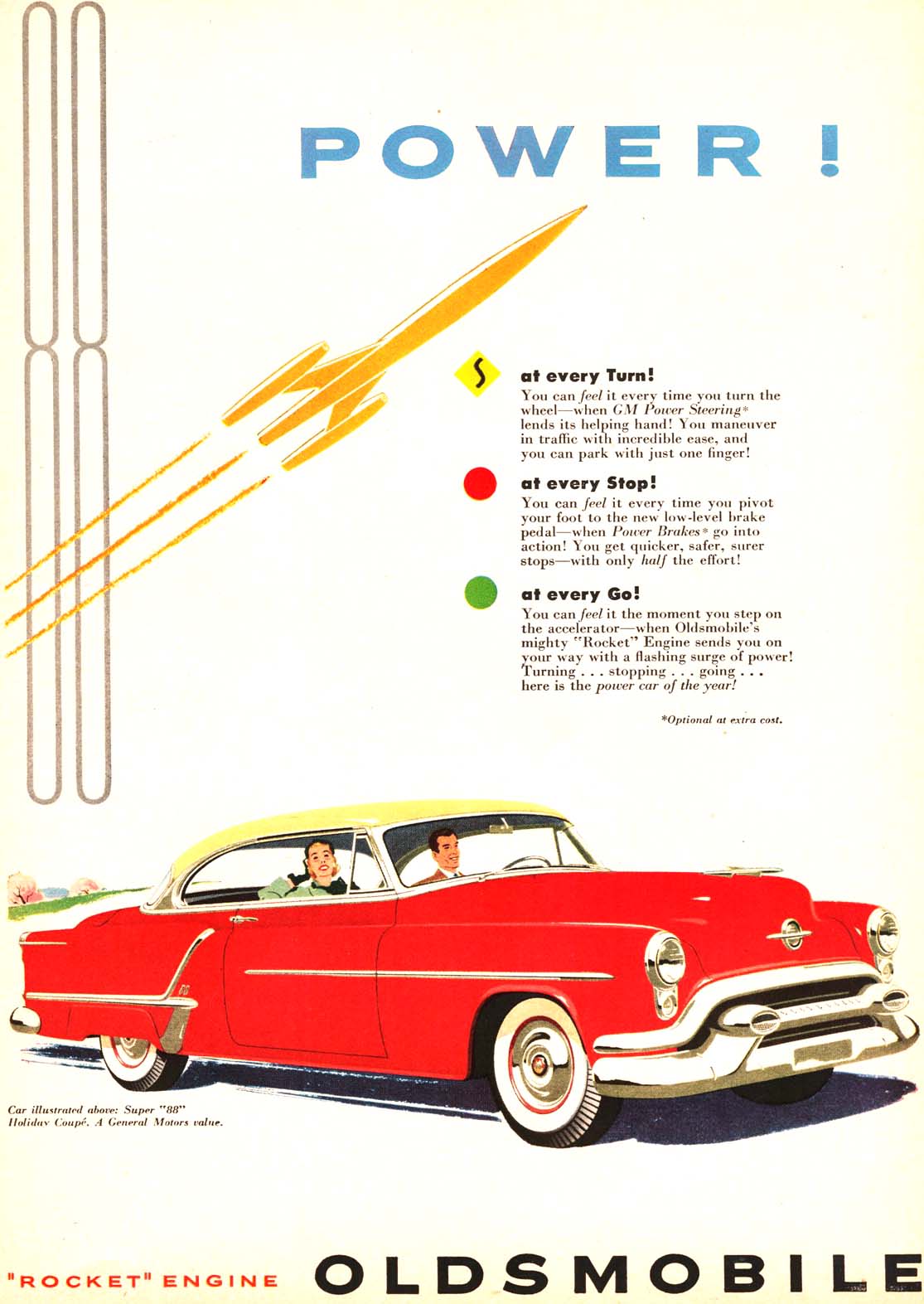


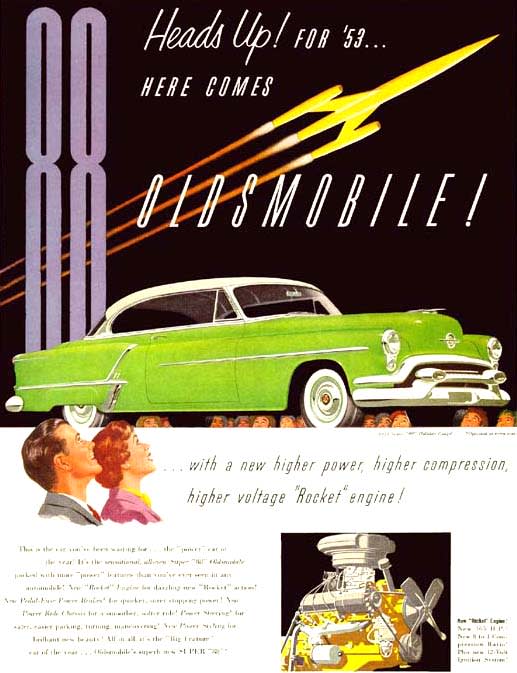



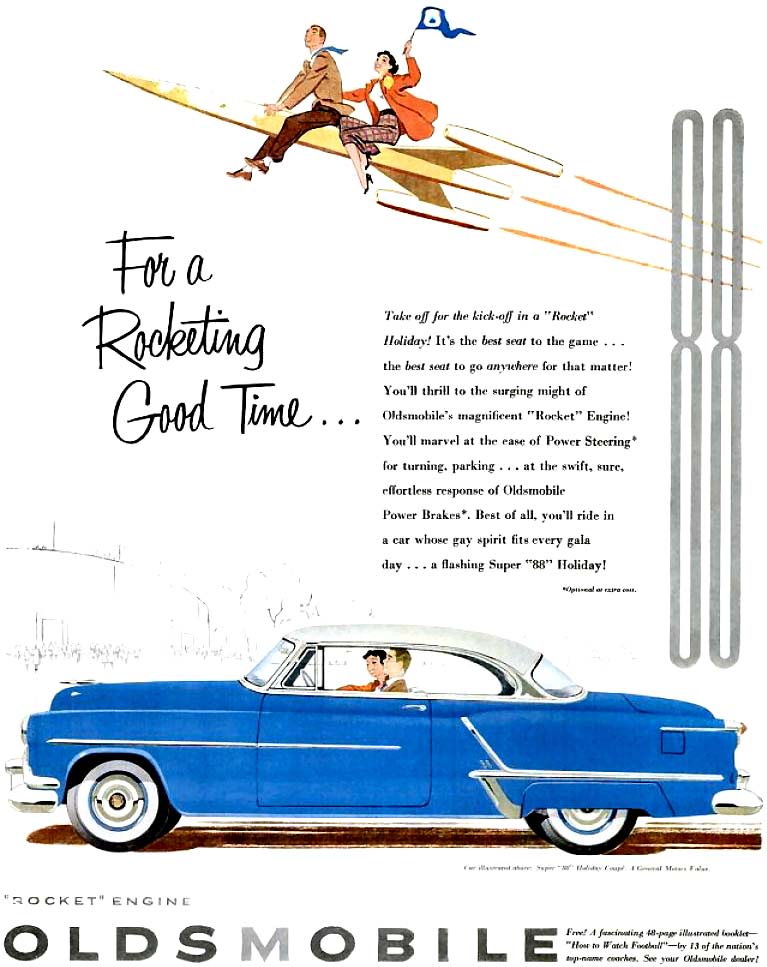






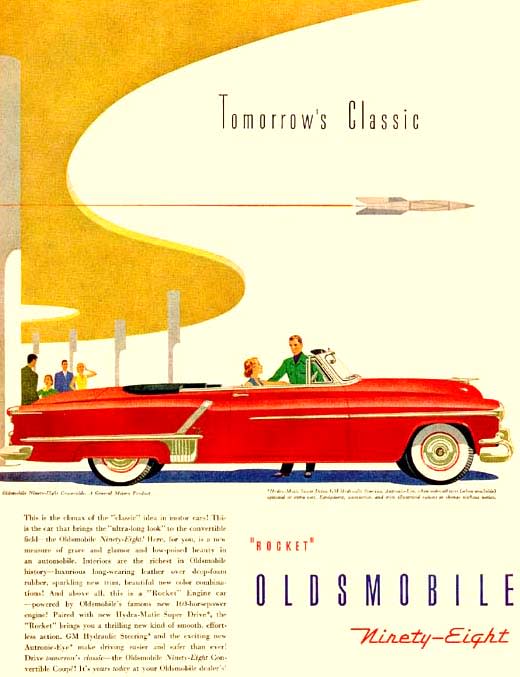


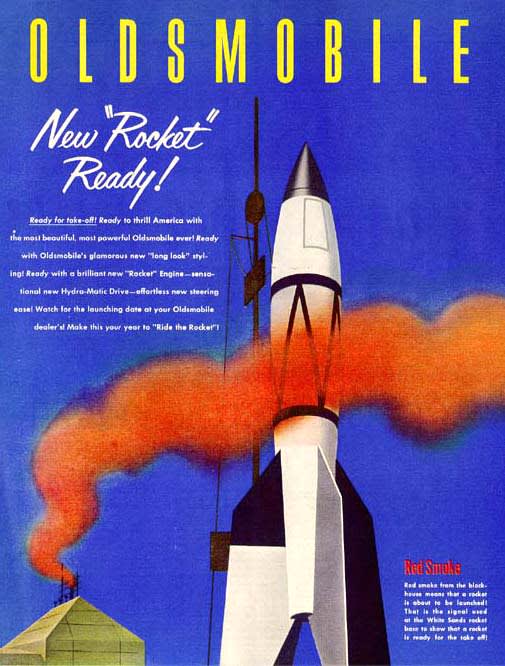
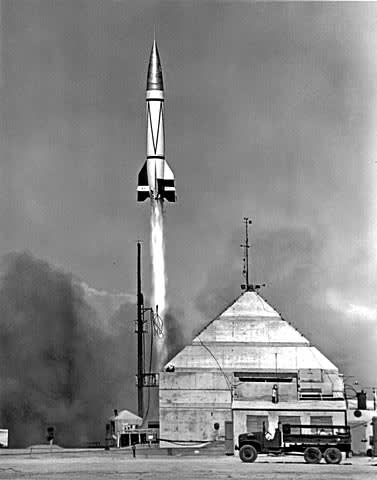



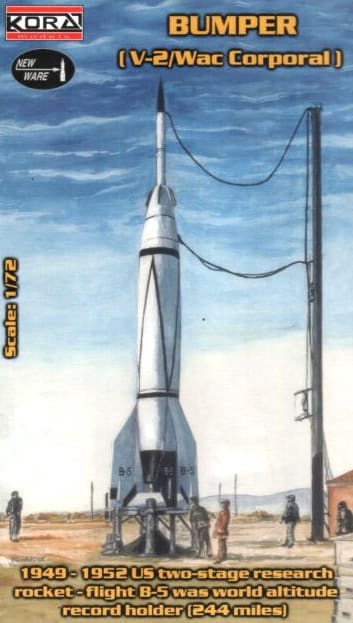

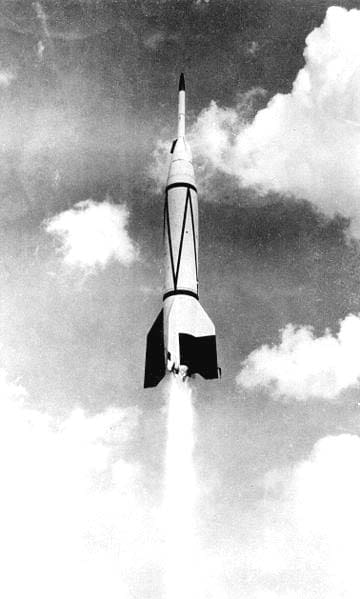
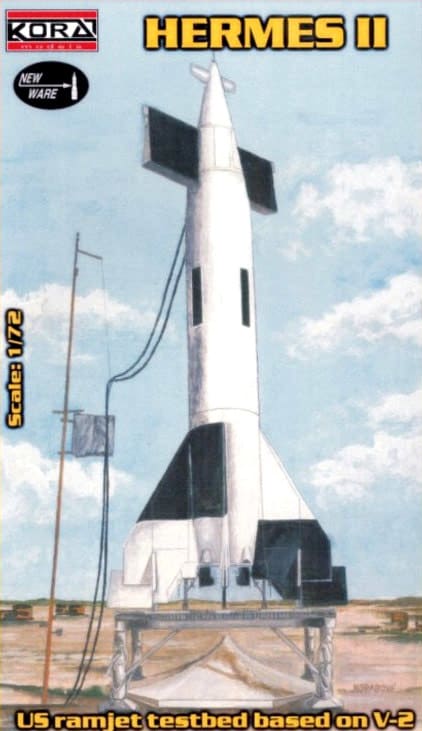



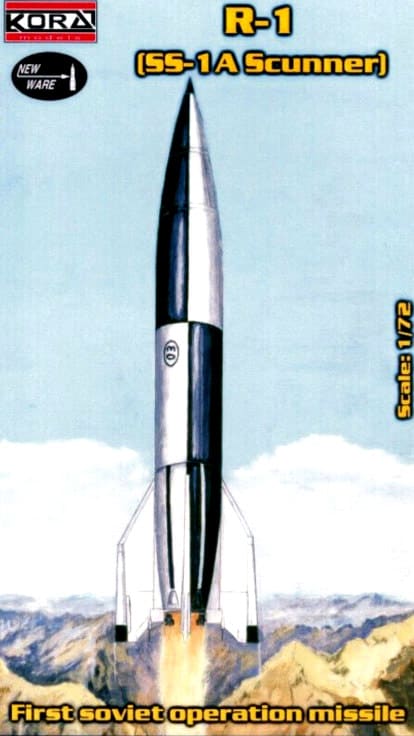
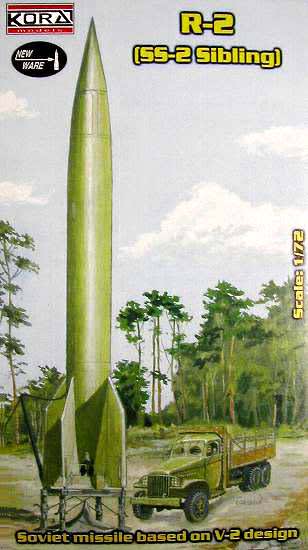
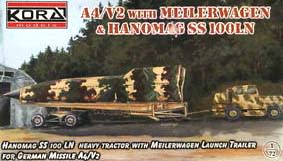


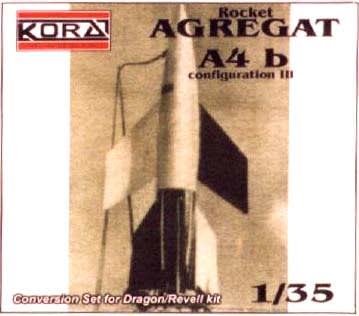
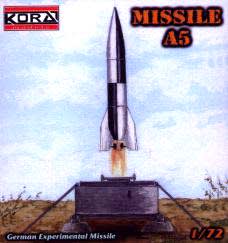
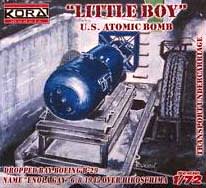


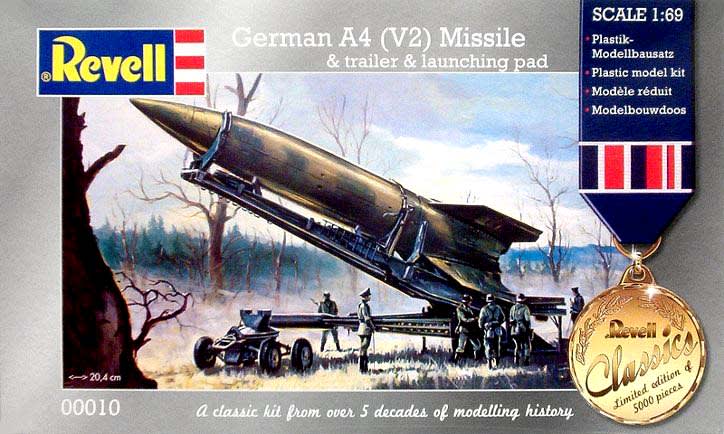


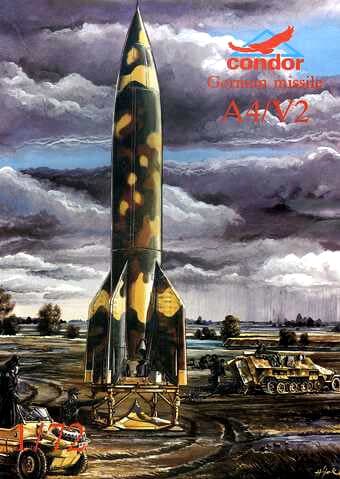


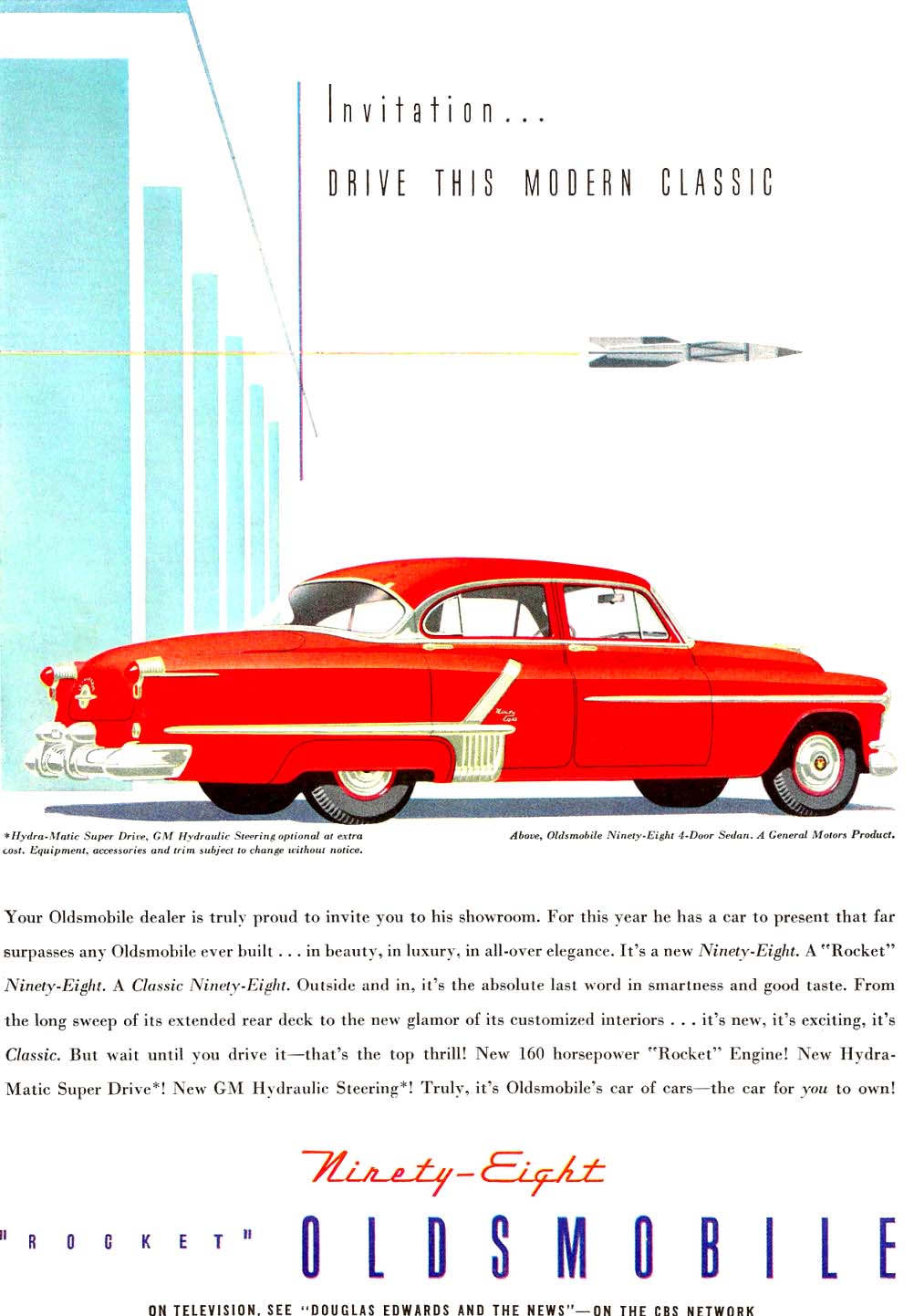
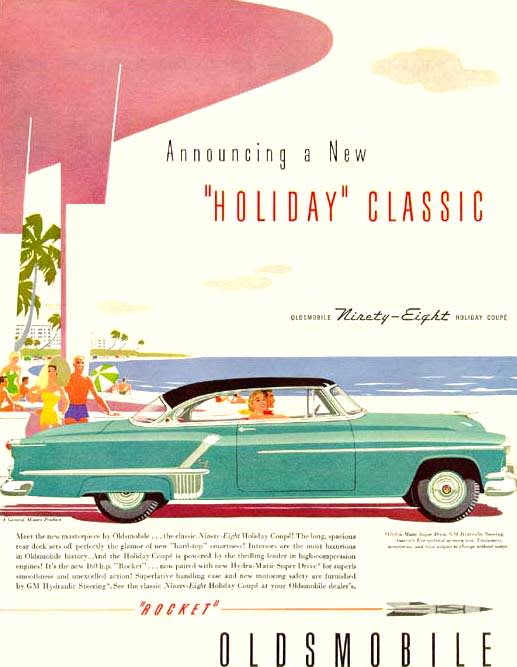



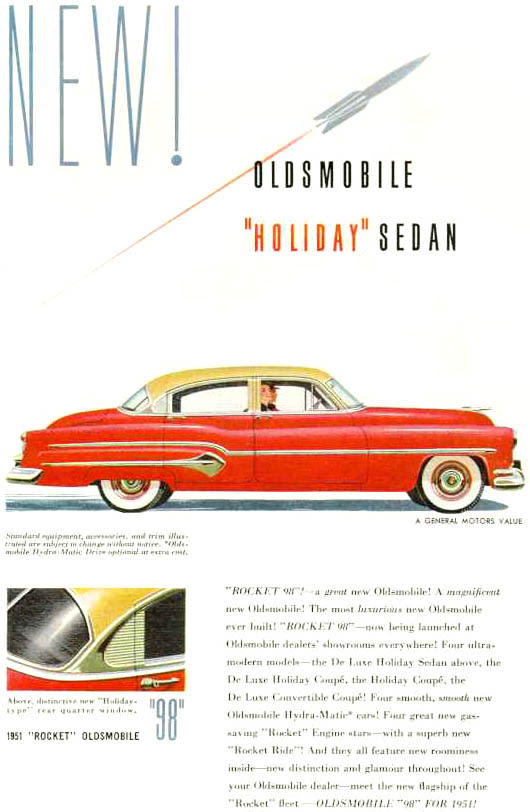

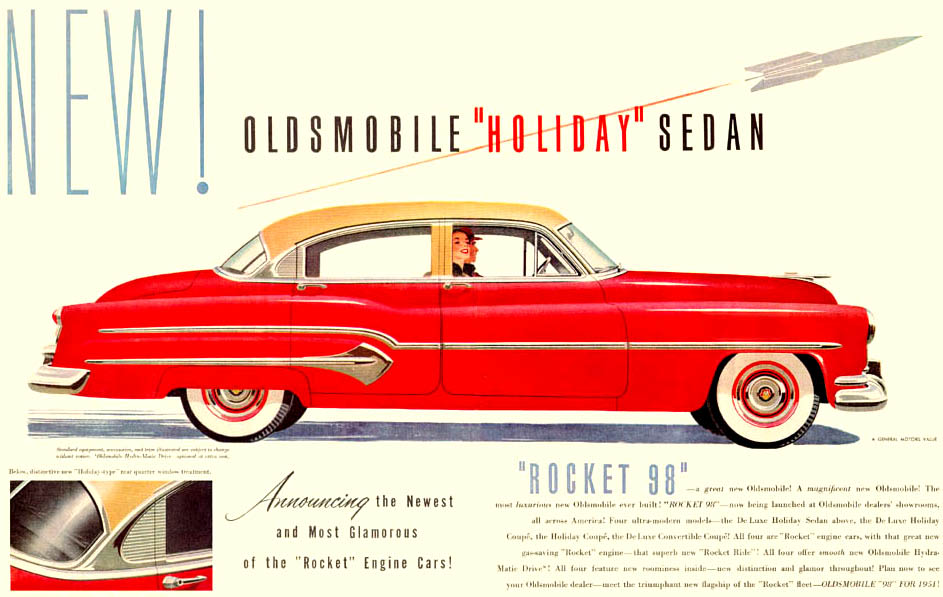





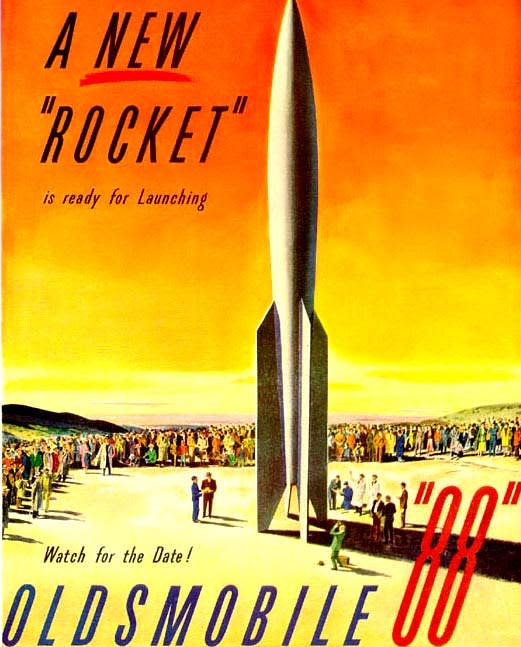
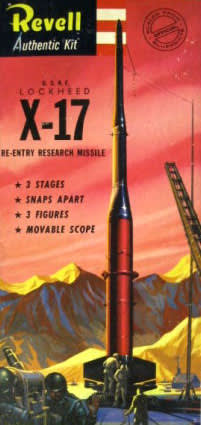


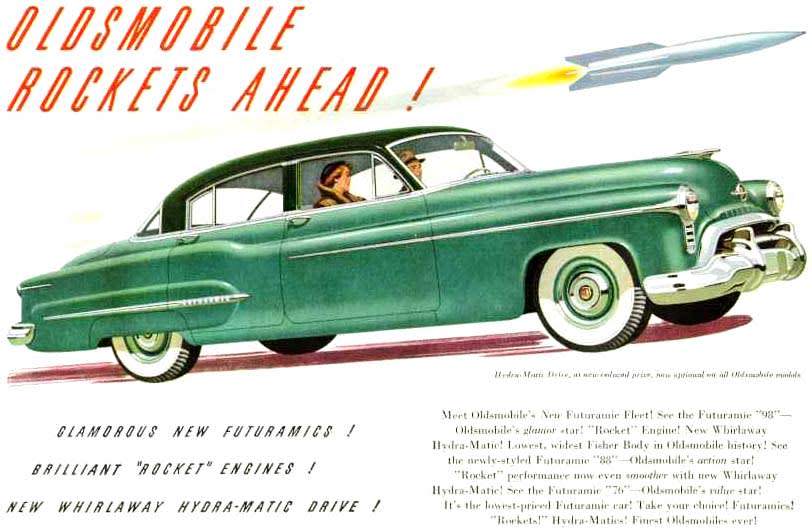

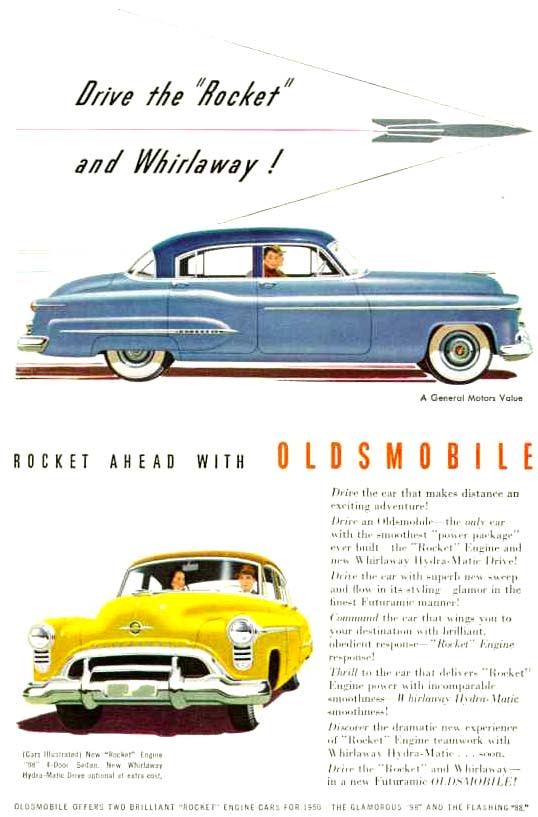
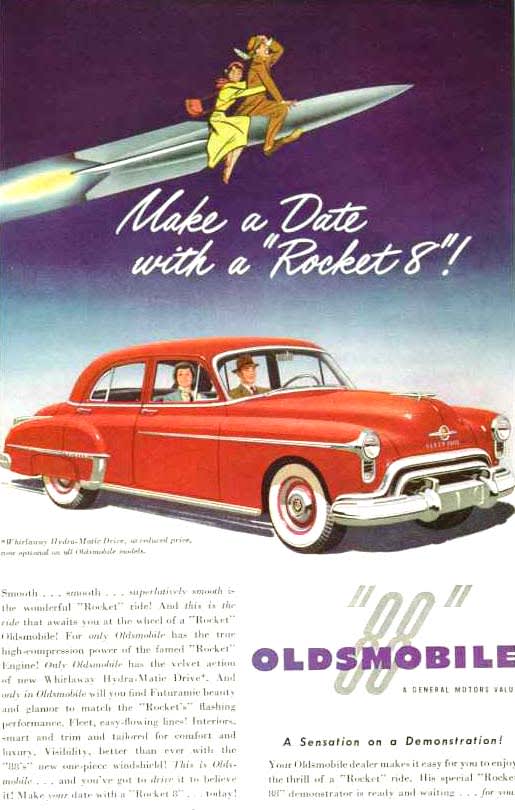
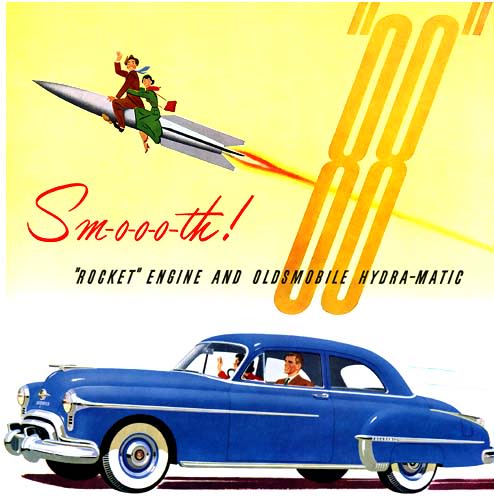








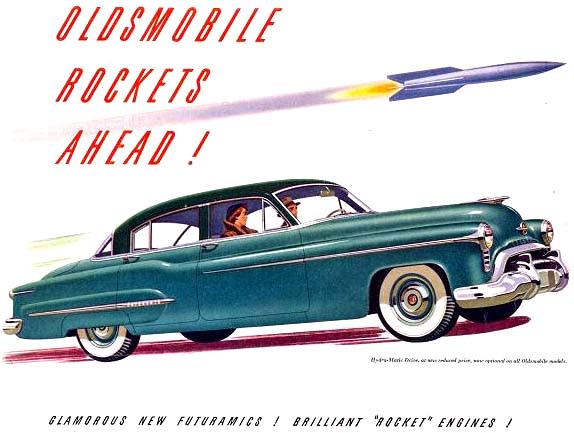





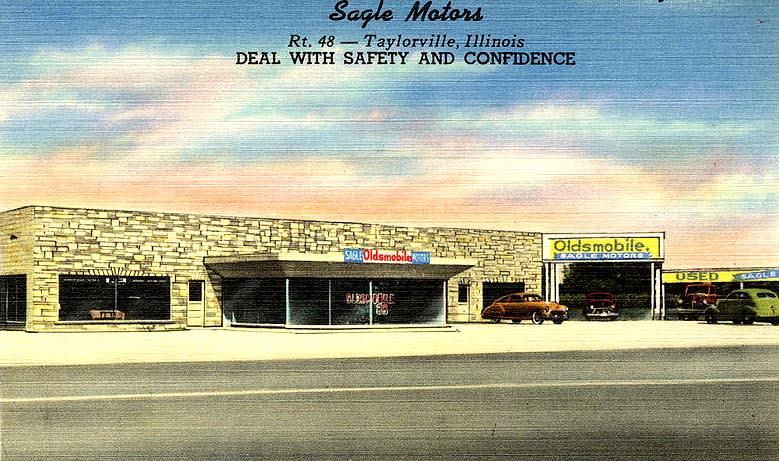
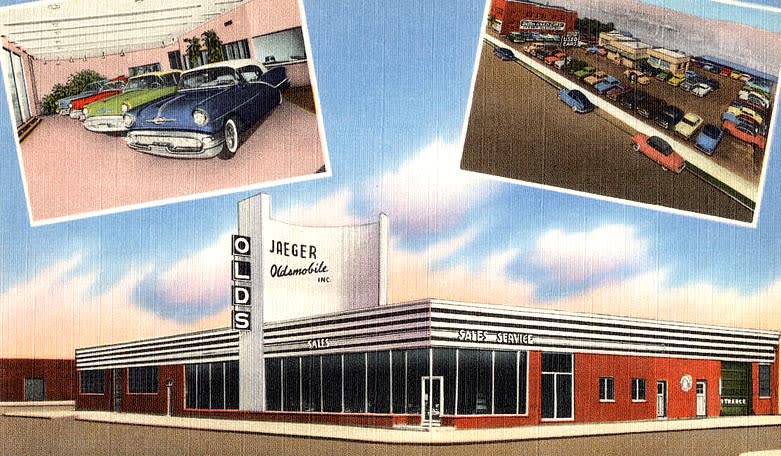
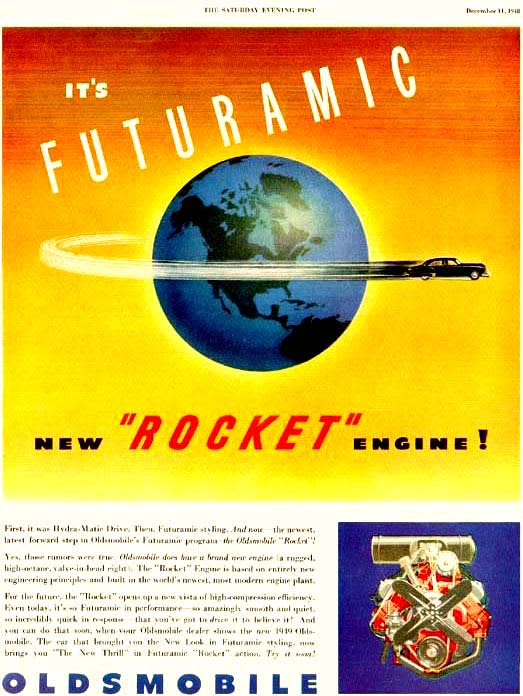
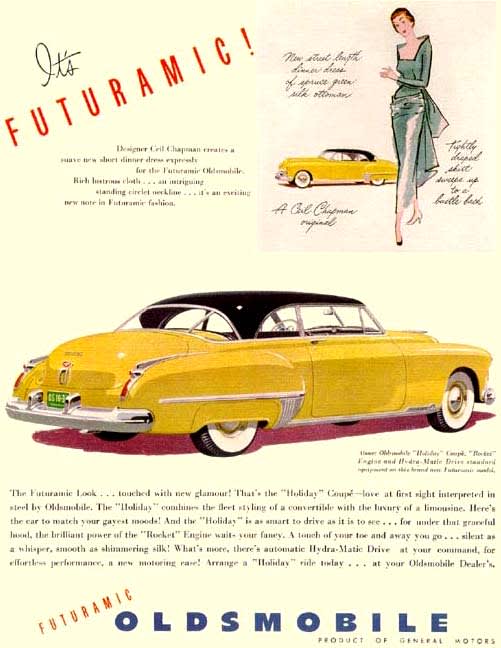


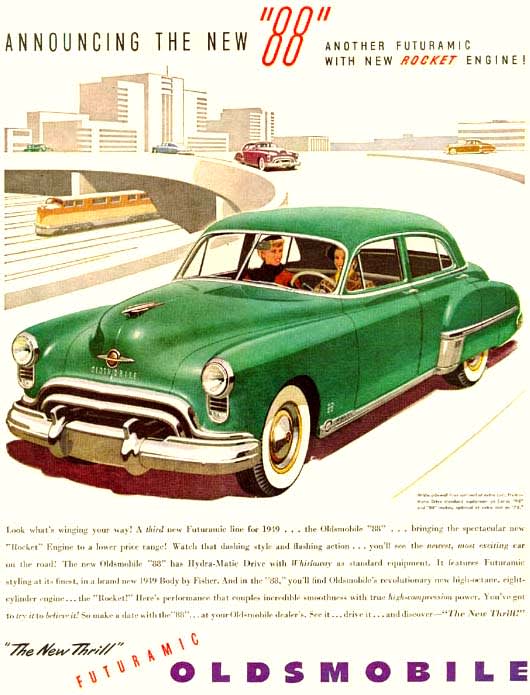

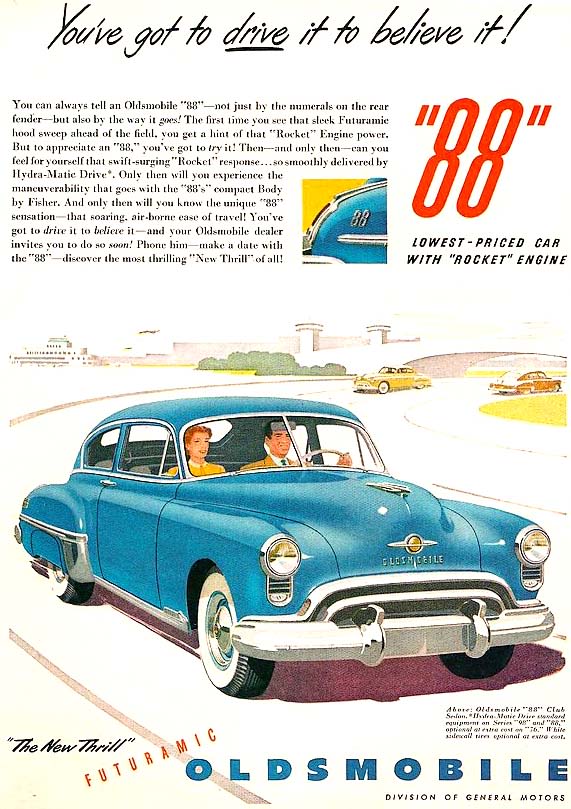

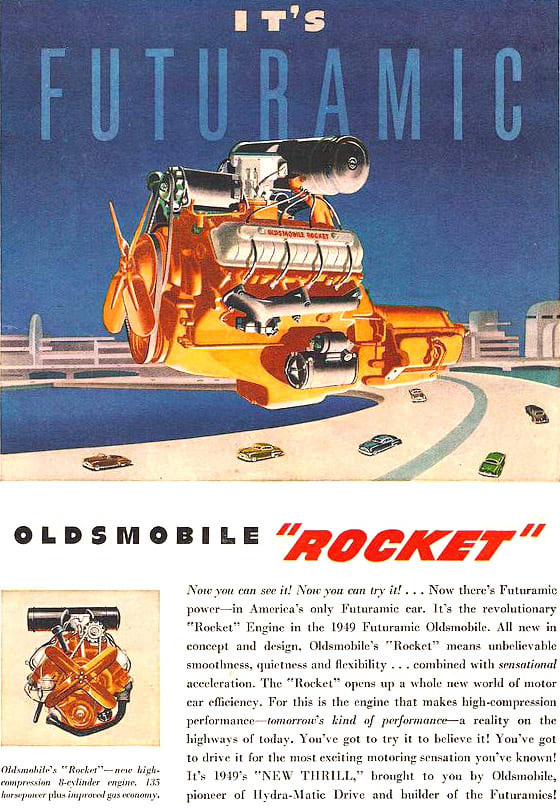
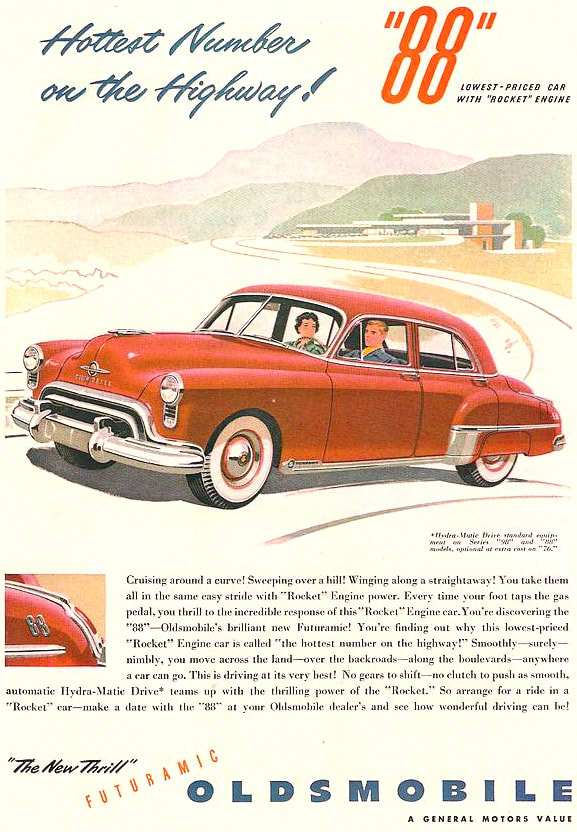




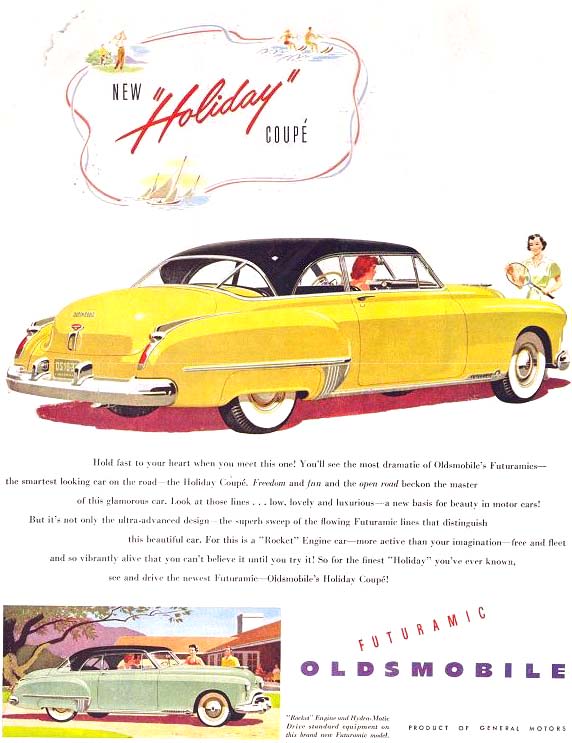

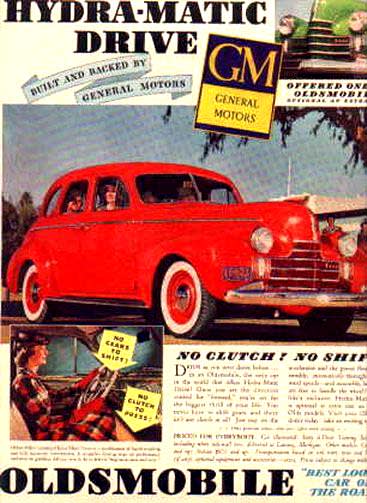
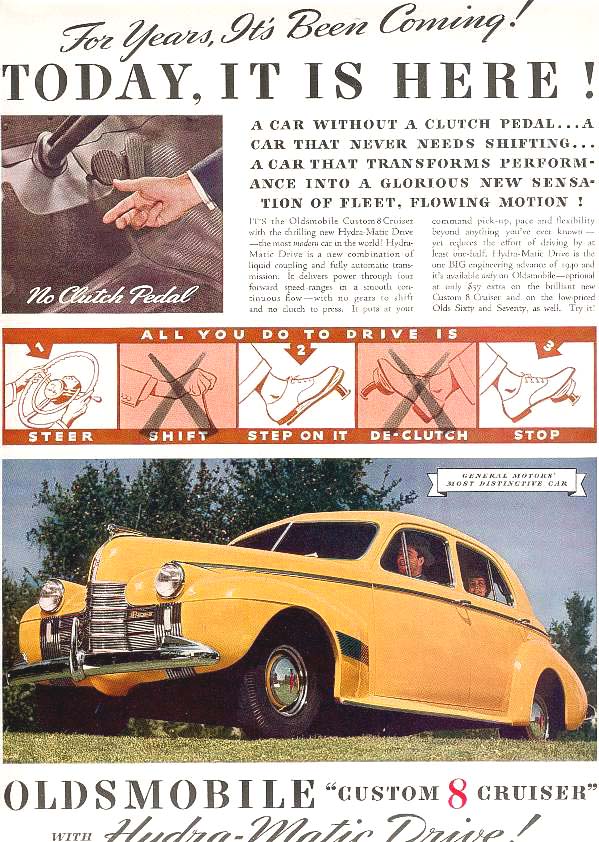
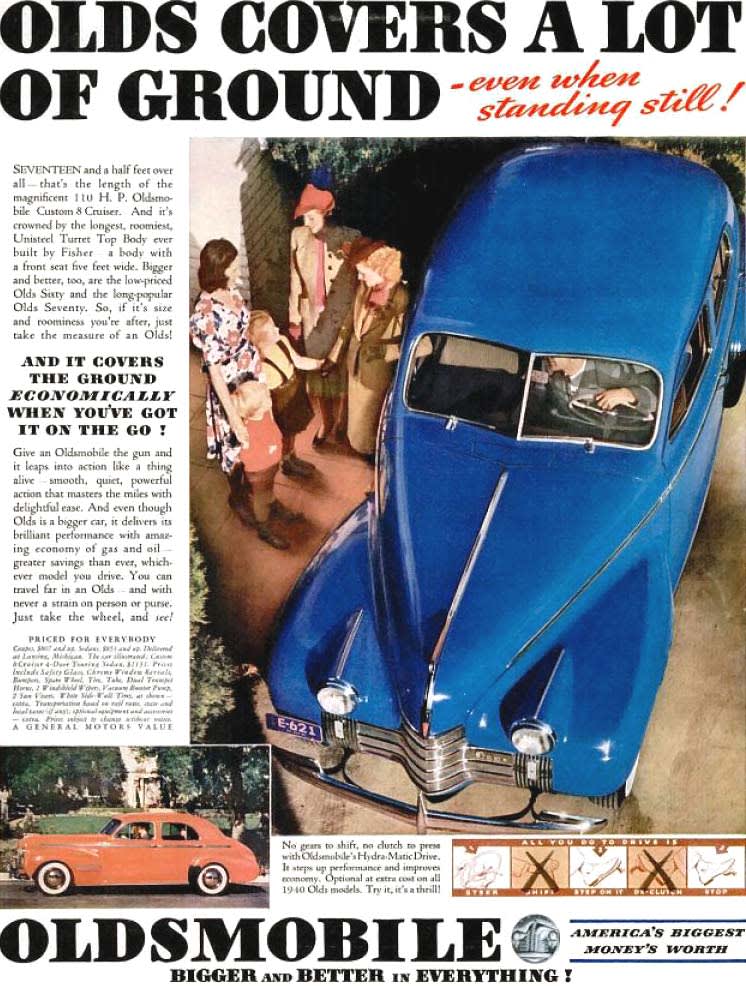
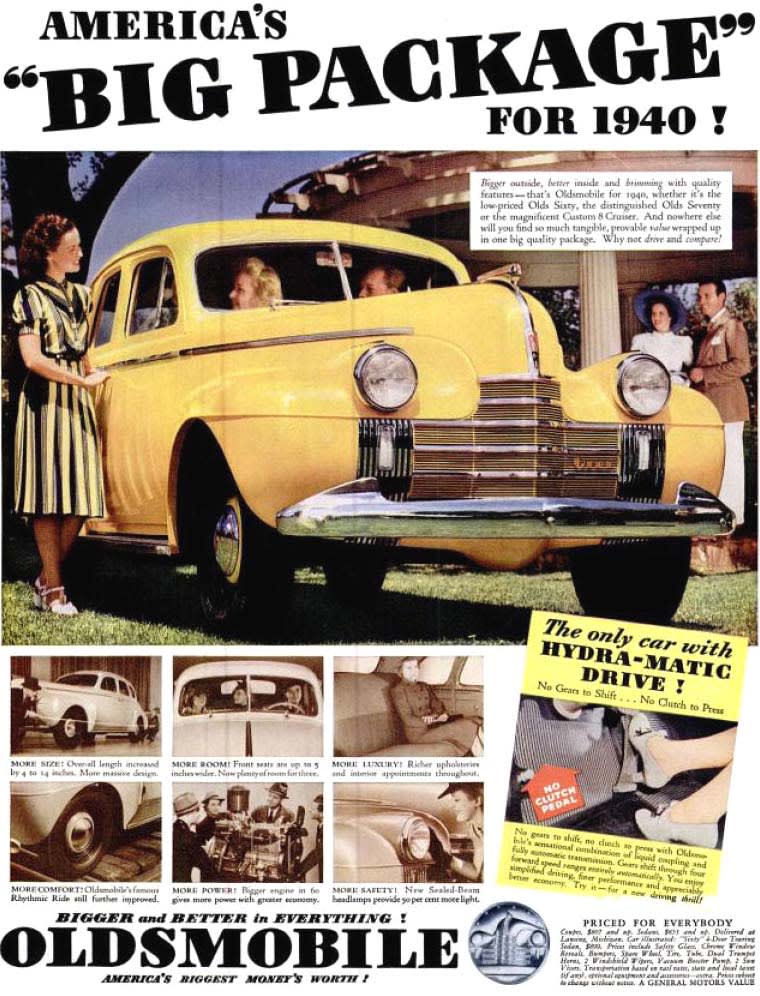
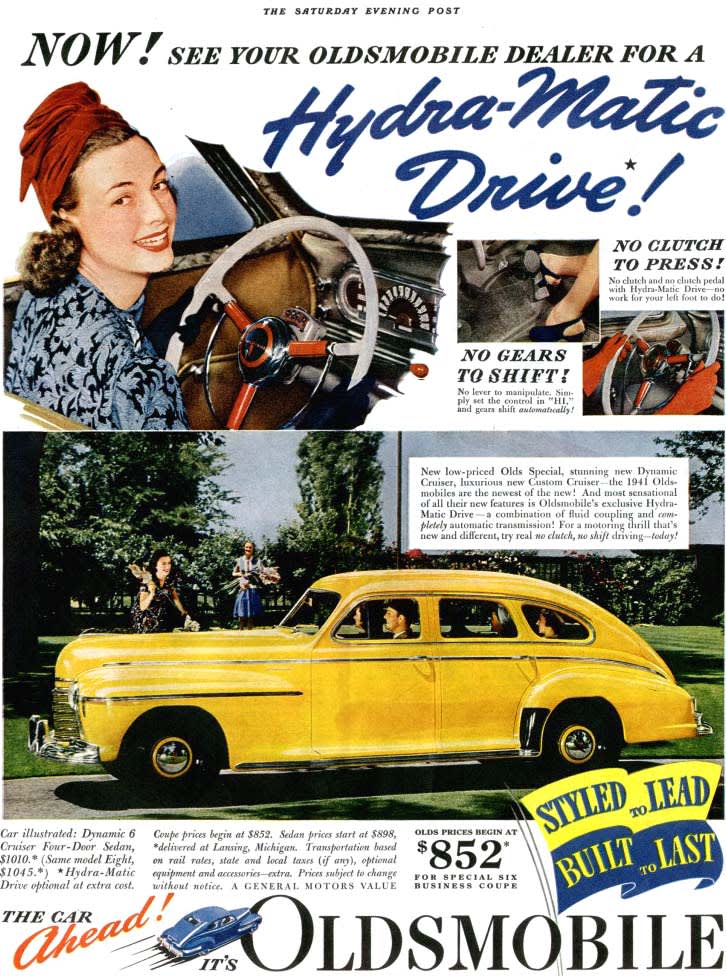











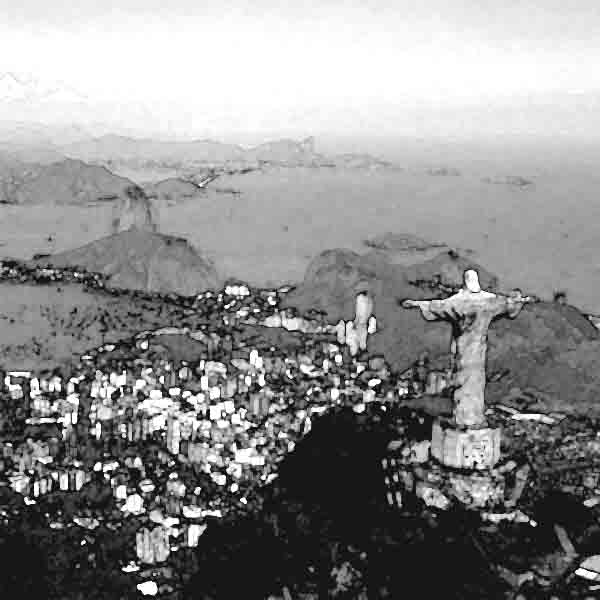








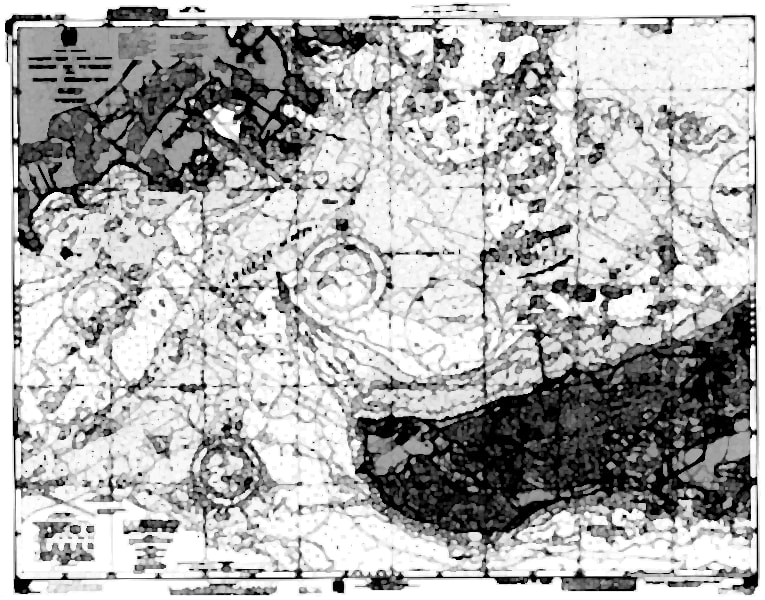

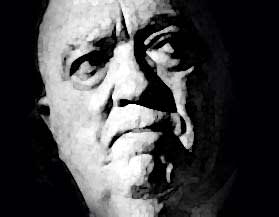



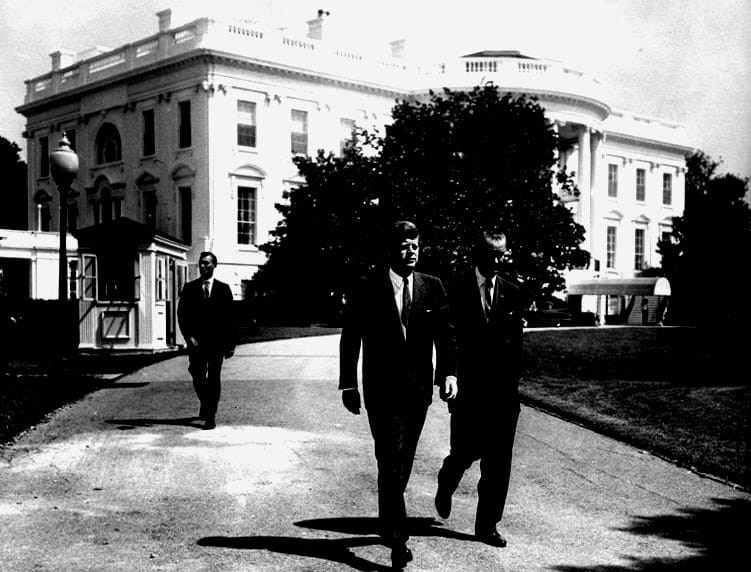
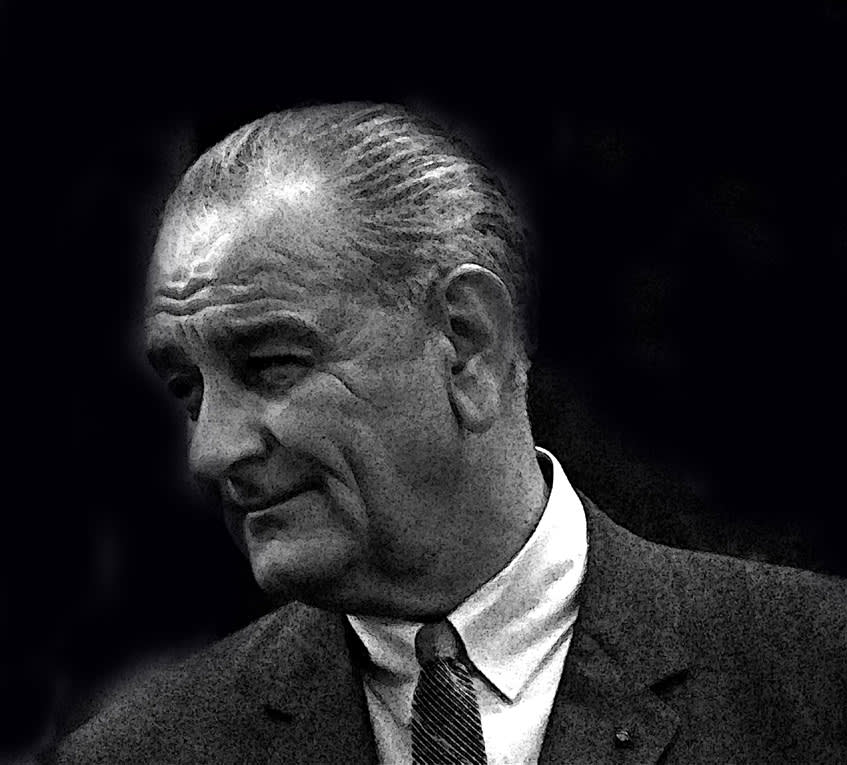
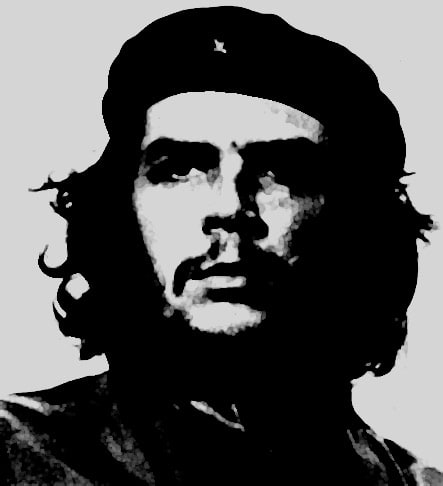


 つづく
つづく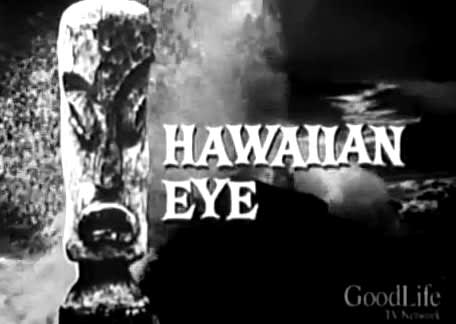
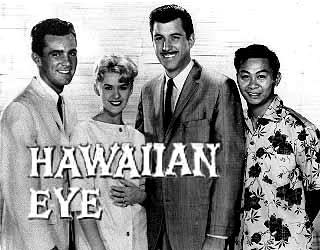




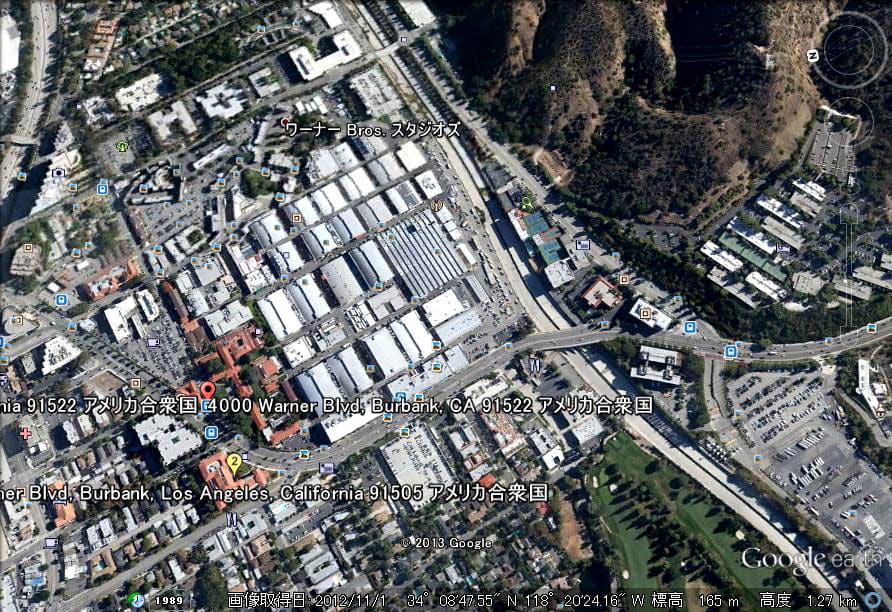






















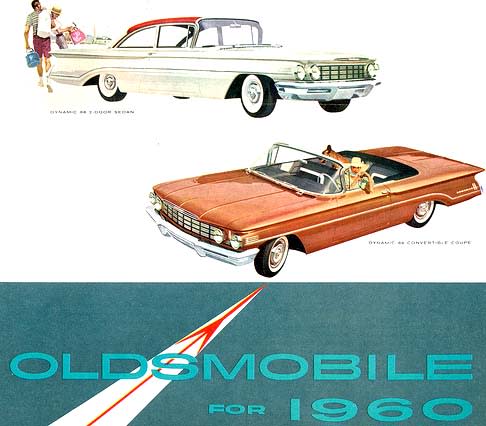
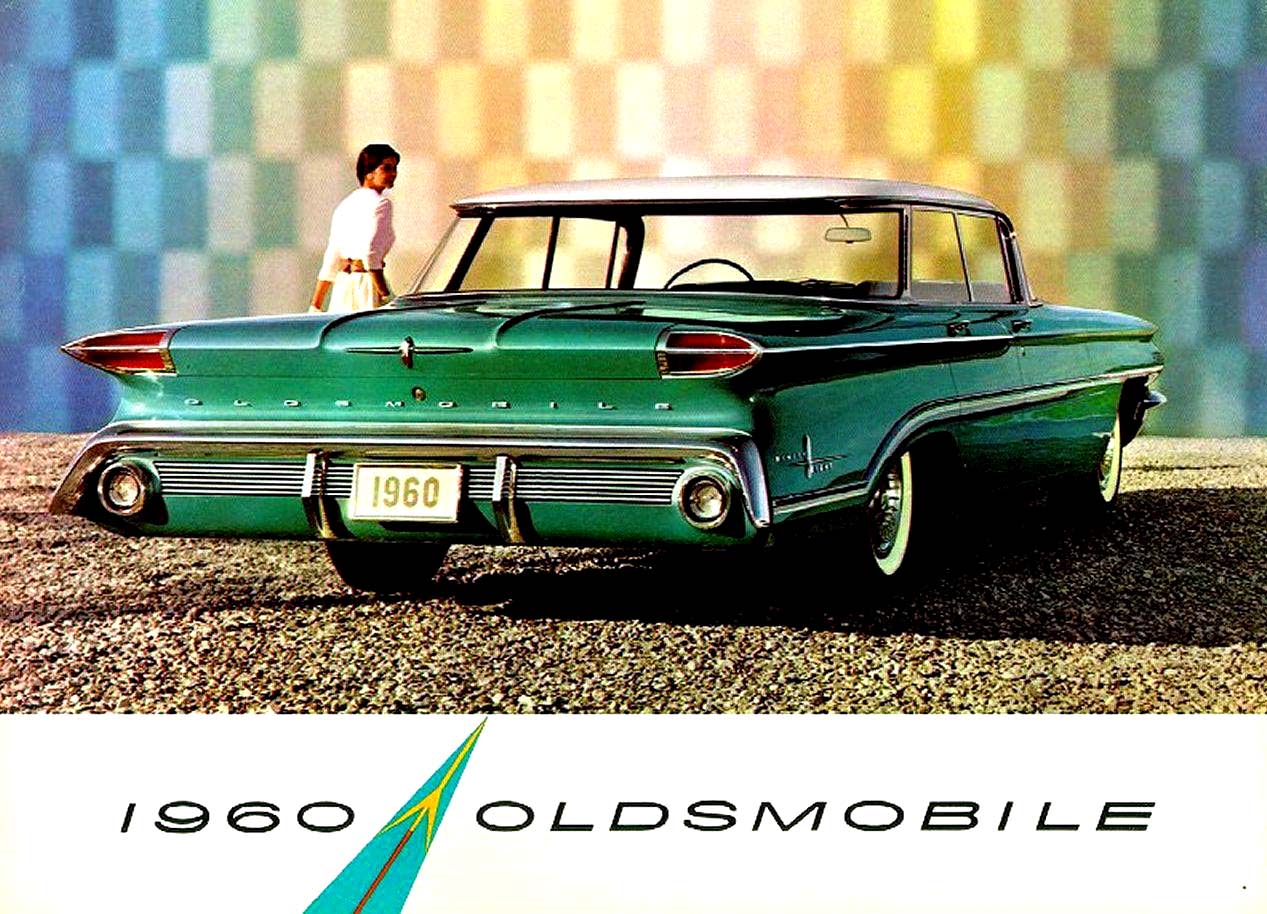

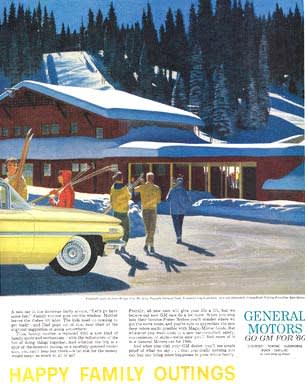











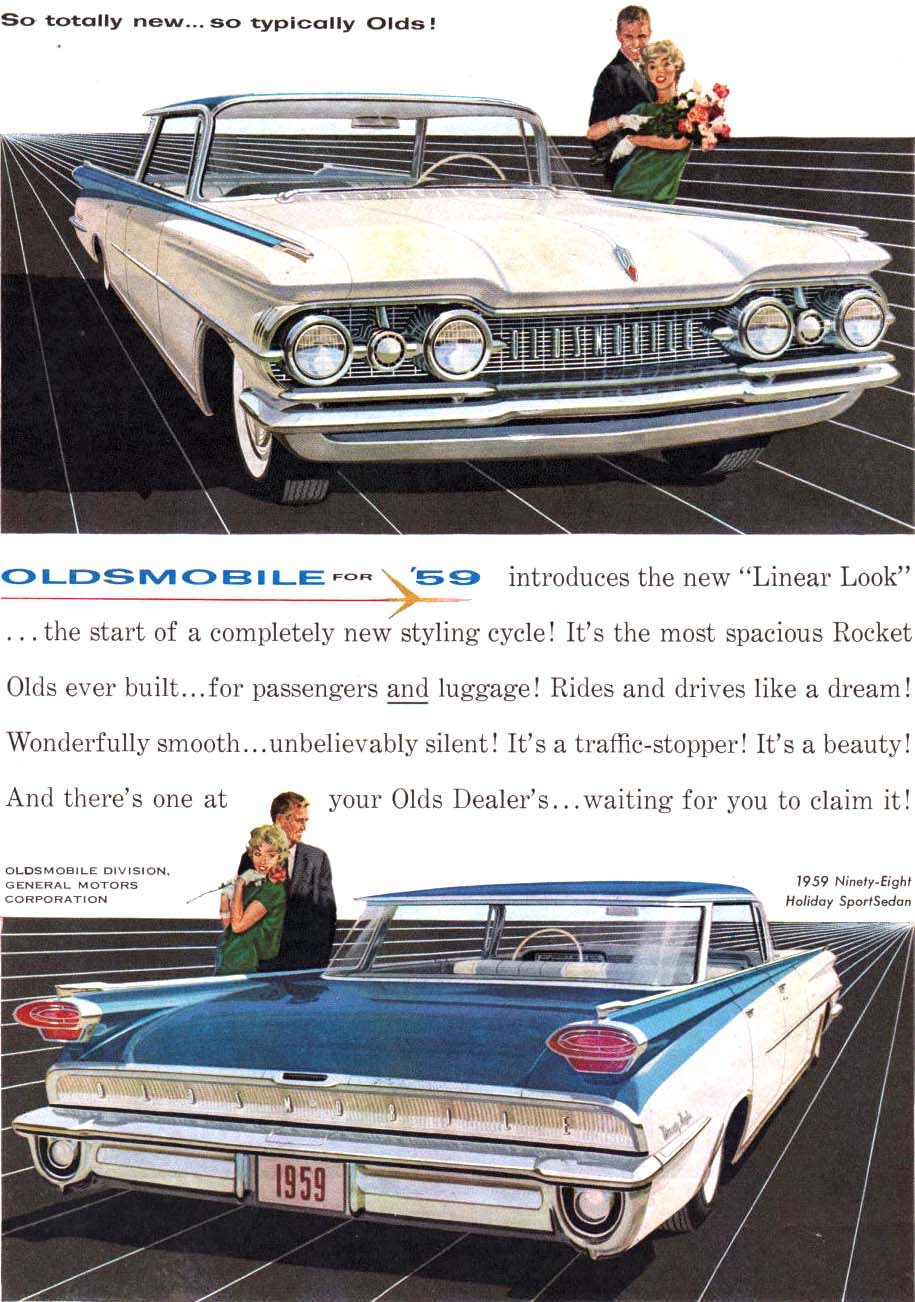
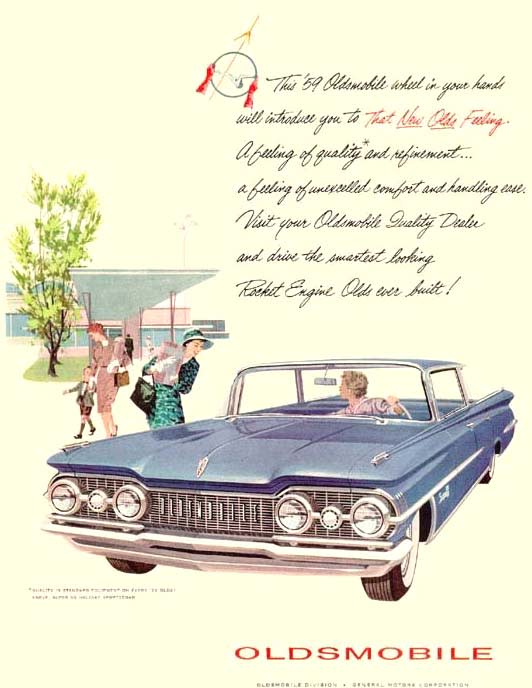
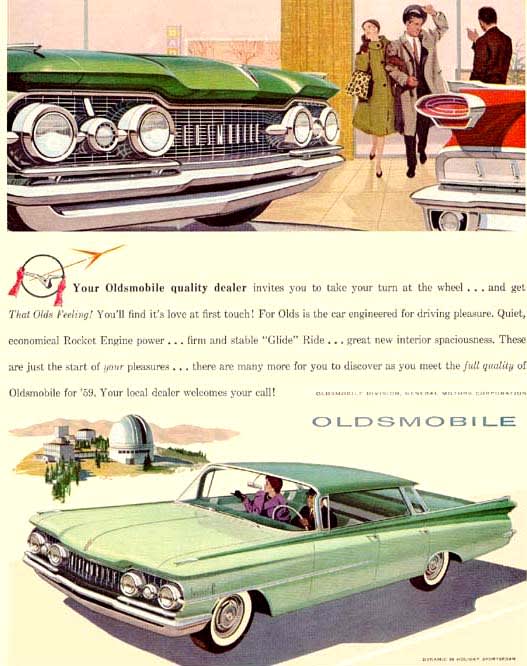
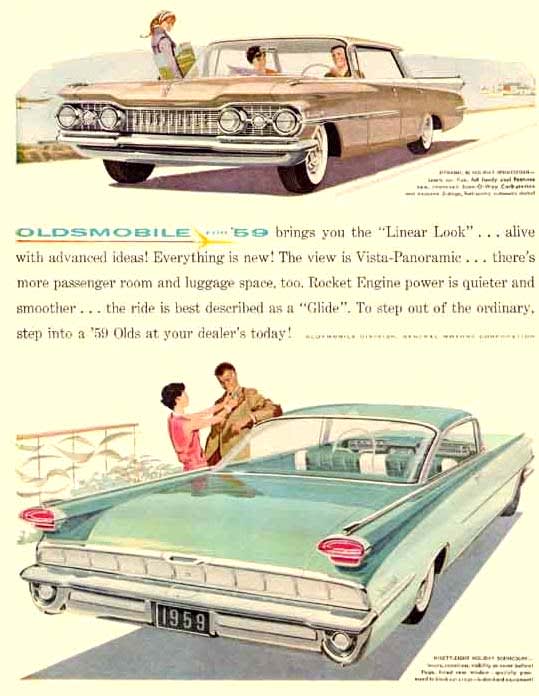

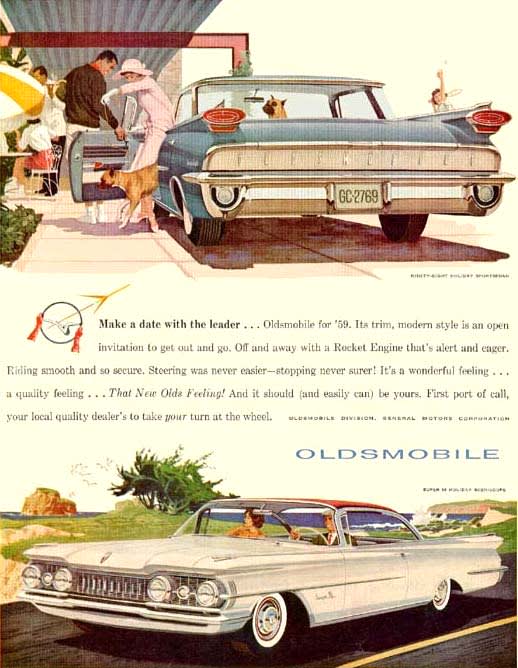
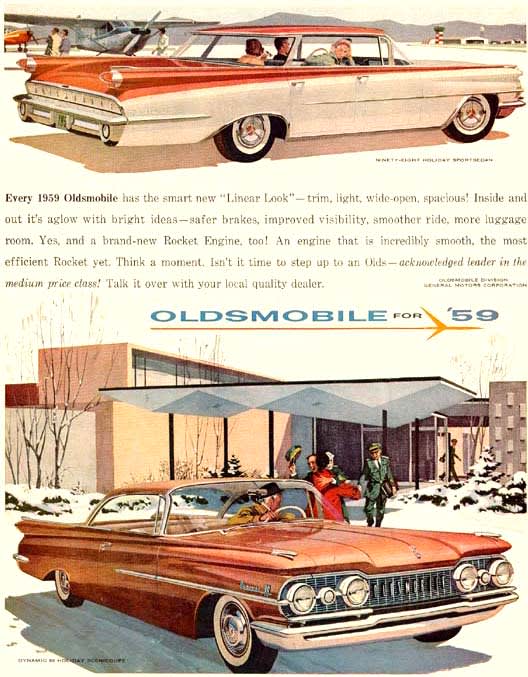


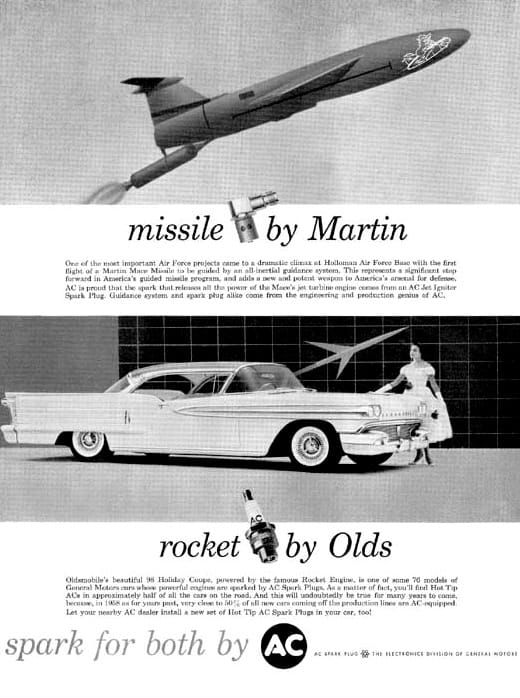



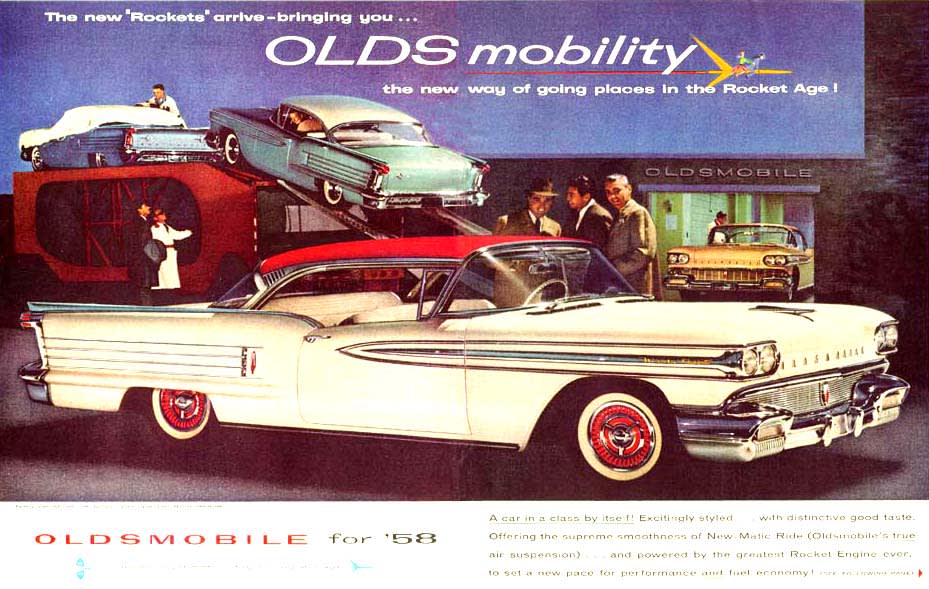


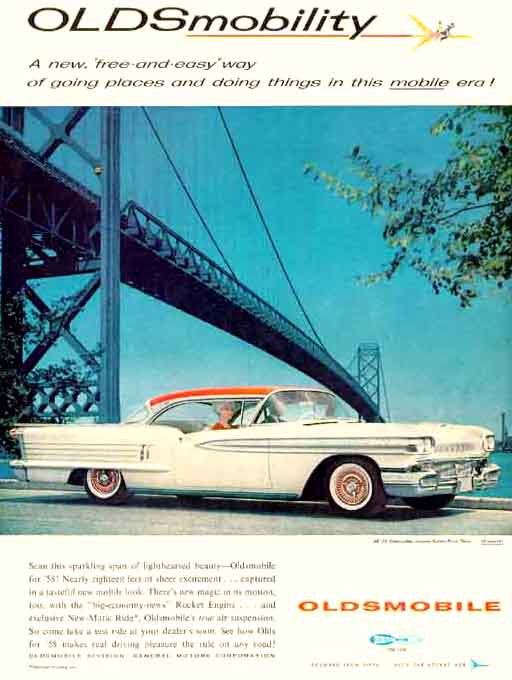



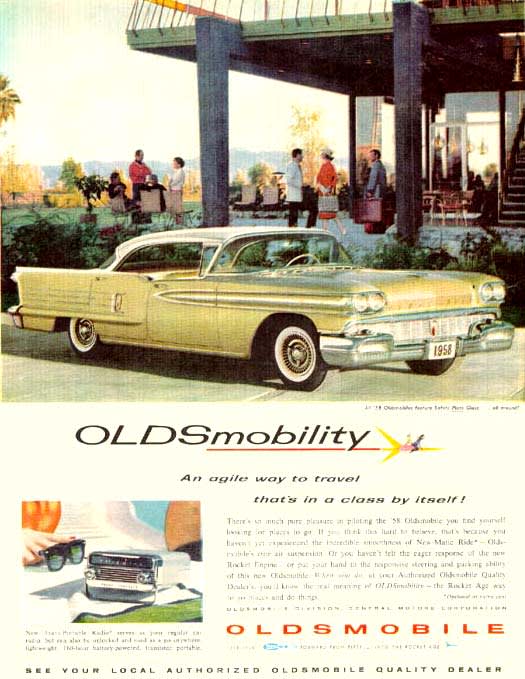
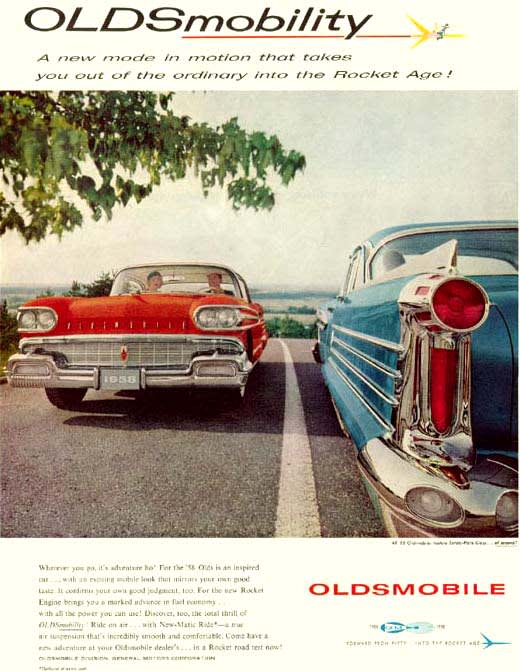
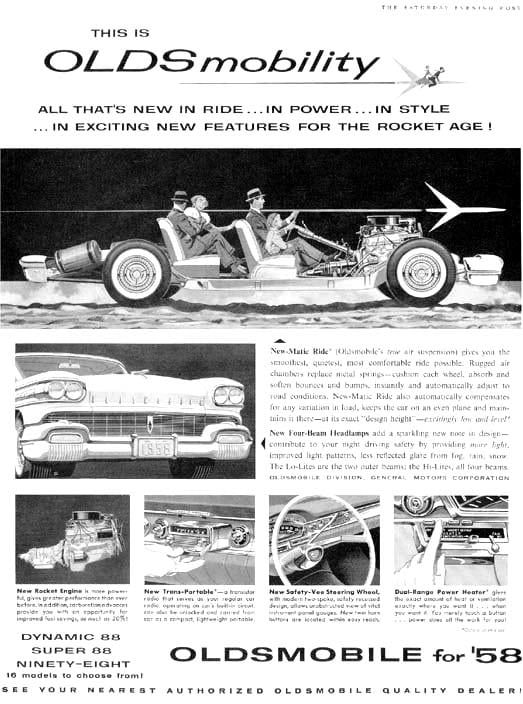


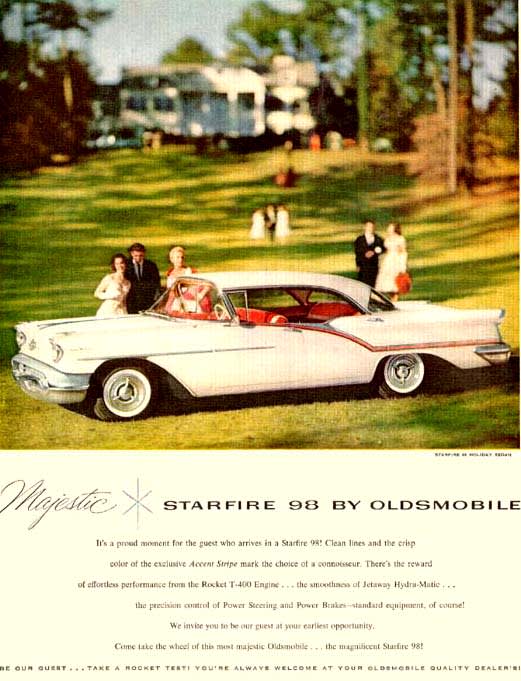
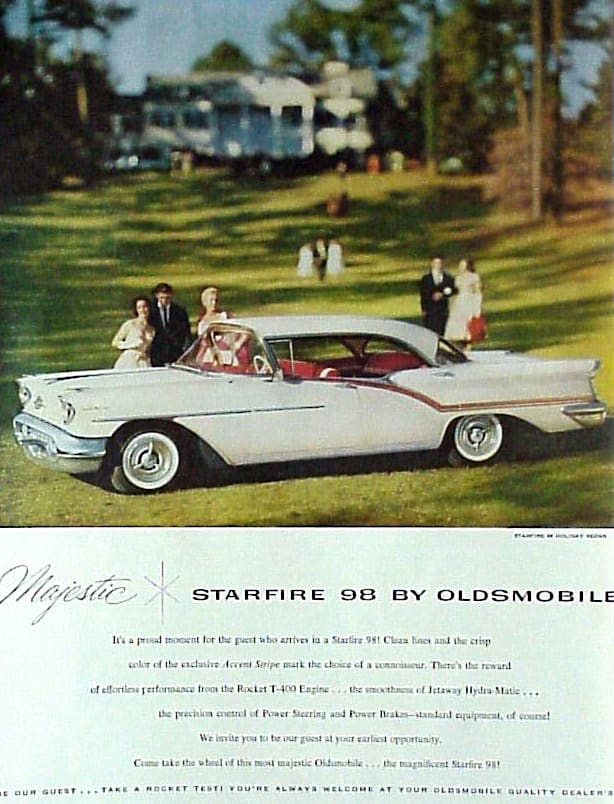



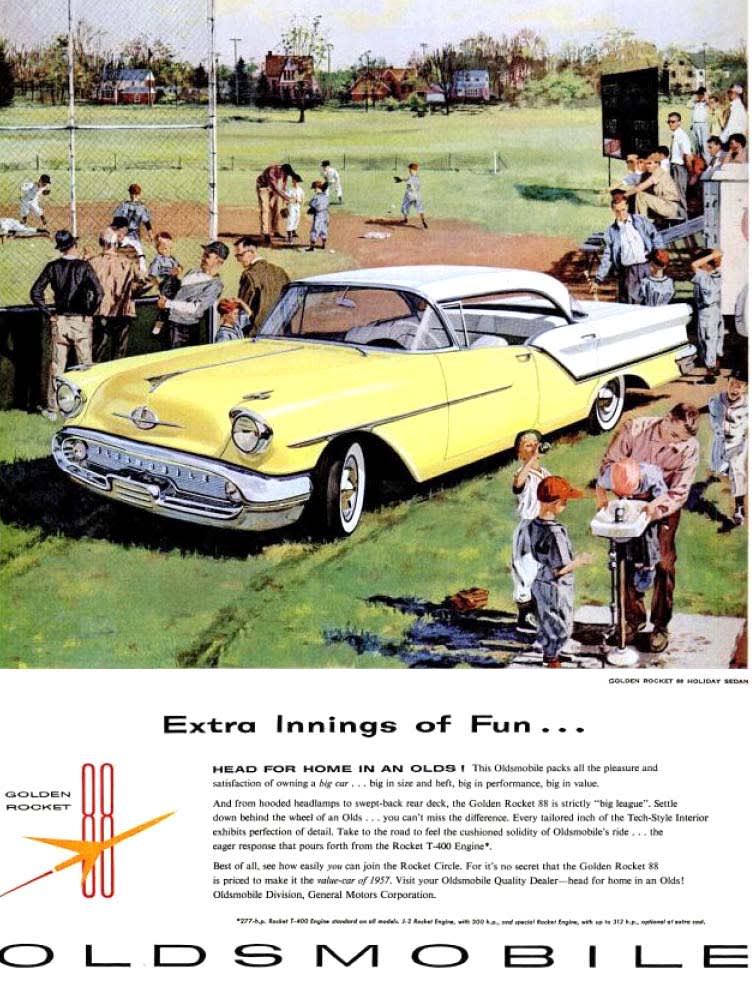


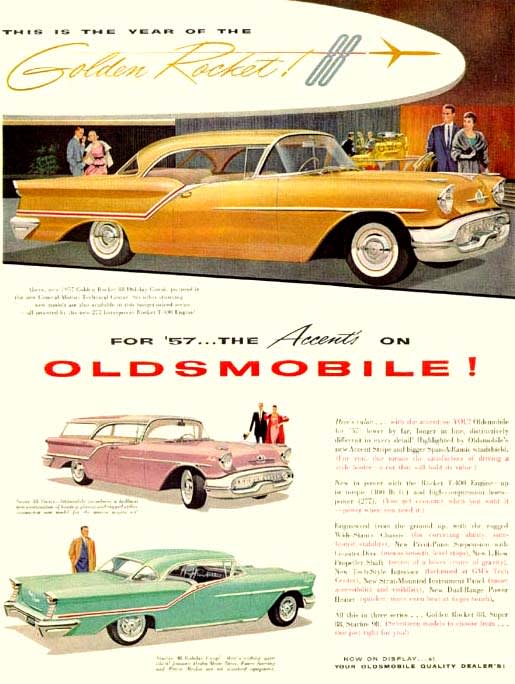

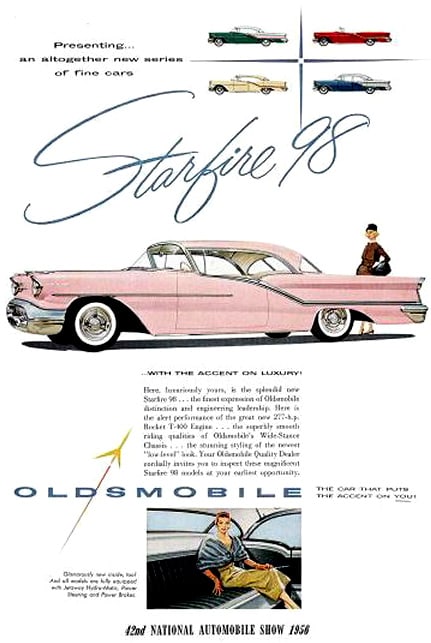
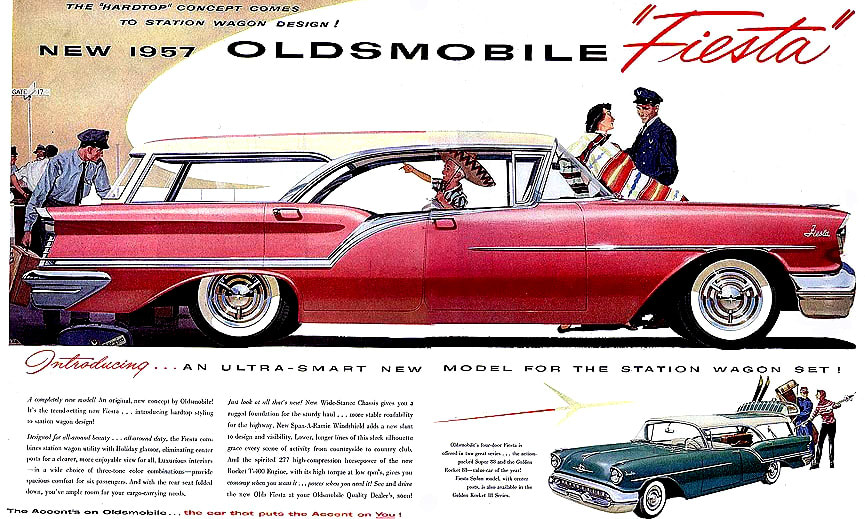
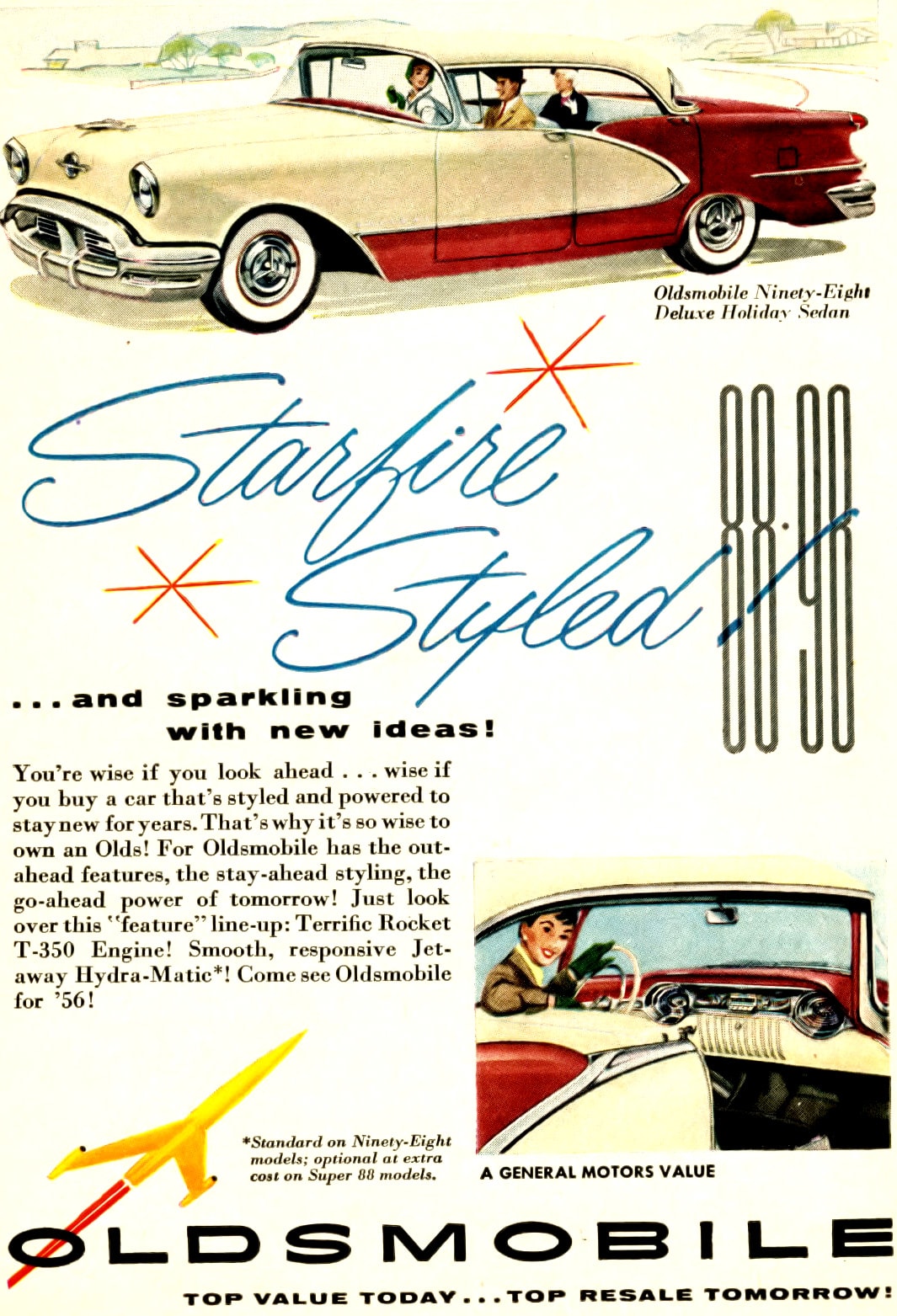








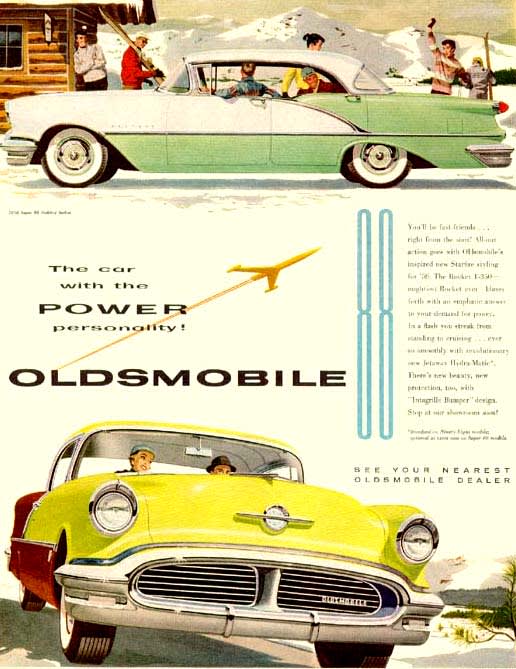

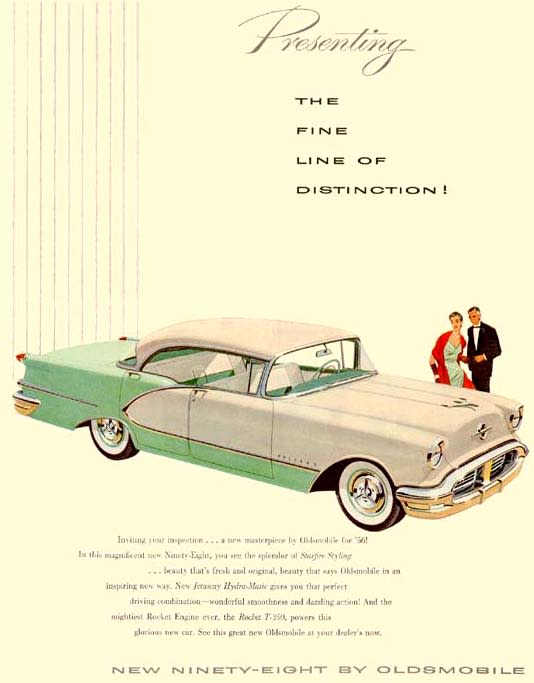
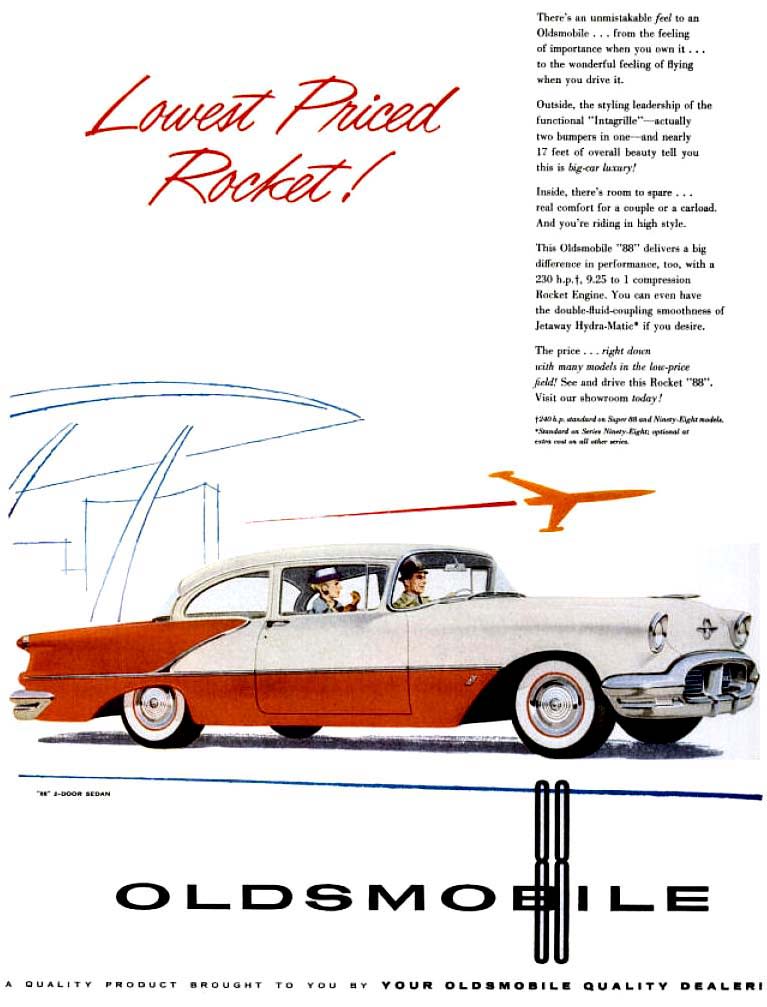

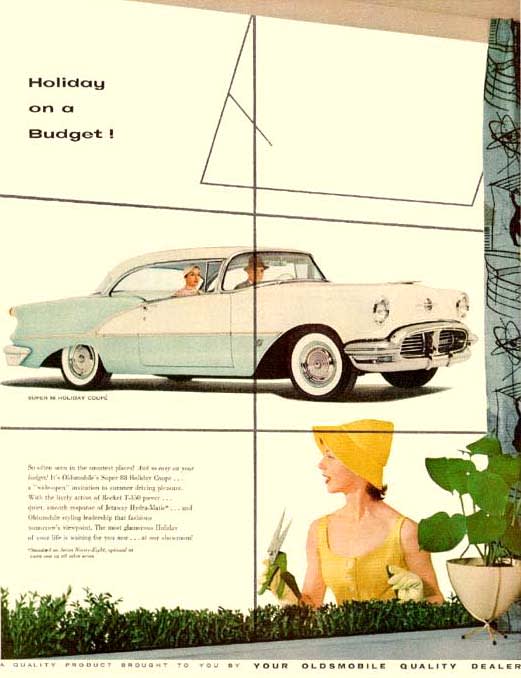
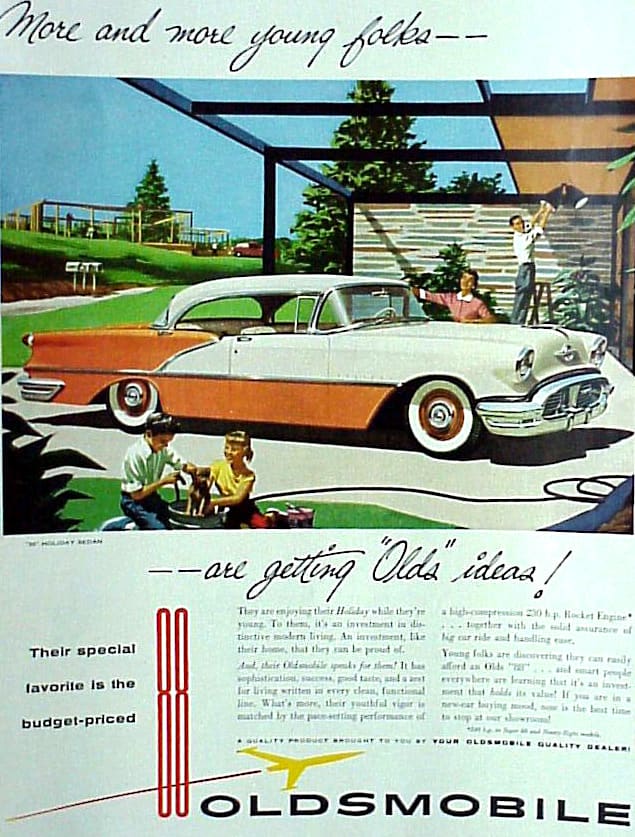


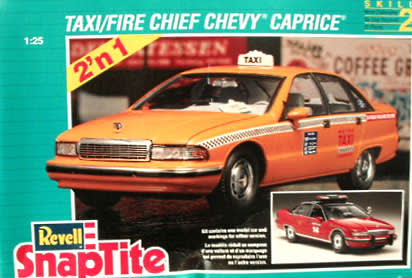

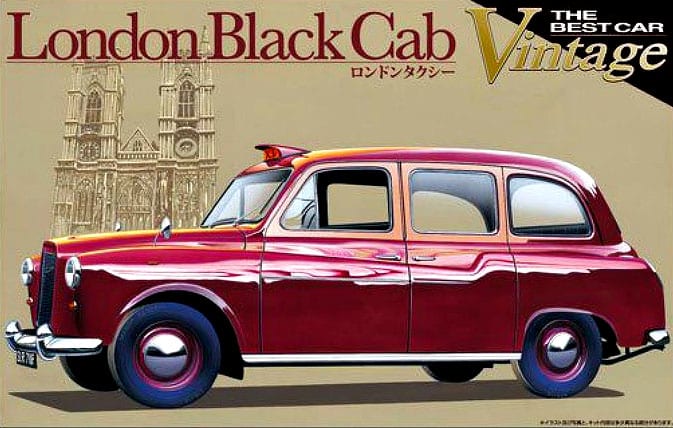


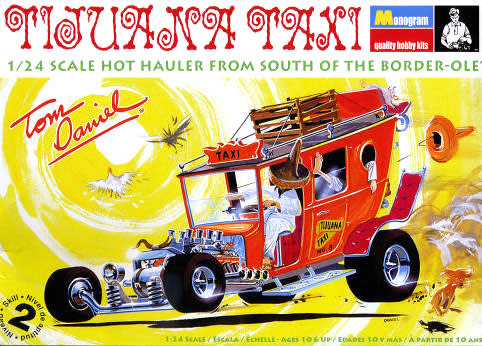
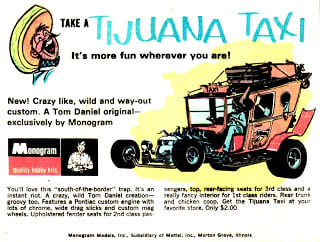
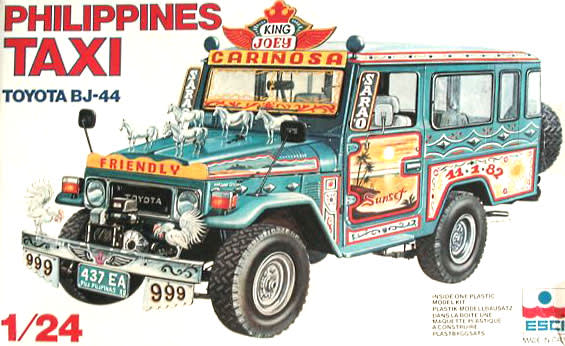

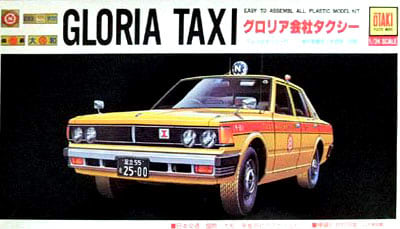
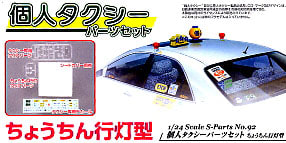
























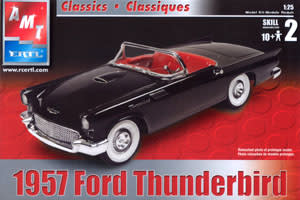
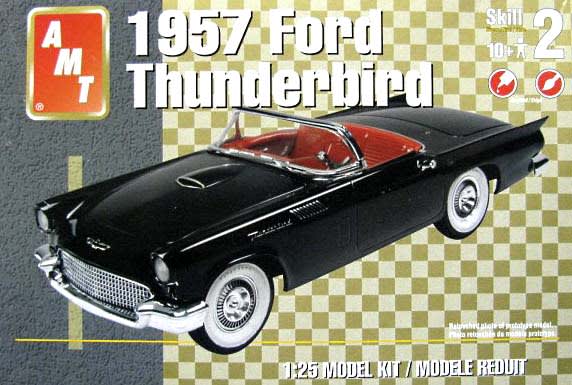




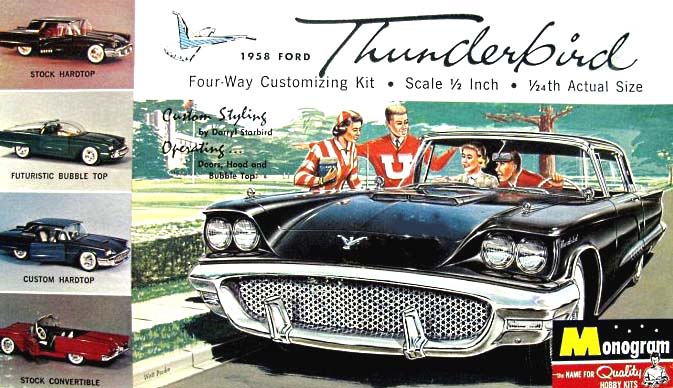
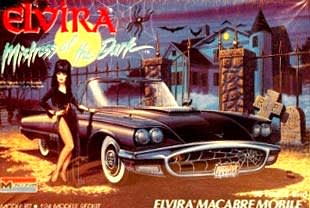



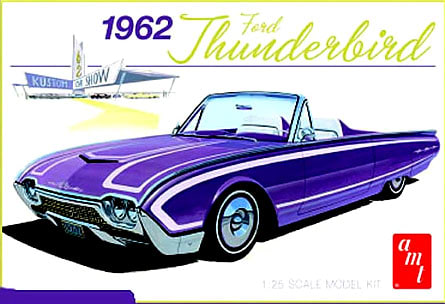



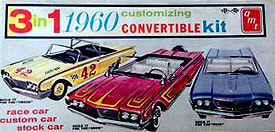
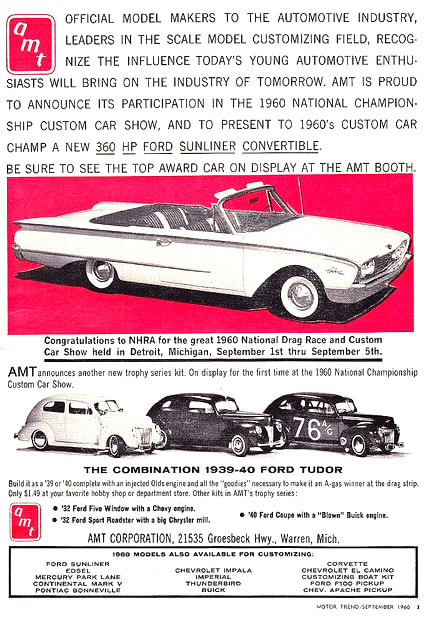

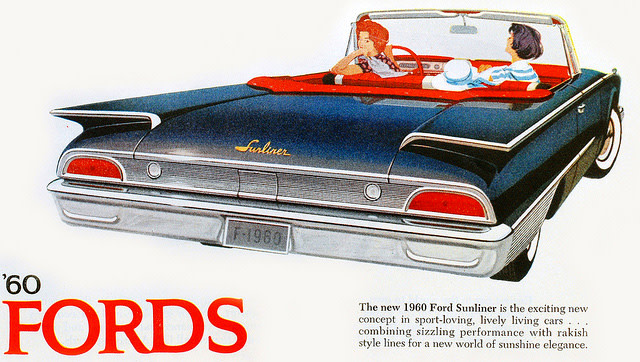



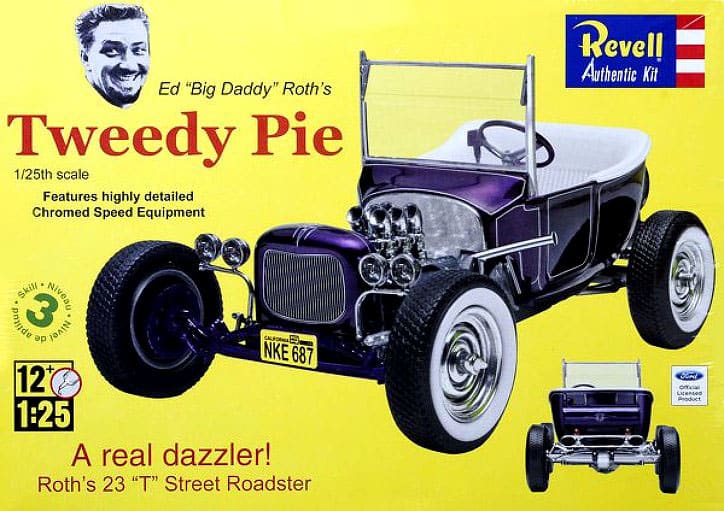
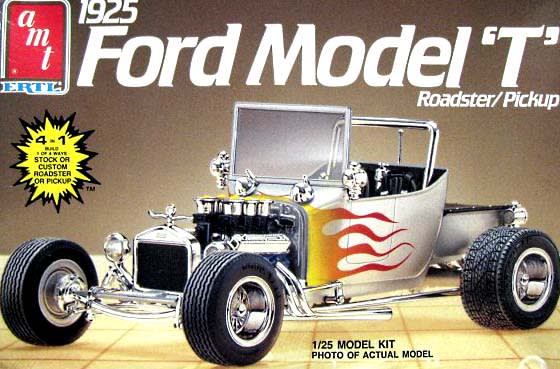


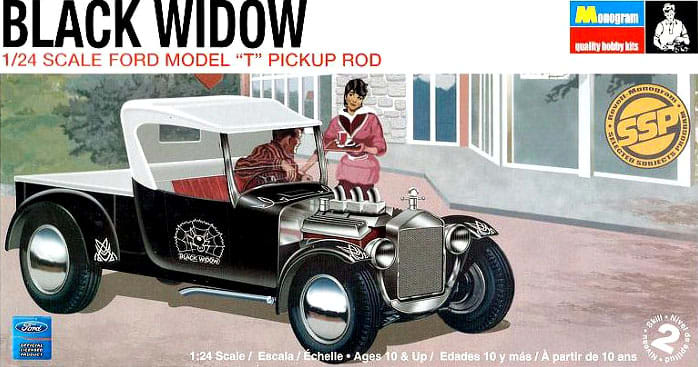

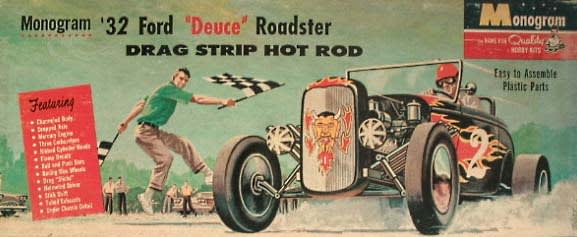
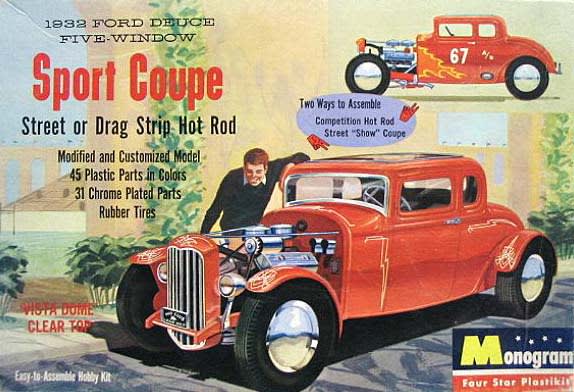




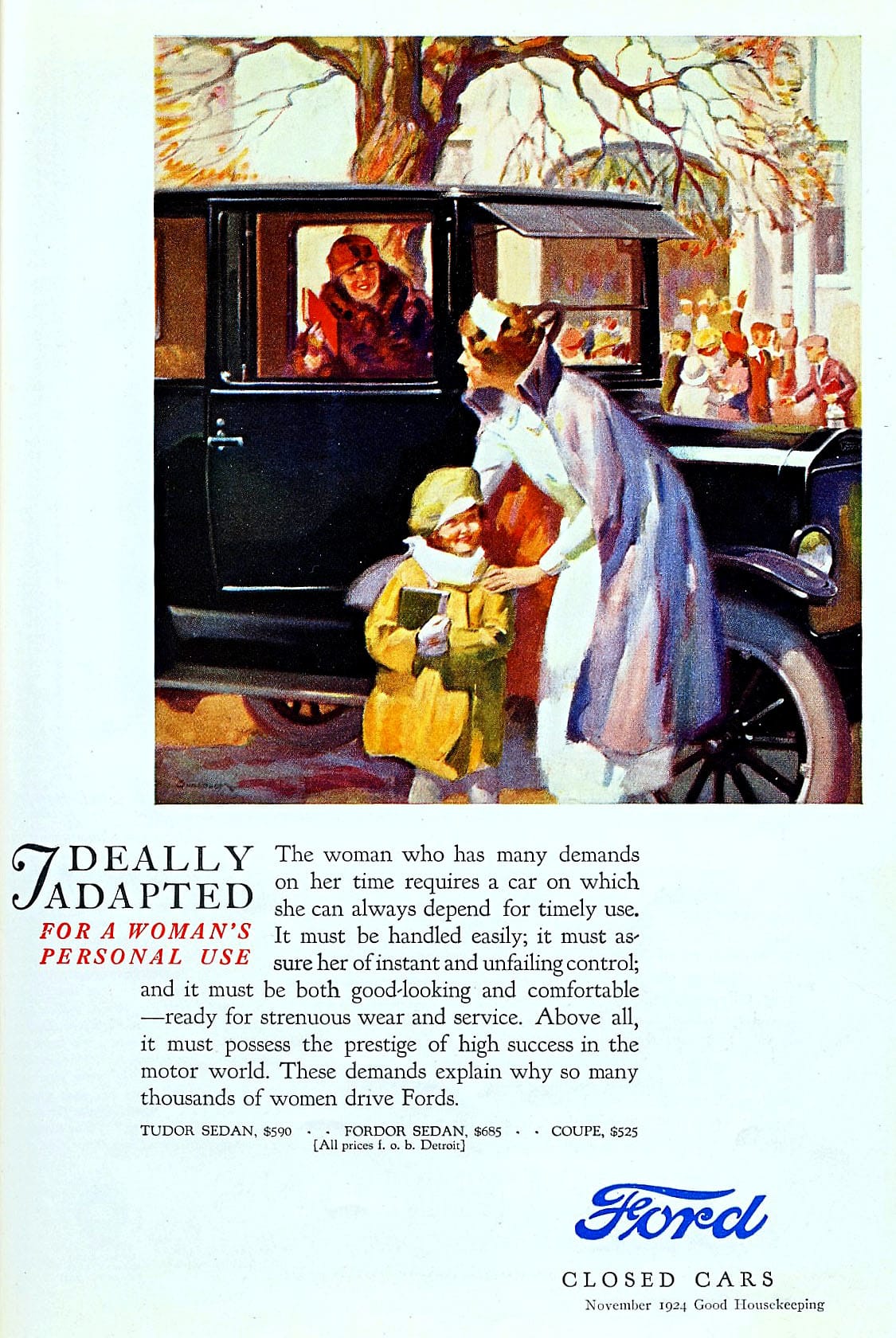

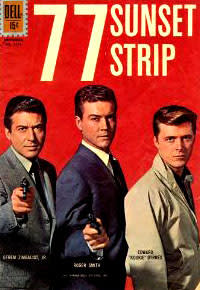


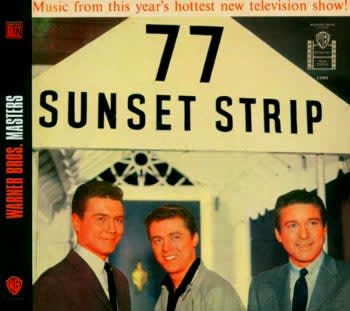


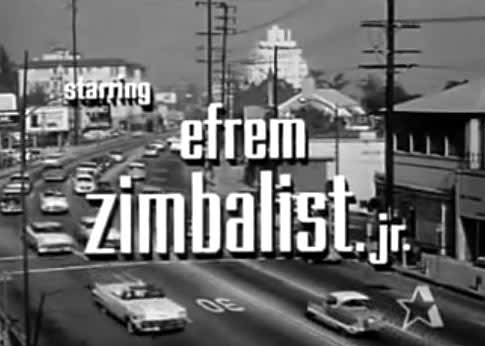













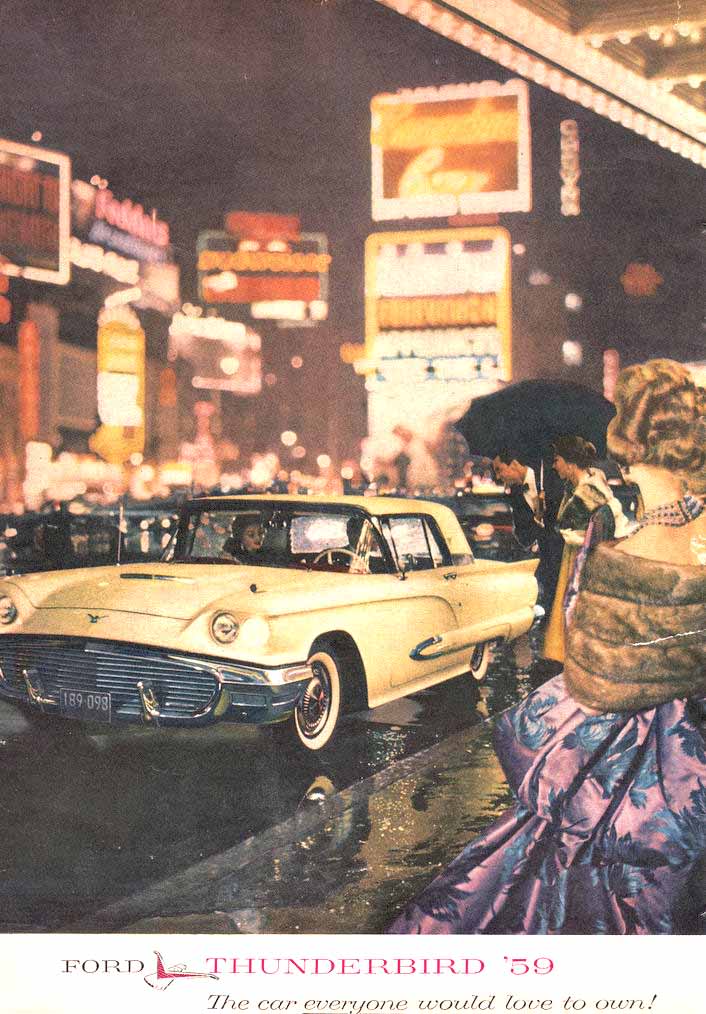







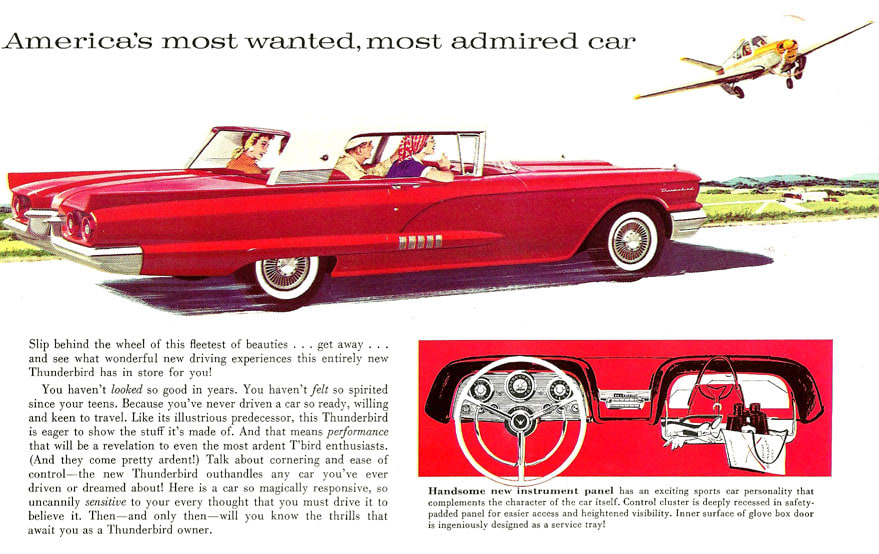
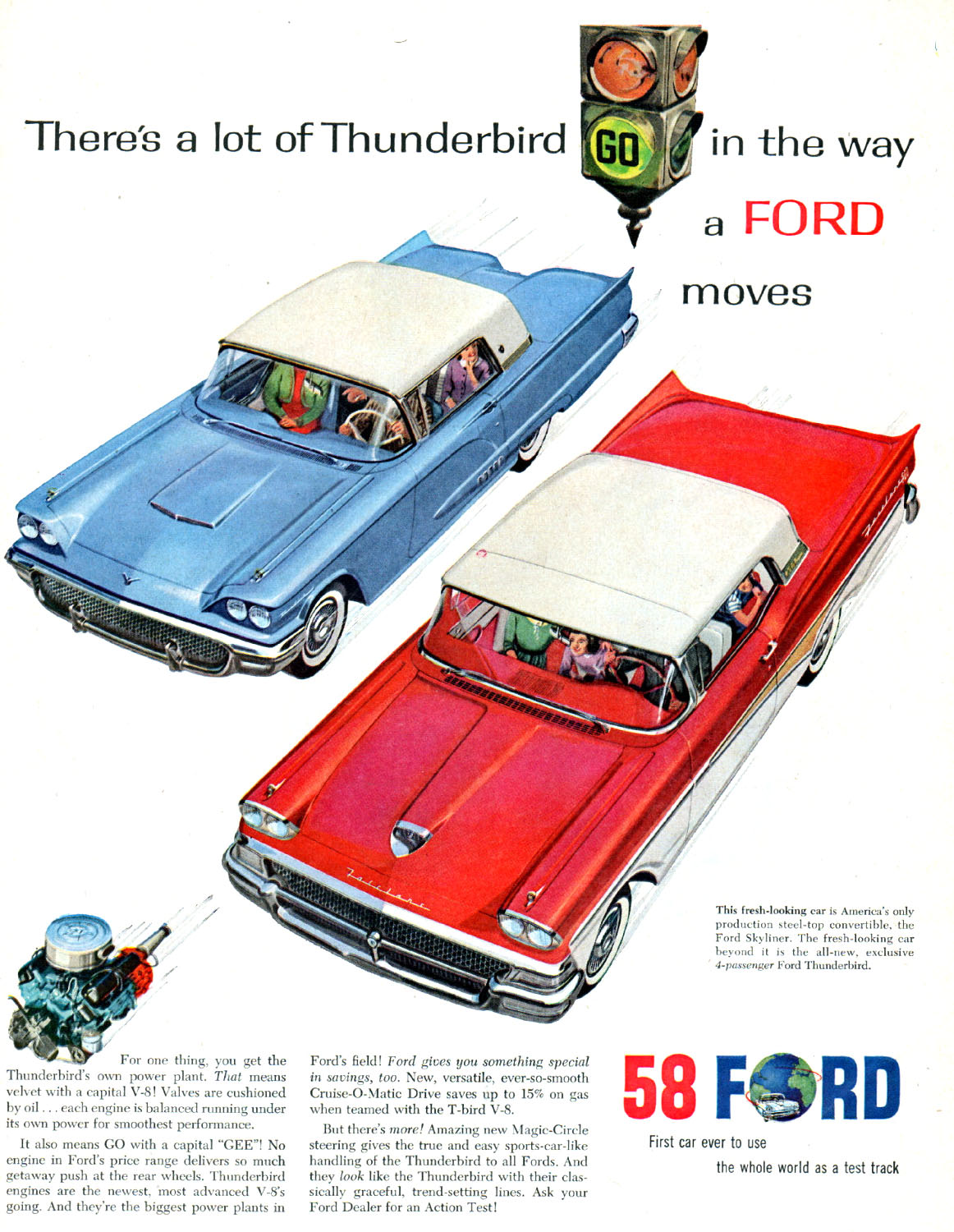



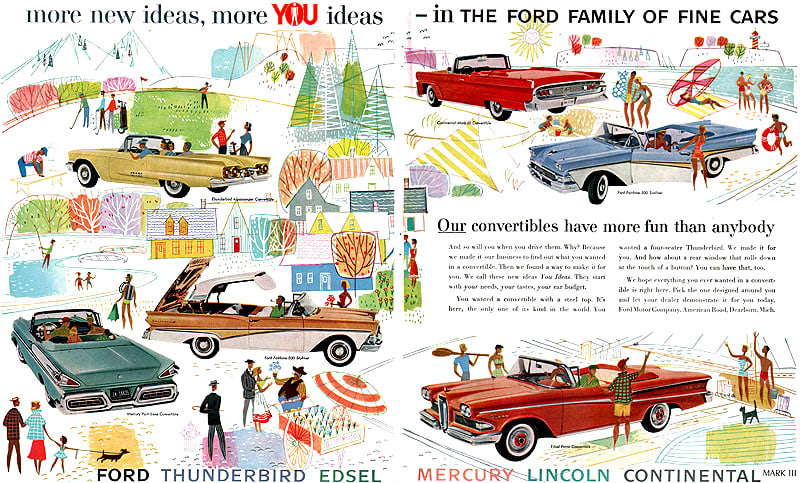
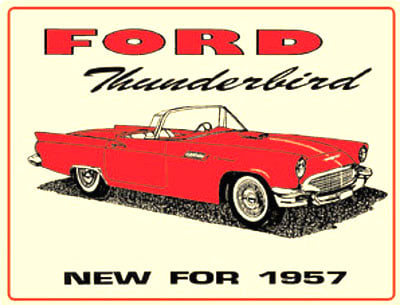







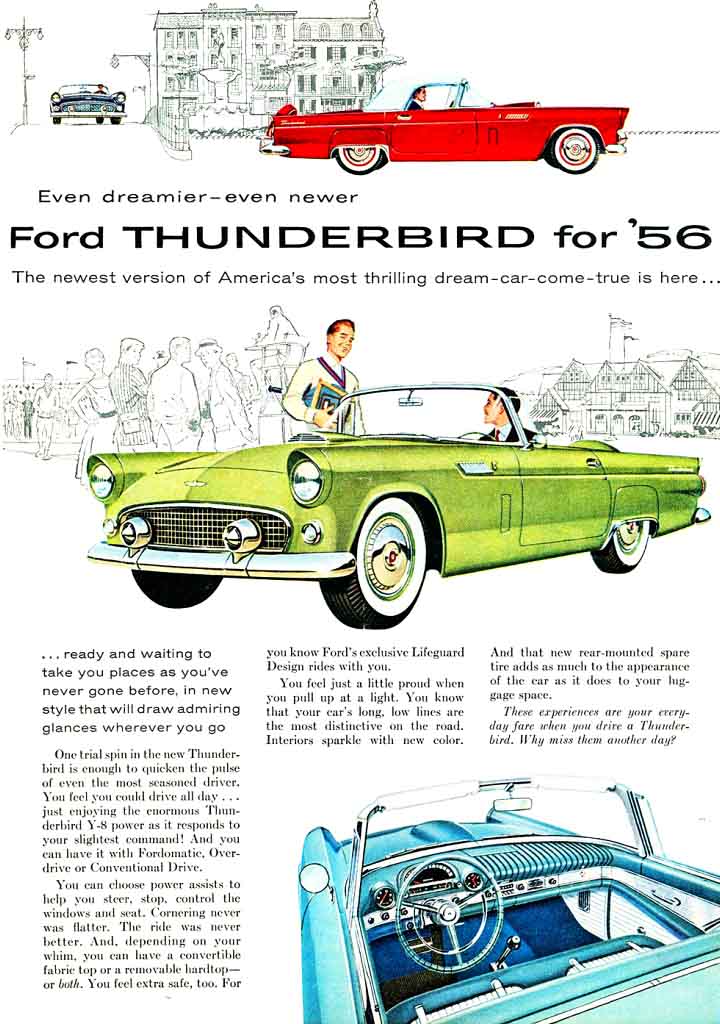

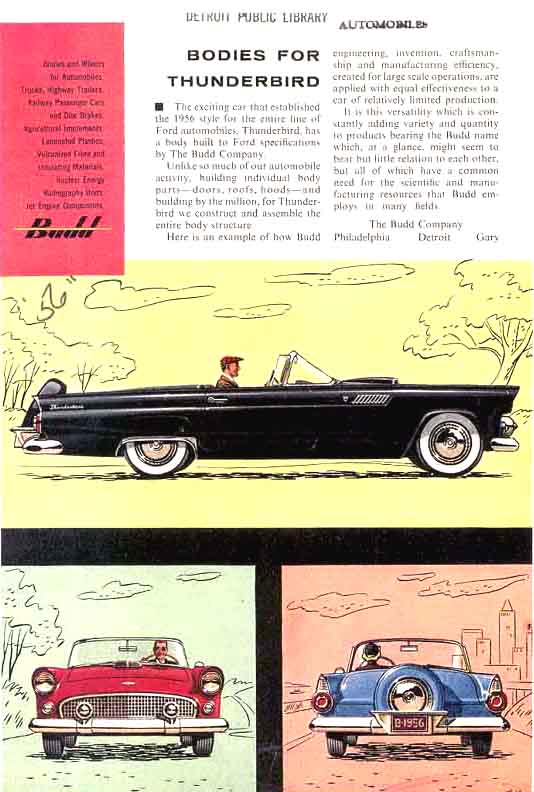
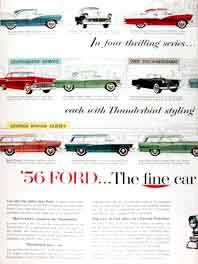


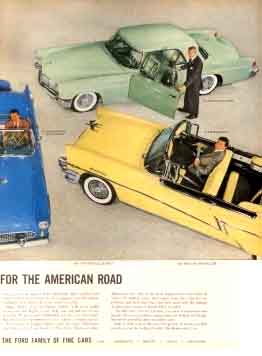


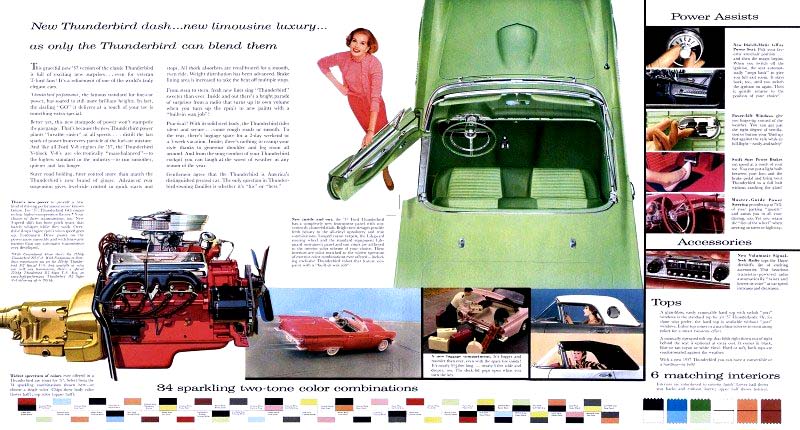
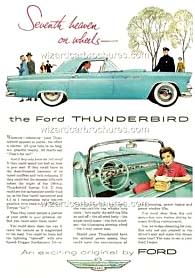


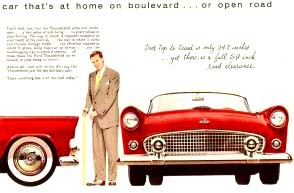
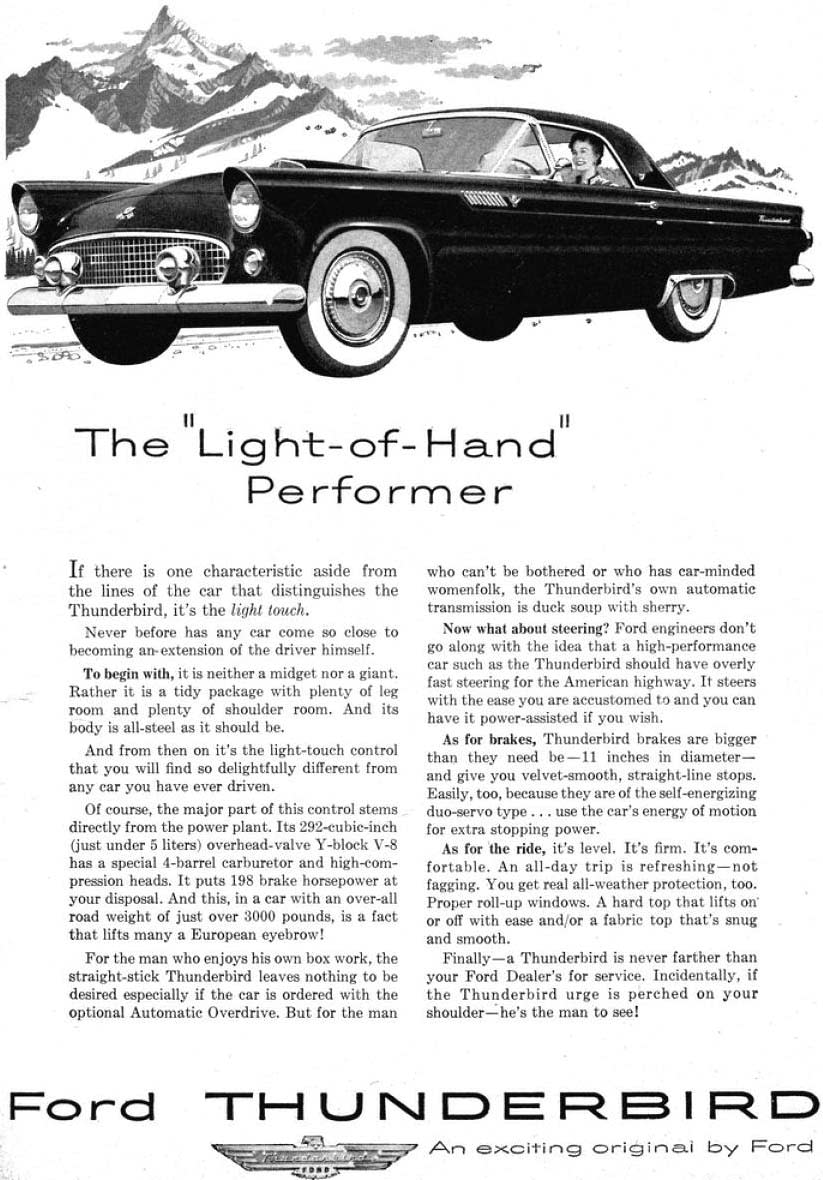
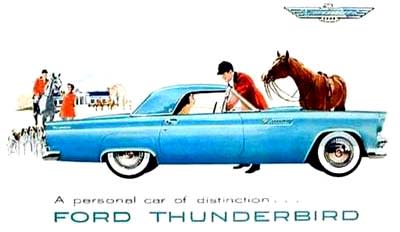

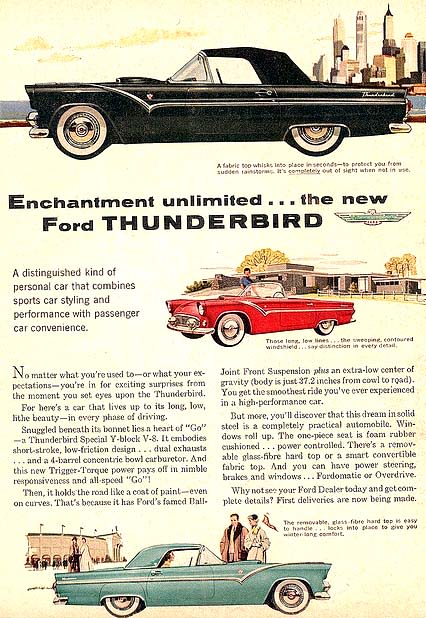
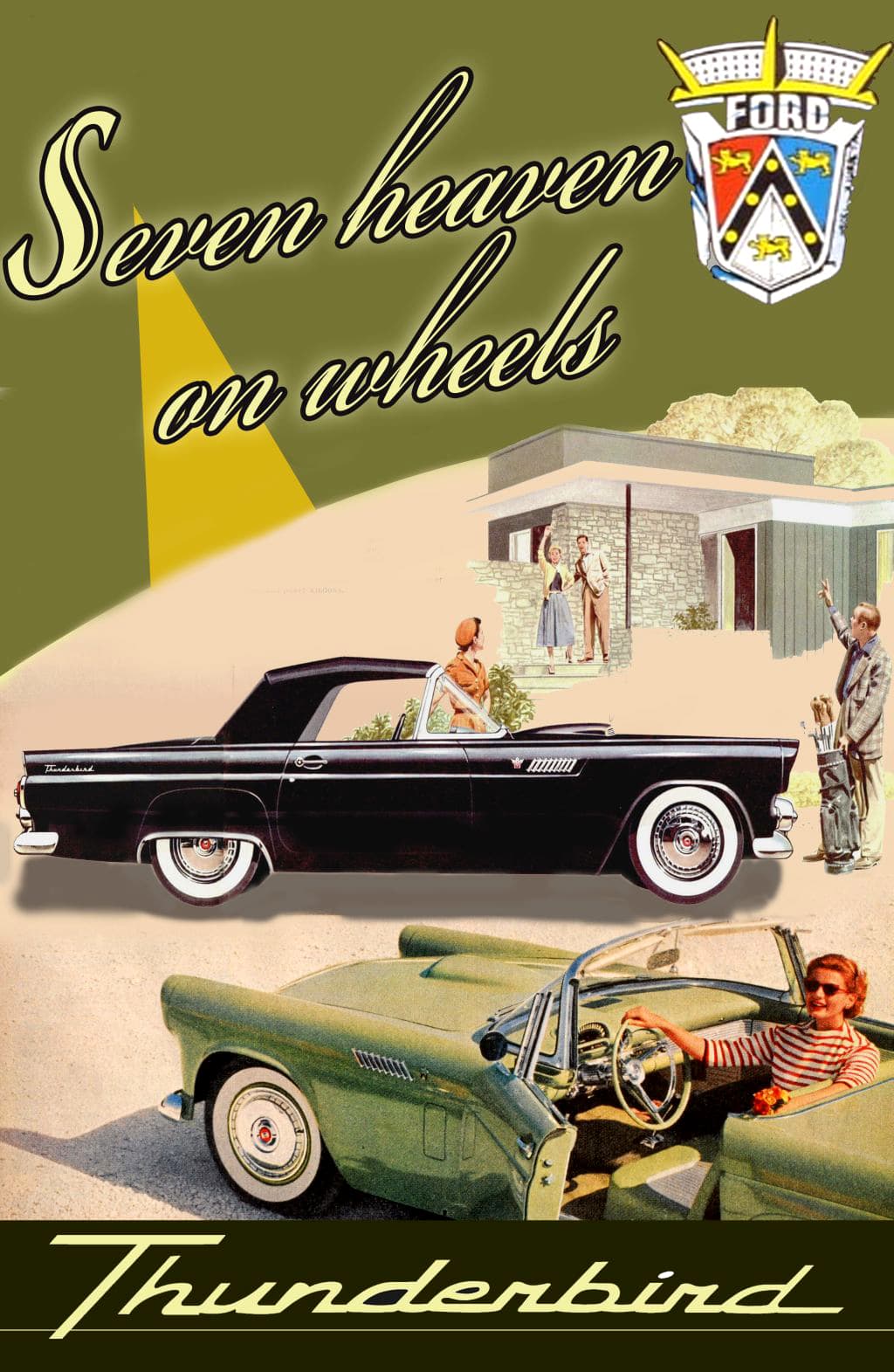




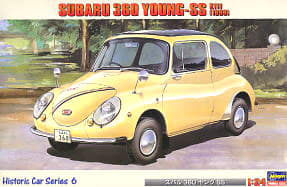

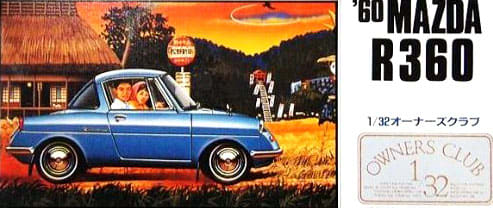
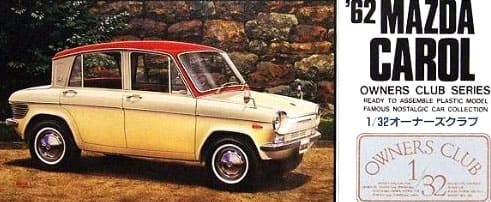











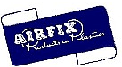

 美術館
美術館







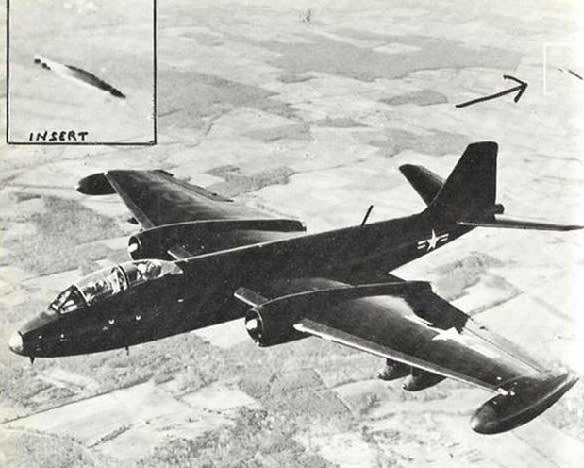








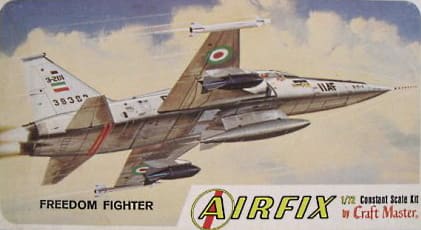


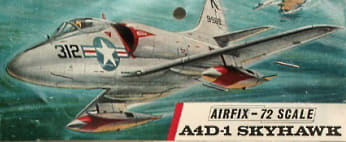

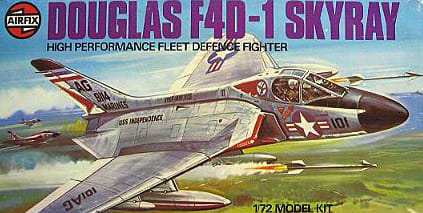
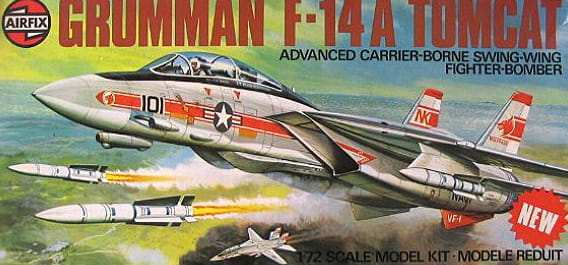


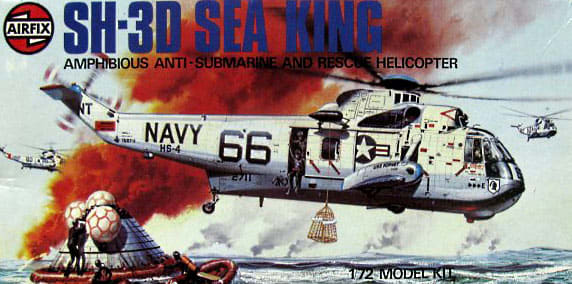

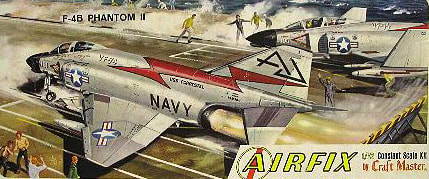


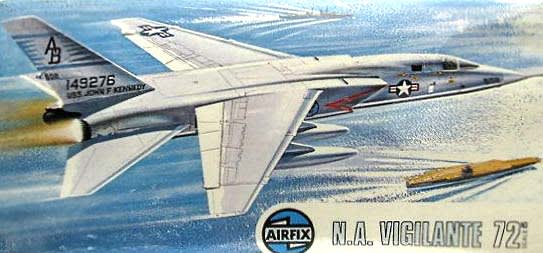

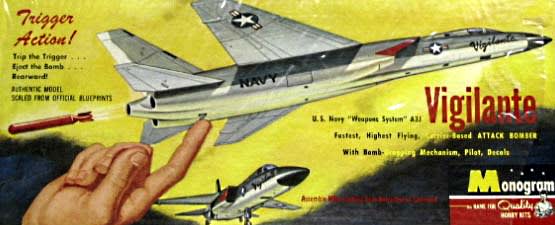



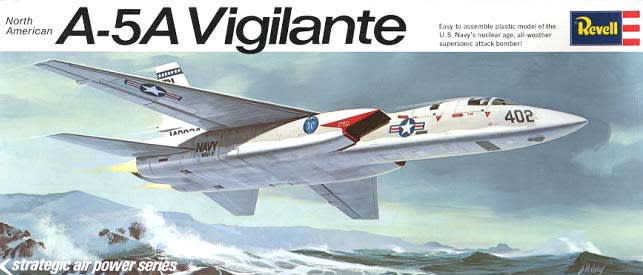



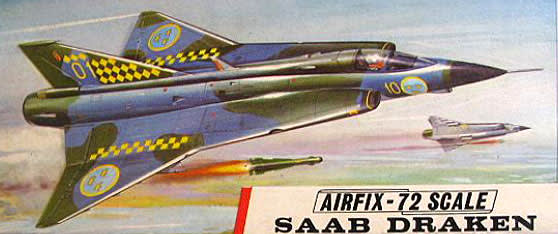


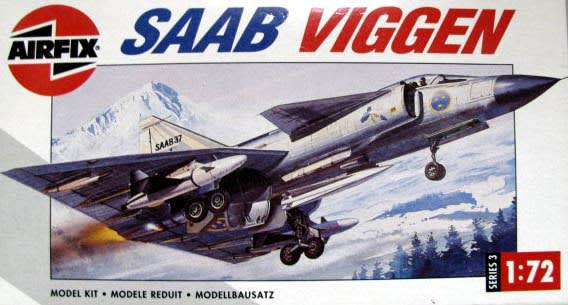




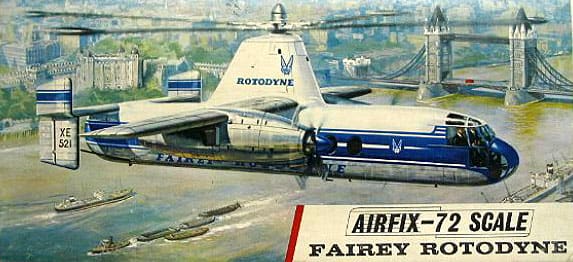
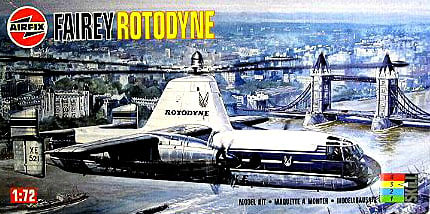






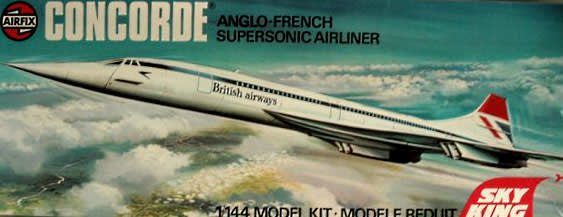


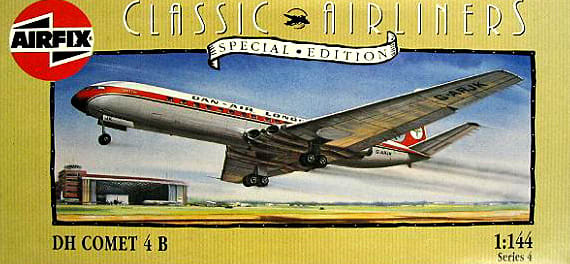


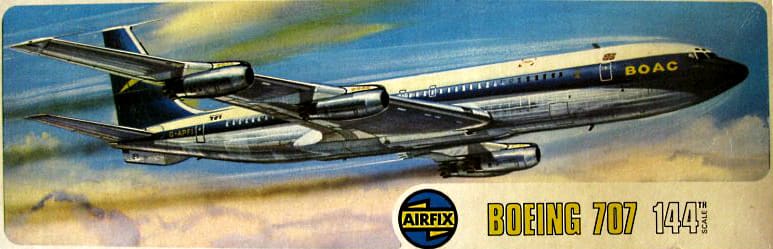


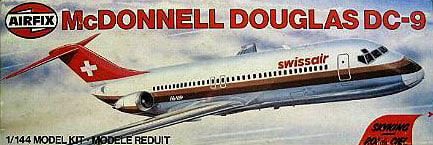

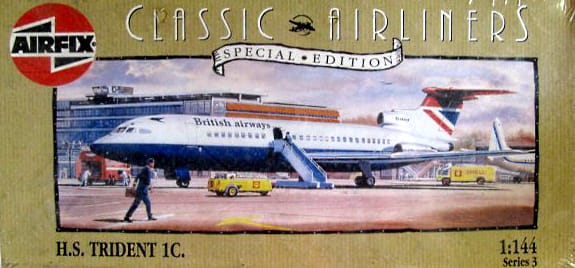
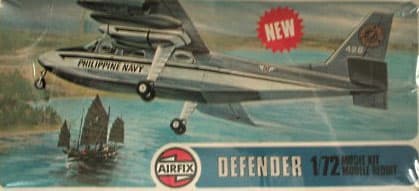
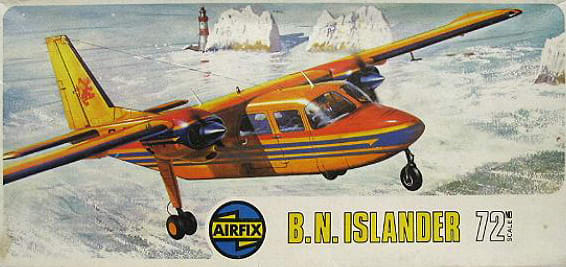


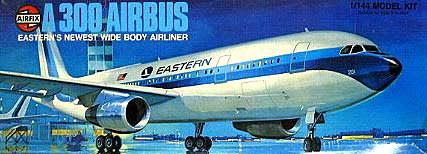
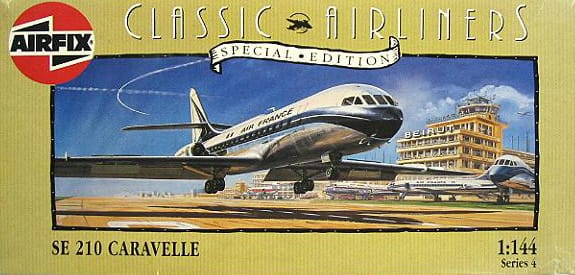
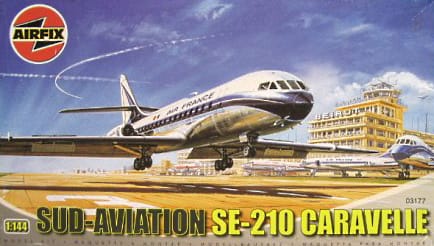



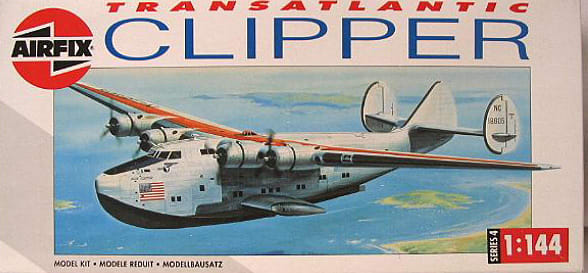





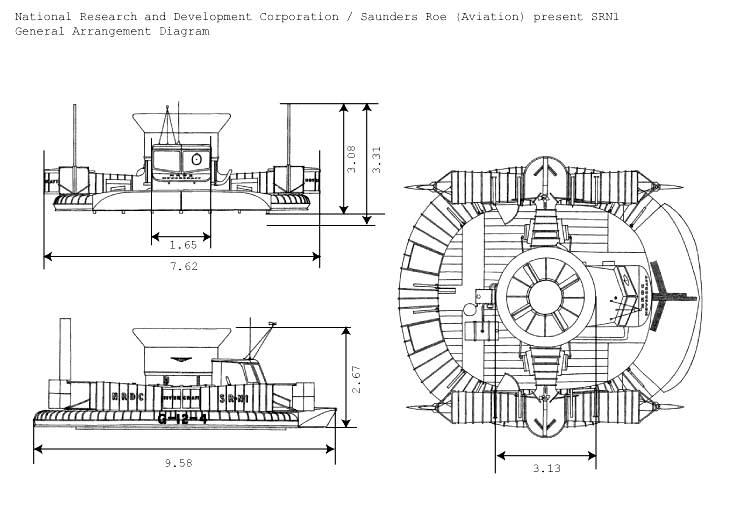







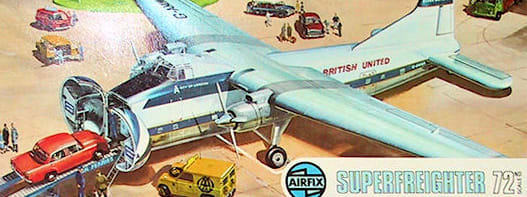


 Wikipedia
Wikipedia