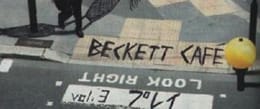『Flowers』は、現代を代表する有名女優を6人も動員(蒼井優、竹内結子、田中麗奈、仲間由紀恵、鈴木京香、広末涼子)した上で、ほぼ均等な登場時間を割り当てて競演させた作品で、まさにタイトルどおり、〈花〉なるものの複数性を具現しようとしている。けれども本作が、化粧品メーカーのイメージ広告の延長線上に敷かれた〈総花的〉な企画物で終わっている、ということを指摘するだけでは、おそらく不十分であろう。
本作が真に批判的に見られなければならないのは、よりシンプルな理由、つまり、保守勢力による少子化対策的プロパガンダとして、このフィルムがじつに牧歌的に「産めや、殖やせや」を謳い上げている事実に、赤面しない者はいないであろうからである。ここに登場する6人のヒロインたちは、女である前に、いやひとりの人間である前に、「母体」であることを要求されている。〈花=flowers〉のアレゴリーは、女という生き物がなにより、単なる花弁であること、生殖する器官でしかないことを、あられもなく主張している。
6人のうち、田中麗奈と鈴木京香だけは自立の道を模索するが、結局は敗残の涙を流し、家族の慰撫によって立ち直る道しか残されていない。「早いところ、くだらない観念など捨てて、命の糸を紡いでいったらどうかね」という、作者側の声が聞こえてくるようだ。これほどの反動的な女卑のプロパガンダが、21世紀を10年も経過した現在に、なぜ出現せねばならないのだろうか。
ただ、この『Flowers』というイメージ成果物が、広告代理店、大手映画会社、化粧品メーカー、保守系新聞メディアの代表者たちの談合から生まれた「オトナの産物」であることを、いまさら問題視するというのは、清和会・ネオコンの跳梁を経験したこの日本ではもはや、それほど意味のあることではないように思える。
最大の問題は、そうした製作環境において、わずか25歳で『タイヨウのうた』(2006)でデビューを果たした小泉徳宏という若手監督が、映画作家という人種は従順な小動物なんかではないのだということを、少しも証明しようとしていないことであり……または、証明する努力を(おそらく意図的に)放棄していることなのである。まだ30歳であり、その実力も認められているのだろうから、次作では、大幅な発想の転換と深化を求めていきたい。
TOHOシネマズ日劇ほか、全国で上映中
http://flowers-movie.jp/
本作が真に批判的に見られなければならないのは、よりシンプルな理由、つまり、保守勢力による少子化対策的プロパガンダとして、このフィルムがじつに牧歌的に「産めや、殖やせや」を謳い上げている事実に、赤面しない者はいないであろうからである。ここに登場する6人のヒロインたちは、女である前に、いやひとりの人間である前に、「母体」であることを要求されている。〈花=flowers〉のアレゴリーは、女という生き物がなにより、単なる花弁であること、生殖する器官でしかないことを、あられもなく主張している。
6人のうち、田中麗奈と鈴木京香だけは自立の道を模索するが、結局は敗残の涙を流し、家族の慰撫によって立ち直る道しか残されていない。「早いところ、くだらない観念など捨てて、命の糸を紡いでいったらどうかね」という、作者側の声が聞こえてくるようだ。これほどの反動的な女卑のプロパガンダが、21世紀を10年も経過した現在に、なぜ出現せねばならないのだろうか。
ただ、この『Flowers』というイメージ成果物が、広告代理店、大手映画会社、化粧品メーカー、保守系新聞メディアの代表者たちの談合から生まれた「オトナの産物」であることを、いまさら問題視するというのは、清和会・ネオコンの跳梁を経験したこの日本ではもはや、それほど意味のあることではないように思える。
最大の問題は、そうした製作環境において、わずか25歳で『タイヨウのうた』(2006)でデビューを果たした小泉徳宏という若手監督が、映画作家という人種は従順な小動物なんかではないのだということを、少しも証明しようとしていないことであり……または、証明する努力を(おそらく意図的に)放棄していることなのである。まだ30歳であり、その実力も認められているのだろうから、次作では、大幅な発想の転換と深化を求めていきたい。
TOHOシネマズ日劇ほか、全国で上映中
http://flowers-movie.jp/










 最後の舞台出演として
最後の舞台出演として