先の考察で完全な拡散を目指した拡散壁ではなく、ある程度拡散性をもちつつ、拡散方向をシミュレーションでき、コントロールできる壁形状として、半円柱を並べる提案をしたが、
半円柱は原木の形体に近く、ログハウスでも使われている形態であるため、コスト的に有利だろうという仮定の下で行った提案である。
だが、壁に半円柱を並べる部屋はネットで調べてもあまりなく、そもそもハードルが低いものなのか疑問に思えてきている。
直径20cmで半円柱のため厚み10cmの建材が果たして入手が容易なのかどうか、
ログハウスは円柱を積み上げるだけだが、先の提案は、石膏ボードに半円柱の木材を取り付けるものである。重すぎて建物への負担が大きいのではないか。
原木のままだとさすがにワイルドすぎるが、そのあたり控えめのコストで違和感なく加工できるのか
など考える逆にコストがかかったり無理なアイディアな気もしてくる。
そもそも拡散性がある程度担保されるのであれば別のアイディアでもいい。
古典的ではあるがリブを使えばそれでいいような気もしてくる。
リブの拡散性はどんなものかというのを論文を少し漁ってみた。
多分同じような研究は沢山ありそうだがさらっと探すだけでも豊富に見つかる
より核心的な論文も他にありそうだが、2編読むとある程度知りたいことが分かった印象。
出典
日本音響学会誌65巻11号の東京大学の佐久間哲哉先生の小特集
壁面の拡散性指標としての乱反射率の測定法
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jasj/65/11/65_KJ00005821986/_pdf
測定法に関しては素人なのでスキップするとして、

厚みの違うクサビリブと矩形リブをで拡散性を比較実験をしている。
結果が以下のとおり

クサビよりも基本的には矩形の方が拡散性が良さそうだ(入手性、加工性も良いので文句なしである)。
とはいえ厚み2.5cmだと750Hz以下の拡散性がイマイチなようである。
もう一つの論文はパラメトリックスピーカーの研究に関する論文。
パラメトリックスピーカーの比較として普通のラウドスピーカーでも対照実験を行っており、今回は対照の方を見るのみ。
出典
東京大学の坂本慎一先生の科研費事業の経過報告書。
パラメトリックスピーカを用いた建築音響材料特性の計測法の開発
https://kaken.nii.ac.jp/ja/file/KAKENHI-PROJECT-26630260/26630260seika.pdf
厚み10cmの矩形のリブ2種類を3種類の排列方法で

反射壁から3mの距離で同心円状にマイクを並べて測定している。

Case.1の5cm×10cmの長方形のリブの拡散性。ラウドスピーカーの測定結果(青)の方のみを見ている。低域の250Hzまで比較的良く拡散できている。

Case.2の10cm×10cmの正方形リブを10cm間隔で並べた場合の拡散性。拡散性は若干落ちる。資材的なコストパフォーマンスとしても悪そうである。

Case.3の10cm×10cmの正方形リブを30cm間隔で並べた場合の拡散性。拡散性は割と良好である。Case.1とコスパの比較は悩ましいところだがCase.1の方が拡散性と勝手が良さそうか。

上の2編の論文を参考にすると5×10cmくらいの矩形リブを15cm間隔で配置できるならリブでもそこそこの拡散性は確保できそうである。
10cmの深さは結構大きいが、それくらいは入れれば250Hzをコントロールできるのなら仕方ないのかもしれない。それより下は定在波の領域になってくるのでそれより大きくする必要はないように思える。
リブの場合のいいところはリブ間の15cmの間隔により細かいリブを入れたり、QRDのように深さを変えたり、シルヴァンアンクのように円柱を入れたりと、さらに細かい拡散を入れる余地があり、
また吸音材を間に入れることで吸音率を調整することもできる。
その追加をDIYで行うのも容易であるところも良い。(リブを水平に走らせることが前提であるが)
さらに10cmの深さというとちょっとした壁シェルフである。棚として本やリモコンやCDなどを置いておくスペースであったりケーブルの遮蔽もしやすかったりと使い勝手がよさそうというのもメリットである。
半円柱は原木の形体に近く、ログハウスでも使われている形態であるため、コスト的に有利だろうという仮定の下で行った提案である。
だが、壁に半円柱を並べる部屋はネットで調べてもあまりなく、そもそもハードルが低いものなのか疑問に思えてきている。
直径20cmで半円柱のため厚み10cmの建材が果たして入手が容易なのかどうか、
ログハウスは円柱を積み上げるだけだが、先の提案は、石膏ボードに半円柱の木材を取り付けるものである。重すぎて建物への負担が大きいのではないか。
原木のままだとさすがにワイルドすぎるが、そのあたり控えめのコストで違和感なく加工できるのか
など考える逆にコストがかかったり無理なアイディアな気もしてくる。
そもそも拡散性がある程度担保されるのであれば別のアイディアでもいい。
古典的ではあるがリブを使えばそれでいいような気もしてくる。
リブの拡散性はどんなものかというのを論文を少し漁ってみた。
多分同じような研究は沢山ありそうだがさらっと探すだけでも豊富に見つかる
より核心的な論文も他にありそうだが、2編読むとある程度知りたいことが分かった印象。
出典
日本音響学会誌65巻11号の東京大学の佐久間哲哉先生の小特集
壁面の拡散性指標としての乱反射率の測定法
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jasj/65/11/65_KJ00005821986/_pdf
測定法に関しては素人なのでスキップするとして、

厚みの違うクサビリブと矩形リブをで拡散性を比較実験をしている。
結果が以下のとおり

クサビよりも基本的には矩形の方が拡散性が良さそうだ(入手性、加工性も良いので文句なしである)。
とはいえ厚み2.5cmだと750Hz以下の拡散性がイマイチなようである。
もう一つの論文はパラメトリックスピーカーの研究に関する論文。
パラメトリックスピーカーの比較として普通のラウドスピーカーでも対照実験を行っており、今回は対照の方を見るのみ。
出典
東京大学の坂本慎一先生の科研費事業の経過報告書。
パラメトリックスピーカを用いた建築音響材料特性の計測法の開発
https://kaken.nii.ac.jp/ja/file/KAKENHI-PROJECT-26630260/26630260seika.pdf
厚み10cmの矩形のリブ2種類を3種類の排列方法で

反射壁から3mの距離で同心円状にマイクを並べて測定している。

Case.1の5cm×10cmの長方形のリブの拡散性。ラウドスピーカーの測定結果(青)の方のみを見ている。低域の250Hzまで比較的良く拡散できている。

Case.2の10cm×10cmの正方形リブを10cm間隔で並べた場合の拡散性。拡散性は若干落ちる。資材的なコストパフォーマンスとしても悪そうである。

Case.3の10cm×10cmの正方形リブを30cm間隔で並べた場合の拡散性。拡散性は割と良好である。Case.1とコスパの比較は悩ましいところだがCase.1の方が拡散性と勝手が良さそうか。

上の2編の論文を参考にすると5×10cmくらいの矩形リブを15cm間隔で配置できるならリブでもそこそこの拡散性は確保できそうである。
10cmの深さは結構大きいが、それくらいは入れれば250Hzをコントロールできるのなら仕方ないのかもしれない。それより下は定在波の領域になってくるのでそれより大きくする必要はないように思える。
リブの場合のいいところはリブ間の15cmの間隔により細かいリブを入れたり、QRDのように深さを変えたり、シルヴァンアンクのように円柱を入れたりと、さらに細かい拡散を入れる余地があり、
また吸音材を間に入れることで吸音率を調整することもできる。
その追加をDIYで行うのも容易であるところも良い。(リブを水平に走らせることが前提であるが)
さらに10cmの深さというとちょっとした壁シェルフである。棚として本やリモコンやCDなどを置いておくスペースであったりケーブルの遮蔽もしやすかったりと使い勝手がよさそうというのもメリットである。

















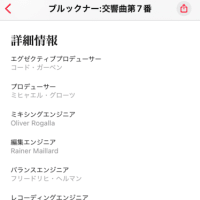

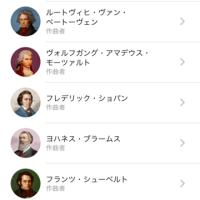
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます