どうやら拡散体は適当ではなく狙って作るもののようだ。
http://actools.tunetown.de/prd/
上記サイトで拡散体のシミュレーションが可能で、散乱させる各種数値を入力すると、こう作ると入力した帯域は散乱するよという拡散体の設計図を自動生成してくれる。
結構真面目にみんな室内音響を考えているんだなあと思いつつ、なかなかオーディオの世界から、この世界にディープに入る通路がなかなか見つからないのがなんとも言い難い。
簡単に手に入るのは何を買って繋げるとどうなるというのばかりだから。
シミュレーションしてみると結構奥行きを必要であることに気付く。
人の定位を感じやすい周波数帯域は100Hz~5000Hz(諸説あり)
その中でもより定位に敏感なのは4000Hzと高音の方。
一般的な声の帯域は男性で500Hz、女性で1000Hz
歌声なども含めれば100Hz〜2000Hz
これらを勘案すると500Hzくらいは拡散できないとね、と思うと
拡散体の奥行きがすぐ30cmくらい行ってしまう。
しかも30cmも確保してもようやく拡散帯域限界に辛うじて入るという状態だ。
一番出っ張ってるところでしか拡散効果が十分発揮できないので、
効果抜群とまでは期待しづらい。

↑をPrimitive Root Diffuser(PRD)と呼称するようだが、設計の計算の仕方によるものであり、別の形態のものもPRDと呼ぶようだ。
区別する名称が分からないのでここではモザイク型PRDと呼ぶ。
このタイプだと小さな直方体の単位を小さくすればピンポイントの部分で幅広い拡散を細かくできるのだが、CAMを使って削るとかしない限りはいかんせん手間が際限なくにかかってしまう。しっかり中低域まで拡散しようとすると先述したようにかなり奥行きも必要になる。
ではQRD Diffuserのような拡散体(今回はバーコード型PRDと呼称する)はどうか。
引用:https://www.takenaka.co.jp/rd/research/gihou_2014/paper3.pdf
九州大学椎木講堂の音響設計 竹中技術研究報告 No.70 2014

で公開されているディフューザーの設計でも厚みは26cmと30cm弱必要になる。
QRDの計算サイト(しっかり探せばもう少しいいのがあるかもしれない。)でも適当に入力しても20cm以上は必要そうだ。
QRD Diffuserも奥行き23cmタイプのものがある。
結局厚みが必要なことには違いない。
それにバーコード型だと網羅したい周波数ぶんの溝の幅の合計が数十cm〜1m程度ある(バーコードを細かく出来るのかは不明)。リスナー近くの一次反射音部分にピンポイントに置くような使い方をしても、一次反射面は溝3つ程度と考えられるので均等な拡散が起こっていると期待しづらい。
講堂やスタジオなど大きめの室内空間の一次反射や二次反射以降の拡散には有用だが、狭い部屋の一次反射音の拡散にはベストな選択肢と考えるには疑問が残る。
それならば日東紡のシルヴァンアンクタイプはどうか。個人サイトのためリンクは伏せるが、直径14cmくらいあれば500Hzが十分拡散できるようだ。
14cmの円柱を入手できるかどうかの問題はあるが、比較的奥行きや圧迫感や異物感を減らすには有利かもしれない。
こう考えるとスピーカーを2種類使いこなす人もいるが、案外音響に悪くない選択なのかもしれない。キャビネットが局面のものであれば、20~30cmくらいの木の円柱の類似物と扱えるので、正面の一次反射面に使っていない方のスピーカーを置けば一次反射音を拡散できる。
結局の所、中域を網羅的に拡散させようとすると、どうしても大きな拡散体が必要なようだ。
今どういうチョイスをするかは決めていないが、圧迫感などを考慮して設計する必要がある。
既製品だとそこまで大きいモノはコストがかかるし、客も嫌がるから薄くて軽いモノになりがちだ。そういうものでも中低域の効果が無いことはないし、中高域の方が敏感なので変化を求める意味でのコスパは良い。
だが、ただでさえ拡散されやすい高域ばかりがさらに拡散され互いが干渉してしまうため、高域の残響時間が短くなってしまう可能性がある。
拡散パネルを無計画に置きすぎると普通の音の部屋になるといわれ易いのはそのあたりにあるのではないだろうか。
残響成分は低域が多目だと良いようだが、中域も高域も同じくらいある残響が良いと言われている。
引用:https://www.jstage.jst.go.jp/article/jasj/47/10/47_KJ00001456312/_pdf

改めて思うのは大きい部屋は有利ということである。1次反射面が遠ければ拡散パネルが厚くても気にならないし、ピンポイントで拡散する必要性もあまりなくなる。
そもそも大きな部屋では残響時間が長くなり易いので小さい部屋よりも拡散の必要性が比較的少ない。小さい部屋だと大きな拡散体を使うべきなのかも知れないが、そもそも小さな部屋にそんなものを入れ込むデメリットも考えないといけない。いろいろと悩ましいが、大きい部屋なら苦労しなくてよかった苦労ばかりだ。
やはり大きくなっても中域を網羅的に拡散でき、なおかつピンポイントでの網羅的な拡散もできるように設計していきたいとは思っている。
http://actools.tunetown.de/prd/
上記サイトで拡散体のシミュレーションが可能で、散乱させる各種数値を入力すると、こう作ると入力した帯域は散乱するよという拡散体の設計図を自動生成してくれる。
結構真面目にみんな室内音響を考えているんだなあと思いつつ、なかなかオーディオの世界から、この世界にディープに入る通路がなかなか見つからないのがなんとも言い難い。
簡単に手に入るのは何を買って繋げるとどうなるというのばかりだから。
シミュレーションしてみると結構奥行きを必要であることに気付く。
人の定位を感じやすい周波数帯域は100Hz~5000Hz(諸説あり)
その中でもより定位に敏感なのは4000Hzと高音の方。
一般的な声の帯域は男性で500Hz、女性で1000Hz
歌声なども含めれば100Hz〜2000Hz
これらを勘案すると500Hzくらいは拡散できないとね、と思うと
拡散体の奥行きがすぐ30cmくらい行ってしまう。
しかも30cmも確保してもようやく拡散帯域限界に辛うじて入るという状態だ。
一番出っ張ってるところでしか拡散効果が十分発揮できないので、
効果抜群とまでは期待しづらい。

↑をPrimitive Root Diffuser(PRD)と呼称するようだが、設計の計算の仕方によるものであり、別の形態のものもPRDと呼ぶようだ。
区別する名称が分からないのでここではモザイク型PRDと呼ぶ。
このタイプだと小さな直方体の単位を小さくすればピンポイントの部分で幅広い拡散を細かくできるのだが、CAMを使って削るとかしない限りはいかんせん手間が際限なくにかかってしまう。しっかり中低域まで拡散しようとすると先述したようにかなり奥行きも必要になる。
ではQRD Diffuserのような拡散体(今回はバーコード型PRDと呼称する)はどうか。
引用:https://www.takenaka.co.jp/rd/research/gihou_2014/paper3.pdf
九州大学椎木講堂の音響設計 竹中技術研究報告 No.70 2014

で公開されているディフューザーの設計でも厚みは26cmと30cm弱必要になる。
QRDの計算サイト(しっかり探せばもう少しいいのがあるかもしれない。)でも適当に入力しても20cm以上は必要そうだ。
QRD Diffuserも奥行き23cmタイプのものがある。
結局厚みが必要なことには違いない。
それにバーコード型だと網羅したい周波数ぶんの溝の幅の合計が数十cm〜1m程度ある(バーコードを細かく出来るのかは不明)。リスナー近くの一次反射音部分にピンポイントに置くような使い方をしても、一次反射面は溝3つ程度と考えられるので均等な拡散が起こっていると期待しづらい。
講堂やスタジオなど大きめの室内空間の一次反射や二次反射以降の拡散には有用だが、狭い部屋の一次反射音の拡散にはベストな選択肢と考えるには疑問が残る。
それならば日東紡のシルヴァンアンクタイプはどうか。個人サイトのためリンクは伏せるが、直径14cmくらいあれば500Hzが十分拡散できるようだ。
14cmの円柱を入手できるかどうかの問題はあるが、比較的奥行きや圧迫感や異物感を減らすには有利かもしれない。
こう考えるとスピーカーを2種類使いこなす人もいるが、案外音響に悪くない選択なのかもしれない。キャビネットが局面のものであれば、20~30cmくらいの木の円柱の類似物と扱えるので、正面の一次反射面に使っていない方のスピーカーを置けば一次反射音を拡散できる。
結局の所、中域を網羅的に拡散させようとすると、どうしても大きな拡散体が必要なようだ。
今どういうチョイスをするかは決めていないが、圧迫感などを考慮して設計する必要がある。
既製品だとそこまで大きいモノはコストがかかるし、客も嫌がるから薄くて軽いモノになりがちだ。そういうものでも中低域の効果が無いことはないし、中高域の方が敏感なので変化を求める意味でのコスパは良い。
だが、ただでさえ拡散されやすい高域ばかりがさらに拡散され互いが干渉してしまうため、高域の残響時間が短くなってしまう可能性がある。
拡散パネルを無計画に置きすぎると普通の音の部屋になるといわれ易いのはそのあたりにあるのではないだろうか。
残響成分は低域が多目だと良いようだが、中域も高域も同じくらいある残響が良いと言われている。
引用:https://www.jstage.jst.go.jp/article/jasj/47/10/47_KJ00001456312/_pdf

改めて思うのは大きい部屋は有利ということである。1次反射面が遠ければ拡散パネルが厚くても気にならないし、ピンポイントで拡散する必要性もあまりなくなる。
そもそも大きな部屋では残響時間が長くなり易いので小さい部屋よりも拡散の必要性が比較的少ない。小さい部屋だと大きな拡散体を使うべきなのかも知れないが、そもそも小さな部屋にそんなものを入れ込むデメリットも考えないといけない。いろいろと悩ましいが、大きい部屋なら苦労しなくてよかった苦労ばかりだ。
やはり大きくなっても中域を網羅的に拡散でき、なおかつピンポイントでの網羅的な拡散もできるように設計していきたいとは思っている。

















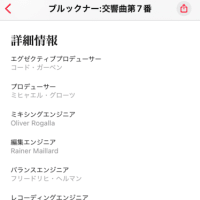

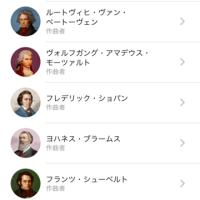





※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます