リブや拡散体などを壁の前に置いた場合、中高域には拡散体が影響を及ぼすものの、低域に関してはほぼ透明、つまりは無いものと同様に挙動する。
そして低域は小空間の場合理屈上は少しくらい形を複雑にしただけでは解決が難しい定在波の問題がある。特定の周波数が出ないとか出過ぎるだけでなく、超低域が存在できない。
ただ一般的な家屋の場合低域は構造壁外に透過するため、定在波が理屈上ほどは支配をしないで済んでいる。
これらの情報を勘案すると、リスニングルームの構造壁をあまり凝ったものにしなくて良いのではないかと思ってしまう。カチカチにしすぎてしまうと定在波の制御が難しくなってしまうので、適度に透過するもので良いのではないか。そして壁の共振など有害事象が起こらないようにして必要十分な遮音性が備わっていれば良いように思えてくる。
板振動型の吸音材、ベーストラップと言われるものは固定されていないフワフワ動く流動的な壁である。ベーストラップを沢山設置して低域を制御するということは、リスニングルームの内壁を固定していない壁に交換するのと原理的には近い行為になる。
低域のコントロールという意味ではガチガチの強固な壁という方向で対応するよりも、問題が起こらないように配慮しつつ適度に柔らかくする方向を模索すべきではないかと思われる。
その上で、低域にとっては「透明」と扱われるようなリブなど中高域に影響する調音構造体を構造壁の内側にリジットに設置することで中高域に必要十分な反射音や残響音をリジットな調音体に反射させる。
内側に中高域に対応するリジットな反射帯を作り、外側に緩い構造壁を作り、その間には取り外しの可能な中音域を吸音できる程度の吸音材を入れることもできるようにすると良いのかも知れない。
調音体に反射せずに透過してきた中高域の音が緩い構造壁に反射した場合にあまり良い音がしないと思われるので調音体を透過してきた音は吸音したいという目的のためである。低域のコントロールにもある程度貢献してくれるとも期待はできる。
低域の挙動のイメージ

中高域の挙動のイメージ

もしくは板振動型の吸音材の板の部分に拡散体を付けることで、低音域は板振動型で吸音しつつ、中高域は拡散させるという挙動を狙える。ただ上記の中高域をリジットに反射+拡散させるというコンセプトは微妙になってしまう。拡散体が吸音材に取り付けてあり強固に固定されているわけではなく、むしろ積極的にフロートされているからである。

となると構造壁の内側にベーストラップ層を置き、その内側に独立してリジットに固定された調音層を作るというのが案になってくるか。

そして低域は小空間の場合理屈上は少しくらい形を複雑にしただけでは解決が難しい定在波の問題がある。特定の周波数が出ないとか出過ぎるだけでなく、超低域が存在できない。
ただ一般的な家屋の場合低域は構造壁外に透過するため、定在波が理屈上ほどは支配をしないで済んでいる。
これらの情報を勘案すると、リスニングルームの構造壁をあまり凝ったものにしなくて良いのではないかと思ってしまう。カチカチにしすぎてしまうと定在波の制御が難しくなってしまうので、適度に透過するもので良いのではないか。そして壁の共振など有害事象が起こらないようにして必要十分な遮音性が備わっていれば良いように思えてくる。
板振動型の吸音材、ベーストラップと言われるものは固定されていないフワフワ動く流動的な壁である。ベーストラップを沢山設置して低域を制御するということは、リスニングルームの内壁を固定していない壁に交換するのと原理的には近い行為になる。
低域のコントロールという意味ではガチガチの強固な壁という方向で対応するよりも、問題が起こらないように配慮しつつ適度に柔らかくする方向を模索すべきではないかと思われる。
その上で、低域にとっては「透明」と扱われるようなリブなど中高域に影響する調音構造体を構造壁の内側にリジットに設置することで中高域に必要十分な反射音や残響音をリジットな調音体に反射させる。
内側に中高域に対応するリジットな反射帯を作り、外側に緩い構造壁を作り、その間には取り外しの可能な中音域を吸音できる程度の吸音材を入れることもできるようにすると良いのかも知れない。
調音体に反射せずに透過してきた中高域の音が緩い構造壁に反射した場合にあまり良い音がしないと思われるので調音体を透過してきた音は吸音したいという目的のためである。低域のコントロールにもある程度貢献してくれるとも期待はできる。
低域の挙動のイメージ

中高域の挙動のイメージ

もしくは板振動型の吸音材の板の部分に拡散体を付けることで、低音域は板振動型で吸音しつつ、中高域は拡散させるという挙動を狙える。ただ上記の中高域をリジットに反射+拡散させるというコンセプトは微妙になってしまう。拡散体が吸音材に取り付けてあり強固に固定されているわけではなく、むしろ積極的にフロートされているからである。

となると構造壁の内側にベーストラップ層を置き、その内側に独立してリジットに固定された調音層を作るというのが案になってくるか。


















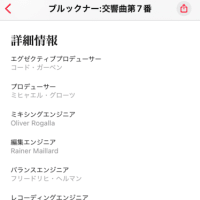

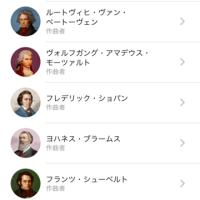
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます