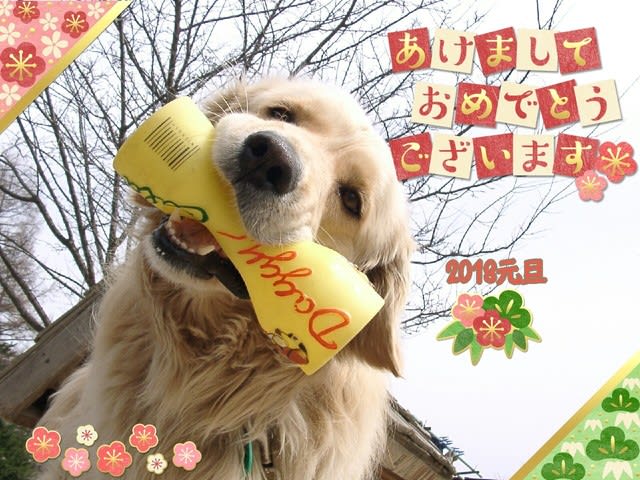こどもの日で祝日の今日は、二十四節気の立夏。
暦の上では、今日から夏になる。
とは言っても、まだ桜も咲かないユー地区でその実感はない。
小雨模様の中、薄くなった耳毛を濡らしてチビトト来店。
この季節になると、給餌も控えて閉店準備に入るのが常なのだが。

どうしたもんじゃろうかの~
チビトトさん。

その目で見つめられると、もう少しだけ延長営業としておこうかの~。

話変わって、町の博物館的施設がこの5月1日、リニューアルオープン
した。
特派員を送り込んだので、さわり程度のご紹介。
奥に見えている、全長7メートル程のシャチ骨格標本もその目玉展示の
ひとつ。
ほど近い、W内市の海岸に打ち上げられたものを、独自の技術を使って
除肉処理し、脱脂・漂白して展示している。
どのような海路を辿って、この近くまで回遊してきたのか?

もう一つの目玉の、絶滅ほ乳類海獣デスモスチルス。
世界的にも貴重なこの化石が、ユー地区のある場所から十数体出ている。
海辺で陸海両生していたらしいこの海獣にとって、楽園だった時代があった
のだろうな。

ユー地区は明治30年、ある農場が未開のこの地に開かれたのを
地区の歴史の始まりとしている。
アイヌ民族や、もっと古い旧石器時代の暮らしがあったことを裏付
ける遺物も見つかっているので、ユー地区近世の始まりか。

大正後期から昭和初期にかけて使われた、木製スキーの展示。
長くわが家で保存していた物が、郷土資料として活かされた。
歴史遺産、自然遺産、先史文化遺産…、ほおって置けば失われて
しまう、これらの財産に息吹を吹き込み展示する。
リニューアルでは、この地の色んな切り口が増えて、オモシロ
そうだな。
午前中、断続的に陽が射し、徐々に気温も上がり気味。
一時の、真冬のような景色と気温は後退しつつある。

この調子なら、新雪はほとんど消えてしまうものと思われる。

ただ、木の下、木陰には若干の雪を残す。
こちらのコーナーでは、首をもたげた“ニゲル”が顔を覗かせている。
タイトルは、「春の香り」だが、ニゲルの花の香り…ではないらしい。

畑の方では、伸びたといってもまだこの程度だが、

根開きで早くから雪が融けた場所では、いい感じになっている。
何となく、香りがしてきたような…

ということで、今日を“採り始め”として、初物をいただくことに。
いつもながら、新芽の緑と茎元の暖色が目に鮮やか。
何もしなければ香りもないが、ナイフで切り始めると一面に匂い立つ。
個人的には、ギョウジャニンニクほど味・香りの優れた山菜はないと思っているが、
食べ過ぎるとやっかいなことにも。
昔は(今でも?)、アイノネギとかアイヌネギと呼んだものだが、正式には上記の
とおり。この時期なら、単に“ネギ”で通る。
焼いても、揚げても、和えても、薬味として漬けても美味い、春山菜の万能選手だ。
しばらく、わが家の香りはこれになる?
古い家にあった、古いスキー。
何となく捨てるのが惜しくて、この物置小屋を建てたときに、ここに移していた。
わが家歴代の、伯父・叔父たちや父が使ったスキーでもある。
このままにすると、やがて朽ち果てる?運命と思われるので、町の博物館で民俗
資料として保存してもらえないかな。

小さな子ども用から、2メートルを超えるものまで4セット余り。
“余り”というのは、その内の2本は揃いではないからだ。
ストックも1セット、プラスワン(3本)というヘンな数。
このあたりは、長い間の事情が何かあったのだろう。

スキーの先端部分。
今のスキーにはない、突起が付いている。
これは、ゲレンデなどの無い時代、スキーと言えば滑走・歩行両用の移動手段だった
ため、斜面を登るときにずり下がらないようストー(シール:アザラシの皮など)を取り
付けるための突起ということだ。
以前、使用者からの耳知識。

滑走面のトップには、メーカーの焼き印が残っている。
曰く、「MADEIN HOKKAIDO」、「MARUI SAPPORO」。
メイドイン・ジャパンや、メイドバイ・トーキョーではないのが、いい。
このスキーは、大正後期から昭和初期のものと思われるが、その頃の北の国は、誇りに
満ちたフロンティアだった。
そのことを、彷彿とさせる。

おそらく高価で貴重なスキー板だが、単板のためによく折れたようだ。
それも決まって先っぽだ。
緩やかに曲がる先が折れると、スキーはどうにもならない。
そのため、トタン板を撒いて補修して使った。
約4セットある内の、子ども用を含む実に3セットの片割れに補修の跡がある。
よく考えると、揃っていない2本の片割れは、補修しようもないほどのダメージを受けて
廃棄されたのかも知れない。

竹製ストックの輪っかも、ヤワなものではなく深雪にも沈まない大きく丁寧な作りだ。

町の博物館も、ホコリだらけ錆びだらけのスキーを持ち込んでも困ると思われるので、
板はぬるま湯で拭き取り、ワイヤーブラシで簡単にサビをこすり落とし、固くなった皮
にはミンクオイルを薄く塗った。
何となく往時の姿が戻ってきたような…。

一部を外に持ち出して、同時代を生きたサイロをバックの記念写真。
このスキー達、何十年ぶりに雪の感触を味わったか。
いいスキー供養?になったことにしておこう。

最後のオマケは、ユー地区市街を望む“H銀台スキー場”。
ただし、昭和の30~40年代。
さすがに、古いスキーと同じ時代のスキー写真は見あたらなかった。
それでも、この時代は、あの市街地からこのスキー場まで歩いて通い、スキーで
ゲレンデを踏み固めながら、手足がかじかむまで滑ったものだった。
これまた古いが、スキーと言えばこの曲、♪白銀は招くよ。
最後のオマケのオマケ。
ご近所さん共同の、年末恒例餅つき。
“餅つき”といっても、文明の利器を使っての作業。
機械自体随分古いものだが、年に一度のこの時期、よく働いてくれる。
以下、小屋の中の作業はデジカメを渡しての記録依頼。




つき上がると、端から丸めて、予め用意してあったあんこに包む。
この時代、少なくなりつつある伝統の手業?

ご近所さん用、三組のお供え餅もできたようだ。

もちろん、合間の楽しみも忘れていない。
ちょっと濃いめの甘酒にホッとする?

この日は、晴れ間が出たと思ったら…

いきなり吹雪いてきたりで、安定しない天気。
ちょっと小吹雪の様子をショートムービーで。

この日の昼餐はお隣さん特製、濃いめ醤油味の雑煮。
ごちそうさまでした。
年末恒例行事の部、先週の続き。
けっこう大量の豚肉は、塩蔵の後水洗されここに吊される。
この後、乾燥・燻煙と進み、翌日には“作り続けて31年” の、あれになる。
もったいぶらなくても、バレバレだが。
もう一つの肉製品、ソーセージの手順。



一週間前に、塩(1.8%)、砂糖(1%)に浸け込んだ豚肩肉に、コショウ、セージ、タマネギ
などで調味し、脂身と合わせてミンチにかける。
ミンチした肉を冷やすのと水分調節のため、かき氷を加えてよく錬る。
ハンバーグの成型時のように空気を抜いて、ケーシング詰めを行い、成型する。
成型の様子は、こちらの動画で。

成型を終えたソーセージは、乾燥・燻煙のためのステンレス棒にくぐしておく。
今日の作業は、古いアイポットのBGM付きのようだ。
アイポットも古いが、出てくるミュージックはもっと古い。


乾燥・燻煙中の様子。
乾燥を2~3時間ほどかけるのは、その後の燻煙のとき、よくスモークが入るようにする
ため。
温度調節がカギ。


殺菌のためボイルし、雪入りの水で急冷すると出来上がり。
ここまでが、この日の作業。

乾燥・燻煙中は、温度管理という大切な役目があるが、ほとんど手を掛けなくとも
大丈夫だったので、去年の続きを貸していただき読書タイム。
このマンガは、けっこう評判になり映画化されたようだ。
ベーコン、ソーセージ作りの場面も出てくるので、ナイスチョイスかも。
そして、翌日。


雪の中を三々五々集まる、肉好き?たち。
仕上がった製品を分配し、人によってはラミネート。
これに、“ソーセージ詰め、ベーコン燻して31年!”というシールを貼ると、何となく
それらしくなる。
年末年始の一品!はできた。
この日は、もう一仕事。
この小屋で、肉製品を作っていたのではないので、念のため。
外に出ている、煙突の元にあるものが作業の中身。



これまで使っていた、鋳物の石炭ストーブを、筒状の鉄板ストーブに交代。
小型の石炭ストーブなので、炉内が小さく大きな薪を燃せないのと、炉内の炎が煙突に
入るようになったのが大きな理由。
来週には、これまた恒例のご近所餅つき行事?があるのと、新品なので、塗料の匂いを
焼き切っておかないと、クレームが来そうなので今日の作業となった。
案の定、初焚きでは盛大に塗料の焼ける匂いと煙が立った。
なかなか、火力はありそうだ。

玄関先の雁木部分。
数時間も放っておくと、新雪が10センチ以上も積もっている。
この後も雪予報なので、雪かきは明日もある見込み。
今日はよく働いた?ので、夕餉には出来上がったソーセージとベーコンでも
焼いてみよう。
フレッシュリースのついでに、季節モノということでもう一つのリース作りの
お披露目。
以前、紹介したような気もするが、忘れた頃ということで…。
素材は、大きめの松ぼっくり。
この松ぼっくりをつける松は、ユー地区に何本かしかないので、落ち頃を
見計らって、拾いに行く。




さっそく、手順。
松ぼっくりの大きさはけっこうまちまちなので、同じくらいのでキレイなものを7~8個
並べてみて仕上がり状態をイメージする。
太めの針金を1m20~30cmに切って半分に曲げ、フックに掛けるための輪っかを
作る。
松ぼっくりの鱗片の間に針金を巻き付け、一つ増やす毎にペンチやプライヤーで2
~3回巻き止めする。
最初の一個は、フックの輪っかに対して90度の角度で巻き止めし、次の松ぼっくりに
繋げていくのがコツ。

横から見ると、こんな感じ。
松ぼっくりの大きさ高さが違う場合は、針金を回す場所で高さ調節できる。
(ちょっと高度なテク)




最初に決めた個数を針金で繋げたら、最初のフック掛けの付いている松ぼっくりに針金を
回し、回し止めする。
ワイヤーカッターで余分な針金を切り落とし、切り口でケガをしないよう内側に曲げるなど
の処理をする。

このままだと、松ぼっくりの“飾り面”が揃っていないので、手のひらで曲げながら形と
方向を整える。
これで、ベースの出来上がり。

使う道具は、こんなところ。
針金は細いと扱いやすいが、出来上がりが“ふにゃふにゃ”した感じになるので、ちょっと
太めを使うのがコツ。
コンベックスは、針金の長さを測るのに使うが、7個リースで120センチ、8個リースでは
130センチ位か。
切断した先が尖っているので、人のいるところで作業をする際には注意が必要。

7個リースが一つと、8個リースが二つできた。
これで完成でも良いのだが、今回はスプレーで彩色してフィニッシュとする。



色づけは好みによるが、やはり白系やシルバー系が無難。
わが家の室内壁は、フィニッシュオイルを塗った杉板壁のため暗色系になっている。
この様な壁色の場合は、ちょっと白っぽい方が引き立つ。
逆に、白壁系ならばそのままのナチュラルカラーを生かしてもいい。
塗装には、アクリル系のスプレーが便利。

何年か前から、デッキの壁に掛かっている松ぼっくりリース。
(これは大型の12個リース。中に7個リースを入れて、その真ん中に1個の構成)
大切な?ホールを塞いでしまっているので、リース本来のデザインからはちょっと
外れるかも。
幸を呼ぶというリースを、あちこちに掛けていよいよ年末を迎える。
空気が冷えて、地上が雪に覆われる直前の時期。
ここの通りは、リースの頃を迎える。
地産のエゾマツ、トドマツンなどのフレッシュリーフでリースを作る。
ご近所さんの女性方の季節行事。


当方の手伝いは、集めておいた松ぼっくりにカラースプレーをかけてオーナメントの
素材を作るくらい。
赤、白、銀、金くらいなら、オーダー受付可。
山ブドウやコクワ(サルナシ)の蔓で作る、リースのベースはまだリサイクルが効いて
いるので大丈夫。

作業小屋の中は、バルサムの香りでいっぱい。
針葉樹の枝先を細いワイヤーで束ねて、ベースの蔓の輪っかにくくりつけていく。
何年も続く、慣れた手順。


今年は、キラキラ系のリボンが特徴のようだ。
松ぼっくりのオーナメントも効いている。

外は?といえば、葉を落としたオニグルミの木が冬日に光っていた。
その後ろのアオキ(針葉樹)が、リース素材となる。

カラマツも葉を落とすと、カラスの巣がくっきりと影を作る。
巣の高さで、その夏の雨や洪水を占うと言うが…。


今日はリースで始まったが、地面に目を移すと、野草たちははや来春への備えに余念が
ない。
ギョウジャニンニク(左)と、アキタブキ(右)の芽がしっかりと顔を出していた。
リースの頃の、季節の表情。
【画像追加】


リース通り、ご近所さんのドアーに飾られた様子を追加。(11/24)
いままでと、ちょっと様子が違うタイトル画像。
HDRとか言うらしい。
デジカメに付属する画像処理機能を使って撮った。
ググってみると、ハイ・ダイナミック・レンジの略で、露出の異なる※複数枚の画像を
合成して作るものらしく、今どきのiPhoneにも付いているようだ。
(※タイトル画像は、3枚合成)
単に明暗合成をして階調を豊かにしたものや、タイトルのように「絵画調」のような
画像を作るメニューがあったりする。

これは、「イラスト調」というメニュー。
本当に、画に描いたような画像だ。
デジカメを使うようになってから、もう13~14年になる。
それまでは、写真と言ったらフィルムカメラだったから、“写す”、“撮る”ことの後に
現像とかプリントといったプロセスを踏まないと、それを見ることはできなかった。
デジカメでも、現像やプリントはあるが、“撮って出し”の画像を、液晶モニターや
パソコン画面で見ることで、それらも省略することができる。
面倒くさがりの自分にとって、それは便利な発明品だった。
ただ、ありがたいのか、そうでないのか相半ばするが、技術革新や進化はフィルム
カメラの比ではなく、毎年のように新製品が発売される。
数え上げてみると、これまで10台ほどのデジカメを使ってきたことに気づく。
言い訳めくが、その内半分ほどはいわゆる「新製品」ではなく、発売後数年経った
「旧型」やネット上で探した「中古品」だ。
デジカメは、新製品の回転が早い分、値崩れもまた早いのだ。
それで、消費増税前とか、年度末を前に自分へのご苦労さんとか理由を見つけて、
またデジカメ一台買ってしまった。
今回のは、2年ほど前の旧型で中古だが、これまでにない機能が付いている。
その一つがHDRとか、イラスト調とかのピクチャーエフェクト機能。




画像が小さいので、その差がはっきり解らないが、上左がノーマル画像。
上右:絵画調HDR、下左:水彩画調、下右:イラスト調
こんなのも。



「効果」の並びは同じ。
「だから、どうした」と、問われれば、「いや、別に」としか答えられないが、シュミ・ドウラクとは
そんなものだ。

でも、何となく、オモチャが増えたようで、嬉しいんだなぁ。
強い霜は降っていないが、木々や草花たちは季節の空気を敏感に感じ取って
いるようだ。
いつになく、上の方まで繁ったサイロの木蔦が、いつものように上の方から色
づいてきた。
サイロに覆い被さるように枝を伸ばしたハルニレも、葉先が黄色くなってきた。
向こうに見える一本カラマツが黄金色に染まるのはまだ先だが、すでにぱら
ぱらと気の早い葉を落とし始めている。

いつもこの頃に登場する画像左のイタヤカエデも、木末(梢)の方から色が付く。
右の黄色いのはハルニレの枝で、枝単位で黄葉が始まるのが面白い。

今シーズン20回目の芝刈りを終えたの図。
さすがに、草の生長も止まり気味で、集草バックにもあまり草が溜まらない。
刈ったとしても、次回で納めることになりそう。

少し彩度を上げているが、オオカメノキの葉がいい感じになってきた。
その向こうはヤバネススキで、いつもの遅めの穂が出てきた。


バックガーデンに咲いている花。
先日の大風でほとんどの茎が飛ばされてしまったガウラ・ハクチョウソウ(左)と
今年初めて花を付けたキミキフーガ・コーディフォリア。
キミキフーガと名乗るくらいだからサラシナショウマ系だと思われるが、背丈は
30~40センチほどでコンパクトだ。
花姿としては、いい感じ。

クリーピング性の小菊の中から出てきたのは八重咲きのコルチカム。
小菊のつぼみも先が染まってきた。


今年のクルミの収穫は、こんなところ。
実はかなり小振り。
右画像を見て道具使いが解る方は、ちょっとしたクルミ通?

何はともあれ、年末の餅つきでは“くるみ餅”が当たりそうだ。
そこまで行くには、まだかなりの手間を残しているが…。

青色に少し遅れて、ピンクのアスターが満開。
背丈も青色の半分くらい。
こぢんまり感がなかなか、いい。


左右の画像のどこが違うかと言えば…、はい、シラカバの高いところにある横枝の
あるなし。
この横枝、今年の冬に湿って重たい雪に曲げられてから、風が吹くたびに屋根に取り
付けたテレビアンテナをなぜるようになっていた。
アンテナの一部が折れて落ちたのは大したことがないにしても、深夜に風が吹いたり
すると、そのなでる音に安眠を妨げられるのには閉口する。
で、高所作業用の梯子と梯子押さえにお隣さんにもお出まし願って、切り落とした次第。


片手で梯子にしがみつき、片手で長柄の剪定用のこぎりを操らねばならないので、
往生した。
落とした枝は、他にストックしていた枝とともに電動チェンソーで薪の長さにカット。
風が吹いた夜も、これで安眠?できそうだ。

それで、何が「5年、」かというと、このブログを初めて昨日で5年。
三日坊主の自分としては、よく続いたと思う。
ブログのタイトルのとおり、ここユー地区の四季のエトセトラを写真日記風に書き留め
たものだ。
どうしても、家周りの景色や季節の野良仕事などがネタになるが、花の咲くのや山菜の
採れる時期に見当を付けるのに、数年の記録があるので塩梅が良い。
同じように、今年の芝刈りが20回目というのも、平均的な回数とわかる。
思いがけない効用は、名前が解らない花などをここに掲載すると、すぐにどなたかが
コメントで教えてくれること。
これで、名無しから名前付きに昇格?した花々も幾たりか…。
「5年、」の「、」は、ある俳優さんの芸名に付いている「、」のつもりだが、そのココロは
「我未だ完成せず」ということらしい。
それで、何となく「、」を打ってみた。
今朝の汁物は、ちょっとだけ春を先取り。
お椀の、中ほどにあるものがそれなのだが…。
わかるかなぁ、わっかんないだろうなぁ。
ということで、春の正体。
数日前に採ってきた、気の早いフキノトウ。
小鉢に入れて水に浸けていたら、花が開いてきた。
外は、まだ雪の世界だが、除雪などで強制的に雪を剥がされた道路脇には、
ぽつらぽつらと、淡い黄緑のフキノトウが見られるようになってきた。

カビの生えたオレンジを置いていたら、すぐにこちらがやってきた。
何事にもくちばしが短いヒヨくん、苦しいが「気の早い」つながりで
登場してもらった。
…。
年に一度、年末になるとここに一人、二人と人が集まってくる。
数個の段ボール箱が持ち込まれ、その周りを牛刀や骨スキ、筋引きといった
特殊包丁を片手に取り巻く面々。

段ボールの中身は、ビニール袋に詰められている。

大量のバラ肉だ。
このあたりで、何をしに集まってきたか解った方に、座布団一枚。

バラ肉に対して、塩1.8%、砂糖1.0%を平均にすり込む。
そう、豚バラベーコンの仕込みだ。
今回は、道産豚バラ36キロを捌き、仕込む。

こちらは、豚肩ロースから筋を取り除き、適当な大きさに切る。
その後は、ベーコンと同じ量の塩、砂糖。
こちらは、約6キロ。
本日の作業はここまでで、仕込まれた肉は冷蔵庫の中で一週間の
眠りにつく。
~ ここで、一週間経過 ~
再びアジトに集まって、作業の続きを。

一週間塩蔵した豚肩ロースと脂身に粗挽きペッパー、セージなどの
香辛料を加えてミンチに。
これを、二度繰り返す。
熱を帯びて変質しないよう、かき氷や雪で冷やしながら根気強く練る。
練ることで、製品になったときのプリプリ感が出る。

美味しそうと見るか、グロと見るかは個人差がある。
羊腸のケーシングに詰め、くるくるとくびれを入れる。
ちょっと熟練?のワザが光る。


このアジトを使う最大の理由の秘密兵器、大型の業務用燻煙機。
奥にひと洗いしたベーコン、手前にソーセージを吊して、炭を焚いて数時間
乾燥する。
この手順をきちんと踏まないと、この後の燻煙が肉に入らず、良い製品には
仕上がらない。

乾燥した後は、スモークウッドと呼ばれる桜のチップで燻煙を掛ける。
燻煙時間と温度管理が味に響く。
燻煙機の小窓から温度計を照らして見ながら調節。
ソーセージは細めの羊腸なので数時間程度、ベーコンは翌日の朝まで
このまま燻煙を続ける。

ソーセージは、燻煙を終えると75度のお湯で20分ほどボイル。
これで、肉の中までかなり殺菌できる。
ボイルした後は、雪を入れた水で急冷し身を引き締める。

ソーセージのできあがり。
すぐに味見するのは、燻煙作業をしている者の特権。
~ ここで、さらに一日経過 ~

ベーコンもいい感じに仕上がっている。
本当は、四十数枚のベーコンを並べた画像を撮ろうと思っていたのだが、
アジトに集まったメンバーに頒布してしまってから気がついた。
で、自分で買った分だけ並べて、ちょっと残念なベーコン画像。

これを、美味しそうと見るかどうかは…。
ここで作るベーコンは、塩・砂糖のみのシンプルな味付け。
好みはいろいろあるだろうが、長年やってみて、ここに落ち着いた。

最終的には、専用のラップマシーンで真空保存。
といっても、保存料など一切使っていないので、長期的には冷凍保存
となる。

貼ってあるラベルに目をやると…、
「ソーセージ詰め、ベーコン燻(いぶ)して29年!」
どうやら、製作者集団は、かなり年季を積んでいるようだ。
本来ならば、作りたてのベーコン・ソーセージ肴に缶ビールを
プシュッとするところなのだが、ユー地区では夕刻に再びの
暴風雪警報発令。
ボスの命令で、自宅待機となってしまった。
やれやれ、災害のないことを祈る。
[オマケ又は付録]
ベーコン、ソーセージの製造過程で、ほとんど何もしないで時間がかかるのは、
乾燥・燻煙の工程。
アジトにテレビもないので、本などを読みながら過ごすが、今回、仲間内から
差し入れされたのがこれ。
今年、何とか大賞をとった話題作らしい。
北の国、東方面に実際にある農業高校を舞台にした連載漫画だ。
一気に、6冊読み切って、丁度燻煙を終えることができた。
作中で、飼われている豚を食肉にし、その肉を使ってベーコンを作るところが
出てきたりして、内容がぴったり。
配慮とセンスが光る差し入れだった。
7月10日は、ユー地区の鎮守の祭礼日だ。
その昔、ユー地区開闢(かいびゃく)の発端となった農場の設立認可日が
明治30年7月10日。
先人は、その日を忘れないように地区の祭りの日にした。
以来、百十余年、途切れることなく地区の安寧と豊作を願いながら今日に
至った。

祭礼の日は朝から、四カ所の御旅所を巡って、一日御輿が練り歩く。

真新しい足袋も、一日練るとほつれが出てくる。

無事に、御輿も鎮守に戻り、担ぎ手からも笑顔が漏れる。
数年前に、鎮座百年を迎えたこの鎮守の記念誌を作ることになっているが、なかなか
進まない。
「鎮座百年を期して」が題名(仮題)だから、いつになってもいいのだが…。
師走に入ると、この時期の恒例行事が幾つか待っている。
玄関ドアに、フレッシュリースを飾るのもその一つ。
ご近所の門毎に、揃いのリースが並ぶ。

リースの芯は、雪が降る前に山取りしたブドウ蔓など。
そこに、エゾマツやトドマツなど常緑針葉樹の葉を束ねて付け、
オーナメント代わりに着色した松ぼっくりなどをあしらう。らしい。
作業は専ら、ご婦人方が中心に行われるので、詳細部分は想像。



揃いといっても、いろいろなバージョンがあるようだ。
シックにホワイト、シルバーバージョンや、ワイン・シャンパンがお好きなお宅には、
口金の金具がオーナメントになっていたりしている。
(画像提供:製作メンバーのAちゃん)




もう一つの行事は、ベーコン・ソーセージ作り。
この日は、30キロほどの豚バラ肉、肩ロースを下ごしらえし、塩・砂糖で
ベースとなる調味を実施。
ミートチョッパーで挽肉にしたり、ソーセージのケーシング詰め、ベーコンの
燻煙などは1週間後の作業となる。
このベーコン・ソーセージ行事は、もう27年ほども続いている。
年末の味を密かに待っている面々も居るようだ。

冬を飾る習慣や季節の保存食は、続けている内に、ここ北の国
ユー地区の伝統になったりするのかも知れない。
あと、いくつか季節行事をこなすと、この一年も押し詰まる。
今年の野良仕事納めは、何になるかな。