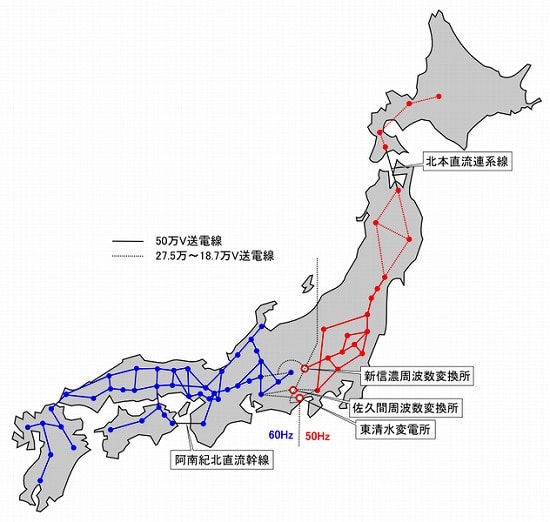民間の原発事故調査委員会がまとめた報告書が昨日公表された。
報道されている内容をみる限り、これが世界でも有数の原発をかかえる政府の対応かと思うと、恐ろしくなってくる。
日本人は元来、リスクマネジメントにうとい国民性だとは思っていたが、あまりにもひどい。
特に報道で強調されていたことは、菅前首相の対応振りである。
自ら担当者に電話を入れ、電源用バッテリーの大きさを確認していたと言うから呆れる。
いくらバッテリーの手当てが急務だったとはいえ、一国の首相がバッテリーの大きさを聞いてどうする。そんな事は他の閣僚に任せ、首相として陣頭指揮にあたるべきだろう。それとも、バッテリーの事が頭から離れず、他に首相としてやるべきことが思い浮かばなかったのだろうか。
彼は東京工大のそれも理学部応用物理学を専攻したというから、多分、事故当時は首相というよりは、一技術者としての関心事が優先してしまったのだろう。
菅前首相の対応以外で次に驚いたことは、枝野前官房長官他、当時の関係閣僚が放射性物質の大気への拡散状況を予測するSPEEDIと言うシステムの存在を知らなかったことである。
更には、原子力事故が起こった際の措置を定めた法律を理解している閣僚がおらず、六法全書で調べていたという。どこまで素人集団かと言いたくなる。
元来、日本の政治家は勉強が苦手なところに持ってきて、短期間で首相や大臣が交替することも、あらゆる事に関して政府の対応能力を低くしている一因だと思うが、それにしても今回の事故対応はあまりにもお粗末である。
こんな頼りない政治家の皆さんに我々の安全が委ねられていると思うと、不安でしょうがない。
報道されている内容をみる限り、これが世界でも有数の原発をかかえる政府の対応かと思うと、恐ろしくなってくる。
日本人は元来、リスクマネジメントにうとい国民性だとは思っていたが、あまりにもひどい。
特に報道で強調されていたことは、菅前首相の対応振りである。
自ら担当者に電話を入れ、電源用バッテリーの大きさを確認していたと言うから呆れる。
いくらバッテリーの手当てが急務だったとはいえ、一国の首相がバッテリーの大きさを聞いてどうする。そんな事は他の閣僚に任せ、首相として陣頭指揮にあたるべきだろう。それとも、バッテリーの事が頭から離れず、他に首相としてやるべきことが思い浮かばなかったのだろうか。
彼は東京工大のそれも理学部応用物理学を専攻したというから、多分、事故当時は首相というよりは、一技術者としての関心事が優先してしまったのだろう。
菅前首相の対応以外で次に驚いたことは、枝野前官房長官他、当時の関係閣僚が放射性物質の大気への拡散状況を予測するSPEEDIと言うシステムの存在を知らなかったことである。
更には、原子力事故が起こった際の措置を定めた法律を理解している閣僚がおらず、六法全書で調べていたという。どこまで素人集団かと言いたくなる。
元来、日本の政治家は勉強が苦手なところに持ってきて、短期間で首相や大臣が交替することも、あらゆる事に関して政府の対応能力を低くしている一因だと思うが、それにしても今回の事故対応はあまりにもお粗末である。
こんな頼りない政治家の皆さんに我々の安全が委ねられていると思うと、不安でしょうがない。