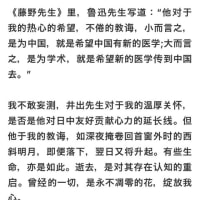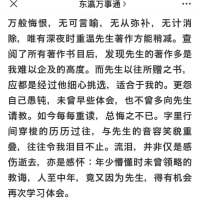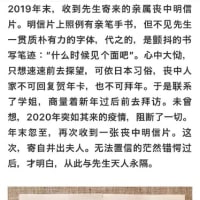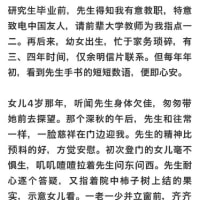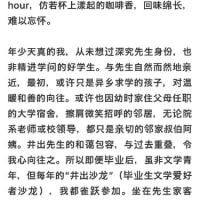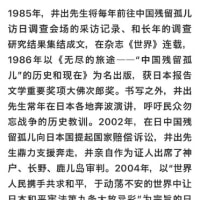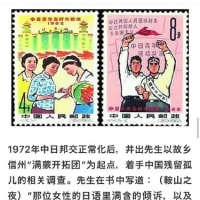拙作が『人民日報』海外版日本月刊に掲載されました。
興味のある方はどうぞ覗いてみてください。

「活到老学到老」
――日本と中国の大人の習い事
劉 心苗
早朝5時半、Sさんの忙しい一日は筋トレーでスタートする。8年前、大手商社を定年退職し、第二の人生を迎えた。定年の数年前にすでに老後の人生設計を立てた----穏やかな定年生活を送るためには、精神と肉体両面での健康を保つが大切との認識で、4つの習い事(スポーツ、語学、楽器、パソコン講座)をメインに定年生活を彩ることに決めたそうだ。

最初に始めたのは大学時代にやっていた弓道の再開だった。
「大学4年間弓道の練習に励み、二段を取得しましたが、学生弓道は的中至上主義でした。しかし、社会人の弓道は道場への入場から退出までのすべての所作が重視される「射」と「礼」の調和です」
社会人弓道の魅力にはまったSさんは週5日、一日3時間以上の練習に励み、現在五段に昇段している。シニアになっての弓道は決して楽ではないが、8年間も続けてこられた大きいな理由の一つは、尊敬する90代の現役師範による愛情たっぷりの厳しい指導だという。
「シニアになっての弓道鍛錬は体力・健康の維持、自分の怠け心などの弱さと、試合での緊張感に打ち勝つ集中力の養成に大いに役立っています」と、これからも弓道を深耕していく決意を示した。
また、弓道のほかに、10年間続けている週一回の中国語、週2回のフルートのレッスン、週1回のパソコン講座も並行している。

「常に自分の好奇心と真剣に向き合い、自分を高める鍛錬を継続することで小さい成果が生まれます。それがさらなる意欲につながるという好循環を実感しています」(Sさん)
日本では、Sさんのように定年後も習い事で充実した生活を送る人が多い。そもそも日本国民の間には、仕事以外に視野を広め、教養を高めていく学習文化が根付いている。そして、その受け皿となるカルチャーセンター、フィットネスクラブ、通信教育、個人事業者が運営する教室・スクールなどの習い事産業が発達しているのも要因の一つだと考えられる。
若い時から複数の習い事を続けたCさんは、「日本人は特に中年以降に習い事を始める人が多いと思います。女性ならば子育てが一段落してから、男性ならば退職後など、時間に余裕ができるととにかく何か習いたくなるみたいです」と説明する。
「語学、趣味、スポーツなど、ジャンルを問わず、死ぬまで学び続けたい傾向が強いように思います。現に私の叔母は80を超えて英会話学校に行っていますし、義父も大学のオープンカレッジにずっと通っていました。知人にも絵や楽器を習っている高齢者がいますし、そう言えば以前行っていた洋裁教室にも80代の方が通われていました。今更、仕事に役立てたいわけでも無く、自分の知的好奇心を満足させるためだけに息子や孫くらいの先生に教えを請い、新しいことを学び続ける」(同)
一方、13億を超える巨大な人口を持つ中国でも習い事は盛んだ。人気があるのはスポーツ、フィットネス、伝統文化、外国語、アートで日本とほぼ変わらない。年代別の傾向も、20~30代は仕事に役立つスキルや語学、30~40代は仕事と子育て中心で忙しく、習い事に興味があっても手がつけられないという実態も日本と変わらない。やはり中国でも子育てが一段落にした中高年になって、やっと念願の習い事を始められるという傾向がある。
また、中国では、一人っ子の子供に好きなだけお稽古をやらせたいと考える人が多く、子どものお稽古にたくさんのお金をかけてしまい、自分のお習い事に回す余裕がないという状況を見られる。
それに、一昔前まで、中国の老人は孫の子守りや世話を行うのが一般的な考えだった。定年後に「孫経理」(孫マネージャー――孫の世話役)に就任するという揶揄があるぐらい、孫の世話にかかりきりになる中国の老人が少なくない。一方、日本では、核家族化によって、日本の老人は習い事で自立し、人生を豊かにし、自分を高めたいと考えるようになった。
しかし、最近の中国でも、新しい世界を知り、自分の視野を広げる目的で習い事がはじまる傾向を見始めた。
中国でシニアを対象に習い事サービスを提供するメインの機関は「老人大学」だ。「大学」と称するが、学校教育法に規定される大学ではない。入学資格は60歳または65歳以上の高齢者と定めているところが多い。手頃な料金でカルチャー講座や軽スポーツや音楽を学べることで高齢者に人気が集まるため、北京や上海などの「一線」都市では、「老人大学」に入学したくても、定員はすぐ満員になり、「待機老人」が大勢発生する。この傾向は日本では見られない。
日本の習い事産業では、すでに供給側で競争状態になっているため、需要以上に学習場所や機会があり、低価格で上質な習い事サービスを受けられる現状となっている。
一方、多数の中国人は生涯学習の理念に賛同を示したにもかかわらず、習い事産業は十分に発達していないため、自ら趣味活動を模索する人が多い。
日本人を驚かせる中国各地で中高年女性を中心にブームになっている「広場舞」(広場ダンス)や、中高年から高い支持を得ている太極拳と書道の活動は代表事例の一つとは言える。活動スペースを求めるため、これらの活動はほとんど公園や広場などの公共の場で行われている。
中国四川省出身の王さんの趣味はジョキングと料理だという。公園でのジョキングやネットで検索したレシピで料理を挑戦し、お金をかけなくても趣味を楽しめると自負している。

「『活到老学到老』(生きている限り学び続ける)をモットーに健康維持と料理の研究で自分自身の進化を実感しています」(王さん)
日本の習い事が永く社会に深く浸透している。幼少時代の習い事は社会人になってからの習い事に影響がある傾向も見られる。また、習い事のジャンルが幅広くカバーしているため、伝統的な「スキルアップのため」、「健康のため」、「視野を広げるため」といった稽古志向のほか、自分の人生をより有意義するよう、人生の目標を習い事に託す側面も見られる。
簿記、心理学を通信大学で学び、現在東京都内某大学院で心理学を更に研究しているYさんは言う。
「人生の傍らに習い事がある、追及できるものを持っていたい。可能なら習い事をきっかけに社会貢献できるとなおいい」
弁護士の多忙な仕事の合間をぬって、スポーツや語学を楽しんでいるZさんは大人の習い事について、「習い事とは、一言で言うと、趣味ですが、軽い意味の趣味ではなく、できる限り真剣に取り組むことによって仕事では学べないことを学ぶ機会を提供してくれる場です。習い事で学んだことは仕事にもその他のことにも役に立っています」と考えている。
中国の習い事の歴史はまだ浅いが、習い事産業のこれからの発展を期待されている。今後、中国も日本のように、幅広い分野の習い事から興味のあるものを自ら選び、自由な時間を自分自身の趣味に使い、人生を豊かにする時代を迎えるだろう。
「僕は若い時に勉強するチャンスはあまりなかったけど、80代になった今でも、習い事で人生を充実させることが大事だと思います」(河北省・李さん)
これから中国の習い事がどのように発展していくのか、興味深く注目していきたい。
苗苗中国語教室
Copyright (C) 2005 MM Chinese All rights reserved