昨日、2月2日は「バスガールの日」だったそうです。CBCラジオ朝の番組、多田しげおの朝からP・O・Nの中の話題で、今日は何の日でお話しされていました。
バスガールの日とは、1920年(大正9年)に東京市内の運行する乗り合いバス「東京市街自動車」に女性車掌の乗務が始まり、その粋な姿から「バスガール」と呼ばれたことからこの2月2日をバスガールの日と呼ばれるようになったそうです。
そしたら、番組宛にたくさんのメールが届き、「(乗合)バスに車掌さんがいたんですか?」とか、「バスの車掌さんは何してたのですか?」というもの。
今では乗合路線バスは、運転士一人のワンマンバスが当たり前ですからね。
バスを動かすだけなら運転士一人でよさそうですが、現在の運行規定でも車掌乗務の二人乗りが基本で、車掌乗務省略のワンマン運行はあくまで特別認可されて運行するものです。
車掌が乗務する目的は、運行の補助です。
つまり道路が狭いところで、左方の確認、また後退するところでは後退誘導。狭い場所でのすれ違い誘導。
踏切では、一旦停止し、車掌が降りて、安全の確認をして誘導します。
また営業の面では、乗客への乗車券販売と案内。乗降用扉の開閉です。
一応、私も車掌さんのいるバスに記憶のある最後の世代です。
バスで車掌さんは、中扉のすぐ後ろに、乗務する場所があり、そこに約2cmほど高くなったところがあって、通称「車掌台」と呼んでいました。
お客が乗ると、乗車券販売にやってくるんですが、走行するバスの中で立ったまま販売しているので、すごい芸当だなと思っていました。
今はさすができないでしょう。保安規定に反しますし(急停止した際に危険)、エンジン出力が高くなり、加速の際のGが大きいので。
停留所では、車掌さんが扉を開閉します。
扉を閉めて、発車の準備が整うと、ブザー鳴らしたり「発車願います」のアナウンスをして運転士に発車の指示をします。
私が乗った区間では踏切は無く、車掌誘導の場は見ませんでしたが、小学校の遠足では見ました。
名鉄バスは、昔は前扉の貸切専用車というものは少なく、中扉のみの路線用の車両も貸切運行に使われていました。
運行の補助を必要とせず運転士一人で行え、安全と認められればワンマン運行の認可があります。
ワンマン運行運行を認める条件としては、
・相応の道路幅を通行すること
・幅の狭い道路を通行する区間では、道路に退避場所と鏡を設置し、その鏡を介して次の待避所まで状況が見通せること
という道路側の条件があり、さらに車両側の設備として、
・後退するおそれのある区間は、後退用後方確認モニタを備えること。
・車内に運行系統を示す図等を掲げること。
・旅客が自身で運賃を投入する、運賃箱を備えること。
・運賃表を掲げること。
という設備が要求されています。これらは今では当たり前のことですが、あくまでワンマン運行は特別な認可によるものです。
あくまでワンマンバスは特認(特別認可)によるもの、というお話。
ところで、2月2日は東京市街自動車という「私バス」で女性バス車掌が始まった日なのですね。
2月1日は、1930年(昭和5年)に名古屋市電気局で乗合バスの運行が始まった日です。いわゆる名古屋市バスの始まり。
名古屋の「市バス」では最初から女性車掌が乗務していました。
当時は市内に多数の民間バス、つまり「私バス」があり、差をつけるため。
つまり営業戦略でした。車掌さんが女性なのは大人気で、お客さんにもあこがれの職業としても。
この営業のための「女性車掌」が、やがて戦局の悪化で必要に迫られて、女性車掌に加え、女性運転士も登場しました。
「名古屋市電気局」は後に「名古屋市交通局」に改称しています。
バスガールの日とは、1920年(大正9年)に東京市内の運行する乗り合いバス「東京市街自動車」に女性車掌の乗務が始まり、その粋な姿から「バスガール」と呼ばれたことからこの2月2日をバスガールの日と呼ばれるようになったそうです。
そしたら、番組宛にたくさんのメールが届き、「(乗合)バスに車掌さんがいたんですか?」とか、「バスの車掌さんは何してたのですか?」というもの。
今では乗合路線バスは、運転士一人のワンマンバスが当たり前ですからね。
バスを動かすだけなら運転士一人でよさそうですが、現在の運行規定でも車掌乗務の二人乗りが基本で、車掌乗務省略のワンマン運行はあくまで特別認可されて運行するものです。
車掌が乗務する目的は、運行の補助です。
つまり道路が狭いところで、左方の確認、また後退するところでは後退誘導。狭い場所でのすれ違い誘導。
踏切では、一旦停止し、車掌が降りて、安全の確認をして誘導します。
また営業の面では、乗客への乗車券販売と案内。乗降用扉の開閉です。
一応、私も車掌さんのいるバスに記憶のある最後の世代です。
バスで車掌さんは、中扉のすぐ後ろに、乗務する場所があり、そこに約2cmほど高くなったところがあって、通称「車掌台」と呼んでいました。
お客が乗ると、乗車券販売にやってくるんですが、走行するバスの中で立ったまま販売しているので、すごい芸当だなと思っていました。
今はさすができないでしょう。保安規定に反しますし(急停止した際に危険)、エンジン出力が高くなり、加速の際のGが大きいので。
停留所では、車掌さんが扉を開閉します。
扉を閉めて、発車の準備が整うと、ブザー鳴らしたり「発車願います」のアナウンスをして運転士に発車の指示をします。
私が乗った区間では踏切は無く、車掌誘導の場は見ませんでしたが、小学校の遠足では見ました。
名鉄バスは、昔は前扉の貸切専用車というものは少なく、中扉のみの路線用の車両も貸切運行に使われていました。
運行の補助を必要とせず運転士一人で行え、安全と認められればワンマン運行の認可があります。
ワンマン運行運行を認める条件としては、
・相応の道路幅を通行すること
・幅の狭い道路を通行する区間では、道路に退避場所と鏡を設置し、その鏡を介して次の待避所まで状況が見通せること
という道路側の条件があり、さらに車両側の設備として、
・後退するおそれのある区間は、後退用後方確認モニタを備えること。
・車内に運行系統を示す図等を掲げること。
・旅客が自身で運賃を投入する、運賃箱を備えること。
・運賃表を掲げること。
という設備が要求されています。これらは今では当たり前のことですが、あくまでワンマン運行は特別な認可によるものです。
あくまでワンマンバスは特認(特別認可)によるもの、というお話。
ところで、2月2日は東京市街自動車という「私バス」で女性バス車掌が始まった日なのですね。
2月1日は、1930年(昭和5年)に名古屋市電気局で乗合バスの運行が始まった日です。いわゆる名古屋市バスの始まり。
名古屋の「市バス」では最初から女性車掌が乗務していました。
当時は市内に多数の民間バス、つまり「私バス」があり、差をつけるため。
つまり営業戦略でした。車掌さんが女性なのは大人気で、お客さんにもあこがれの職業としても。
この営業のための「女性車掌」が、やがて戦局の悪化で必要に迫られて、女性車掌に加え、女性運転士も登場しました。
「名古屋市電気局」は後に「名古屋市交通局」に改称しています。













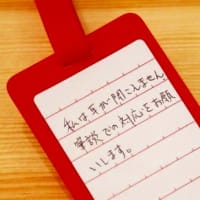
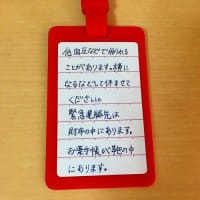





自分も年をとったもんです。
名古屋の市バスでも、ちょうど市電全廃の2年ほど後、確か1976年まではツーマンバスが走っていました。
ちょうど私が中学3年生で、受験生だった頃、多分模試か何かに行くため、新瑞橋の停留所から市バスに乗ろうとしたら、女性車掌さんが乗ったバスが来て、ビックリした事を覚えています。それが1976年の春あたりでしたから、ツーマン車の最後の最後の頃だったのでしょう。当時はもうほとんどツーマン車が走っていなくて、もう無いものと思っていたら、久しぶりに見たので、ビックリしたのです。
もっと以前、私が物心ついた1960年代の半ば頃は、名古屋の市バスは、運賃均一制ではなく、対キロ区間制で、1区~2区~3区とか分かれていました。
そのまだ幼い頃、親に連れられて市バスに乗ると、女性の車掌さんが、どこまで行くか聞くやいなや、手に持った乗車券束から手際よく、その区間の乗車券をちぎって、パンチを入れて渡してくれた光景、今でも脳裏に焼きついています。なんか懐かしい思い出です~
そうなんですよね。今や乗り合いバスの車掌さん(の存在)を、全く知らない日本人が増えたんですね。
日本以外の多くの国々では、まだまだ健在なんですが・・
巷を走るバスは、ワンマン運行ばかりですし、あのバスという自動車に乗務員が二人もいるんか?というのが多くの方の素朴な思いでしょう。
故に、CBCラジオで多くの反響があったのかなと思います。
これも世代間の差かもしれません。
今回の記事を書くにあたって、資料を出してみましたが、どうもつじつまが合わず、あえて外しましたが、名古屋市バスは昭和50年台まで車掌乗務のツーマン運行がありました。
対キロ区間制ではなく、当時の運賃制度は特殊区間制で、最大三区。
二区系統はワンマンで運行していましたが、三区系統はツーマンだったそうです。
このツーマン対応用車両で、昭和49年にワン・ツーマン兼用の車両が登場しました。
車両番号が「2HR・2FR」など前中扉の車両です。
特殊区間制ですので、運賃が変わる停留所の位置を数えれば、乗車区間の運賃が分かる仕組み。
そこを立ったまま、パンチを入れて、お客に渡すのは、職人芸ですね。名鉄バスで覚えています。
バスの車掌さんと言えば、バスガイドのことを指すと思われている方がおられるようです。
ある地域では、車掌ではなく、狭隘区間における誘導員として乗り込んでおられる路線もあります。