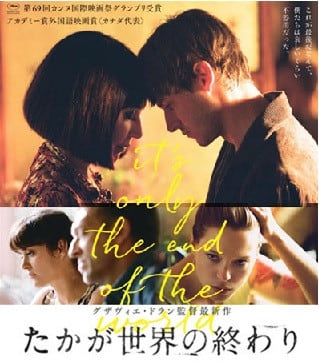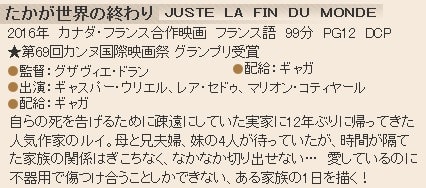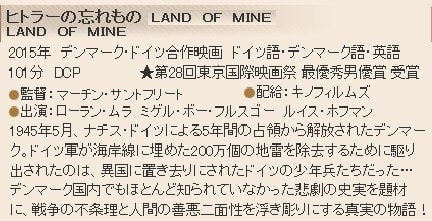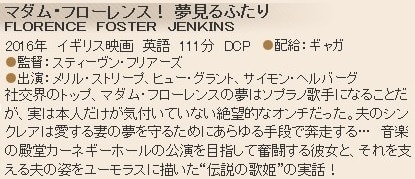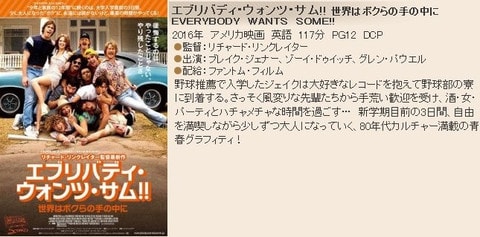原題:Bacalaureat、英題:Graduation、狭義のバカロレアはフランスの大学入学資格のこと、
ちなみにバカロレアの語源はラテン語の「月桂樹の実」だそうです。
珍しいルーマニアの映画です。私は初めてかもしれません。フランス、ベルギーの会社がお金を出したのでしょう。
可もなく不可も無く、と言ったところでしょうか。
ストーリーは単純で、サスペンス調映画です。
舞台は、チャウシェスク後のルーマニアです。
冒頭、ロメオの家の窓ガラスが石を投げられて割られます。
このシーンは、この映画の謎解きを暗示しています。
医師のロメオは娘のエリザの英国留学に大きな期待を持っています。
奨学金を受けられるかどうかの最終試験の日、エリザは、街中で強姦未遂を受けます。
そのショックで、エリザは試験を受けられませんでした。
ロメオは、かつてのコネ・賄賂の習慣を駆使して再試験と採点をよくする為の違法な工作を始めます。
彼は、エリザが閉塞するルーマニアを脱することが彼女の唯一の幸福で、その実現には奨学金が絶対必要だと言います。
しかし、このストーリーの設定・前提が無理筋で、説得性がありません。
社会的地位もあり、裕福なロメオですから奨学金など無くとも娘を留学させることは出来るはずです。
なのに彼は、若いシングルマザー・サンドラと不倫関係にあります。
こんな設定ですから、背後にかつての社会主義ルーマニアのコネ・賄賂の「残滓」が潜んでいる何て言われても、です。
ロメオに検察の手が伸びてきます。なんだ、ルーマニアは結構まともじゃないか、何て思わせます。
なのに、もっと深刻な真っ昼間の強姦騒ぎは?のまま、です。
エリザが乱暴された場に、エリザの恋人マリウスが居たか居なかったか問題にされますが、本筋ではありませんし、
このエピソードが挿入された意味が私には全くわかりませんでした。
ロメオの車の窓ガラスも石で割られ、その後、家の窓ガラスが再度割られます。これらの謎は最後まで明らかにされません。
石を投げた人間は、ロメオの不倫相手の息子で言語障害を持つマティであることは間違いありません。
公園で遊具の順番を待つ子ども達の列に割り込んだ子に、彼が石を投げるエピソードが唐突に挿入されました。
彼は、「順番を守らない人をどうすればいいの?」、つまり「法を守らない人をどうすれば良いの?」と言うわけです。
言語障害を持つ子が、言葉の代わりに「石を投げる」かは私は知りませんが…。
エリザは、不正を働いてまで奨学金試験に受からなくても良いと、高校を卒業します。
卒業写真のエリザは、吹っ切れたように明るい顔です。
彼女は人生の一つの過程で父とは違う卒業を選んだと言うわけでしょうか。
私は、風景としてのブカレスト以外はルーマニアについては知りません。
この映画が、今日のルーマニアの現状をどのように反映しているかは想像もつきません。
エリザ、妻、サンドラ、そして彼女の息子達は、「卒業」しつつあるのに、彼だけがチャウシェスク時代のルーマニアや、
その残滓を彼の心の中に引きずり、決別できないのです。 【2017.7.24】