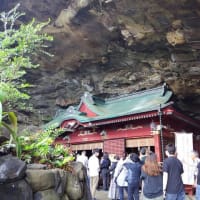<前編の続き>
『前編・弥生人の銅鏡は何を語ったのか』の続編である。先ず前回に用いた方格規矩四神鏡解説図に誤りがあったので、朱字で訂正し掲載しておく。

<後編>
古代中国において羽人つまり鳥装の人々には、二通りの解釈が存在していたと思われる。下掲の写真は、人民中国より拝借したものであるが、殷(商王朝・紀元前17世紀ー紀元前1046年)の玉製羽人である。

玉製羽人 殷(商王朝) 人民中国より
金関恕氏は、鳥霊信仰の源流は殷時代の中国にあり、それが山東半島から遼東半島南岸沿いの長山列島を経由して、朝鮮半島に流入したと述べ、半島に鳥竿(ソッテ)が存在するのが、その証という。それは有力な水田稲作伝播ルート説と一致し、やがて半島南部を経て日本列島に至ったとする。この見解については、次のように多少疑問に感じている。稲作とそれにともなう文化の伝播は、大陸より直接渡海し日本列島に至ったものであり、半島からの伝播はやや後の時代であると考えている。
羽人について話を戻す。先ず羽人は仙人であるという。後漢の王充(27年ー1世紀末)が著した『論衡』は仙人について、以下の如く記している。
『圖仙人之形體生毛臂變為翼行於雲則年增矣千歲不死』・仙人の姿とは、体には毛が生え腕は翼となり雲の上を歩く。年齢は長寿で千年も死なない。つまり翼が生えて天に昇って仙人になったという故事である。
ここで二通りの解釈のうち一番目は、羽人は仙人という解釈である。これは前回記事にした『方格規矩四神鏡』の文様解釈と同じである。
以下、二番目の解釈である。漢族は、揚子江流域の諸民族を『鳥夷(ちょうい)』と呼んだ。紀元前200年頃の『今文尚書・夏書』は次のように記している。“冀州(きしゅう)の条に「鳥夷被服」、また同じく揚州の条に「鳥夷冀服」とある”。冀州は河北・山西の二省及び河南省北部にかけての古代九州の一つで、揚州は現在の江蘇・浙江の地域にあたる。これによれば揚子江下流域には、鳥夷と呼ばれる人々が存在していたことになる。鳥夷とは鳥装の人々で、冀服とは卉服(きふく)と記す古代の注釈書が存在しており、鳥夷と呼ばれる揚子江流域の人々は卉服(草の繊維で織った衣服で夷蛮の人々の服装)を着用していたことになる。
そこで『論衡』は次のようにも記している。“周時天下大平越裳献白雉倭人貢鬯草食白雉服鬯草不能除凶”つまり、周の時は天下太平で越裳は白雉を献じ、倭人は鬯草(ちょうそう)を貢す。白雉を食し鬯草を服用するも、凶を除くあたわず・・・となる。
周とは紀元前1000年頃のことで、日本は縄文時代のことであり、当時は縄文人で倭人ではなかったであろう。高島忠平氏は、周の時代に縄文人が中国と交流したとは考えられない・・・としておられる。『論衡』がいわゆる“ウソ”を記述しているとも思えず、これらの倭人は呉越の地にいた人々の一部族かと思われる。紀元前5世紀頃、この呉越の倭族が、呉越の相克と漢族の南下圧力に押され、日本列島や朝鮮半島南部に逃れた人々が、倭国を建国したものと考えている。従って倭族は『鳥夷』につながる人々で、鳥をトーテムとする民族であった。従って二番目の解釈は、鳥装の羽人は鳥夷で鳥をトーテムとする人々である・・・と云うことになる。
これらの羽人=仙人、羽人=鳥夷が考古遺物で証明できるかどうかという課題がある。日本の弥生遺跡から羽人というか鳥人に関する遺物が、それなりに出土している。それらは鶏冠の人頭土製品や線刻板絵と鳥装の人物絵画土器片である。以下、それらを写真付きで紹介する。
先ず『鶏冠の人頭土製品や線刻板絵』から紹介する。尚、紹介する遺物は全て弥生時代前期ー中期である。

松江市・西川津遺跡

福岡県糸島市・上鑵子(かんず)遺跡

香川県・鴨部川田遺跡

岡山県総社市・上原遺跡

京都府・温江遺跡
以下、『鳥装の人物絵画土器片』である。

岡山市・新庄尾上遺跡

佐賀県・川寄吉原遺跡 銅鐸形土製品線刻絵画の模写

奈良県・清水風遺跡(1)

奈良県・清水風遺跡(2)

奈良県・清水風遺跡(3)

清水風遺跡(4)

清水風遺跡(5)
異形の頭飾りと盾・戈を持つ当該絵画を方相氏と解釈する識者が存在する。筆者は異形の頭飾りは羽と膾炙している。

奈良県橿原市・坪井遺跡

鳥取県米子市・稲吉角田遺跡
これらの遺物を先に紹介した二通りの解釈のどれをもって理解すればよいであろうか。鶏冠の人頭形土製品は、鳥夷で鳥をトーテムとする人々を表しているであろう。鳥装の人物絵画土器片は、仙人ではなく鳥装のシャーマンとする見解が識者には多いように見受けられる。しかし、その中で清水風遺跡の土器片に描かれた人物の頭は、鳥の羽根ないしは異形の装飾か判断つきかねる形状である。これをもって方相氏であるとの見解もある。これについては別に紹介することとし、今回のブログ記事は終了するが、最後には訳の分からない締めとなった。今回云いたいことは、我々の祖先は、揚子江下流域から渡来した人々で、それは鳥をトーテムとしており、かつ考古学的遺物で証明できるという話であった。
<蛇足・1>

過日、『鬼と日本人の歴史』小山聡子著なる図書を読んでいると、以下の一文が眼に入った。“横浜市称名寺所蔵の「日本図」は鎌倉時代後期から室町時代初期頃に製作されたとされている。そこには日本を囲むように鱗をもつ龍ないしは蛇の胴体が描かれている。その内側が国内で外側が国外と思われる。その国外に「龍求国」、「宇嶋」、「対馬」、「隠岐」、「新羅国」などが描かれている。龍求国(琉球国)、宇嶋は『身人頭鳥』と記されている(写真の赤線参照)。『身人頭鳥』とは、身体は人で頭は鳥である。沖縄の人々には失礼であるが、当該上から目線の記述は、本土を囲む島々には鎌倉時代後期でさえ鳥装の人々が存在すると認識されていたことになる。『身人頭鳥』は、古代からの伝承無には記述できない文言である。
<蛇足・2>
下に掲げるのは、鶏冠の人頭や鳥装の人物に関する遺物の出土地点をグーグルアースにプロットしたものである。5点集中しているのが天理市清水風遺跡であるが、その年代は弥生中期以降である。それに比較し他の出土地点は、弥生前期から中期にかけての出土である。九州から西日本は邪馬台国を遡る時代から揚子江下流域の文化が及んでいたことになる。やや的外れかとも考えるが、邪馬台国九州説の傍証になりそうだ。

<了>