これまでのNY株の回復度合いを見て、今回の関税戦争を起爆剤とした下落についても、ここで買えばいずれ上昇軌道に回帰するとの期待から、個人投資家を中心に底値を拾う動きが活発なようです。
逆に機関投資家は、過去の大幅下落の時と同様、3ヶ月決算を睨んでの売りが優勢になっているようです。しかし、あのバフェットは既に高値で相当な株を現金化しており、ヘッジファンドなど短期筋とは真逆の動きをしております。
今日は、これまでの筆者の経験(といってもここ20年ほどですが)から、本当にNY株は上昇軌道に速やかに回帰するものなのか、特にリーマンの時との差を見ながら検討してみました。
<リーマン時の下落の特徴>
・住宅担保債券を巧妙に仕組んで、世界の投資家に売りさばいていた。
・住宅価格が上昇している限り、その債券の「やばさ加減」は露呈せず。
・CDSを相互に掛け合ってリスクを担保していた。
従って、住宅価格の下落が誰の目にも明らかになった途端に、上記のやばさ加減が一気に露呈。ほんの少し前まで好決算を叩き出していたはずのリーマン・ブラザーズが、この逆流に飲み込まれてたったの数週間で破産。
これを機に「世界金融恐慌」なる大きな災禍が金融市場を襲いました。
この危機に対して、世界の金融当局はなるふり構わずに公的資金を投入しました。そして、当時の中国が巨額の開発投資を振り向け、世界の経済のシュリンク状態を除々に取り除いていくことができました。
要するに、金融システム危機だった訳です。そして、これを何が何でも収束させないことには、貨幣のやりとりをベースとした人々の日常の生活がなりたたない、つまり資本主義がなりたたない金融システム上の危機だったということですね。
<今回の下落の特徴>
・資本主義を支えてきた自由貿易体制へのアメリカの離脱要求。
・戦後の世界秩序を支えてきたアメリカの役割のアメリカ自身による終焉化。
・その背景にあるのは資産格差の拡大による一般の人々の怨嗟。
以上のことが背景となり、トランプ大統領を再度生み出し、今回の関税戦争を通じてのアメリカの覇権国家からの下野による、戦後の世界の秩序を根本的に変えることによる、資本主義体制の延命を狙った動き、と考えることができるかと思います。
リーマンの時は資本主義体制を是としての、金融システム上の動乱の収束が対応策であったのに対して、今回は、資本主義体制そのものの延命をかけての、まずは関税戦争をしかけて、戦後の世界秩序の組み直しを行う動きという風に理解するのが妥当かと思います。
このような資本主義体制に基づく世界秩序そのものの組み直しという動きは、単に金融システムの再興を行うのとは次元が全く異なる話です。
つまり、ヨーロッパ中世の宗教的信仰に支えられた社会が資本主義を胚胎し、それが今日まで何とか続いていたが、今回は資本主義体制の上記のような根本的な危機に対する処方箋がないまま、まずは関税戦争という戦争がアメリカという巨大資本主義国家により仕掛けられた、という見方ができます。
このように考えると、リーマンの時のように株価はいずれ右肩上がりの軌道に戻る。従って、今のこの底値で買わなければどうする、という個人投資家の動きは、極めてリスキーであることを認識しておいた方が良さそうです。
事態はこれまでとは全く異なります。
今回はアメリカを中心とした戦後世界の資本主義体制を揺るがす事態です。実際の着地点は全く見えません。従って、今が底だと思って株式を難平(買い増し)しても、更なる大きな下落に見舞われ、いわゆる難平地獄に嵌まって資金的に行き詰まり、市場からの退場を余儀なくされる恐れがあるということだけは、個人投資家の方々は認識しておいた方が良さそうです。
以上です。














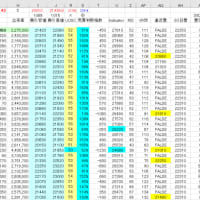



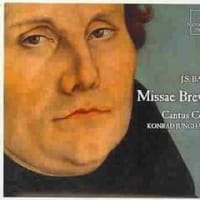








※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます