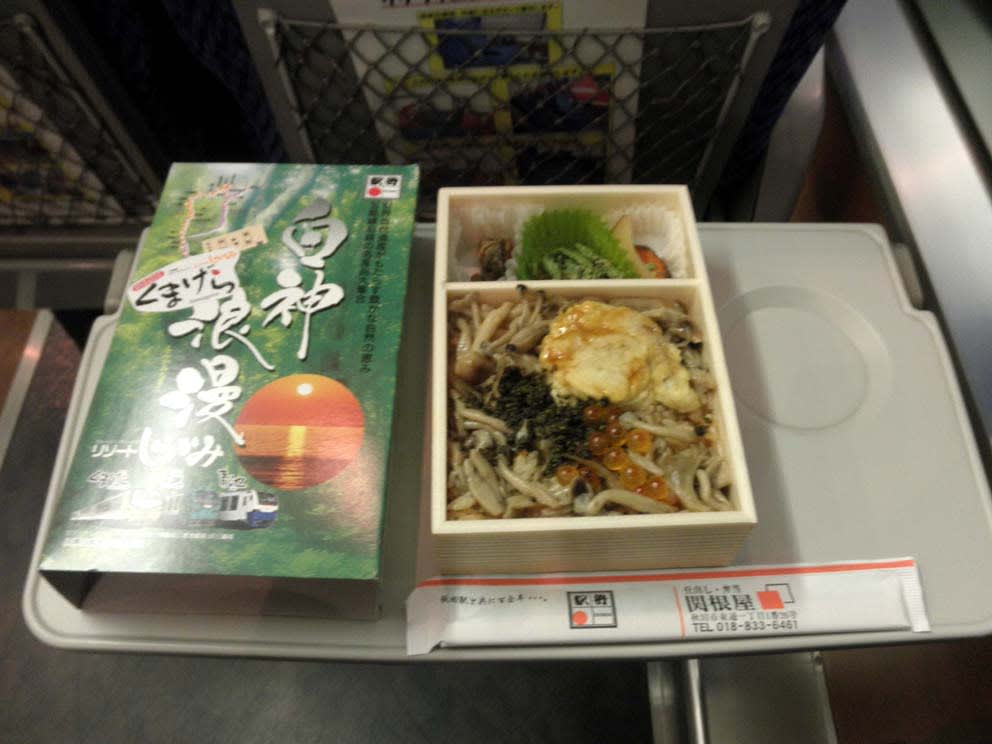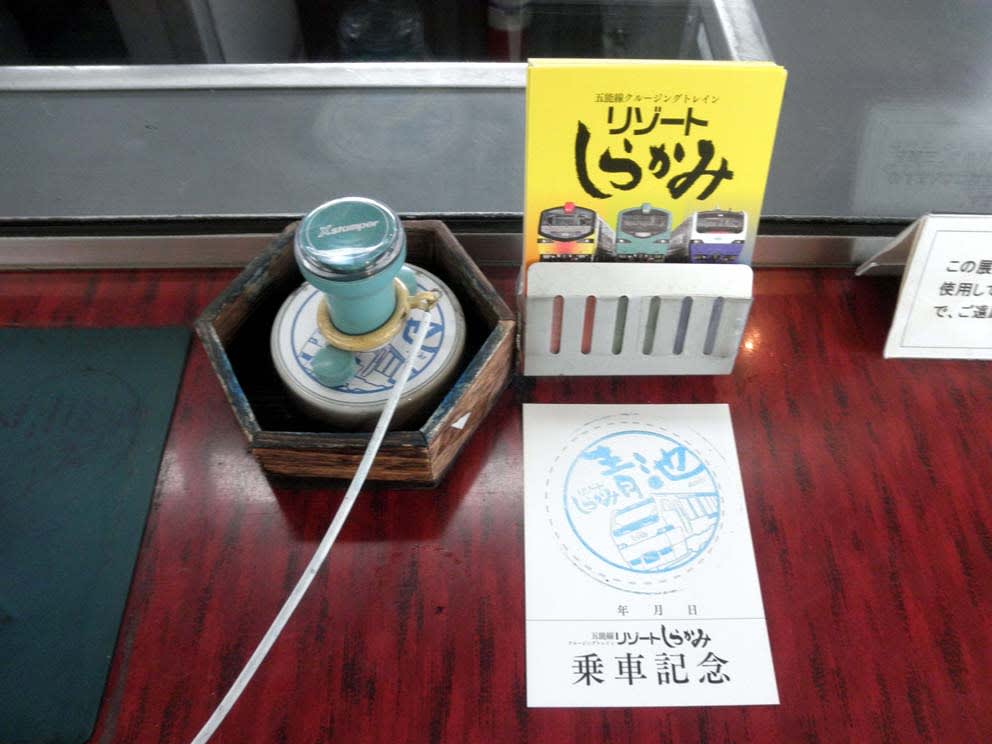数日前MAKIKYUは福島県の会津地方へ足を運ぶ機会があり、第3セクターの会津鉄道や野岩鉄道にも乗車したのですが、その際には会津若松~鬼怒川温泉間を直通運転する4社直通運転(JR只見線・会津鉄道・野岩鉄道・東武鬼怒川線)列車「AIZU尾瀬エクスプレス」にも乗車したものでした。
この「AIZU尾瀬エクスプレス」や、列車名称こそ異なるものの、やはり4社直通運転を行う「AIZUマウントエクスプレス」では、東武線直通運転に対応した会津鉄道の気動車が用いられています。
かつては名鉄の北アルプス号で使用していた気動車を、名鉄時代と同じキハ8500形の形式・装いのまま「AIZUマウントエクスプレス」として運転していた事もあり、MAKIKYUは以前この列車にも乗車した事がありますが、同車は経年や路線条件などが災いし、さほどの老朽車ではないとはいえ、近年残念ながら運用を退いてしまった事は、ご存知の方も多いかと思います。
(キハ8500形に関して以前取り上げた記事は、こちらをクリックして下さい)
キハ8500形の代替も兼ね、2010年に導入された新形式車両がAT-700・750形で、車両自体は近年会津鉄道が導入した他形式と同形で、最近各地の第3セクター鉄道で増殖している新型気動車の典型とも言えるメーカー標準仕様車両ですので、当然他形式車両との併結運転(ブレーキ方式が異なるお座トロ列車の各車両を除く)も可能で、実際に他車両との併結運転を行う事もある様です。

このAT-700・750形は、MAKIKYUは先日「AIZU尾瀬エクスプレス」で初めて乗車したものでしたが、真っ赤な装いは非常に目を引くもので、同社の他形式車と並んだ時も、存在感は別格と感じます。

またAT-700・750形は装い以上に、車内設備に大きな特色があり、一応快速列車を主体に運用される一般型車両で、基本的に特別料金を要する列車に充当される事はないものの、座席は回転式リクライニングシートを装備しているのが大きな特徴です。
第3セクター鉄道ではイベント兼用車などで、転換式クロスシートを装備した特別仕様車を保有する事業者こそ幾つも存在するものの、それを凌ぐローカル列車用車両にしては破格の設備を誇り、まして1両だけの特別仕様車的扱いではない事も踏まえると、極めて異例の車両と言えます。
内装も暖かみと高級感を感じさせる色彩を用いており、会津鉄道が「グリーン車並み」と宣伝している告知を目撃した程で、さすがにJRの
特急グリーン車程の設備とは言い難いものの、普通列車グリーン車や特急普通車の標準レベルには達しており、東武線の特急車両(スペーシア)と乗り継いで首都圏~会津地方間の連携輸送を担う花形車両ならではと感じるものがあります。

ただ第3セクター向け標準仕様の一般型気動車をベースに、設備を特急並みに仕立てた車両であるだけに、窓柱が視界を邪魔する座席が多いと感じたのは難点で、シートピッチもスペーシアなどに比べると…と感じたもので、半室式運転台やワンマン運転用の各種装備なども、会津鉄道の輸送実態を反映した一般型車両ならではと感じたものです。
おまけに各座席には、パイプ式の足置きが設けられており、豪華な雰囲気を醸し出すには良いアイテムなのかもしれませんが、この足置きのお陰で足元が若干支えると感じたものです。

座席下部は最近の車両だけあり、脚台部分以外は空洞で足を伸ばせる造りである上に、パイプ式の足置きはネジで取り外し出来そうな雰囲気ですので、個人的にはこの足置きを撤去して頂ければ…と感じたものです。
このAT-700・750形は現在、基本的に東武日光直通の「AIZUマウントエクスプレス」と「AIZU尾瀬エクスプレス」や、両列車と関連する運用の会津鉄道線内普通列車(JR会津若松直通)に充当され、基本的に鬼怒川温泉発着の「AIZUマウントエクスプレス」(以前は「AIZU尾瀬エクスプレス」用として告知していたAT-600・650形車両を充当)には充当されませんので要注意です。
設備的にはAT-600・650形でも転換式クロスシートを装備し、一般型車両にしては乗り得な部類に入る上に、設備的には野岩鉄道や会津鉄道の電化区間(会津田島以南)を走る電車(東武6050系や、野岩鉄道などの名義になっている同等車両)よりも上等ですので、決して悪い車両ではないのですが、座席や内装の雰囲気などではAT-700・750形と比べると、どうしても見劣りが否めない気がしますし、MAKIKYUには余り関係ない事なのですが、こちらは今の所車内での無線LAN使用にも対応していません。
おまけに会津鉄道や野岩鉄道の運賃は、お世辞にも安いとは言い難く、両線の列車は観光向けのお座トロ列車を除くと、現行営業列車は基本的に特別料金不要とはいえ、運賃自体が特別料金込みと言っても過言ではない印象があります。
この決して安くない運賃を支払って2鉄道を利用するなら、できればその運賃に見合うだけの設備を誇る車両に乗車したいもので、路線実態を考えると割安な運賃設定などは難しいかと思いますが、AT-700・750形に乗車した際には、高運賃に見合うだけの付加価値の高いサービスを提供するという意気込みを感じ、事情が許すのであれば、次回以降の2鉄道利用でもなるべくAT-700・750形充当列車を選んで乗車したいと感じたものです。
(高額運賃で悪評名高く、首都圏の辺境・北総監獄(千葉ニュータウン)を走る「開発を止めた某鉄道」(元○○開発鉄道)も、少しは会津鉄道を見習って欲しいもので、特に7260形車両の惨状は呆れる限りです)
また鬼怒川方面への東武線直通列車は基本的には2両運行であるものの、閑散期は1両でも座席が埋まらない程空いている事などを考えると、混結可能なAT-600・650形とAT-700・750形を各1両ずつの2両で運行する事で、長距離利用客や無線LAN利用客が恩恵を受ける機会を増やすと共に輸送力を確保する策を講じても…と感じたものでした。
東武線直通列車の名称もキハ8500形が退役し、「AIZUマウントエクスプレス」で2形式が充当される状況になっていますので、そろそろ「AIZUマウントエクスプレス」か「AIZU尾瀬エクスプレス」のどちらかで一本化した方が…と感じたものでした。