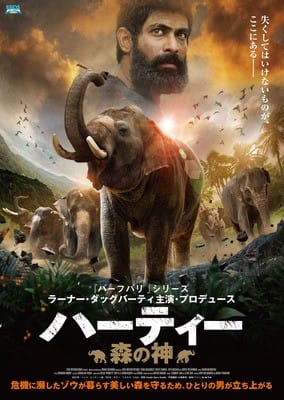[書籍紹介]

伊坂幸太郎による殺し屋シリーズ、
「グラスホッパー」「マリアビートル」に続く第3弾。
おなじみのハンコによる節目立てと、
はじめの方で、
「同業者」として、
「蜜柑」や「檸檬」が出て来るので、
主人公の職業が殺し屋であることが分かる。
普段の「兜」の仕事は、文房具メーカーのサラリーマン。
時々オフィス街にある内科診療所の医師から秘密の仕事を受ける。
殺人の依頼は「手術」と言われ、
医学用語に隠した隠語で詳細が伝達されるので、
他の患者には分からない仕組み。
情報はカルテの形を取っているので、
個人情報を楯に解明されることはない。
この設定が面白い。
もう一つの面白い設定が、
兜が大の恐妻家である点で、
妻のご機嫌を損ねないことに腐心する。
深夜家に帰って来た時は、
妻を起こさないように冷蔵庫も開けず、
コンビニで買った魚肉ソーセージで飢えを満たす。
兜が妻に気を使っていることを
息子の克己は知っているが、
妻はどうも自覚がないらしい。
兜が物騒な仕事をしていることは、家族は知らない。
兜は、殺し屋稼業に嫌気がさしており、
やめたいと思っているが、
医師は、それには先行投資を返してもらわなければならない、という。
それだけでなく、
組織から離脱すると、命を狙われ、
その標的は家族にも及ぶ。
だから、兜は殺し屋をやめることができないのだ。
そういう設定の中で、
孤独な殺し屋兜は、
友人を求め、
可能性がある友を、
その稼業ゆえに失ったりする。
ある日突然、兜はビルから飛び下りて死ぬ。
そして、10年が飛び、
息子の克己の話になる。
克己は、父親が自殺した理由が分からない。
訪ねてきたジムのトレーナーに、
父が忘れたという診察券を渡される。
その診療所を克己は訪ねる。
あの殺人の中継点となっている診療所だ。
要領を得ない医師の説明に、克己は不審感を抱く。
父の遺品を整理していると、
一つの鍵が出て来る。
克己はその筋から鍵が何なのかを探る。
ある一軒のマンションの鍵らしい。
克己は、そのマンションを訪ねてみるが・・・
という話が、過去の兜の行動と重なって描かれる。
兜の死の真相は何か、
借りていたマンションとは?
という謎解きが終盤の興味。
家族への愛ゆえに、裏稼業を脱したいと願う男の悲哀。
そして、復讐物語。
5篇構成で、
前の3篇は宝島社の雑誌に掲載され、
後の2篇は書き下ろし。
章の題名は、「AX」「BEE」「Crayon」「EXIT」「FINE」と
ABC順になっている。
Dが欠けているのは、本来「Drive」という一篇が予定されていたが、
途中で挫折したのだという。
読んでみたかった。
ユーモラスな会話、
摩訶不思議なシチュエーションに満たされて、
伊坂ワールドを堪能した。