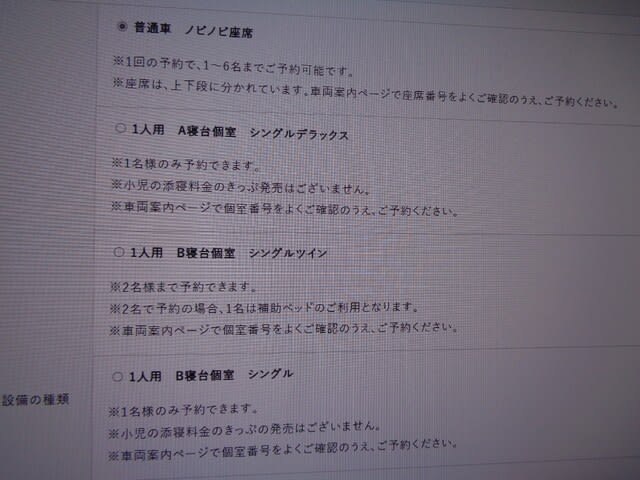ブログを引っ越しするための準備をしていたところ、
過去に「下書き」のままに放置していた文書があることに気づきました。
2月のマニラ旅行に関するものです。
掲載しないままではもったいないので、
古い話題で恐縮ですが、
今日、掲載します。
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
マニラから帰って、
先日、銀座に出かけたら、
日本の社会の特色がよく分かりました。
とにかく静か。
町中人があふれ、車も道路一杯なのに、
ものすごく静か。
その一因は、
車がクラクションを鳴らさないこと。
東南アジアを旅すると、
クラクションに追い立てられます。
ビービービービー、やかましい。
しかし、日本では、めったに警笛を聞くことはありません。
そのような日本の町を見ながら、
日本という国は、
「快適さ」を追求した国なんだな、
と感じました。
ひと昔前は、日本でも、クラクションが鳴り響いていました。
しかし、ある時から、
クラクションを鳴らしてもあまり意味がない。
むしろ、警笛がない方が快適だ、
と日本人は気付いてしまったのです。
それは自動車教習所で、
「みだりに警笛は鳴らすな」
と教えられたことが効果を表わしたのでしょう。

車の往来も、東南アジアでは
無秩序に車が陣取り合戦を繰り広げています。
北京では、わずかな隙間に入り込もうとする車で
渋滞が発生していました。

でも、日本でも昔はそうでした。
反対方向の信号が青から黄色に変わると、
みんな発進していました。
別方向から車が来ると、
互いに譲らず渋滞を起こしました。
しかし、ある時から、
「譲り合った方が効率がいいし、
気持ちもいい」
と日本人は気付いてしまったのです。
駅のホームでもそう。
整列乗車を外国人が見ると驚くそうです。

中国では、切符売り場でも
乗車口でも、横入り、割り込みは当たり前。
ちゃんと並んでいる人は永遠に辿り着けません。
これも、ひと昔前は、
日本でも降りる人を押しのけて、
乗ろうとしていました。
しかし、ある時に日本人は気付いてしまった。
降りる人がちゃんと降りてから乗る方が、
効率がいいし、その方が快適だ、と。

ゴミも同じ。
マニラの町には、ゴミがあふれ、
誰も片付けようとはしません。

日本も昔はそうでした。
ポイ捨ては当たり前。
誰も片付けない。
しかし、ある時、ゴミがない方が、
町がきれいで快適だ、
と日本人は気付いてしまった。
外国人が日本に来ると、
町にゴミ箱がないことに驚くそうです。
ニューヨークでは、
ブロックごとに大きなゴミ箱が置かれています。

しかし、日本人は、自分の出したゴミは
自分で片付けようと、ゴミを持ち帰る。
これも快適さの追求で、そうなりました。
そして、もう一つの日本社会の特色が
「便利さ」の追求。
地下鉄と電車は
東京中を網羅し、
どこでも行けないところはありません。
しかも、時間が正確。
これも、長年かけて便利な町作りをしてきたからでしょう。
町中に溢れるコンビニ。

その名称のとおり、便利な存在。
たいていの生活必需品はコンビニで手に入るし、
弁当、おにぎり、スイーツの質は高い。
しかも24時間営業。
夜中でもオーケー。
コンビニの発祥はアメリカですが、
日本はそれを高度に進化させました。
東南アジアでもコンビニは普及しましたが、
質において日本のコンビニにはかないません。
ヨーロッパで、コンビニが普及しないのはなぜでしょうか。
町のどこにもある
飲料の自動販売機。

マニラの町でのどが乾いて飲み物を探しても見当たりません。
路上で飲み物を販売している人はいますが、
冷えていないので敬遠。
しかし、日本ではミネラルウォーターもお茶も
ジュースも炭酸飲料も、
コーヒーもお茶も
街角で手軽に求めることができます。
暖かいのも、冷えたのも。
アメリカでは路上の自動販売機はまず見かけません。
ホテルなどはありますが、割高。
お金が入っているので、
盗まれたり、破壊を恐れて
配置しないのだといいます。
マニラのハッピーランドに住む人は、
聞いてみると、幸福だそうです。

しかし、日本人の目から見て、
住環境が良いとは言えません。
ゴミゴミした町、非衛生な食べ物。
快適な生活を知らないから、
これで満足しているのだとしか思えません。

話は飛びますが、
世界幸福度ランキングというのがあって、
いつも北欧諸国が上位に並び、
フィンランドは7年連続で1位を占めています。

医療や教育が無償であることが原因らしい。
その見返りとして、税金は高い。
しかし、私から見ると、
一年のうち4分の1が太陽が顔を見せない生活が
幸福だとは思えません。
冬になると、昼の3時には日が沈み、外が暗くなってしまう。
新鮮な国産野菜を買い求めることができるのが
4か月程度、という生活が幸福と言えるでしょうか。
自然は幸福度に大きく影響するはず。
調べてみると、
フィンランドは精神疾患の発生が最も高く、
5人に1人だといいます。
うつ病の発生率が世界第9位。
冬の暗い生活が影響し、
気分が沈んだり、
やる気を失ったり、
家の中に閉じこもりになってしまい、
人を避けることで、社会から孤立するようになってしまう。
うさを晴らそうと酒を呑むので、
人口の5から10%がアルコール依存症。
政府は法律で、一定の度数をこえたお酒の販売を
厳しく制限しているほど。
ホームレスの比率も高く、薬物乱用も高い。
医療は無料でも、申し込んでから
実際に治療を受けられるのは
最大で1から3週間の待ち時間です。
自殺も多い。
国をあげて「国家自殺防止プロジェクト」というのを実施
しているというから深刻なのでしょう。
こんな現状で幸福度ナンバー1とは、
どんな基準で選んでいるのでしょうか。
よくブータンを「国民幸福度」が高い
「しあわせの国」といいますが、
私は疑問を呈します。

識字率が最新のデータで72.1パーセント。
以前はもっと低かったです。
国民の4人に1人を文目のまま放置している国が
幸福とは思えません。
失業率も、日本が2.59%なのに対し、
5.90%もあります。
よく、外国に行って帰国すると、
日本が良い国だと分かる、といいますが、
教育と医療の2点をとっても、
日本ほど恵まれた国はありません。
国民皆保険制度で、
高度な医療を受けられる国。
イギリスのように、
予約して1か月待つ、
などということはなく、
その日のうちに診察可能な国。
そういう意味で、
快適さ、便利さにおいて、
日本ほど幸福な国はありません。
しかもそのために、
絶えず改善・改良する。
給料が上がらない、といいますが、
その分、物価もずっと上がっていませんでした。
欧米のすさまじいインフレを見ると、
一体いくら給料をもらったら、
このインフレに対処できるのか。
給料が高くても、物価が高ければ同じ。
給料の多寡だけで比較するのではなく、
物価も考慮しなければ、
正しい判断とはいえないでしょう。
日本のいいところ。
四季があること、
公共交通機関が充実していること、
食べ物がおいしい、
つまり、食材が豊富であること、
教育が充実していること、
医療が発達していること。
もちろん過疎地の問題はありますが、
普通の町に住み、普通の生活をしている人にとって、
こんな快適で便利な社会はありません。
久しぶりに東南アジアに行って、
改めて日本の良さを実感しました。
快適さと便利さがシステム化した国を
日本人は長年かけて作りあげたのです。
日本人の不幸は、
その幸福を実感出来ない点だと言われています。