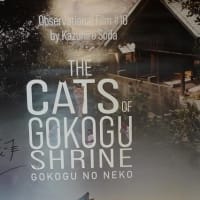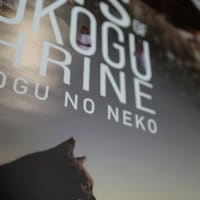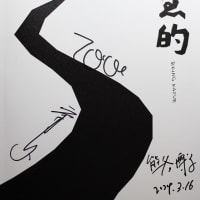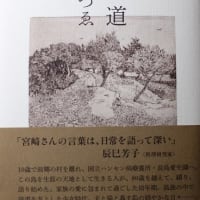ダイヤモンドオンラインより(2020-04-25)
当時、福知山線を利用していた西上いつきさんのレポートです。
転載させていただきます。
※岩清水日記でもカテゴリー「JR西福知山線脱線転覆事故&安全」にて当日からの経過を書いています。
私も事故前日にJR福知山線に乗車していました。
===
JR西日本が2005年に起こし、107人もの犠牲者を出した福知山線脱線事故から15年がたつ。事故の原因を改めて振り返りつつ、この15年間で進歩したことと、まだ対策が不十分なことを整理してみたい。(鉄道アナリスト 西上いつき)
● 107人死亡の大惨事に… 事故後も大混乱が続いた
2005年4月25日に発生したJR西日本・福知山線脱線事故から、丸15年がたとうとしている。運転士と乗客107人が死亡、562人が負傷するという未曽有の大惨事だった。
筆者は当時大学生で、福知山線と直通するJR学研都市線を使って通学していたから、当時の事故のことをとても生々しく記憶している。当日、事故の一報を聞き、学校でニュースを見てみたが、一瞬で背筋が凍りついた。何せ今朝も利用したばかりの青と水色をした207系車両が脱線・横転している。特にマンションに沿うようにひん曲がった状態となった車両を見たときは驚愕した。
そしてさらに血の気が引いたのは、7両編成のはずの列車が、いくら数えても6両しか確認できなかったときだ。先頭車両が、マンションに突っ込んで見えなくなってしまったのだ。その後の調べにより、事故を起こした運転士が、普段私の利用する路線を運転していたと知った。ひとつ間違えれば私の身にも降りかかったのかもしれなかったこと、また同じ学校から犠牲者が出たことを聞き、改めて人ごとには感じられなかった。
事故直後から運転再開までの2カ月近くの間、関西圏の鉄道ネットワークはまさに大混乱だった。アーバンネットワーク(JR西日本が当時使っていた京阪神近郊エリアの愛称)管内では、ダイヤ乱れが慢性的に続き、私自身も通学には余裕をもって30分も早く家を出るという生活がしばらく続いた。沈静化するまでは、毎日が異常時のようなすし詰め状態。だが皮肉にも、1・2両目は他車両と比べて極端に空いていたのが特に印象的だった。皆、事故の報道を受けて「先頭車は危険だ」という意識があったのかもしれない。その後、207系車両の塗色も、遺族・被害者への配慮からネイビー・オレンジへと変更された。
大学卒業後、私は鉄道会社へ入社し、当該運転士と同じ免許を取得するのだが、各指導者から「安全」という鉄道における原理原則についてたたき込まれた。同じ職種に就いて、いやが応でもあの事故がどれほど危険で重大な事故だったのかを改めて思い知らされることとなった。
事故の防波堤となるべきだったATS(自動列車停止装置)も、当時から大きな争点となった。事故現場となったカーブには、速度照査するATS装置が設置されていなかったのだ。もし整備されていれば、この悲惨な事故は発生しなかったかもしれない。しかし、2017年の最高裁で「ATSを本件曲線に整備するよう指示すべき業務上の注意義務があったとはいえない」との判断がなされ、JR西日本歴代社長3人については無罪が確定している。法治国家である以上、判決は受け入れるしかないが、やはり今でもATSが整備されていれば、と悔やまれる。
● ATSなど設備面の 進歩だけでは事故は防げない
ただし、この事故を受けて、当該事故区間を含めたATS装置の配備は進んだ。そのほかにもホーム柵の設置をはじめ、JR西日本は事故以降、毎年1000億円前後という多額の安全投資を行ってきた。そのおかげもあってか、同社の鉄道運転事故の件数は、事故が起きた2005年度には133件あったものが、2018年度はわずか58件と、大幅な減少となった。
さらには2014年、鉄道事業者で初めてとなる計画運休を実施して、自然災害時における前向きな運休を業界で一般的にした功績も大きい。事故から15年たった今も、同社は「福知山線列車事故のような事故を二度と発生させない」として安全に対する誓いを打ち立てている。その取り組みは今後も終わりはないだろうし、決して忘れてはならない。
しかし、安全計画や設備が整ったのに、扱う側の人間によって発生してしまった事故がJR西日本で近年、2つ起きている。いずれも多くの人々が犠牲になるような大惨事には至らなかったものの、一歩間違えれば大事故になっていた。
1つ目は、2017年12月11日に発生した、のぞみ号台車破損トラブルだ。博多駅を発車し、小倉駅到着時点で乗務員は異臭に気がついていたものの、JR西日本管内は運行を継続してしまった。JR東海に運行が引き継がれた後、名古屋駅で異常を確認して運転打ち切り。その後の点検で台車の亀裂が確認されたという、新幹線初の「重大インシデント」に認定された事故だ。指令員の判断で途中で点検できる機会はあったものの、運転を継続してしまうという、あわや大惨事の一歩手前まで来ていた事故だった。
2つ目は、2018年6月14日 山陽新幹線博多~小倉駅で発生した、人と新幹線の接触事故だ。事故発生後に到着した小倉駅では、係員が 車両に異変を感じながらも停止措置をしなかった。運転士も異音に気づきながらも、次の新下関駅に到着するまでの15分間走行し続け、指令員の指示でようやく臨時停止したのだった。破損によって部品が散乱しており、高架下に落ちれば落下事故、運が悪ければ、対向列車や後続列車に接触して脱線にもつながりかねない危険な状態であった。
同社は「JR西日本グループ鉄道安全考動計画2022」の中で、「異常時には現場の判断を最優先とする」という考えを掲げている。しかし、これら2つの事故は、いずれもこれだけ危険な状況にありながらも「運転継続」という現場判断を下してしまった。
はたから見れば、異臭・異音を感知すれば、真っ先に停止措置を取れば大きな事故を防げるのではないか?と考えるかもしれないが、当事者にとっては列車を止めること、つまり遅延・運休は、とても罪深いことであるという考えが染み付いていて、多数の乗客や先のJR東海管内にも迷惑をかけることを考えると、決断する勇気がなかったのだと予想できる。それほど、「定時運転こそが鉄道の原理である」という考え方が、今もなお根深く残っており、その風土が本来、真っ先に守るべきはずの安全を揺るがしているのである。
● 問題となった「日勤教育」 鉄道会社のタテ社会は改善されたか? 福知山線の事故においても、事故現場直前の伊丹駅でオーバーランしてしまい、運転士が列車の遅延を回復したいがためにむちゃな運転をしたともみられている。当時のアーバンネットワークのダイヤは、他社に対抗し、少しでも早く運転するために秒刻みのダイヤ構成だった。そんなプレッシャーの中で運転士たちは、少したりとも遅れを出すことはできないと気を張っていたことだろう。 事故を起こした運転士は、速度超過をしてまでも遅延を出すのが怖かったのか、それとも立て続けのミスによりパニック状態だったのか…。本人が亡くなっている以上、その真意は永久にわからない。 もちろん、この運転士は規則の範疇を大幅に超えた運転をしており、これこそが事故発生の引き金となったのだが、その後の調査では、事故に関係するバックグラウンドが明らかになっている。 運転士が無謀な速度超過をした背景として、JR西日本の「日勤教育」が連日ニュースなどで取り上げられた。日勤教育は本来、事故再発防止を目的とした教育制度だったのが、実際には、トイレ掃除を命じられたり、暴言を浴びせられたりするなど、見せしめともいえる懲罰的な教育になっていたことが問題となった。この運転士も、過去に日勤教育を受けている。再度、日勤教育を受けなければならないという恐怖心が、彼に異常運転をさせてしまった可能性も語られた。 現在、鉄道のみならずさまざまな業界で組織の改善が行われている。今年6月にはパワハラ防止法(改正労働施策総合推進法)が施行されるが、2005年当時は、このような社会通念は、今ほど一般的ではなかった。ましてや、保守的な会社は、いわゆる「縦社会」の組織であることが容易に想像できる。JR西日本においても、先述の行動計画の中で、鉄道は「専門分野ごとの縦割り意識や指揮命令系統を明確にした上意下達の風土になりやすい素地」があるとしている。 この記事を書くにあたって、鉄道各社の従業員にインタビューしたが、直接的な日勤教育制度のようなものはないにせよ、いまだに現場には、そのような体質が多かれ少なかれ残っているのが現実だという。この辺りは、ほかでもないJR西日本が事故を教訓に15年にわたって研究しているだろう。今後は業界全体の進化に向けて、他社にも知見を還元してくれることを期待したい。
● 台湾でも遅延を恐れた 運転士が衝撃の事故を起こした 列車遅延やオーバーランは、利用客の不便になることはあっても、人命に直接関わる問題ではない。むしろ、乗務員が焦ったり、パニックになったりするリスクの方がよっぽど危険だ。 また指令員も、とっさの判断力が求められる中で、最善を尽くした指示を下して遅延・運休を発生させたのなら、それは責任追及されるべきではない。何より、安全と定時運転の優先順位は決して逆転してはならず、事実を正確に報告できて、不利益を被らない環境を醸成することが大変重要になる。 ただし、各従業員がミスを防ぐための業務改善のPDCAに意識して取り組み、日々自己研鑽を惜しまないことが大前提だ。最善が尽くせる環境を醸成し、トップダウンでの原因究明と対策を進める、これが本来の健康的な「縦社会」のあり方だろう。 2018年、台湾鉄道の宜蘭線特急列車で、乗客18人もの死亡者を出した鉄道事故が起きた。事故直前の車両トラブルや、制限速度のおよそ2倍、140km/hで突っ込んでいったという衝撃の内容だった。 装置の設計ミスもあったが、運転士が安全装置を切ってしまったことも大きな問題だったこの事故は、福知山線事故を経験している我が国には決して対岸の火事とは思えないものだ。そして、ATSなどハード面だけを整備しても、事故は防げない可能性があるということを、改めて世間に知らしめた。 グローバル化が進み鉄道技術も国境を越えて普及している現在、ハード面だけではなく、社員育成の仕組みや組織の考え方なども、今以上に垣根なく共有されなければならない。将来の進歩に期待しつつ、二度と悲惨な鉄道事故が繰り返されないことを心から願う。
西上いつき
===
転載終わります。
当時学生だった西上いつきさんの健筆に感謝です。
亡くなられた107名の方々、ご遺族の方々に謹んで哀悼の意を表します。
お読みいただきありがとうございました。