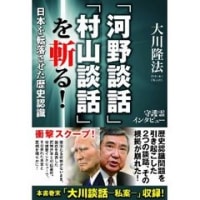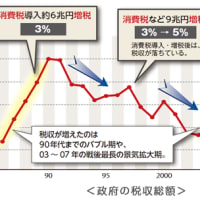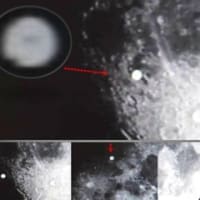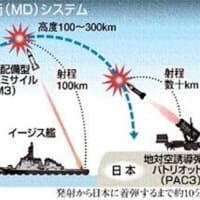人物伝ヘレン・ケラー アナザーストーリー 信仰の力で試練に打ち克つ 勇気を与えた霊界思想
2024.05.20(liverty web)
<picture> </picture>
</picture>
見えず、聞こえず、話せないという「三重苦」の試練を乗り越え、世界の人々を勇気づけた「奇跡の人」、ヘレン・ケラー(1880~1968年)。
そのヘレンが、実は、「霊界思想」を広めようとしていたことについて、本誌6月号「ヘレン・ケラーは『霊界の真相』を伝えたかった ──果たし切れなかった『もう一つの使命』」で紹介した。
本欄のアナザーストーリーでは、ヘレンがどのような形で霊界思想に触れ、深めていったのか、という点に注目していきたい。
「なぜ、この世界がつくられたのか」というヘレンの疑問
17世紀の北欧に生まれ、霊界の実在を訴えた宗教思想家のスウェーデンボルグ(1688~1772年)の霊界思想に感化されたヘレンは、それを心の拠り所としていた。
しかし、ヘレンにこの思想を紹介した元スイス大使のジョン・ヒッツが「ヘレン・ケラーの伝記類のほとんどに登場してこない」(日本スウェーデンボルグ協会公式HP)と指摘されているように、その事実は伝記などで省かれていることが多い。ヘレンを献身的に教育したサリバン先生が、スウェーデンボルグの思想に否定的だったことも要因の一つとして挙げられている。
ヘレンは、当時、高名だったフィリップス・ブルックス神父から「神は愛なり」というキリスト教の教えを学んだ。それは素晴らしい機会ではあったが、ヘレンは自著『私の宗教』で、造物主がいて、神が愛であることを知っても、この世界がつくられた理由が分からなかったことを明かしている。
ヘレンの疑問、キリスト教に欠けていた教えに「答え」を示したのが、スウェーデンボルグであった。
この世の苦しみは、魂を磨くための材料であり、選択を迫っている
スウェーデンボルグは、自分が見聞した教会における「信仰」のあり方は不十分なものだと考えていた。
「現在、信仰というと、教会がそう教えているからそうだと、思うことくらいにしか考えられていません。《中略》『信じて、疑うな』と言われている通りです。もし『わたしはよく分かりません』とでも言おうものなら、『それだから信じなさい』といわれます。現代の信仰が、無知な人の信仰といわれ、いわゆる盲目的信仰とされるのは、そのためです。またある人が別の人にたいして言ったことを信じる点では、移し植えの信仰です。このような信仰は、霊的信仰ではありません」(『信仰について』newchristianbiblestudy.orgの日本語訳)
キリスト教会の多くは、人々に知識を与えるというよりは、「素朴な心で信ぜよ」と訴えることが多かった。しかし、ヘレンのように重い試練に直面している人にとっては、「信じて、疑うな」と言われるだけでは納得しがたかったのかもしれない。
ヘレンが巡り合ったスウェーデンボルグの思想。そこでは、天国と地獄が実在し、人間は永遠の生命を持つ。その魂を磨く試練の場が「この世」である。だから、この世の苦しみは、魂を磨くための材料であり、人間に「選択」を迫っている。そう説かれていた。
「どんな出来事やどんな障害の中にも選択の機会があり、選択は創造である」(Helen Keller "My Religion")
同じ苦しみを与えられても、ある人は利他の人生を選び、ある人は不平不満の人生を選ぶ──ヘレンは、そこで何を選ぶかを神に試されている、と気付いた。
善事が報われないことはなく、悪事が苦しみをもたらさないこともあり得ない
そして、スウェーデンボルグは天界や地獄の光景を語り、死後の審判を乗り越えられるように現在の生を生き切り、人生の試練を乗り越えなければならないと呼びかける。
死後の審判においては、「探索の任務を与えられた天使たちがその人の顔を覗き込む」時に、その人生の全てが明かされる。「考えたり行なったりしたことは、すべてその体全体に書きこまれており、それらが記憶から呼び出されるときは、あたかも本から読み取るかのように明らかとなる」(Helen Keller "My Religion")。
死後、その人の正体は明らかになり、隠し事はできない。つまり、善事が報われないことはない。悪事が苦しみをもたらさないこともあり得ない。
ヘレンは、そうした答えを知ると、その教えを元に自分の未来を築き上げようとした。
「(天界では)天使の衣裳が煌めき、偉大な生命と創造的な精神が暗澹たる境遇に光明を投げかけ、事件や力ずくの闘争は永久に一掃され、神の微笑みによって夜は永遠の昼へと照らされてゆく」(同書)
そして、その霊界思想には、死の恐怖を一掃する力があるとも述べている。