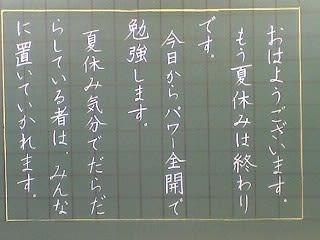放課後に,同僚の先生と次のような会話を交わした。
「今日の練習,よかったですね」
「いえ。全然分からない状況の中で行ったので,大変迷惑を掛けたと思います。どこがよかったのでしょうか」
「やり直しをさせたところがよかったです。全校にやり直しを命じるということはなかなかできません。
前の体育主任は,今の状況をあきらめていたようなところがありました。
まわれ右の指導も,ああやって一つ一つきちんと指導したのがよかったです」
私がこの話で印象に残ったのは,前体育主任があきらめていたというところである。
地域との共催ということで,子どもたちの気が緩むという状況は確かにあるだろう。保護者や地域の方々がだらけていれば,当然子どももそうなる。子どもは大人の背中を見て育つのである。仕方がないところもある。
しかし,それでは教育活動ではない。仕方がないと言ってそのまま放置するのでは,教育ではない。
ましてや今回は,保護者も地域の方もいない,授業としての全体練習なのである。
何の指導もせず,ただ活動させるだけならば,何もしなくても同じである。まさに「活動あって学習なし」である。
硬派な私としては,やり直しは当然の措置であった。
来週は総練習がある。私は,総練習は必要ないと思っているのだが,やるからには子どもたちに何らかの学びがあるようにしていきたい。
「今日の練習,よかったですね」
「いえ。全然分からない状況の中で行ったので,大変迷惑を掛けたと思います。どこがよかったのでしょうか」
「やり直しをさせたところがよかったです。全校にやり直しを命じるということはなかなかできません。
前の体育主任は,今の状況をあきらめていたようなところがありました。
まわれ右の指導も,ああやって一つ一つきちんと指導したのがよかったです」
私がこの話で印象に残ったのは,前体育主任があきらめていたというところである。
地域との共催ということで,子どもたちの気が緩むという状況は確かにあるだろう。保護者や地域の方々がだらけていれば,当然子どももそうなる。子どもは大人の背中を見て育つのである。仕方がないところもある。
しかし,それでは教育活動ではない。仕方がないと言ってそのまま放置するのでは,教育ではない。
ましてや今回は,保護者も地域の方もいない,授業としての全体練習なのである。
何の指導もせず,ただ活動させるだけならば,何もしなくても同じである。まさに「活動あって学習なし」である。
硬派な私としては,やり直しは当然の措置であった。
来週は総練習がある。私は,総練習は必要ないと思っているのだが,やるからには子どもたちに何らかの学びがあるようにしていきたい。