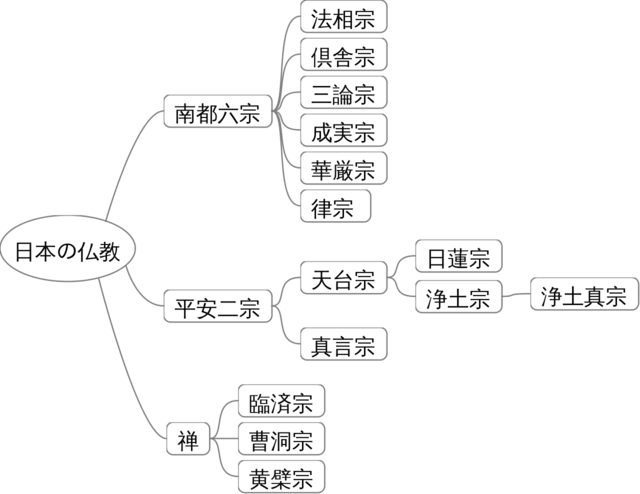『ガンジスに還る』(ガンジスにかえる、原題:Hotel Salvation / Mukti Bhawan)は、2016年に公開されたインドのコメディドラマ映画。監督・脚本はシュバシシュ・ブティアニ(英語版)、プロデューサーはサンジャイ・ブティアニが務め、ヴァーラーナシーで人生の終焉を迎えようとする父とその世話をすることになった息子を描いている。アディル・フセイン(英語版)とラリット・ベヘル(英語版)が主演を務め、2016年9月2日に第73回ヴェネツィア国際映画祭で上映され、インドでは2017年4月7日から公開された。
世界が認めた交渉の達人が、水面下の真実を語る!
交渉相手の警戒を解き真意を引き出すテクニック、決裂必至の国際会議で合意を作る根回し術、当事者全員に利がある調停の肝は、「戦わない」交渉哲学から生まれた――。コソボ軍事紛争調停からCOP10名古屋議定書採択まで、不可能を可能にした交渉・調停の達人が、知られざる国際交渉の舞台裏を生々しく伝える。日本の底力と可能性を浮き彫りにする、驚きと感動の書。
内容(「BOOK」データベースより)
交渉相手の警戒を解き真意を引き出すテクニック、決裂必至の国際会議で合意を作る根回し術、当事者全員に利がある調停の肝は、「戦わない」交渉哲学から生まれた―。コソボ軍事紛争調停からCOP10名古屋議定書採択まで、不可能を可能にした交渉・調停の達人が、知られざる国際交渉の舞台裏を生々しく伝える。日本の底力と可能性を浮き彫りにする、驚きと感動の書。
著者について
1975年大阪府生まれ。国際ネゴシエーター。(株)KS InternationalStrategies CEO、環境省参与。2000年米アマースト大学卒。2002年ジョンズ・ホプキンズ大学大学院国際学修士(紛争解決・国際経済学)。1998年より国連紛争調停官として紛争調停に携わる。2005~10年まで環境省国際調整官として日本政府代表団で環境交渉における首席交渉官や議題別議長を歴任。
2011年以降は、国内外、官民問わず交渉・調停のアドバイザーを務める
ほか、ハーバード大学やカリフォルニア大学バークレー校、オックスフォード大学の交渉プログラムに関わったり、環境・エネルギー問題や安全保障問題からみた国際情勢の解説にあたるなど多方面で活躍中。2012年世界経済フォーラム(WEF)ヤンググローバルリーダー(YGL)に選出。
著書に『最強交渉人のNOを必ずYESに変える技術』(かんき出版)。
著者略歴 (「BOOK著者紹介情報」より)
島田/久仁彦
1975年大阪府生まれ。国際ネゴシエーター。(株)KS International Strategies CEO、環境省参与。2000年米アマースト大学卒。2002年ジョンズ・ホプキンズ大学大学院国際学修士(紛争解決・国際経済学)。1998年より国連紛争調停官として紛争調停に携わる。2005~10年まで環境省国際調整官として日本政府代表団で環境交渉における首席交渉官や議題別議長を歴任。2011年以降は、国内外、官民問わず交渉・調停のアドバイザーを務めるほか、環境・エネルギー問題や安全保障問題からみた国際情勢の解説にあたる。
交渉相手の警戒を解き真意を引き出すテクニック、決裂必至の国際会議で合意を作る根回し術、当事者全員に利がある調停の肝は、「戦わない」交渉哲学から生まれた――。コソボ軍事紛争調停からCOP10名古屋議定書採択まで、不可能を可能にした交渉・調停の達人が、知られざる国際交渉の舞台裏を生々しく伝える。日本の底力と可能性を浮き彫りにする、驚きと感動の書。
内容(「BOOK」データベースより)
交渉相手の警戒を解き真意を引き出すテクニック、決裂必至の国際会議で合意を作る根回し術、当事者全員に利がある調停の肝は、「戦わない」交渉哲学から生まれた―。コソボ軍事紛争調停からCOP10名古屋議定書採択まで、不可能を可能にした交渉・調停の達人が、知られざる国際交渉の舞台裏を生々しく伝える。日本の底力と可能性を浮き彫りにする、驚きと感動の書。
著者について
1975年大阪府生まれ。国際ネゴシエーター。(株)KS InternationalStrategies CEO、環境省参与。2000年米アマースト大学卒。2002年ジョンズ・ホプキンズ大学大学院国際学修士(紛争解決・国際経済学)。1998年より国連紛争調停官として紛争調停に携わる。2005~10年まで環境省国際調整官として日本政府代表団で環境交渉における首席交渉官や議題別議長を歴任。
2011年以降は、国内外、官民問わず交渉・調停のアドバイザーを務める
ほか、ハーバード大学やカリフォルニア大学バークレー校、オックスフォード大学の交渉プログラムに関わったり、環境・エネルギー問題や安全保障問題からみた国際情勢の解説にあたるなど多方面で活躍中。2012年世界経済フォーラム(WEF)ヤンググローバルリーダー(YGL)に選出。
著書に『最強交渉人のNOを必ずYESに変える技術』(かんき出版)。
著者略歴 (「BOOK著者紹介情報」より)
島田/久仁彦
1975年大阪府生まれ。国際ネゴシエーター。(株)KS International Strategies CEO、環境省参与。2000年米アマースト大学卒。2002年ジョンズ・ホプキンズ大学大学院国際学修士(紛争解決・国際経済学)。1998年より国連紛争調停官として紛争調停に携わる。2005~10年まで環境省国際調整官として日本政府代表団で環境交渉における首席交渉官や議題別議長を歴任。2011年以降は、国内外、官民問わず交渉・調停のアドバイザーを務めるほか、環境・エネルギー問題や安全保障問題からみた国際情勢の解説にあたる。
ランキング 宗派 人数
1 浄土真宗本願寺派
(西本願寺) 792万人
2 浄土宗 602万人
3 高野山真言宗 383万人
4 曹洞宗(禅宗) 354万人
5 真宗大谷派
(東本願寺) 320万人
6 天台宗 153万人
7 法相宗 52万人
8 華厳宗 4万人
1 浄土真宗本願寺派
(西本願寺) 792万人
2 浄土宗 602万人
3 高野山真言宗 383万人
4 曹洞宗(禅宗) 354万人
5 真宗大谷派
(東本願寺) 320万人
6 天台宗 153万人
7 法相宗 52万人
8 華厳宗 4万人
2018年10月~12月の放送予定
「登山のススメ ~ 医師として、登山家として」
講師 :今井通子(医師・登山家)
「山の日」は2014年に国民の祝日(8月11日)として「山に親しむ機会を得て、山の恩恵に感謝する」ことを趣旨として制定されました。日本人にとって山は身近な存在であり、古来から山岳信仰や自然観賞、山菜やキノコ採り、渓流釣り、スキーなど、敬意や愛着を持ちながら山を大切にしてきました。一方、危険な登山に挑み続ける人も後を絶ちません。リフレッシュ・冒険心・生活の一部など、山に入る気持ちは人それぞれですが、近年では人がなぜ本能的に山へ行きたくなるのか、その理由も生物学的な見地から解き明かされてきています。
今回は、山と人の向き合い方について、西欧諸国と日本を比較しながら考えていきます。登山の歴史をひもときながら、山が人間に与える効用について、科学的な分析も含めながら、登山の魅力を伝えていきます。
出演者プロフィール
今井 通子(いまい みちこ)
1942年東京生まれ。東京女子医科大学卒業。東京農業大学客員教授。(公社)日本山岳ガイド協会副会長。兵庫県立森林大学校特任大使。13ヶ国30名の学者、科学者を率いる国際自然・森林医学界(INFOM)会長。
東京女子医科大学在学中に山岳部へ入部し、登山を始める。1967年世界初女性パーティー、マッターホルン北壁登攀に成功。1969年アイガー北壁、1971年グランドジョラス北壁と、女性で世界初の欧州三大北壁完登者となる。
1971年より始めた国内・海外トレッキングツアー講師を現在も務め、医学と登山活動などで得た知識や体験をもとに講演・執筆活動を行なっている。
著書に「山は私の学校だった」(山と渓谷社)、「マッターホルンの空中トイレ」(中公文庫)など。
NHK Eテレビで「日本仏教の歩み」再放送
竹村牧男先生のテレビが再放送になっています。 ぜひ、ご覧ください。
http://blog.canpan.info/jitou/archive/3140
こちらでご紹介しました。
言い足りなかったことを加えたいと思います。
常住の大悲
第1回で、先生は「大悲」について、繰り返し強調されました。
「初めに大悲ありき」
「常住の大悲」
すべての人の心の根底で、救済の働きが起きているのです。 常に仏性、絶対無が働いている。 一瞬一瞬、絶対的に苦、自己、世界が否定されています。自我の死、苦の消滅、救済されているのです。 そして、絶対無は、自己、世界、苦楽、様々なもの、「有」に分節します。世界の創造です。これが、悟りで自覚するありさまです。自己、世界のすべてが絶対無の現成です。
それを知らずに、苦悩します。いつも、絶対者からの救済、大悲がきているのに気がつかない。
「維摩経義疏」でも、これを次のようにいっていると、紹介されました。
「大悲やむときなし」
「衆生の在る所至らずという所なし」
すべての人の根底にあるのです。このブログをご覧になっているあなたにもです。常に、自己の根底で世界の否定と世界の創造が繰り返されている。自己は絶対と一つである。 西田幾多郎博士は、自己は創造的世界の創造的要素といいます。
禅僧はこれを自覚するために修行したのです。坐禅や念仏がありました。ただ、公案や坐禅をもちいる方法は在家には不利ですので、西田幾多郎博士は、別の方法を期待しました。独断を捨てて見、独断を捨てて考え、独断を捨てて働く(行為する)と、自覚できるとされました。
私たちは、出家ではないので、家族の中で職場で、これを実践していかねばなりません。現代の日本的マインドフルネスです。意志作用のマインドフルネスを実践し、さらに行為的直観を実践していく。家族の中、職場で、独断を捨てて見、独断を捨てて考え、独断を捨てて行為する(これを西田博士は「至誠」という。竹村先生も日本仏教に至誠心があったことを浮き彫りにしておられます)生活を送る。そうすると、絶対無、絶対有の現成の体験が起きる。すると、意識的自己が消えて、絶対と一つの自覚を得て、社会のために働く、それを西田哲学では、創造的直観といいます。
竹村牧男先生は、この6回でいつも、この根底の核心から説明していかれます。実践は、世界の立場からですから「至誠」です。自己の独断でない立場、広く深い立場から見、考え、行為する。 無評価とは違います。
西田博士は、従来のもの(公案、坐禅)は、家庭、職場のただなかで、活用されないので現代人向きでないと批判しました。聖徳太子が、静かなところで坐禅するのを批判したのと類似する問題点です。大切なことは、形でなく内面でしょう。独断を捨てて見、独断を捨てて考え、独断を捨てて行為すること。すると根底にあるものが働くわけです。いつか、自己の根底に働く大悲の現場に遭遇するのです。マインドフルネスは「正念」「観察」「気づき」です。感覚、動作だけでなく、社会貢献できる価値、そして、自己、他者、社会を傷つける独断、偏見も観察します。
この竹村先生のテレビ放送はすべての仏教者、仏教学者、マインドフルネス者が見て、深く検討してほしいと思います。
竹村牧男先生のテレビが再放送になっています。 ぜひ、ご覧ください。
http://blog.canpan.info/jitou/archive/3140
こちらでご紹介しました。
言い足りなかったことを加えたいと思います。
常住の大悲
第1回で、先生は「大悲」について、繰り返し強調されました。
「初めに大悲ありき」
「常住の大悲」
すべての人の心の根底で、救済の働きが起きているのです。 常に仏性、絶対無が働いている。 一瞬一瞬、絶対的に苦、自己、世界が否定されています。自我の死、苦の消滅、救済されているのです。 そして、絶対無は、自己、世界、苦楽、様々なもの、「有」に分節します。世界の創造です。これが、悟りで自覚するありさまです。自己、世界のすべてが絶対無の現成です。
それを知らずに、苦悩します。いつも、絶対者からの救済、大悲がきているのに気がつかない。
「維摩経義疏」でも、これを次のようにいっていると、紹介されました。
「大悲やむときなし」
「衆生の在る所至らずという所なし」
すべての人の根底にあるのです。このブログをご覧になっているあなたにもです。常に、自己の根底で世界の否定と世界の創造が繰り返されている。自己は絶対と一つである。 西田幾多郎博士は、自己は創造的世界の創造的要素といいます。
禅僧はこれを自覚するために修行したのです。坐禅や念仏がありました。ただ、公案や坐禅をもちいる方法は在家には不利ですので、西田幾多郎博士は、別の方法を期待しました。独断を捨てて見、独断を捨てて考え、独断を捨てて働く(行為する)と、自覚できるとされました。
私たちは、出家ではないので、家族の中で職場で、これを実践していかねばなりません。現代の日本的マインドフルネスです。意志作用のマインドフルネスを実践し、さらに行為的直観を実践していく。家族の中、職場で、独断を捨てて見、独断を捨てて考え、独断を捨てて行為する(これを西田博士は「至誠」という。竹村先生も日本仏教に至誠心があったことを浮き彫りにしておられます)生活を送る。そうすると、絶対無、絶対有の現成の体験が起きる。すると、意識的自己が消えて、絶対と一つの自覚を得て、社会のために働く、それを西田哲学では、創造的直観といいます。
竹村牧男先生は、この6回でいつも、この根底の核心から説明していかれます。実践は、世界の立場からですから「至誠」です。自己の独断でない立場、広く深い立場から見、考え、行為する。 無評価とは違います。
西田博士は、従来のもの(公案、坐禅)は、家庭、職場のただなかで、活用されないので現代人向きでないと批判しました。聖徳太子が、静かなところで坐禅するのを批判したのと類似する問題点です。大切なことは、形でなく内面でしょう。独断を捨てて見、独断を捨てて考え、独断を捨てて行為すること。すると根底にあるものが働くわけです。いつか、自己の根底に働く大悲の現場に遭遇するのです。マインドフルネスは「正念」「観察」「気づき」です。感覚、動作だけでなく、社会貢献できる価値、そして、自己、他者、社会を傷つける独断、偏見も観察します。
この竹村先生のテレビ放送はすべての仏教者、仏教学者、マインドフルネス者が見て、深く検討してほしいと思います。
Windows95発売
1995年11月23日日本語版Windows95が発売されました。それまでMS-DOSとは別製品として追加で購入していたWindowsが統合されて発売されました。発売日に大々的にキャンペーンが行われて、秋葉原などでは午前0時に発売したために、インパクトが大きく、デファクトスタンダードを握ることとなりました。
Windows95では、それまでサードパーティ製品に頼っていたネットワーク機能を標準で装備しました。特に、インターネットに接続するためのプロトコルTCP/IPとWebブラウザとしてInternet Explorerを標準で(初期バージョンではMicrosoft Plus! による拡張機能)搭載したことで、インターネットに接続するためのOSとしても普及しました。
Windows95ではMS-DOSのコマンドを入力しなくても起動するようになりましたが、内部的にはあくまでもMS-DOS上でWindowsを稼働させていました。Windows95ではウィンドウの1つとしてのコマンドプロンプト以外に、MS-DOSそのものを稼働させることも可能でした。Windows95はその後、Windows98、Windows98 SE(Second Edition)、Windows Me(Millennium Edition)と改良されてきました。これらはWindows95と同様にMS-DOSベースのWindowsで、Windows9X系と呼ばれていました。
1995年11月23日日本語版Windows95が発売されました。それまでMS-DOSとは別製品として追加で購入していたWindowsが統合されて発売されました。発売日に大々的にキャンペーンが行われて、秋葉原などでは午前0時に発売したために、インパクトが大きく、デファクトスタンダードを握ることとなりました。
Windows95では、それまでサードパーティ製品に頼っていたネットワーク機能を標準で装備しました。特に、インターネットに接続するためのプロトコルTCP/IPとWebブラウザとしてInternet Explorerを標準で(初期バージョンではMicrosoft Plus! による拡張機能)搭載したことで、インターネットに接続するためのOSとしても普及しました。
Windows95ではMS-DOSのコマンドを入力しなくても起動するようになりましたが、内部的にはあくまでもMS-DOS上でWindowsを稼働させていました。Windows95ではウィンドウの1つとしてのコマンドプロンプト以外に、MS-DOSそのものを稼働させることも可能でした。Windows95はその後、Windows98、Windows98 SE(Second Edition)、Windows Me(Millennium Edition)と改良されてきました。これらはWindows95と同様にMS-DOSベースのWindowsで、Windows9X系と呼ばれていました。
諸仏の王 阿弥陀如来
仏(如来) 釈迦如来(お釈迦様)
大日如来
薬師如来
ビルシャナ如来 等
菩薩 観音菩薩
勢至菩薩
弥勒菩薩
地蔵菩薩
文殊菩薩
普賢菩薩 等
神 梵天
帝釈天
多聞天
持国天
増長天
広目天 等
『西遊記』(さいゆうき、繁体字: 西遊記; 簡体字: 西游记; ピン音: Xī Yóu Jì; ウェード式: Hsi-yu chi; 粤拼: sai¹ jau⁴ gei³、タイ語: ไซอิ๋ว、ベトナム語: Tây du ký)は、中国で16世紀の明の時代に大成した伝奇小説で、唐僧・三蔵法師が白馬・玉龍に乗って三神仙(神通力を持った仙人)、孫悟空、猪八戒、沙悟浄を供に従え、幾多の苦難を乗り越え天竺へ取経を目指す物語、全100回。中国四大奇書に数えられる。 著者は、『淮安府史』(明、天啓年間成立)に、呉承恩(1504年頃 - 1582年頃、江蘇省出身)の著書として「西遊記」という書名が記述されていることから、彼が作者であると20世紀の中国では定説化していたが、後述のように批判的な説が存在し、明確な結論は出ていない。詳しくは後述。
「西遊記」でおなじみの三蔵法師を、岡田准一がプロファイル!▽その実像は世界一タフな僧侶だった!唐から天竺へ往復6万キロの旅をし、未知の経典を持ち帰った玄奘三蔵。前人未到の旅を実現した秘密は、シルクロードの砂漠を乗り越える体力と、さまざまな言語を習得し、現地の王や学者を魅了する頭脳だった。▽さらに唐の皇帝をも取り込み、経典の翻訳をはじめ都に仏教の一大拠点を作り上げた玄奘。彼は最後に何を目指したのか?
【司会】岡田准一,【ゲスト】中嶋朋子,夢枕獏,はあちゅう
「西遊記」でおなじみの三蔵法師を、岡田准一がプロファイル!▽その実像は世界一タフな僧侶だった!唐から天竺へ往復6万キロの旅をし、未知の経典を持ち帰った玄奘三蔵。前人未到の旅を実現した秘密は、シルクロードの砂漠を乗り越える体力と、さまざまな言語を習得し、現地の王や学者を魅了する頭脳だった。▽さらに唐の皇帝をも取り込み、経典の翻訳をはじめ都に仏教の一大拠点を作り上げた玄奘。彼は最後に何を目指したのか?
【司会】岡田准一,【ゲスト】中嶋朋子,夢枕獏,はあちゅう
「声でつづる昭和人物史~平塚らいてう」
「朝の訪問」(1954(昭和29)年2月8日放送)聞き手・小沢寅三アナウンサー ノンフィクション作家・評論家…保阪正康,【司会】宇田川清江
4回にわたり婦人運動家を取り上げます。第1回は女性思想家で婦人運動の先駆者として知られる平塚らいてうです。明治44年(1911)、平塚らいてうが中心となって発刊した文芸誌『青鞜』での言葉「元始、女性は太陽であった」はあまりにも有名です。今回は1954年放送の「朝の訪問」を紹介、「らいてう」という名前の由来、「青鞜」を創刊した経緯、女性の地位向上を目指し活動してきた婦人運動などについて語っています。
「私の自叙伝~婦人運動50年」(1961(昭和36)年9月4日放送) ノンフィクション作家・評論家…保阪正康,【司会】宇田川清江
第2回は、婦人運動家の神近市子です。神近市子は津田塾在学中に『青鞜社』に傾倒、その後、女学校教師を経て新聞記者になります。三角関係のもつれから大杉栄刺殺事件を起こし服役。戦後、65歳で衆議院議員選挙に出馬し当選、売春防止法の成立などに尽力します。今回は1961年放送「私の自叙伝~婦人運動50年」から「青鞜社」との関わり、毎日新聞社での記者時代、大杉栄との出会い、婦人運動の流れなどを語っています。
「教養特集・日本回顧録~婦人参政運動のあゆみ」(1)聞き手・古谷綱正(1962(昭和37)年4月9日放送)
2回にわたり婦人運動家の市川房枝を取り上げます。市川房枝は女子師範学校を卒業。小学校教師を経て新聞記者になり26歳の時に平塚らいてう等と「新婦人協会」を創立し婦人解放運動を始めます。28歳で渡米し帰国後「婦人参政権獲得期成同盟会」の創立に参加します。今回は1962年放送「教養特集・日本回顧録~婦人参政権運動のあゆみ」から婦人解放運動を始めた経緯、女性の参政権を得るための活動の様子を語っています。
「教養特集・日本回顧録~婦人参政運動のあゆみ」(2)聞き手・古谷綱正(1962(昭和37)年4月9日放送)
婦人運動家・市川房枝の2回目。1925年「普通選挙法」が成立し女性参政権に向け1930年「第一回婦選大会」が開かれます。与謝野晶子作詞の「婦選の歌」が披露されるなど機運は高まります。しかし、戦争の足音と共に運動は消沈し女性の参政権は結局、戦後となります。今回は1962年放送「教養特集・日本回顧録~婦人参政権運動のあゆみ」を紹介、女性の参政権に奔走した昭和初期から参政権を得た戦後までを語ります。
2018年4月15日放送「シリーズ マンダラと生きる 第1回 なぜマンダラか」
マンダラとは、密教が世界や心の構造に関する最高の真理を、言葉や文字ではなく、視覚を通して伝えるために開発した図像だ。その特徴は幾何学的な構成や強い対象性。日本では1200年ほど前に空海が留学先の唐から持ち帰って以来、独特の展開を遂げてきた。一方で、密教のマンダラとは縁がない地域にもマンダラに似た図像が存在する。これはマンダラ型の図像が人類に共通する深い精神性と無縁ではないことを示唆しているという。
【出演】正木晃(宗教学者)【きき手】渡邊あゆみアナウンサー
2018年5月20日放送「シリーズ マンダラと生きる 第2回 密教のなりたち マンダラ誕生の背景」
仏教の伝来から250年あまりが経った9世紀初め、日本に新たなタイプの仏教、密教が伝わった。この密教こそがマンダラの生みの親。日本における密教の第一人者、弘法大師・空海は、当時の日本人にとって新しい儀礼「護摩」を取り入れた。所願の成就を願う護摩で修行者はいくつもの象徴(シンボル)を駆使して、仏と一体となることを目指す。そこでは何が行われているのか。密教とマンダラの関係の一つ、瞑想についても考える。
2018年6月17日放送「シリーズ マンダラと生きる 第3回 世界とつながる 胎蔵マンダラの叡智」
胎蔵マンダラは、空海が唐から持ち帰った最も重要なマンダラのひとつ。密教の本尊・大日如来の広大無辺の慈悲を説く。描かれているのは、ほとけばかりでなく、地獄に住む鬼や異教であるヒンドゥー教の神々の姿も。あらゆる存在を等しく尊いとみる革新的な世界観を提示している。さらに、胎蔵マンダラには星や星座などの天体も描かれている。自然と人間はどう関わってゆくべきか、そこに込められた現代的なメッセージも読み解く。
2018年7月15日放送「シリーズ マンダラと生きる 第4回 心をきわめる 金剛界マンダラの世界」
金剛界マンダラは、弘法大師・空海が唐から持ち帰った最も重要なマンダラのひとつ。この身このままで悟りに至る“即身成仏”のための道を説く。密教が考える悟りは、本尊である大日如来と自らが、本質的に同じであるという実感を持つこと。金剛界マンダラには、その実感を得るための瞑想法があらわされている。強い自己肯定感と他者への慈しみにもつながるという、その深遠な教えの世界を読み解く。
2018年8月19日放送「シリーズ マンダラと生きる 第5回 むすびつけるということ 両部マンダラの革新」
日本では、胎蔵マンダラと金剛界マンダラという2つのマンダラが、教えの根幹として伝承されてきた。胎蔵マンダラは、利他行と慈悲の心。金剛界マンダラは、悟りへの修行法を説く。大きく性格の異なる2つのマンダラを結びつけたのは、空海の師・恵果和尚。恵果は、マンダラを空海に託し、人々の幸福に役立てるよう説いたという。その後の空海の人生を大きく変えた2つのマンダラ。空海の行動をもとに、その智慧をひもとく。
2018年9月16日放送「シリーズ マンダラと生きる 第6回 マンダラと日本人 わたしたちはどう生きるべきか」
平安時代に空海によってもたらされたマンダラは、その後、日本独自の変化を遂げていく。ほとけの姿よりも、寺社を取り巻く山々の姿が大きく描かれた「宮曼荼羅」、熊野や那智、伊勢などの霊地へ参る人々の姿を描いた「参詣曼荼羅」など。そこには、日本人の自然観や神仏習合の考え方が色濃く投影されている。日本人は何を考えてきたのか、これからどう生きていけばよいのか。最終回は、マンダラの現代的なメッセージを読み解く。
マンダラとは、密教が世界や心の構造に関する最高の真理を、言葉や文字ではなく、視覚を通して伝えるために開発した図像だ。その特徴は幾何学的な構成や強い対象性。日本では1200年ほど前に空海が留学先の唐から持ち帰って以来、独特の展開を遂げてきた。一方で、密教のマンダラとは縁がない地域にもマンダラに似た図像が存在する。これはマンダラ型の図像が人類に共通する深い精神性と無縁ではないことを示唆しているという。
【出演】正木晃(宗教学者)【きき手】渡邊あゆみアナウンサー
2018年5月20日放送「シリーズ マンダラと生きる 第2回 密教のなりたち マンダラ誕生の背景」
仏教の伝来から250年あまりが経った9世紀初め、日本に新たなタイプの仏教、密教が伝わった。この密教こそがマンダラの生みの親。日本における密教の第一人者、弘法大師・空海は、当時の日本人にとって新しい儀礼「護摩」を取り入れた。所願の成就を願う護摩で修行者はいくつもの象徴(シンボル)を駆使して、仏と一体となることを目指す。そこでは何が行われているのか。密教とマンダラの関係の一つ、瞑想についても考える。
2018年6月17日放送「シリーズ マンダラと生きる 第3回 世界とつながる 胎蔵マンダラの叡智」
胎蔵マンダラは、空海が唐から持ち帰った最も重要なマンダラのひとつ。密教の本尊・大日如来の広大無辺の慈悲を説く。描かれているのは、ほとけばかりでなく、地獄に住む鬼や異教であるヒンドゥー教の神々の姿も。あらゆる存在を等しく尊いとみる革新的な世界観を提示している。さらに、胎蔵マンダラには星や星座などの天体も描かれている。自然と人間はどう関わってゆくべきか、そこに込められた現代的なメッセージも読み解く。
2018年7月15日放送「シリーズ マンダラと生きる 第4回 心をきわめる 金剛界マンダラの世界」
金剛界マンダラは、弘法大師・空海が唐から持ち帰った最も重要なマンダラのひとつ。この身このままで悟りに至る“即身成仏”のための道を説く。密教が考える悟りは、本尊である大日如来と自らが、本質的に同じであるという実感を持つこと。金剛界マンダラには、その実感を得るための瞑想法があらわされている。強い自己肯定感と他者への慈しみにもつながるという、その深遠な教えの世界を読み解く。
2018年8月19日放送「シリーズ マンダラと生きる 第5回 むすびつけるということ 両部マンダラの革新」
日本では、胎蔵マンダラと金剛界マンダラという2つのマンダラが、教えの根幹として伝承されてきた。胎蔵マンダラは、利他行と慈悲の心。金剛界マンダラは、悟りへの修行法を説く。大きく性格の異なる2つのマンダラを結びつけたのは、空海の師・恵果和尚。恵果は、マンダラを空海に託し、人々の幸福に役立てるよう説いたという。その後の空海の人生を大きく変えた2つのマンダラ。空海の行動をもとに、その智慧をひもとく。
2018年9月16日放送「シリーズ マンダラと生きる 第6回 マンダラと日本人 わたしたちはどう生きるべきか」
平安時代に空海によってもたらされたマンダラは、その後、日本独自の変化を遂げていく。ほとけの姿よりも、寺社を取り巻く山々の姿が大きく描かれた「宮曼荼羅」、熊野や那智、伊勢などの霊地へ参る人々の姿を描いた「参詣曼荼羅」など。そこには、日本人の自然観や神仏習合の考え方が色濃く投影されている。日本人は何を考えてきたのか、これからどう生きていけばよいのか。最終回は、マンダラの現代的なメッセージを読み解く。
イスラエル、パレスチナの双方に多くの人脈と知人を持ち、パレスチナ問題を取材し続けている。チェルノブイリを事故以来25年以上に渡って取材し、また救援活動を行っている。福島第一原発事故の後は、主に日本の原発や放射能に関する諸問題を取材するかたわら、福島の子どもの救援活動を行っている。福島の子ども保養プロジェクト「NPO法人 沖縄・球美の里」理事長。
日本中東学会、日本写真家協会、日本写真協会、日本ビジュアル・ジャーナリスト協会(JVJA)、各会員。 パレスチナの子供の里親運動顧問、チェルノブイリ子ども基金・元代表。
日本中東学会、日本写真家協会、日本写真協会、日本ビジュアル・ジャーナリスト協会(JVJA)、各会員。 パレスチナの子供の里親運動顧問、チェルノブイリ子ども基金・元代表。
当初は中国原産と考えられていたが、現在はビロードアオイ属(Althaea)のトルコ原産種と東ヨーロッパ原産種との雑種(Althaea setosa ×Althaea pallida)とする説が有力である。
日本には、古くから薬用として渡来したといわれている。
花がきれいなので、園芸用に様々な品種改良がなされた。草丈は1~3mで茎は直立する。花期は6~8月で、花は垂直に伸びた花茎の下から上に咲き上っていく。ちょうど梅雨入りの頃に咲き始め、梅雨明けと共に花期が終わる(花茎の頭頂部まで開花が進む)ことになぞらえて、「ツユアオイ(梅雨葵)」という別名も冠されている。花は一重や八重のもあり、色は赤、ピンク、白、紫、黄色など多彩である。花の直径は品種によるが大きなものでは10cmくらいである。本来は宿根性の多年草であるが、品種によっては一年草でもある。アオイの名から会津若松市と静岡市が市花に制定している。
花弁の根元が粘着質であり、引き抜いた花弁を顔などに付けてニワトリを真似て遊ぶことができるため、北海道の一部ではコケコッコ花、コケコッコー花青森県の一部では"コケラッコ花"などと呼ばれる。
花弁や根を、薬用として利用する。
日本には、古くから薬用として渡来したといわれている。
花がきれいなので、園芸用に様々な品種改良がなされた。草丈は1~3mで茎は直立する。花期は6~8月で、花は垂直に伸びた花茎の下から上に咲き上っていく。ちょうど梅雨入りの頃に咲き始め、梅雨明けと共に花期が終わる(花茎の頭頂部まで開花が進む)ことになぞらえて、「ツユアオイ(梅雨葵)」という別名も冠されている。花は一重や八重のもあり、色は赤、ピンク、白、紫、黄色など多彩である。花の直径は品種によるが大きなものでは10cmくらいである。本来は宿根性の多年草であるが、品種によっては一年草でもある。アオイの名から会津若松市と静岡市が市花に制定している。
花弁の根元が粘着質であり、引き抜いた花弁を顔などに付けてニワトリを真似て遊ぶことができるため、北海道の一部ではコケコッコ花、コケコッコー花青森県の一部では"コケラッコ花"などと呼ばれる。
花弁や根を、薬用として利用する。
知里 幸恵(ちり ゆきえ、1903年(明治36年)6月8日 - 1922年(大正11年)9月18日)は、北海道登別市出身のアイヌ人女性。19年という短い生涯ではあったが、その著書『アイヌ神謡集』の出版が、絶滅の危機に追い込まれていたアイヌ民族・アイヌ伝統文化の復権復活へ重大な転機をもたらしたことで知られる。
近年、マスコミや各地のセミナー等でその再評価の声が高まっており、また幸恵への感謝から「知里幸恵」記念館の建設運動が活発化している。2008年10月には、NHKの『その時歴史が動いた』で幸恵が詳細に取り上げられ[要出典]、インターネット書店「アマゾン」の「本のベストセラー」トップ10に『アイヌ神謡集』が入った。また、『アイヌ神謡集』は、フランス語・英語・ロシア語にも翻訳されており、2006年1月には、フランス人作家ル・クレジオが、そのフランス語版の出版報告に幸恵の墓を訪れている。
なお、弟に言語学者でアイヌ人初の北海道大学教授となった知里真志保がおり、幸恵の『アイヌ神謡集』の出版以降、大正末期から昭和にかけて、新聞・雑誌などからはこの姉弟を世俗的表現ながらも「アイヌの天才姉弟」と評された。他の弟の知里高央(真志保の長兄)も、教師をつとめながらちりアイヌ語の語彙研究に従事した。
アイヌ問題については、問題とは、事情が異なります。
まず、そもそもアイヌとは、北海道や樺太(からふと、)(= サハリン)、千島列島の先住民族のことです。
アイヌは、日本とは異なる、独自の言語や独自の文化を持っていました。
明治時代に、北海道は日本に併合されました。その結果、アイヌ民族も正式に日本に支配されることになったので、日本政府はアイヌ民族に対して、日本文化への同化政策を押し進めたので、アイヌ民族の固有の文化が否定されました。また、北海道の開拓にともない、アイヌの土地がうばわれたので、貧困におちいるアイヌ人も増えました。また、併合前のアイヌの生計は狩猟や漁労などで生計を立てていましたが、開拓にともない、農耕などに強制的に生業を変えさせ、また併合後に狩猟などが規制されたので、アイヌが生活の場を失い、貧困におちいりました。
第二次大戦後、このような同化政策がしだいに批判されます。そして1997年にはアイヌ文化振興法されました。また、2008年には国会で「アイヌ民族を先住民とすることを求める決議」によって、アイヌ民族を日本の先住民族の一つだと認めることが日本の国会で正式に認められました。
なお、この2008年の決議の背景として、2007年に国連総会で「先住民族の権利に関する国際連合宣言」が採択されたことも受けています。
近年、マスコミや各地のセミナー等でその再評価の声が高まっており、また幸恵への感謝から「知里幸恵」記念館の建設運動が活発化している。2008年10月には、NHKの『その時歴史が動いた』で幸恵が詳細に取り上げられ[要出典]、インターネット書店「アマゾン」の「本のベストセラー」トップ10に『アイヌ神謡集』が入った。また、『アイヌ神謡集』は、フランス語・英語・ロシア語にも翻訳されており、2006年1月には、フランス人作家ル・クレジオが、そのフランス語版の出版報告に幸恵の墓を訪れている。
なお、弟に言語学者でアイヌ人初の北海道大学教授となった知里真志保がおり、幸恵の『アイヌ神謡集』の出版以降、大正末期から昭和にかけて、新聞・雑誌などからはこの姉弟を世俗的表現ながらも「アイヌの天才姉弟」と評された。他の弟の知里高央(真志保の長兄)も、教師をつとめながらちりアイヌ語の語彙研究に従事した。
アイヌ問題については、問題とは、事情が異なります。
まず、そもそもアイヌとは、北海道や樺太(からふと、)(= サハリン)、千島列島の先住民族のことです。
アイヌは、日本とは異なる、独自の言語や独自の文化を持っていました。
明治時代に、北海道は日本に併合されました。その結果、アイヌ民族も正式に日本に支配されることになったので、日本政府はアイヌ民族に対して、日本文化への同化政策を押し進めたので、アイヌ民族の固有の文化が否定されました。また、北海道の開拓にともない、アイヌの土地がうばわれたので、貧困におちいるアイヌ人も増えました。また、併合前のアイヌの生計は狩猟や漁労などで生計を立てていましたが、開拓にともない、農耕などに強制的に生業を変えさせ、また併合後に狩猟などが規制されたので、アイヌが生活の場を失い、貧困におちいりました。
第二次大戦後、このような同化政策がしだいに批判されます。そして1997年にはアイヌ文化振興法されました。また、2008年には国会で「アイヌ民族を先住民とすることを求める決議」によって、アイヌ民族を日本の先住民族の一つだと認めることが日本の国会で正式に認められました。
なお、この2008年の決議の背景として、2007年に国連総会で「先住民族の権利に関する国際連合宣言」が採択されたことも受けています。
「私の自叙伝」(1)(1961(昭和36)年12月1日放送) ノンフィクション作家・評論家…保阪正康,【司会】宇田川清江
10月は「北海道命名150年」にちなみ、ゆかりの人物・金田一京助と三浦綾子を取り上げます。第1回は1961年12月放送「私の自叙伝」から言語学者の金田一京助(1882-1971)です。自身の生い立ちから、中高時代、生涯の友となる石川啄木との出会いとその後の交流、東京帝国大学に入学しアイヌ語を研究するきっかけとなった恩師の言葉、アイヌ語の研究のために初めて北海道を訪ねた時の様子などを語っています。
「私の自叙伝」(2)(1961(昭和36)年12月1日放送) ノンフィクション作家・評論家…保阪正康,【司会】宇田川清江
1961年放送「私の自叙伝」から言語学者・金田一京助の2回目です。石川啄木が死んだ年に父も亡くなったこと、父の死の悲しみを乗り越えアイヌ語研究に一層の情熱を注いだこと、勤め先が倒産し無収入になり生活に困ったがかえってその時間をアイヌの研究にあて、ユーカラの研究で日本学士院の恩賜賞を受けたこと、ユーカラの名人を訪ねた際にそこの養女、知里幸恵との出会いとその早すぎる死などを思いをこめて語っています。
10月は「北海道命名150年」にちなみ、ゆかりの人物・金田一京助と三浦綾子を取り上げます。第1回は1961年12月放送「私の自叙伝」から言語学者の金田一京助(1882-1971)です。自身の生い立ちから、中高時代、生涯の友となる石川啄木との出会いとその後の交流、東京帝国大学に入学しアイヌ語を研究するきっかけとなった恩師の言葉、アイヌ語の研究のために初めて北海道を訪ねた時の様子などを語っています。
「私の自叙伝」(2)(1961(昭和36)年12月1日放送) ノンフィクション作家・評論家…保阪正康,【司会】宇田川清江
1961年放送「私の自叙伝」から言語学者・金田一京助の2回目です。石川啄木が死んだ年に父も亡くなったこと、父の死の悲しみを乗り越えアイヌ語研究に一層の情熱を注いだこと、勤め先が倒産し無収入になり生活に困ったがかえってその時間をアイヌの研究にあて、ユーカラの研究で日本学士院の恩賜賞を受けたこと、ユーカラの名人を訪ねた際にそこの養女、知里幸恵との出会いとその早すぎる死などを思いをこめて語っています。
「自作を語る ベストセラーからの出発・氷点」(1)聞き手・小林篤子ディレクター(1986(昭和61)年7月27日放送)
今月は「北海道命名150年」にちなみ北海道ゆかりの人物を紹介。2回にわたり作家・三浦綾子(1922-1999)を取り上げます。旭川出身で高等女学校卒業後、小学校教員を7年勤め退職。その後13年間の闘病生活の間にキリスト教に目覚めます。1963年、朝日新聞主催の懸賞小説に応募し「氷点」が入選。今回は1986年放送「自作を語る~ベストセラーからの出発・氷点」から、小説誕生の背景や経緯を語っています。
「自作を語る ベストセラーからの出発・氷点」(2)聞き手・小林篤子ディレクター(1986(昭和61)年7月27日放送)
作家・三浦綾子(1922-1999)の2回目。1963年、朝日新聞主催の一千万円懸賞小説に入選した『氷点』は生まれて初めて書いた長編小説でした。ストーリーは一晩で出来たとのことです。今回は1986年に放送した「自作を語る~ベストセラーからの出発・氷点」から、入選した時の喜び、「氷点」のテーマである「原罪」について、また小説を書く際の夫・光世さんとの奮闘ぶりなどを語っています。