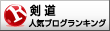〇将棋について。
私は碁や将棋は余りやりませんが、時々高段者の対局を新聞紙上で興味をもって見ています。
その中でサンケイ新聞の社会部山口昭記者の「盤上に人生を見た」と題した神谷五段(26才)と米長九段(44才)との将棋対局を観戦した記事に「息が詰まるような濃密な空気に包まれ、二人の男の知力、気力が火花を散らす、その気迫には終始圧倒された」と、そして又、「棋は対話なりという。盤上の一手一手が棋士の思想感情を何よりも雄弁に物語り、対局中の棋士はお互い、ほとんど言葉を交わさない。」中略「勝負に集中した棋士は無意識のうちに、さまざまなくせを見せる」引退した升田幸三九段は、煙草に火をつけては、すぐもみ消し、灰皿に花びらのように並べ、石田和雄八段は扇子で頭をたたき続け、一局でボロボロにしてしまう」中略「随分長時間たってから神谷五段は怖いような顔付きで盤上をにらんでいる。耳が真っ赤に染まっている。『ウン』とうなずいて、7・九銀を打ち込み、米長九段の顔をチラリと見たあと手洗いに立った。残った米長九段は険しい表情で考え込む。実はこの場面が神谷五段が勝ちを決めた瞬間だったという。中原誠名人は勝ちを読みきると手洗いに立つ。「もうあきらめなさい」という意思表示で対局相手はこれで負けを悟らされるという。「参りましたね」午後4時41分、米長九段が投了した。八十手だった。表情を崩す神谷五段、幾多の修羅場をくぐってきた米長九段は悔しげな気配を表には出さなかった。「指せると思ったが・・・」「7・九銀で勝ちが見えました」駒を並べ直して、指し手を振り返る感想戦、以下省略
さて皆さん、この将棋の無声の気当たりが、一刀流の真剣そのもので、互いに先の先まで読み合って、長考一番、静寂を破って神谷五段が「パチン」と打った最後の一手に、私は一刀流の切落を見た感があり、又それまでに相手の心を読むところ、「拳の払」の組太刀の読心術を思い浮かべます。よく心、自体を養い、技、自体を磨いて相手の打ち間を知る読心術で最後は調子よく美しく上品に勝つのです。ただ勝たんがため、相手の人格を無視してまで勝とうとするのは、たとえ勝ったとしても相手に人格で負けていることを悟らなければなりません。碁でも「碁は勝とうとして打つな、負けじと打て、勝とうとするのは義を害す」と言われています。われわれ剣道を修行する者、心すべきことであります。
〇証文を書く時、依而件(よってくだん)の如し。と書きますが、国語の解釈では、前文の通り。即ち件(くだん)=くだりの音使から来たものですが、古くから伝わっている話では、くだんとは、体が牛で顔が人間という妖怪動物で、絶対あとへは引かない。即ち、いったん証書を書いた限り、うそ、いつわりはない。書いた限り、絶対あとへは引かないという深い意味が含まれているのです。こういう古い話を後進に伝えていきましょう。
〇少年剣道の錬成試合で試合をやる前に代表者が、宣誓する言葉に「私達選手一同は、本大会の趣旨に則り、正々堂々と戦うことを誓います」と言っていますが、この狭い日本の国の中で、お互いに戦って、どうするんだと言いたい。今、世界の中で日本はどうあるべきか、という時代に、この小さい国の日本民族同志で勝ち負けを争って、よろこんでいる時代ではありません。正々堂々と試合(試し合う)或いは演武することを誓いますというように(続く)