○『ラストグラディエーターズ』を探して
古いゲーム批評を押入れから出して読んでいると、その中で「注目メーカー全特集」と言う記事ありました。特集されているメーカーの中で一際目立っていたメーカーが、ある意味で今は亡きKAZeです。当時から、そして今でもまったく持ってピンボールゲームに意義を見出せていなかったぼくもインタビュー記事を読んで初めてピンボールゲームに、というかKAZeの一連のデジタルピンボールに惹かれてしまいました。
と言うことで、KAZeの一連の作品、具体的には『ラストグラディエーターズ』、『ネクロノミコン』と『パワーレンジャー ピンボール』を探しに行きました。『ラストグラディエーターズver9.7』はともかく、この3作品とも特にレアソフトと言うことも無く高くても1000円以下で購入が可能なソフトであるようなので、容易に買えるだろうと高をくくってゲームショップに向かいました。向かいましたが…
結論から言えば、サターンのソフトを取り扱っているゲームショップが圧倒的に減ってしまっている現状に愕然としました。次世代ゲーム機の浸透や売れ線である任天堂ゲーム機のために棚を空けるということもあるのでしょうが、やはりPSE法の施行がボディブロウのように効いてきている印象です。後にゲーム機などは適用除外されましたが、時既に遅しというか棚撤去の背中を押した格好になっているようです。
○中古レトロゲームの現状
サターンの取り扱いが減っているのを尻目に、ファミコンやスーパーファミコン、プレイステーションといった”勝ち組”ハードは古かろうとも棚が存続されたりしていました。またゲームキューブやゲームボーイアドバンスなど(ここにはプレイステーションも含まれますが)現行機種で下位互換が実現されている機種もまたその棚を大きくとは言わないまでもそれなりの規模で未だ残していました。
問題はサターンをはじめとした過去のハード戦争で敗れ去っていった所謂”負け組”ハードです。ファミコン、スーパーファミコンに敗れ去ったメガドライブ、メガCD、PCエンジン、CD-ROM2そしてネオジオ。プレイステーションに僅差で負けたセガサターン。(不思議なのは負けたはずのニンテンドー64は棚を残していたりすることです。)プレイステーション2に勝てなかったドリームキャストやXBOXがそれです。
○ようやく見つけるも
そして何軒か回ってようやく『ラストグラディエーターズ』を一部店舗で展開されていると言うゲオのレトロゲーム100円均一セールのワゴンの中に見つけることが出来ました。『ラストグラディエーターズ』の他に気になってはいたものの食指は伸びなかったソフトを数本一緒に購入。探していたソフトを見つけることができ、100円で買えたのは嬉しかったのですが、一方で100円は投売りと言うことです。
ゲオの100円均一ワゴンにはメガドライブ、PCエンジン、セガサターン、ネオジオ、ワンダースワン、ドリームキャストの6機種のゲームが入っていました。そしてそのワゴンには「(上記6機種について)12月12日(土)を持ちまして、買取を終了させていただきます」といった趣旨のポップが添えられていました。投げ売られているということはそういうことだとは思いましたが、買取の終了は取り扱いの終了を意味します。
○ゲームのアーカイブス化と中古ゲーム
映画はDVD化ということでよほどのマニアックな作品以外は古い作品も現在でも観る事が可能です。小説も文庫化などされて100年以上前の作品が未だに流通し、容易にアクセス出来ます。ゲームも昨今ようやくWiiを中心に過去のハードのソフトも遊べるようになってきていますが、比較的アーキテクチャが複雑といわれるセガサターンやアーキテクチャを公開したため、個々に複雑化したPS2など難しいものもあります。
立命館大学などで全機種エミュレータを開発などの動きもありますが、それはあくまで研究のためのエミュレートでありぼくのような一般人には縁遠いものです。なので現時点で、一般人が過去のゲームにアクセスするもっとも容易な方法は当時のハード、当時のソフトを用意することです。その機能を担っていた中古を扱うゲームショップはさながら図書館・博物館のようなゲーム文化の公共性を有していました。
しかし結局PSE法の施行によって結果的にゲーム文化は断絶されてしまいました。それほどプレゼンスが高くなかったであろうレトロゲームの取り扱いを中止させるには十分な役割を果たしたようです。ゲーム機自体を売ることが出来なければ、ソフトの取り扱いを中止するのもやむを得ません。図書館のなどのようなある種の文化的側面を持ちつつもそれは商売です。しかも収益構造が脆弱なゲームショップにゲーム販売以上を期待するのは酷なことかもしれません。
 ※後から調べると、どうやら正規ケースは透明のよう。少しがっかりです。※追記:どうやら『ラストグラディエーターズ』は中古店やオークションに出品されているものを見ると、黒いプラケース、透明(裏紙白)、透明(裏紙緑)の3種類がありそう。『Ver9.7』以外に。
※後から調べると、どうやら正規ケースは透明のよう。少しがっかりです。※追記:どうやら『ラストグラディエーターズ』は中古店やオークションに出品されているものを見ると、黒いプラケース、透明(裏紙白)、透明(裏紙緑)の3種類がありそう。『Ver9.7』以外に。
―ソニー/セガのミーティング資料流出、PS3にドリームキャスト・PS2エミュレータ登場?(joystick Japan)
過去のゲームがプレイステーション3でサポートされるのではという噂が絶えません。でもたとえそれが実現したとしてもすべてのゲームがサポートされることはありえず、ユーザーに用意された手段は究極的にはオリジナルを用意する外ありません。けれどその手段が中古ゲームの取り扱い中止で次第に狭められてしまっているのが現状です。確かにネット流通は留保されていはいますが、アクセサビリティという点で難があります。
○レトロゲームへのアクセサビリティ
ゲームはもはや文化です。任天堂は工業製品というかもしれませんが、映画や音楽、文学と同様の文化です。けれどもゲーム業界自体が軽視し続けてきたためか、未だ文化として社会的なコンセンサスは得られていない様相です。だからこその中古ゲーム論争だったのかもしれません。厳しい出版業界すら、新品書籍販売を圧迫していると非難されるブックオフを毛嫌いはしていますが、中古販売禁止を法廷にまで持ち込んではいないのですから。
今ようやくネットでのダウンロード販売などのシステムが整理され始めて、メーカも過去のゲームの資産価値に気づき始めています。ビジネスとして成り立っているのかという点は微妙のようですが、ハード的にエミュレートするのであれば元データをいじる必要はほぼ皆無であり、開発費をかけることない新たな収益として期待はされているようです。また版権会社のような会社が著作権を纏めてもいるようです。
研究も重要ですが、やはりゲームは遊んでなんぼ、ユーザーに遊ばれてこそなんぼでは無いでしょうか。古典文学の研究者でもない一般人が『徒然草』を今でも読めるように、気軽に『ガールズガーデン』をプレイできるようなアクセサビリティがゲームが文化として深められるのには必要だと思います。普通の人たちが遊んでこそのゲームです。でも実際はレトロゲームは2003年ごろのファミコンの”発見”まで大して省みられていませんでした。
古い文学が新しい文学に劣っていないように、古いゲームが新しいゲームに劣っているわけではありません。新しいゲームさえあれば良いわけでも無いはずです。だからこそのファミコンの”発見”だったわけです。歴史が存在するから文化として成立するわけで新しいゲームしか省みられないのであれば、それはまさに工業製品と変わりがありません。でも現状はその逆で、徐々に中古レトロゲームは消滅していっています。
文化としてゲームを担保するものはレトロゲームに他なりません。そのレトロゲームを扱うゲームショップの棚が限られているとしたら、ネットオークションやネットショッピングに期待するしかないのです。しかしネットオークションなどでは一般的に敷居が高すぎます。昔の文学を近所の書店で気軽に購入するようにはいきません。そこではやはりダウンロード販売などの施策といった研究者、研究機関では出来ないメーカー側の努力が不可欠だと思います。
古いゲーム批評を押入れから出して読んでいると、その中で「注目メーカー全特集」と言う記事ありました。特集されているメーカーの中で一際目立っていたメーカーが、ある意味で今は亡きKAZeです。当時から、そして今でもまったく持ってピンボールゲームに意義を見出せていなかったぼくもインタビュー記事を読んで初めてピンボールゲームに、というかKAZeの一連のデジタルピンボールに惹かれてしまいました。
と言うことで、KAZeの一連の作品、具体的には『ラストグラディエーターズ』、『ネクロノミコン』と『パワーレンジャー ピンボール』を探しに行きました。『ラストグラディエーターズver9.7』はともかく、この3作品とも特にレアソフトと言うことも無く高くても1000円以下で購入が可能なソフトであるようなので、容易に買えるだろうと高をくくってゲームショップに向かいました。向かいましたが…
結論から言えば、サターンのソフトを取り扱っているゲームショップが圧倒的に減ってしまっている現状に愕然としました。次世代ゲーム機の浸透や売れ線である任天堂ゲーム機のために棚を空けるということもあるのでしょうが、やはりPSE法の施行がボディブロウのように効いてきている印象です。後にゲーム機などは適用除外されましたが、時既に遅しというか棚撤去の背中を押した格好になっているようです。
○中古レトロゲームの現状
サターンの取り扱いが減っているのを尻目に、ファミコンやスーパーファミコン、プレイステーションといった”勝ち組”ハードは古かろうとも棚が存続されたりしていました。またゲームキューブやゲームボーイアドバンスなど(ここにはプレイステーションも含まれますが)現行機種で下位互換が実現されている機種もまたその棚を大きくとは言わないまでもそれなりの規模で未だ残していました。
問題はサターンをはじめとした過去のハード戦争で敗れ去っていった所謂”負け組”ハードです。ファミコン、スーパーファミコンに敗れ去ったメガドライブ、メガCD、PCエンジン、CD-ROM2そしてネオジオ。プレイステーションに僅差で負けたセガサターン。(不思議なのは負けたはずのニンテンドー64は棚を残していたりすることです。)プレイステーション2に勝てなかったドリームキャストやXBOXがそれです。
○ようやく見つけるも
そして何軒か回ってようやく『ラストグラディエーターズ』を一部店舗で展開されていると言うゲオのレトロゲーム100円均一セールのワゴンの中に見つけることが出来ました。『ラストグラディエーターズ』の他に気になってはいたものの食指は伸びなかったソフトを数本一緒に購入。探していたソフトを見つけることができ、100円で買えたのは嬉しかったのですが、一方で100円は投売りと言うことです。
ゲオの100円均一ワゴンにはメガドライブ、PCエンジン、セガサターン、ネオジオ、ワンダースワン、ドリームキャストの6機種のゲームが入っていました。そしてそのワゴンには「(上記6機種について)12月12日(土)を持ちまして、買取を終了させていただきます」といった趣旨のポップが添えられていました。投げ売られているということはそういうことだとは思いましたが、買取の終了は取り扱いの終了を意味します。
○ゲームのアーカイブス化と中古ゲーム
映画はDVD化ということでよほどのマニアックな作品以外は古い作品も現在でも観る事が可能です。小説も文庫化などされて100年以上前の作品が未だに流通し、容易にアクセス出来ます。ゲームも昨今ようやくWiiを中心に過去のハードのソフトも遊べるようになってきていますが、比較的アーキテクチャが複雑といわれるセガサターンやアーキテクチャを公開したため、個々に複雑化したPS2など難しいものもあります。
立命館大学などで全機種エミュレータを開発などの動きもありますが、それはあくまで研究のためのエミュレートでありぼくのような一般人には縁遠いものです。なので現時点で、一般人が過去のゲームにアクセスするもっとも容易な方法は当時のハード、当時のソフトを用意することです。その機能を担っていた中古を扱うゲームショップはさながら図書館・博物館のようなゲーム文化の公共性を有していました。
しかし結局PSE法の施行によって結果的にゲーム文化は断絶されてしまいました。それほどプレゼンスが高くなかったであろうレトロゲームの取り扱いを中止させるには十分な役割を果たしたようです。ゲーム機自体を売ることが出来なければ、ソフトの取り扱いを中止するのもやむを得ません。図書館のなどのようなある種の文化的側面を持ちつつもそれは商売です。しかも収益構造が脆弱なゲームショップにゲーム販売以上を期待するのは酷なことかもしれません。
 ※後から調べると、どうやら正規ケースは透明のよう。少しがっかりです。※追記:どうやら『ラストグラディエーターズ』は中古店やオークションに出品されているものを見ると、黒いプラケース、透明(裏紙白)、透明(裏紙緑)の3種類がありそう。『Ver9.7』以外に。
※後から調べると、どうやら正規ケースは透明のよう。少しがっかりです。※追記:どうやら『ラストグラディエーターズ』は中古店やオークションに出品されているものを見ると、黒いプラケース、透明(裏紙白)、透明(裏紙緑)の3種類がありそう。『Ver9.7』以外に。―ソニー/セガのミーティング資料流出、PS3にドリームキャスト・PS2エミュレータ登場?(joystick Japan)
過去のゲームがプレイステーション3でサポートされるのではという噂が絶えません。でもたとえそれが実現したとしてもすべてのゲームがサポートされることはありえず、ユーザーに用意された手段は究極的にはオリジナルを用意する外ありません。けれどその手段が中古ゲームの取り扱い中止で次第に狭められてしまっているのが現状です。確かにネット流通は留保されていはいますが、アクセサビリティという点で難があります。
○レトロゲームへのアクセサビリティ
ゲームはもはや文化です。任天堂は工業製品というかもしれませんが、映画や音楽、文学と同様の文化です。けれどもゲーム業界自体が軽視し続けてきたためか、未だ文化として社会的なコンセンサスは得られていない様相です。だからこその中古ゲーム論争だったのかもしれません。厳しい出版業界すら、新品書籍販売を圧迫していると非難されるブックオフを毛嫌いはしていますが、中古販売禁止を法廷にまで持ち込んではいないのですから。
今ようやくネットでのダウンロード販売などのシステムが整理され始めて、メーカも過去のゲームの資産価値に気づき始めています。ビジネスとして成り立っているのかという点は微妙のようですが、ハード的にエミュレートするのであれば元データをいじる必要はほぼ皆無であり、開発費をかけることない新たな収益として期待はされているようです。また版権会社のような会社が著作権を纏めてもいるようです。
研究も重要ですが、やはりゲームは遊んでなんぼ、ユーザーに遊ばれてこそなんぼでは無いでしょうか。古典文学の研究者でもない一般人が『徒然草』を今でも読めるように、気軽に『ガールズガーデン』をプレイできるようなアクセサビリティがゲームが文化として深められるのには必要だと思います。普通の人たちが遊んでこそのゲームです。でも実際はレトロゲームは2003年ごろのファミコンの”発見”まで大して省みられていませんでした。
古い文学が新しい文学に劣っていないように、古いゲームが新しいゲームに劣っているわけではありません。新しいゲームさえあれば良いわけでも無いはずです。だからこそのファミコンの”発見”だったわけです。歴史が存在するから文化として成立するわけで新しいゲームしか省みられないのであれば、それはまさに工業製品と変わりがありません。でも現状はその逆で、徐々に中古レトロゲームは消滅していっています。
文化としてゲームを担保するものはレトロゲームに他なりません。そのレトロゲームを扱うゲームショップの棚が限られているとしたら、ネットオークションやネットショッピングに期待するしかないのです。しかしネットオークションなどでは一般的に敷居が高すぎます。昔の文学を近所の書店で気軽に購入するようにはいきません。そこではやはりダウンロード販売などの施策といった研究者、研究機関では出来ないメーカー側の努力が不可欠だと思います。










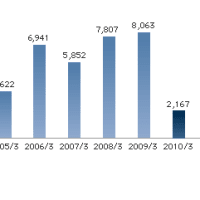

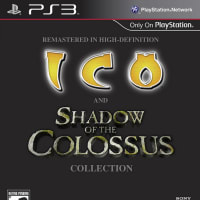
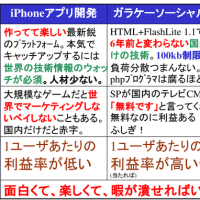
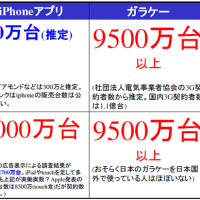
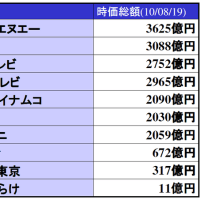

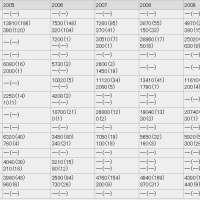


※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます