TBSラジオで放送された「Life」の番外編の「ヱヴァスペシャル」を聴いてしまったら、堪えきれずに『ヱヴァンゲリヲン:破』を観に行ってしまいました。劇場に行くといつもの劇場とは違った客層だったのが「エヴァ」が「エヴァ」であることを思い起こさせてくれました。ここは秋葉原かという印象の一方で旧エヴァとは異なりカップルが多かったのも「エヴァ」が単なるアニメじゃないことをまた思い起こさせてくれました。
以下大量にネタバレです。注意。絶対ネタバレ見ないで映画館で観たほうが良いです。
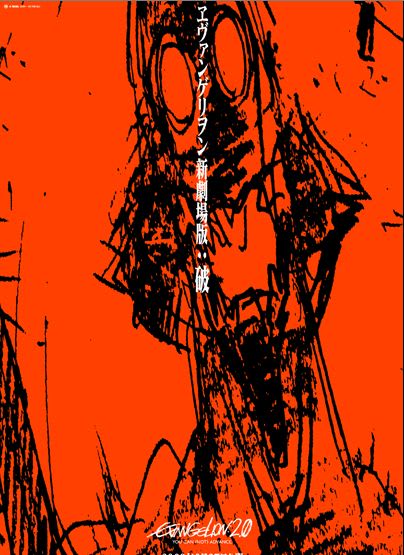
のっけから庵野総監督の趣味爆発でいきなり科特隊な効果音が鳴ったと思いきやミサトの車がマツダコスモスポーツ!などなど。ほかにもわんさかそれっぽいのが心なしかテレビ版よりも戦闘シーンが『ウルトラマン』のようなジオラマ感が増しているような。アスカが手にしていた携帯ゲーム機がもろワンダースワンで涙。「キュイィーーーン」の起動音が。カードリッジのラベルがファミコンのソレっぽいのはご愛嬌。『謎の円盤UFO』は該当箇所が分からなかったです。
ゲンドウが年食ったなぁというか、微妙に髪が伸びている感じでどこと無く監督っぽいです。作画の変更以上に意図的に見かけの歳が上がっている印象が強い。竹熊さんが指摘してたように、シンジのSDATは『序』からトラック25と26を行ったり来たりしていましたが、真希波がシンジにボーイミーツガールした(ぶつかった)途端にトラックが27へ。たぶんそういうことなんだなぁ。
後半カヲルくんが登場し、「今度こそシンジ君だけは幸せにしてみせる」と言い、綾波も意図的に状況を改善しようと努力していて(それが健気でとてもかわいい!)、それもシンジが変わったために及ぼされた影響に見えます。それはミサトやアスカにもあって、みながみな可能な範囲内で建設的にして行こうと努力していると。『序』の公開当時に囁かれていた、「ループ」設定は現実を帯びてきたように思います。鶴巻監督が言ったとされる山手線と京浜東北線というのがぴったり。
こうした「生きることを望む人々」はアニメ版・旧劇場版を知っているほど、キャラクターが魅力的に見えます。ファンの贔屓目ですが、こういうのを見ると『新世紀エヴァンゲリオン2(Evangelions)』の存在というものは何らかの影響を芝村さんの意図通り与えたのかなぁとうっかり思ってしまいそうです。新劇場版が全部終焉したらループを前提とした『エヴァンゲリオン3』とか出してくれないかと妄想をしてしまいます。
安直な言い方ですが、凄かったです。凄い情報量と迫力で圧倒されます。消耗させられます。ファンだったら、元ファンならそれこそ観に行くべき。細部の違いを探し出したらきりがないですが、エンターテイメントとして楽しむのが一番。エンターテイメントだし、分かりやすくなってはいるけれど、安直には落ちないのはエヴァは名前が変わってもエヴァだなぁ。『Q』が待ちきれません。
そしてゲーム版『破』はあるのか、あったとしてどうこれをゲーム化するのか。よほどの覚悟とテクニカルなものを持ってないとかなり難しいと思います。『エヴァ2』はエヴァに向き合ってましたが、『序』は見事に避けてしまっていたので駄作でした。それよりも出せるのかどうかですか。
以下大量にネタバレです。注意。絶対ネタバレ見ないで映画館で観たほうが良いです。
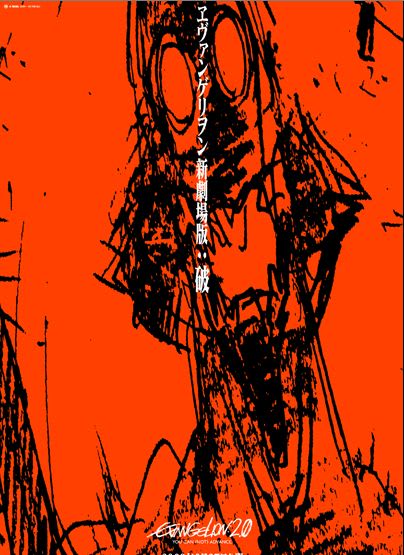
のっけから庵野総監督の趣味爆発でいきなり科特隊な効果音が鳴ったと思いきやミサトの車がマツダコスモスポーツ!などなど。ほかにもわんさかそれっぽいのが心なしかテレビ版よりも戦闘シーンが『ウルトラマン』のようなジオラマ感が増しているような。アスカが手にしていた携帯ゲーム機がもろワンダースワンで涙。「キュイィーーーン」の起動音が。カードリッジのラベルがファミコンのソレっぽいのはご愛嬌。『謎の円盤UFO』は該当箇所が分からなかったです。
ゲンドウが年食ったなぁというか、微妙に髪が伸びている感じでどこと無く監督っぽいです。作画の変更以上に意図的に見かけの歳が上がっている印象が強い。竹熊さんが指摘してたように、シンジのSDATは『序』からトラック25と26を行ったり来たりしていましたが、真希波がシンジにボーイミーツガールした(ぶつかった)途端にトラックが27へ。たぶんそういうことなんだなぁ。
後半カヲルくんが登場し、「今度こそシンジ君だけは幸せにしてみせる」と言い、綾波も意図的に状況を改善しようと努力していて(それが健気でとてもかわいい!)、それもシンジが変わったために及ぼされた影響に見えます。それはミサトやアスカにもあって、みながみな可能な範囲内で建設的にして行こうと努力していると。『序』の公開当時に囁かれていた、「ループ」設定は現実を帯びてきたように思います。鶴巻監督が言ったとされる山手線と京浜東北線というのがぴったり。
こうした「生きることを望む人々」はアニメ版・旧劇場版を知っているほど、キャラクターが魅力的に見えます。ファンの贔屓目ですが、こういうのを見ると『新世紀エヴァンゲリオン2(Evangelions)』の存在というものは何らかの影響を芝村さんの意図通り与えたのかなぁとうっかり思ってしまいそうです。新劇場版が全部終焉したらループを前提とした『エヴァンゲリオン3』とか出してくれないかと妄想をしてしまいます。
安直な言い方ですが、凄かったです。凄い情報量と迫力で圧倒されます。消耗させられます。ファンだったら、元ファンならそれこそ観に行くべき。細部の違いを探し出したらきりがないですが、エンターテイメントとして楽しむのが一番。エンターテイメントだし、分かりやすくなってはいるけれど、安直には落ちないのはエヴァは名前が変わってもエヴァだなぁ。『Q』が待ちきれません。
そしてゲーム版『破』はあるのか、あったとしてどうこれをゲーム化するのか。よほどの覚悟とテクニカルなものを持ってないとかなり難しいと思います。『エヴァ2』はエヴァに向き合ってましたが、『序』は見事に避けてしまっていたので駄作でした。それよりも出せるのかどうかですか。










