先日『ヱヴァンゲリヲン新劇場版:序ver.1.11』のディスクソフト内に挿入されていたチラシの中で発表された『葛城ミサト報道計画』、Cellを活用するためにSCEとバンダイの合弁会社セリウスが開発に関わったということでどれほど凄いのかと期待されましたが、あけてガッカリ進化はしたもののやはり今までの合成音声の延長線の産物でした。初音ミクなどの登場で俄然注目・ハードルが上がっているだけに、です。
合成音声はゲームの中では昔から、手の届く夢の技術でした。ファミコンで初めて合成音声が聞こえてきたときの衝撃は今でも覚えています。いつもコールドで終わるのに『ファミスタ』をやっていたのは合成音声の「アウトッ!」とかが聞きたかったからだと思います。
ファミコン時代には合成音声がしばしば登場したものでしたが、容量の増加と圧縮技術の進化から合成音声ではなく録音した音声が主流となり、次第に合成音声はロストフューチャーな技術になってしまってました。それが森川さんの『くまうた』で大々的に復活したのです。それも今まで補助的であったり、実際の音声の代替物でしかなかったものがそれ自体の合成っぽさが魅力になり、宇宙のくまの”声”として主役に躍り出ました。
-『トモダチコレクション』(公式)
で、『トモダチコレクション』です。特に公式を観たり、情報を集めたりはしてませんが、パッと見はPCゲームの時代から連綿と続く神の視点のゲームのよう。CMを見る限りアバターを作り、容姿ばかりか内面も設定し、それを観察するというのが趣旨のよう。ちょっと退屈な作りに見えなくも無いですが、『どうぶつの森』の任天堂ですのでゲーム性は信頼しても良さそうな。
普通自然な発音の方が好ましいはずですが、発音が変なことで自然な発音には無い魅力が生まれるというアンビヴァレンツ!アバターはリアルじゃないほうが、イメージとして許容範囲が大きく、結果として似ていると感じられます。音声の場合は違和感が前提の方が下手に流暢なものよりもイメージの破綻が少ないのかなぁ。何ともそこはかとなく面白そうです。ぼんやり面白そう。
合成音声はゲームの中では昔から、手の届く夢の技術でした。ファミコンで初めて合成音声が聞こえてきたときの衝撃は今でも覚えています。いつもコールドで終わるのに『ファミスタ』をやっていたのは合成音声の「アウトッ!」とかが聞きたかったからだと思います。
ファミコン時代には合成音声がしばしば登場したものでしたが、容量の増加と圧縮技術の進化から合成音声ではなく録音した音声が主流となり、次第に合成音声はロストフューチャーな技術になってしまってました。それが森川さんの『くまうた』で大々的に復活したのです。それも今まで補助的であったり、実際の音声の代替物でしかなかったものがそれ自体の合成っぽさが魅力になり、宇宙のくまの”声”として主役に躍り出ました。
-『トモダチコレクション』(公式)
で、『トモダチコレクション』です。特に公式を観たり、情報を集めたりはしてませんが、パッと見はPCゲームの時代から連綿と続く神の視点のゲームのよう。CMを見る限りアバターを作り、容姿ばかりか内面も設定し、それを観察するというのが趣旨のよう。ちょっと退屈な作りに見えなくも無いですが、『どうぶつの森』の任天堂ですのでゲーム性は信頼しても良さそうな。
普通自然な発音の方が好ましいはずですが、発音が変なことで自然な発音には無い魅力が生まれるというアンビヴァレンツ!アバターはリアルじゃないほうが、イメージとして許容範囲が大きく、結果として似ていると感じられます。音声の場合は違和感が前提の方が下手に流暢なものよりもイメージの破綻が少ないのかなぁ。何ともそこはかとなく面白そうです。ぼんやり面白そう。










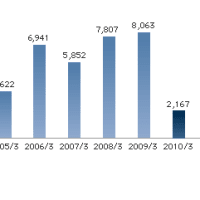

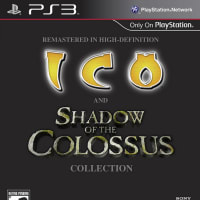
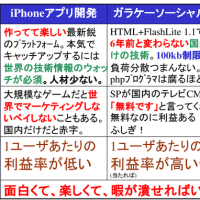
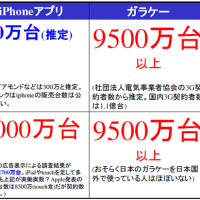
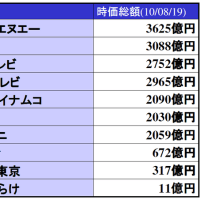

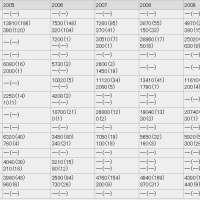


※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます