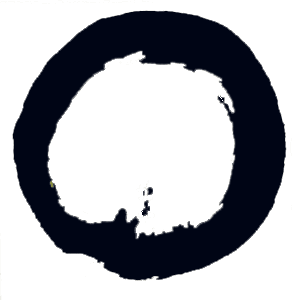🔵大東亜戦争に敗れて77年が経つ。戦後、米国の傘のもと軍隊を持たず、経済を最優先して復興に集中できた事は、幸運そのものと言っていい。
今回の敗戦特集に際し、かずかずの文献に目を通してきた。其処には当時の日本の家庭それぞれの苦衷の記録も多かった。また昭和天皇はじめ吉田茂など数々の日本の偉人はもとより、敗戦国日本に支援を頂いた諸外国の首脳の姿もあった。
🔵中でも日本の国体維持を始め、平和憲法、戦力不持の再建スキームを構想し、米国主導で政治力を発揮したマッカーサー元帥の存在は格別であった。
元帥の戦後統治がなかったら、今の日本は存在しえなかったのではないのか。時の米国大統領と意見が合わず解任後帰国、大統領選挙の機会に恵まれず
他界され国葬となった。米国内はもとより世界の支持は最高の人だった。今回は冒頭のビジュアルに、1945年厚木基地に着任時のマッカーサー総司令官の
パイプ姿を飾る事にした。本日は終戦に因んで戦争に纏わる家族の「想い出物語」
をお届けしたい。(Yama)●冒頭の写真は提供(JIJI通信)
. . . 本文を読む
●北京冬季オリンピックは、昨日幕を閉じた。大国の覇権やスポーツの政治利用、
加えてパンデミックなど、さまざまな事象が危惧されたが無事に終える
事が出来た。ご同慶の至りである。
出場選手は、国の大小に拘わらず勝ちを制すれば、こよなくゴールドメダリストの
栄冠と名誉に浴する事が出来る。これを称して「フエアー」という。だからこそオリンピックが、創始のオリンピアの時代から、粛々と「平和の祭典」として愛され続いてきた所以だ。
●新しい松本語録「感動の続編」によると、アスリートの能力はその技能ばかりか、
その精神力、無我の心を体得することで大変な進化があるという。
無我無心の心境は、日本古来から伝承の「禅」の心に通じる。無我無心のアスリートが、どんどん育つ事を期待して止まない。
●ポスト五輪の世界情勢は、ロシアによるウクライナへの侵攻の危機がクローズアップされる。
平和の祭典が終われば、すぐ対立と闘いの再開というのは、余りにも過ぎたる五輪の冒瀆と
言える。プーチン大統領は大の柔道家だと聞く。この際、岸田総理は柔道の本家家元を
伴い、明日にでもモスクワへ飛んでウクライナからの軍隊撤収を説得してはどうか。
日本の伝統武芸を愛するアスリート同志の気合の話合いが奏功する確率は極めて高いと思うが如何?(Yama) ●標題の絵は、禅の極意、無を象徴する「丸」
. . . 本文を読む
🔵いま北京五輪がたけなわ、中盤を迎えて世界のアスリートの戦いが続く。わずか1回の試合チャンスに、培ってきた修練の成果を賭ける。スノーボードなど長い回転飛翔の後、着地を誤れば一瞬にして全てはご破産となる。
イチかバチかの一面もある。勝利は、平素の修練の成果と試合に臨む気概しかない。誰しもでき得ない試合の成果が、見る人々に「感動」をもたらす。
感動とは、それほど貴重でとてつもなく希有な出来事である。
🔵長年にわたり、あらゆるスポーツの真髄を研究してきた筑波大学の松本名誉教授は、今の世の中、感動の受け売りが多すぎると
警告する。
「真の感動」とは、今まで経験した事のない快挙など驚きにも似た心の響きだという。北京五輪の戦いは20日迄続く。(Yama)
. . . 本文を読む
🔵「国境の長いトンネルを抜けると雪国だった。」川端康成の名作「雪国」の冒頭の一節である。
まだテレビもない戦後12年の昭和32年(1957年)岸恵子,池部良主演、豊田四郎監督の映画「雪国」が全国上映され一世を風靡した。
筋書きもさることながら、その雪国の情景描写が素晴らしかった。私を含め当時の若者たちは、この映画で雪国への憧れをもつ事になる。ーー
🔵雪国と言えば2月開催予定の北京五輪が、新型コロナウィールスが席巻するなか、いまその開催が危ぶまれている。
私どもは昨年7月,東京五輪で同じ苦しみを体験しただけに、人ごとならぬ思いに浸っている。
去る2008年に夏季五輪を開催した北京は、夏と冬の五輪を世界で始めて
開く都市になる。しかも中国は次の五輪を「中華民族の偉大な復興」と
言う国威発揚の場と考えている。
それが西側自由諸国から見ると、いかにも公式行事を活用した政治利用に映る。
🔵2030年、日本は長野に次いで2回目の冬季五輪を札幌で開催する。
理念は、国連の活動に因んで「持続可能な五輪」を目指す。
しかしマスコミ予測では、世界の動静は「グレートリセットへ」に向かい、
地政学的な政治リスクが高まり世界の不安が募ると言う。
本来オリンピックは世界のリスクを解消するために、世界
全ての国が
スポーツで一同に会するのではないのか。改めて世界五輪の開催理由が問われる所以だ。
🔵「大局着眼,着手小局」この格言をなぞらえ、敢えて「大局着眼、着足小局」としてこの大局に挑む、日本アスリートの心意気について語る。最新の「松本語録」をご覧ください。(Yama)
. . . 本文を読む
🔵戦後の教育制度の改革と相まって、家庭教育の在り方が問われて久しい。爾来「家庭は全ての教育の出発点」と言われて来た。
しかし核家族化が進み、祖父母から孫への伝承的な躾などの教えは、ほぼ不可能になった。加えて都会地では女性の社会進出がすすみ、家庭における
子供教育は衰退の一途を辿りつつある。しかも小学低学年からの塾通いが定番になり、親が手塩にかけて子供を育てると言う温もりある家庭教育は、後退を余儀なくされている。⚫️一方、育てる側にも問題がある。特に戦後生まれの団塊世代(今年75歳前後)は、自我が強い割に依存性が強く、子育てもいい加減だったという。そのツケが小子高齢化と格差による難しい社会をもたらした。その団塊世代800万人足らずが既に定年を迎え、核家族化の中で孫達はいま小学、中学の教育過程にある。そして世界的なデジタル化の中で、殆どがアイパッドを操り、日常はスマホを使いこなす。親とは違った多くの新しい社会情報に触れうる立場にある。爺婆の世界では百歳時代の到来に備えて、「リカレント」(学び直し)の波が押し寄せている。まさに「教育、混濁の時代」と言っていい。
⚫️そして世界は、大国の覇権に揺れ動く。そのパワーバランスの基盤は、経済力や外交力や軍事力だが、その根底にあるのはマンパワー(知力と体力)だと言われる。いま世界はどの国も、SDGs化のなかで優れた人材を求め続ける。
長い道のりではあるが、人材育成のための教育の是非が決め手になる。
改めて松本名誉教授の「教育の再発見」に注目が集まる所以だ。(Yama)
. . . 本文を読む
🟢私も2人の子供を持つ。戦後昭和の日本にあって昭和40年代(今から約50年前)の子育ては女房任せだった。何しろ忙しく、土曜日は半ドン,日曜だけ休みの体制が続いた。丁度、子供たちの小学から中学の時期に当たる。
振り返ると子供たちの学校参観や運動会や卒業式に出た記憶はない。「父親の資格」全くなしである。
それでも「何とか子は育つ」と強がりを言い張ってきたが、今はそんな暴言は通らない。
振り返ると当時は、世の中全体が貧しかった。しかし国も家庭も子供の教育を最優先の課題として努力を積み重ね、それが後の国の成長に大きく貢献した。
🟢
僅か20年前に始まった知力によるデジタル化の波は留まるところを知らない。第2の産業革命ともいえる大変革が起こりつつある。脱炭素然り、SDGs然り、
果たして世界はどう変わっていくのか。その足取りは極めて速い。世界は知財による勝負の時代になって来た。人生における学びの所産が問われる。(Yama)
. . . 本文を読む
●人の生涯は、実に変化に富んでいる。一人ひとりの生い立ちと老後がある。千差万別というに相応しいものといえる。
そのなかでも幸せな生涯があつたり、不幸な一生があったりする。だからややこしい。識者によると、その要因は、
子供の頃の教育に起因する事が多いと言う。何はともあれ、こどもの教育は親の責任事項であることだけは確かだ。
こどものよい
生涯を願うなら、良い教育の「場」を子供に与える事。まずは、まがいない結論である。
. . . 本文を読む