
■■■■■■■■■■■■■■本屋の危機■■■■■■■■■■■■■■
■■「本が売れない」
🔵いま,街の「本屋さん」が危ない。1日1軒の割でなくなりつつある
という。しかし都会に住んでいると, 都心,周辺には,大型の書店が点在し,
本屋が、なくなりつつあるとは思えない。
しかし,日本全国の地方都市の商店街では,毎月のように街の本屋さんが、
閉店や廃業に追い込まれている。
その主な理由は, デジタル化によるスマホの台頭で,情報形態の激変やネッ
ト通販の普及などで、本を書店で買うという日常習慣が, 大きく後退しつ
つあるという。それに伴い,紙に印刷するという情報伝達の仕組みが,大き
く変わつた。
そのために毎日読む新聞までも,その影響をモロに受けてつつあるという。
🔵「日本全国の書店数の推移」

このペースで行くと 人口が1億を切ると予測される1950年代には, 日本
の書店数が約3000店にまで落ち込む可能性がある。
🔵出版科学研究所調査によると、日本の2023年現在の書店の総数は、
1万900店で昨年対比577店減少した。1日1店舗が減り続けている
「本が売れない」実態が,書店の経営難に拍車をかける結果になつた
とみていい。
🔵この様な書店減少の大きな理由は、
・インターネット通販による本の購入が手軽になった事。
・この8年間で4倍に拡大した電子書籍市場の存在がおおきい。
これによって出版物を電子情報の形で読者に届けると言う,新しい利便の
仕組みが生み出され,広く普及したという事に尽きるという。
ECで本を購入するのは当たり前の時代となった。既に電子書籍の市場は
この8年間で約4倍に拡大した。
全国の図書館は増加傾向にあり,住民との絆を深めて、地域密着型で生き
残りを目指す書店も少なくない。中には,市民の居場所としての図書館と,
賑わいを産む書店が融合して,大成功した事例も多い。
🔵「日本の書店の売り場面積の推移」

■■「本屋の由来」
︎🔵本来,書店の役割は大きかつた。かつて人々は,知識を得る手筈として、
紙に印刷された「本」や「雑誌」を購入するため本屋に行つたものだ。
街の本屋さんは, 新しい情報や文化を読者に届ける枢要な存在だった。
高齢者の中には、予後の生きがいの常套手段として,読書を嗜む人が多い。
この人たちにとって、行きつけの本屋さんは、かけがえのない存在であり
また新しい本との出会いの場でもあった。
🔵それがデジタル化と言う世界的な情報の仕組みの出現によつて,出版物
を電子情報の形で,読者に届ける新しい利便の仕組みが生み出された。
しかもこれが時代の波というか、新しい利便のせいか、恐ろしいほどのス
ピードで普及が進んだとみていい。
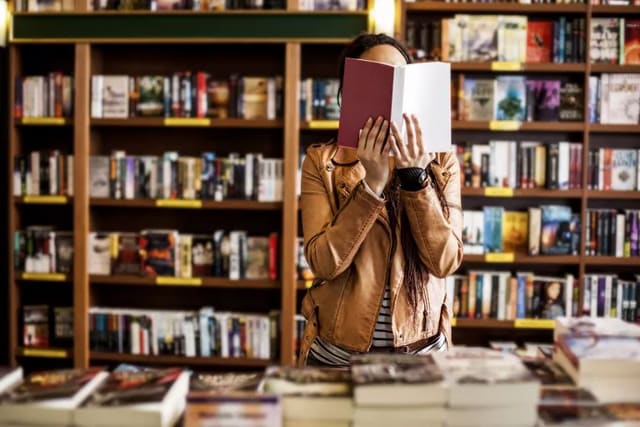
■■「書店振興の動向」
🔵大手出版取次会社の「トーハン」は 「書店振興プロジェクト」を立ち
上げ、「小さな書店」の開業を支援する。そして業界挙げて,書店への
一般の関心の高まりを後押ししする。最近は ,店主の個性で品揃いにする
「独立系書店」が,増えつつあるというしやすい取引制度を始めた。
・気軽に人々が立ち寄りコーヒーも飲める小さな書店、
・そこには、出版社が刊行した単行本や文庫本や雑誌がならぶ。
・月の取引額が30万から100万円規模の取引を主体にして, 過疎地にも本
屋が出せる様、支援する。
・本屋店内の書籍の区分や並べ方、対顧客への告知のしかたなど、お客に
とって本が買いやすい売り場の環境整備のアドバイスなど、専門的な支
援を強化する。
🔵政府調査によると「書店0」の自治体は、約28%に達する。
しかし,新しい活字離れが止まらないなか、新しい価値を打ち出す書店の開
業を支持する声も増え続けている。その核心は、
・地域貢献
・コト消費
・一芸に特化
書店減少に対するこのような新しい試みに対して、全国から注目が集まる。
■■「売る改革への挑戦」
🔵日本を代表する大型書店「紀伊國屋書店」と「蔦屋書店」を運営する
CCC(カルチュア・コンビニエンスクラブ)と出版取次の日本出版販売は、
新しい合弁会社を設立、新しい書店創りのために「売れる本」を仕入れ
返品についても送料を負担するなど、新しい書店の開業に対し,支援の手を
差し伸べる。

・行き付けの超大型書店「 TSUTAYA書店」(梅田)
そして、ネットから地域の書店に客を誘導する 新しい試みの実証実験にも着手
した。苦境にある書店をめぐっては「書店振興プロジェクトチーム」が協働して、
手厚い支援策を提案,本が売れる環境整備を支援する。

■■「書店アラカルト」
🔵「戦後から昭和」は「努力すれば報われる」時代だった。それが後の
平成になると、日本経済は低迷し格差が広がった。しかもそれが,30年も
続き、俗に「平成30年の低迷と不況」と言われた。しかも「本屋の衰退」
が「平成の不況」と符合する。
識者は「日本経済の低迷は、海外に比べ本を読まなくなったからではない
のか。いい仕事には想像力が不可欠だ。」と読書の効用を解く。
🔵日本の本屋が総じて衰退に向かうなか「再生と復活」で成長する書
店がある。京都に本社を置く「創業80年の「大垣書店」だ。
そもそも京都は、大学生が人口の10%を占める肥沃な読書基盤の土地柄、
年商10億になると事前の仕入れ交渉が良くなるとの期待から、地道な出
店努力を重ねてきた。いまは全国に50店を超える。
聞くところでは、大垣書店の経営スローガンは「商売は牛のよだれ」
細くながく辛抱強くが、商いの基本理念だと言う。
全国的に衰退が進む書店ビジネスに「再生と復活」と言う力強いメッセ
ージをたれで奮起を促す。
私も、大垣書店の事を詳しくなかったが、先日の午後、amazonに急ぎ
の本を頼んだら、翌日の午前中に本が届き書籍通販の手際良さに驚いた。
実は,その発送元の書店が「大垣書店」だった事が判り、2度びっくり。
「不況理由の克服こそ、ビジネスの商機」と言う永遠の経営原則を追求
する大垣書店の差別化対応に感動した。改めて書店ビジネスにも,確たる
差別的な経営戦略が不可欠な事を学んだ。

■■「本との出会い」(私の場合)
🔵私的な事例だが、活字文化で物事や人生の表裏を学んできた者にとって、
急にデジタル化で本が無くなると言われても,容易には納得しがたい
都会の近隣には,いまも大型の書店が健在だ。大阪の場合,都心には
「ジュンク堂書店」
「紀伊國屋書店」
「蔦屋書店」など
超大型書店が、覇を競うように存在する。まさに世界に誇る日本の伝統文
化の象徴的な存在と言っていい。
本の購入は、あらゆる新刊本が,種目別に区分され、綺麗に並ぶ書棚の中か
ら、じっくりと時間をかけて、目指す本を探す妙味は格別だ。
大きな書棚から 読みたい書籍を選び出し、同じフロアの喫茶コーナーで、
お茶を飲みながら序文などに目を通し購読を決める。
🔵決め手は,手にした時の本の装丁やデザイン,その表題、著者の履歴や
序文など、一つ一つ紐解いていく一時、時には「新しい言葉のあやや文脈
の妙」に 出会うなど、さすがと著者に敬服する事しばしば、その時の感動
でその本を求める事が多い。至福のひとときでもある。
最近では、通販サイトamazonを利用するケースもあるが, 本の購入は、
最新の新刊本が並ぶ書店の書棚の中から、時間をかけて、目的の本を探す事
の妙味に尽きる。その本との出会いの感動も、本を選ぶ重要な要素だ
■■「本屋への期待」
🔵本は、人間にとって知識や情報を習得するための不可欠な媒体である「本」
を振り返るに, 人々が、知識を習得するのに「本」の果たした役割は大きい。
本来「本」は、
-識者である著者の存在、
-その著作を探索、本に構成する編集者の力量、
-その本を商品化するデザインの力、
-その本を本屋の並べ、読者に届けていく出版社の力量、
-その本を読者に紹介し、届ける書店(本屋)の努力、
-それらの優れた本の存在を知らす、マス媒体の書評力、
以上の様な様々な人達の力で、名著が読者の手元に届けられていく。
これに関わる人達は、多くの人々に知識や情報や文化を届ける極めて枢要な
「知の伝導者」と言っていい。
「本屋」は,その最先端を担う枢要な存在であり,今後の復活に期待したい。

























※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます