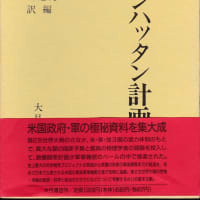▲フーコーの著作、そして中村雄二郎訳『知の考古学』、中村雄二郎の著作など 右端はフーコーと並んで再読・再々読に値すると私が思うレンフルーの快著『ことばの考古学』 誰か、この著を凌ぐ大作をものする人はいないか
中村雄二郎さん追悼 中村雄二郎 訳 フーコーの『知の考古学』
中村雄二郎さん追悼
2017年8月末、新聞に中村雄二郎さんの訃報が載った。91歳だったそうだ。『現代思想』、『思想』、『世界』誌、などで、中村雄二郎の論文や評論をよくみかけたのだが、ここしばらく、読んだ記憶が薄れ、雑誌などの掲載を見ていなかったのだ。どうしているのだろうと思っていた矢先である。1969年に出版された、ミシェル・フーコーの『知の考古学』をいち早く紹介し、1970年秋には訳・注・解説を入れて400頁を越える『知の考古学』を河出書房から出していた。
中村雄二郎訳の『知の考古学』は、学生時代、河出書房新社から出版された直後、偶然に通りかかった高円寺駅北口付近の本屋で入手し、しばらくの間、この本に夢中になって読んだはずなのだが、アンダーラインがほとんどの頁に残っているものの、読後の興奮が何だったのか、うまく思いだせない。また、何回かに分け、鉛筆や色鉛筆、ペン書きなどの痕からすると理解できずに相当苦しんで繰り返し読んでいたらしい。なにしろ、この本は考古学のコーナーにあったのだから摩訶不思議なのだ。
しかし今から47年も前のことになると、今では高円寺の古本屋の主人がページもめくらずに、考古学の本と間違えてその棚に置いたのではなく、犀利な頭で気を利かせ哲学の棚に置かず、いわゆる・ほんとうの考古学のコーナーに置いたのではないかと考えてもみたくなるのだ。知の攪乱者ミシェル・フーコー、そして道化の思想家山口昌男の盟友・中村雄二郎にふさわしいではないか。
かくして、ミシェル・フーコーの『知の考古学』は、我が家の本棚では、考古学の本に限りなく隣接したところに居座っているのだ。
さて、その後、思想・哲学に関する本は、それなりに入手していたものの、大学時代の友のような対話する同好の士が見つからず、ほかの関連分野・考古古代史に関心領域も移り、そちらに埋没していたのだろう。1990年代末に刊行され始めたフーコーの『思考集成』(筑摩書房)も60年代末頃の、『知の考古学』の時期の論考をのぞいて、積読状態だったのだ。
しかし、ふとしたことから、中村雄二郎が、『知の考古学』について、自分の訳を何度も訂正・改訳していたことを知った。
フーコーが新しい方法で、また新しいものさしで、歴史を解読する以上、従来の通念に従うものさしや概念の使用をやめ、分析を開始するのだから、翻訳した中村雄二郎はそれ以上に試行錯誤・難問だらけ・艱難辛苦・暗中模索の訳業だったはずだ。
・
・
1970年10月 ミシェル・フーコー 中村雄二郎 訳 『知の考古学』 初版発行
1981年2月 中村雄二郎 改訳新版 初版発行
1995年8月 中村雄二郎 改訳版新装 発行
2006年2月 中村雄二郎 新装新版 発行
・
・
1995年8月の改訳版新装の訳本を入手していないので、2006年2月の新装新版のものと比較できないのだが、後で確認してみたい。
2006年2月の新装新版 訳本の末尾には、1995・1・31の日付で以下のように中村雄二郎は記している。
「追記 その後、東北大学の「文化ゼミナール」グループ(代表宮崎祐助氏)から原書の厳密な読解に照らして不適切な訳や不改行個所などの指摘をいただいた。それに応じて、現在のかたちで、可能なかぎりあいまいなところがないように訳文に手を入れた。ご指摘に感謝したい。」
とあった。
70歳をを過ぎてもなお、研究上の、はるか後輩の人たちの指摘にも、ていねいに応答し、何度も、改訳を施していたと思われる。
また、『現代思想』2017年11月号で、中沢新一が中村雄二郎追悼を書いている。
若い頃、中沢新一は、若いものにありがちなのだが、初めて親しく会話を交わした中村雄二郎に向かって、「作者フーコーと翻訳者の体質の違い」などを、ずけずけとしゃべってしまったと書いている。」
それを聞いていた、
山口昌男は
「お前、言いにくいことを平気で言う奴だな」
と私をいなしたが、
中村雄二郎のほうは平然として、
「はは、それはどうも見破られたな」と、むしろ楽しそうであった。」
(『現代思想』2017年11月号 250頁「中沢新一 「レンマの贈与」
ナルホド、これが、レンマの贈与者 中村雄二郎のすばらしさなのだな。
今頃、中村雄二郎は、盟友山口昌男と、山内得立の『ロゴスとレンマ』を酒の肴にしていることだろう。
・
・
中村雄二郎の最初の訳業の後、ミシェル・フーコーの『知の考古学』は、慎改康之訳の新訳も河出書房から出ている。
私も二十歳の頃の疾風怒濤の世界に戻り、中村雄二郎が何度も試みていた『知の考古学』の訳業の痕跡を追いかけてみたくおもう。解読の方法的格子すら痕跡なのだが・・・・・

▲ミシェル・フーコーの著作集、右端の緑色の本は、『季刊パイデイア』フーコー特集号1972年春
今は存在していないが、竹内書店がこの雑誌を刊行していた。『ゴダール全集』もここから出ていた。あのころ、せりか書房と並んで、刺激的な本を続々刊行していた。
人生の残り時間を考えると、フーコーの著作すべてを精読する時間も気力もないが、フーコーとデリダとの間の1960年代末~1970年代初頭頃の論争は、世紀の思想大乱闘だったのではないか。この数年間の論争については、互いに譲らずの真剣勝負。この論争を語り、記すにはまだ、場外乱闘の持久戦も必要だ、この論戦の追及は、能力からしてしばらくは遠慮するのほかはないのだが。
また、コリン・レンフルーの著作『ことばの考古学』についての、著作を上回る展望を披歴した論評も見たことがない。
ことばの誕生・民族の概念の使用法の根拠・規定、考古遺物と民族をどう関連させるのかなどの解決方法、神話の起源と時間軸・空間分布の理解の提示なども未解決のようだから。・・・・
かつてデュメジルの「三機能体系」印欧神話解釈を利用して大陸から騎馬民族の道ー新羅を経由して日本神話の「三種の神器」に援用する吉田敦彦の方法にもコリン・レンフルーは疑念を表明していた。
ミシェル・フーコーの『言葉と物』には、デュメジルにも言及した箇所もあり、印欧言語の起源・考古学・民族の起源にからみ、批評的エッセー・文学作品としてではなく、『言葉と物 人文科学の考古学』として理解しようとすると、膨大な文献探索と、考古学遺物の解釈の難問に遭遇する。
「語族」「民族」「影響」「移動」というような未検証であるかも知れない概念を使用しないで、歴史・空間の記述をすることができるのだろうか。そうすると体系的・線的・空間記述はできるのだろうか。体系的ではない、また線的記述でもない記述法とは何か。
フーコーの『言葉と物』以降、「パンドラの箱」が開かれてから50年。
コリン・レンフルーの思考や歴史記述のなかにも、「絶対」を失ったものの宿命が宿されているようにも見える。
歴史記述は、いったい、どこに足場を持っているのだろうか。