政治には、政局と政策があります。
この話は、以前にも一度書きましたが、いまこのとき、
非常に重要な話だと思いますので、再度、同じ話を取り上
げます。
いまはあまり言わなくなりましたが、かつて、「床屋政
談」という言葉がありました。床屋さん、というか、理髪
店ですね、髪の毛を切ってもらいながら、お客さんと店主
が政治の話をします。
「お客さん、最近、菅さんはなんだかすごいですねえ」
「ねえ、いったい、どうしちゃったんだろうね」
「このまま居座るつもりでしょうか」
「うーん、そうでしょうねえ。辞める気配がないものね」
「そうですねえ、全然辞める感じがないですものね」
「ねえ」
「でも、自民党もそうだろうけど、与党の民主党だって
困っているのでしょうね」
「いやあ、それはそうでしょう。こんなことになるなん
て、だれも思ってなかったんじゃないのかなあ」
「でも、こんなことで、日本はどうなるんでしょうね」
「ほんと、困るよなあ」
とまあ、こんな調子です。
政治の話は、なんとなく、話題にしやすい。
最後は「こんなことで、日本はどうなるんでしょうねえ」
という感じで終わることが多いと思います。
怖いのは、こうやって政治を話題にしているうちに、我
々が政治を馬鹿にしてしまうことです。
それが一番怖い。
実は、この床屋政談で取り上げたような政治は、「政局」
と呼びます。
政治部の記者が、「政局」という場合は、首相交代とか、
派閥抗争とか、総選挙とか、狭い意味の動きを指します。
しかし、ここでは、「政局」という言葉を、もっと広い
意味で使います。
では、「政局」以外の政治とはなんでしょうか。
それが、「政策」です。
たとえば、大震災で被害を受けた地域のがれきを撤去す
る、あるいは、仮設住宅を建設する。あるいは、消費税率
を上げる。
もっと広く、景気と財政再建のどちらを重視するのかと
か、デフレにどう対応するのかというのも、当然、政策で
す。
高速道路の無料化をどうするかというもの、政策です。
中国との関係をどうしていくのか、というのも、もちろ
ん、政策です。
「政局」と「政策」はどう違うのでしょうか。
「政局」は、人と人の話です。首相が辞めるとか辞めな
いとか、鳩山由紀夫氏が「だまされた」とぼやいたとか、
亀井静香氏がだれと会ったとか、そういうのは、「政局」
です。いずれも、人間が出てきています。
だれか人間が主語になるのが、「政局」です。
だれか具体的な政治家の名前が主語になるのです。
具体的な政治家の名前が前面に出るから、わかりやすい
し、おもしろい。
「政策」は、文字通り、政策です。
税金をどうするとか、景気をどうするとか、主語は人間
ではありません。どちらかというと、無機質な話になりま
す。
デフレにどう対応するのかというのは、ものすごく大切
な話ですが、主語は、日本経済であったり、経済成長率G
DPであったりします。数字と%が出てきます。
そして、「政局」の話のほうが、「政策」の話より確実に
おもしろいのです。
GDPがマイナス0.5%になったが、その原因は何か
という話より、岡田幹事長が菅首相を説得しに行ったけれ
ど失敗したという話のほうが、おもしろいに決まっていま
す。
だから、我々は、どうしても、「政局」に目が行く。
政治といえば、「政局」になってしまうのです。
新聞もテレビも、実は、インターネットでも、政治とい
えば政局の話が大きく取り上げられてしまうのです。
菅首相の批判は、おもしろいし、簡単です。
しかし、デフレ対策の批判は、デフレの意味が分かって
いないと出来ないし、ちっともおもしろくない。
だから、政治は、ほうっておくと、政治家も我々国民も、
みな「政局」の話ばかりになってしまうのです。
しかし、実は、日本にとって、あるいは、我々にとって、
「政策」のほうが、「政局」なんかより、はるかに重要な
のです。
菅首相と岡田幹事長が対立しても、我々の生活にはあま
り影響はありませんが、しかし、デフレがひどくなると、
我々の生活はさらにダメージを受けます。
本当は、政策のほうが、政局よりも、はるかに大事なの
です。
ところが、政局のほうがわかりやすいし、おもしろい。
そして、いまの菅政権は、「政局」のネタばかり提供し
ています。
だから、日本中、どこに行っても「床屋政談」が展開さ
れる。
理髪店では店主と、タクシーに乗ると運転手さんと、居
酒屋では隣り合わせたお客さんと、職場では同僚と、家で
は奥さんと、「床屋政談」をやる。
「まったく、菅というのはどうしようもないなあ」
「鳩山由起夫だってそうよ」
「岡田幹事長は何やってんだろうね」
「亀井静香は不思議なことをするなあ」
「自民党の谷垣だって、なにもできないし」
などなど、政治家と政治に対する批判のオンパレードで
す。政治家を批判し、そして、馬鹿にする。
そして、政治家を馬鹿にし、批判しているうちに、我々
は、「政治」を馬鹿にするようになってしまうのです。
そう。
「政治」を馬鹿にし始めるのです。
「政局」を馬鹿にするのなら、それはかまいません。
しかし、国民が、「政治」そのものを馬鹿にし始めると、
それは危ないです。
政治を馬鹿にし始めると、「政策」に批判の目が行かな
くなります。
日本の国の行く方向を決めるのは、政策です。
政策に批判の目が行かなくなると、政策がいい加減なも
のになります。
だれが政策を考え、作っているのか、分からなくなりま
す。
だれかが勝手に政策を決め、勝手に実行しても、全然分
からなくなります。
国民が政治を馬鹿にし始めると、国民は政策にも知らん
顔をし始めます。そうすると、国民は政策にも無関心になります。
それが最も危険なのです。
そうやって見ると、いまは、かなり危険な状態になって
います。
民主党も自民党も、こんなことをやっている場合ではあ
りません。
政治家は覚醒しないといけません。

















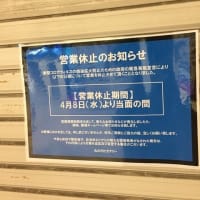



※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます