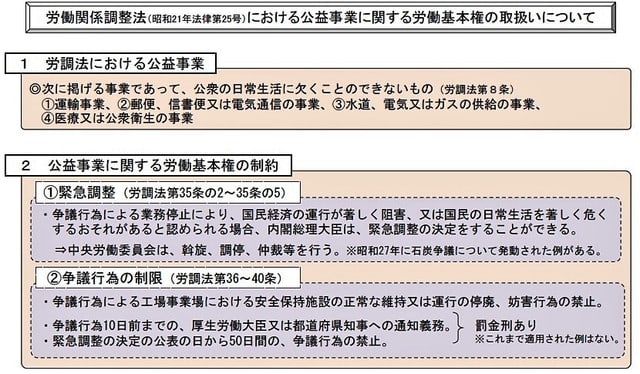昨日は、衆議院第一議員会館で、私鉄総連「19春闘交通政策要求実現中央行動」を開催。
中央行動には、政策推進私鉄国会議員懇談会・鉢呂吉雄弘会長、近藤昭一・柳田稔・吉川元・辻元清美・道下大樹・中谷一馬・阿部知子・枝野幸男・福山哲朗・福田昭夫・岡本あき子・山花郁夫・榛葉賀津也・荒井さとし・田名部匡世・広田一・落合貴之衆参議院議員が参加してくれた(敬称略)の18名の国会議員、私鉄自治体議員団会議から8名の自治体議員、9地連・沖縄・ハイタクから110単組212名が参加した。
全体会で私鉄総連を代表してあいさつに立った清水副委員長は「生活路線の維持・活性化と安全運行の確保は私鉄総連の交通政策要求の基本」とした上で「職場で一番大きな課題となっている要員の確保について、交通運輸産業の長時間労働が求職者に敬遠される大きな要因となっている。働き方改革でも自動車運転者は時間外上限規制が5年猶予され、適用後も960時間と一般則との乖離が大きい。魅力ある産業とするためにも賃金・労働条件の改善を踏まえた実効性のある要員確保対策を強く求める」と述べた。
政策推進私鉄国会議員懇談会の鉢呂会長からは、「私鉄では昨年、再度、議員懇を立ち上げた。皆様には全国から馳せ参じていただき御礼申し上げる。参議院でも予算委員会が開会されて、まだ議員懇全員が来ていないが、順次来ると思う。以前、紋別バス労組の役員が私のところに来て地域間の国の補助金が削減されそうだと要請に来られた。私は国交委員だったから大臣に要請して撤回させた。都市部は超過密、地方は超過疎化、問題が山積しているがどう改善していくか。たとえば北海道でも鉄道施設が老朽化しているという問題もある。 今日だけで片付かない問題に関しては、私ども私鉄議員懇の議員が、きちっと継続して対応していくことを約束する。」と挨拶。
19春闘 交通政策要求実現中央行動要請項目については、
1 鉄軌・バス・ハイタク共通の要請
1.交通政策基本計画の着実な実行
(1)交通政策基本計画に基づく施策を着実に推進するために必要となる法制上・財政上の支援措置の充実をはかられたい。また、引き続き、進捗状況の「見える化」とフォローアップを着実に実施されたい。
(2)次期交通政策基本計画について、策定に向けた検討をすみやかに取り組まれたい。この他、以前の運輸政策審議会答申に相当する交通政策に関わる中長期の方針等が策定されるようであれば明らかにされたい。
(3)要員確保対策の強化
①交通政策基本計画では「交通サービスの安定的な運行と安全確保に資するため、地域公共交通事業者等の交通関連事業について、生産性向上と人材確保も含めた基盤強化方策や適正な競争環境整備を検討」とあるが、交通の各分野における要員不足は深刻さを増している。働き方改革への対応や賃金・労働条件の改善を踏まえた実効性ある要員確保対策を再度検討されたい。
②交通政策基本計画では、2020年度までの女性労働者の倍増を目標に掲げているが、現在までに具体的な成果は見られていない。目標の達成に向けてどの様な取り組みが行われているか明らかにされたい。また、厚生労働省には、「両立支援等助成金・女性活躍加速化コース」などがあるが、交通運輸産業では女性が働く環境の整備が特に遅れていることから、国土交通省としても女性が働きやすい環境整備に対する支援を創設されたい。
(4)地域公共交通ネットワークの再構築
①地方自治体による地域公共交通網形成計画・地域公共交通再編実施事業計画策定が、より推進するように、国土交通省として積極的に指導・情報提供をおこなわれたい。 また、地方自治体に交通政策を定着させるための人材育成にも取り組まれたい。
②改正地域公共交通活性化再生法では、まちづくりと一体となった公共交通の再編が求められていることから、地方自治体の都市計画等と連携がはかれるよう指導されたい。また、クリームスキミング的な参入が問題となったことから、新規参入に対しては、真に持続可能な地域公共交通の確立に向けて本省と地方運輸局、地方自治体が連携を密にしながら対応されたい。
(5)現在、国はキャッシュレス化をすすめているが、交通系ICカードの導入については、中小の地域鉄道・バス事業者にとって費用負担が大きいことから、導入が進んでいない。このため、中小事業者や地方自治体による地域独自カード向けに接続費用が低廉なカードシステムを国主導で構築し、そのカードシステムを利用して、スイカ、パスモ等10カードとの相互利用を可能なものとされたい。
2.東日本大震災および大規模災害対策
(1)東日本大震災被災地の早期復旧・復興に向けて、引き続き地域公共交通確保維持改善事業等の被災地特例による支援を今後も継続されたい。
(2)大規模な災害が続き、今後も発生が予測されていることから、被災した公共交通が早期に復旧・復興が図れるよう支援制度を創設されたい。
(3)大規模な地震が予測されている中で、国は、中央防災会議で「大規模地震・津波災害応急対策対処方針」を策定しているが、各地域においても帰宅困難者対策や避難輸送対策が整備されるよう各自治体における対策マニュアルの策定を指導されたい。
(4)大規模災害の被災地などの復興には風評被害払拭に向けた取り組みが重要であることから、これら地域に対する観光誘致などのキャンペーンについて支援を強化されたい。
3.自家用ライドシェア
(1)道路運送法は、「道路運送事業の運営を適正かつ合理的なものとし、並びに道路運送の分野における利用者の需要の多様化及び高度化に的確に対応したサービスの円滑かつ確実な提供を促進することにより、輸送の安全を確保し、道路運送の利用者の利益の保護及びその利便の増進を図るとともに、道路運送の総合的な発達を図り、もつて公共の福祉を増進することを目的とする」とされていることから、道路運送事業者以外の者が有償で運送をおこなう、いわゆる「ライドシェア」等白タク・白バス行為の合法化は、例外的な措置も含めて、輸送の安全や利用者の保護のため、国土交通省として今後も断固として認めることのないよう強く要請する。
(2)観光客が使用するレンタカーを運転することによって、反復継続して報酬を得る行 為は、道路運送法第2条第3項で定義される「他人の需要に応じ、有償で、自動車を使用して旅客を運送する事業」である。また、実態として、レンタカーの貸渡しとそのレンタカーを運転するドライバーの仲介が一体として行われており、白タク・白バス行為にあたることは明らかである。早急に取締りをされたい。
(3)増加する訪日旅行者を対象とした白タク行為が、国内各空港や港湾、観光地において顕著となっている。引き続き、警察とも連携の下、取り締まりを強化されるとともに、白タク・白バスへの乗車は違法であることと、安全や補償が担保されていないことについて、訪日旅行者への啓蒙を強化されたい。
4.長時間労働の是正と働き方改革への対応
(1)働き方改革関連法として改正された労働基準法では、バス・タクシー等の自動車運転者は、改正労基法施行の5年後に上限960時間として、一般則の適用までさらに猶予する方向性が示されているが、自動車運転者は、過労死を含む労災認定が多い職業であることから長時間労働の是正は「命と安全」にかかわる喫緊の課題であり、関係省庁連絡会議等で早期に一般則が適用されるよう協議されたい。
(2)厚生労働省において「改善基準告示」改正に向けた議論がはじめられようとしているが、国土交通省としても過労運転の防止による安全運行確保の観点から、積極的に意見反映されたい。また、運輸規則第21条に基づく国土交通大臣告示「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」について、①勤務間の休息期間の延長、②分割休息特例の見直し、を国土交通省としても検討されたい。検討にあたっては国土交通省自動車局安全政策課実施の「自動車運転者の労働時間等についてのアンケート」結果、および厚生労働省で実施された「過労死等に関する実態把握のための労働・社会面の調査研究事業」等の結果を活用されたい。
(3)2018年2月に「自動車運送事業者における脳血管疾患対策ガイドライン」が策定されたが、事業者にはスクリーニング検査費用の負担が大きく、実施されていない。脳MRI検査を含むスクリーニング検査の受診に対する助成措置を創設されたい。
5.消費税率引き上げへの対応
2019年10月に予定されている消費税率の引き上げの実施に際しては、各交通事業者に対して消費税率引き上げに伴う運賃改定を指導するとともに、運賃改定申請に対して速やかな対応をはかられたい。
6.燃料費高騰対策
燃料油脂費は国際情勢により価格が不安定であり、公共交通事業の経営に著しく影響を与えることを踏まえ、燃料に係る暫定税率の撤廃、自動車関連諸税の税体系の簡素化等を含む負担軽減と、原油価格高騰時のトリガー条項の凍結解除と緊急避難的な支援制度の創設をはかられたい。
7.公共交通利用促進に関する要請
公共交通の利用促進には利用者の理解や協力、参加が極めて重要であり、CO2排出削減等、地球環境保護への対応も必要な状況である。地域任せではなく、国土交通省としても、公共交通利用エコポイント制度の導入、また、警察庁等と連携した高齢者免許返納優遇制度等、公共交通の利用促進に向けた施策を創設されたい。
8.観光立国政策に関する要請
(1)順調に訪日旅行者が増加しているが、その受入体制や安全対策の強化については、十分とは言いがたい状況にあることから、①駅・バスターミナル施設等における多言語対応の看板案内・標識の設置、②観光地等での安全に配慮した貸切バス乗降場所やタクシーベイの整備をはかられたい。
(2)貸切バスに実施されている総合的な安全対策や下限運賃厳守に向けて訪日旅行者に対する啓蒙啓発や海外の旅行業者・ランドオペレーターに対する指導を徹底されたい。
(3)訪日旅行者の手荷物は、大型化していると同時に個数も多いため、手荷物取り扱い時の労働災害が増加していることから、駅・空港にポーターを配置されたい。また、バス車両ではトランクに積みきれず、客席に積むことによって乗車定員未満での運行を余儀なくされていることから、「手ぶら観光」施策の更なる推進をはかるとともに、手荷物の個数制限や寸法・重量の規格化を検討されたい。
9.東京オリンピック・パラリンピックの対応について
(1)期間中の輸送計画等について現在の検討状況を明らかにされたい。また、輸送計画の具体化に当たっては事前に労働者代表とも調整されたい。
(2)各輸送機関におけるテロ対策を強化されるとともに、防犯カメラ等の増設に対する支援や対応マニュアルの整備や訓練なども行われたい。
4 ハイタクに関する要請
1.タクシー事業適正化の推進と違法営業の根絶、監査の強化
(1)「改正特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法」は、賃金水準も含めた運転者の労働条件の改善が重要な目的となっていることを鑑み、また法施行後5年以上経過するが未だ実効性が上がっておらず、多くの地域で指定期間が延長されている状況を踏まえ、特定地域協議会の運営ガイドラインの見直しをされたい。また、真に適正化が必要な地域が特定地域に指定されるよう、特定地域の指定要件には、賃金水準の改善状況を加え、人口要件や実働実車率等不合理な要件については見直しをされたい。また、特定地域・準特定地域の指定を解除する際には、一時的な事業環境変化の要素は排除するための要件を追加されたい。
(2)道路運送法違反や労働諸法令の違反等、違法な営業をおこなっている事業者に対する重点的な監査を強化し、違法不適切な事業運営の摘発・排除されたい。また「旅客自動車運送適正化事業実施機関」については、実効性のある適正化事業が的確に実施されなければならない。早急に全都道府県に設置されるよう指導を強化されたい。
(3)タクシー利用者の安全を確保するため、事故防止対策支援推進事業について、先進安全自動車(ASV)の導入促進に向けてタクシー車両を補助対象として拡大することを含めて支援措置を拡充されたい。
(4)自家用車有償旅客運送は公共交通機関であるタクシー・バス事業者による十分な運送サービスの提供が困難である場合に、認められるものであるが、運営協議会等において、既存のタクシーやバス事業と競合するような、制度の目的を逸脱した運送が検討されている地域があることから、指導を徹底されたい。また、非営利事業であることからおおむねタクシー運賃の半額以下とされている輸送対価は純然たる実費とし、事故発生状況、運行管理体制等、適正に処理・運営されているか事後チェックのための監査体制を強化されたい。なお、自家用有償運送事業者に対する監査や指導の状況も明らかにされたい。
(5)運転代行の違法営業行為に対する取り締まりを下記のとおり強化されたい。
①利用者保護の観点から、随伴車両の保険加入や代行要員の二種免許保有のチェック等監査を強化すること。
②運転代行適正化法の改正により、事業者資格を厳格化したうえで事業区域を設定し、タクシー特措法の目的に準じた需給の適正化をおこなうこと。
③過労防止の観点から、代行運転者をタクシー業務適正化特別措置法の運転者登録制度の対象とすることとし、代行運転者の過労運転防止と利用者の安全確保のため、タクシー等自動車運転者との兼業を禁止する施策を講じること。
2.衆参附帯決議の履行による運転者の労働条件改善
(1)改正タクシー特措法の附帯決議では「本法の施行後における施行の状況や効果について、3年毎に総合的に検証を行い、その結果を両院に報告すること」について、特定地域については一部の調査項目については公表されたが、準特定地域も含めて、すべての調査結果について早急に公表し、具体的な対策を講じられたい。
(2)附帯決議において「事業者は、歩合給と固定給のバランスの取れた給与体系の再構築、累進歩合制の廃止、事業に要する経費を運転者に負担させる慣行の見直し等賃金制度等の改善等に努める」よう事業者に求められたが、改善は進んでいない。最低賃金法や労働時間規制の違反、長時間労働による過労運転を防止するため、適切な労働時間管理をおこなうことが必要であることから、労働時間管理が曖昧になる歩合給中心の賃金制度から、固定給を中心とした賃金制度に改善されるよう、行政の立場からガイドラインの策定や、改善した事業者に対するインセンティブ等、措置を講じられたい。
(3)現在検討されている「ホワイト経営認証制度」(仮称)について、制度概要と導入までのスケジュールについて明らかにされたい。
(4)改正タクシー特措法は、賃金水準も含めた運転者の労働条件の改善を重要な目的としており、また、参議院附帯決議において「一般旅客運送事業者は…過度な遠距離割引運賃の是正等運賃制度等の改善に努める…」とされていることを踏まえ、過度な遠距離割引運賃の改善について、行政として事業者に対する措置を講じられたい。また、深夜割増運賃や営業的割引運賃等、運転者の適正な賃金に影響がある運賃については公定幅運賃の対象とされたい。さらに、昨今、タクシー配車アプリ提供事業者が、様々な割引サービスを実施しており、新たな運賃に関する過当競争となることが懸念されていることに留意されたい。
3.タクシー事業活性化と財政的支援
(1)特定地域協議会・準特定地域協議会において、タクシー需要の拡大や事業の活性化について積極的に検討し、それら特定地域協議会・準特定地域協議会が進める活性化施策に必要な法整備や助成措置を講じられたい。
(2)交通政策基本法の制定を受け、改正された地域公共交通活性化再生法により新たに位置付けられた地域公共交通再編事業において、既存の旅客運送事業からタクシーへの転換についても当該事業の対象となっていることから、「地域公共交通確保維持改善事業」にもとづく乗合タクシーやデマンドタクシー等の運行に係る支援措置の充実を図るとともに、事業者等の意見を踏まえながら活用しやすい制度を構築されたい。また、バスの運行のない時間帯の交通確保や、バスの幹線路線への接続として、自治体が、乗合タクシーやデマンドタクシーではなく通常のタクシーとして活用する際には、「地域公共交通確保維持事業」の措置として運行に係る支援措置の対象とされたい。
(3)「地域公共交通バリア解消促進等事業」において、福祉タクシー・UDタクシーの購入等については、購入費及び改造費について補助対象となっているが、社会的要請も高まっていることから、補助率の増率や助成額の増額と、税制の減免措置等の財政支援措置を拡充されたい。また、新たにUDタクシーの対象となった車両は、車いす利用者への対応の際、操作性や安全性に問題があるため、早急な改善をメーカーに指導されたい。
(4)タクシー事業に係る助成制度については、タクシー事業関連法や労働法等の違反事業者は助成の対象としないこととし、一方で、法令遵守を積極的に行っている優良事業者に対しては助成額や助成率を優遇することにより、タクシー事業の適正化を推進されたい。
(5)大規模自然災害や大規模交通障害の際、個別輸送機関であるタクシーは柔軟な運行で非常時輸送に対応できる場合があるが、事業区域によって対応できていない現状がある。非常災害時の「臨時営業区域の対応」によって、安全運行を前提として、事業計画等の変更の必要なく、隣接する営業区域外の事業者による運行ができるよう、実態に即した適切で迅速な対応をされるよう、地方運輸局に徹底されたい。
4.白タク合法化の阻止
(1)道路運送事業者以外の者が有償で運送をおこなう、いわゆる「ライドシェア」等白タク・白バス行為の合法化は、例外的な措置も含めて、輸送の安全や利用者の保護のため、今後も認められることは許されない。また、「道路運送法における許可又は登録を要しない運送の態様について」(国自旅第338号 平成30年3月30日)によって、主として、ボランティア活動における送迎行為等を念頭におきながら、許可又は登録が不要な場合の考え方及びこれに該当すると思われるケースの例が示されたが、反復継続された、偶発的でない運送に対して、その個々の運送の終了後、運送経費に加えて、任意の謝礼の支払いを促すような運送が、この通達によりあたかも認められた運送行為であるとして、運送を行っている実態がある。明らかに白タク行為であるので、取り締まりをされたい。
(2)訪日旅行者の利便性の向上のため、海外のタクシー配車サービスとの事業提携が進められているが、それら配車サービスが諸外国で行っているライドシェア事業が非合法に日本国内でも行われないよう、注視されたい。またそれら配車サービスに支払う配車手数料が、労働者負担とならないよう事業者への指導を強化されたい。
本日は、日本教育会館にて、私鉄総連第3回拡大中央委員会を開催、全国から中央委員、単組代表が約500人が結集した。
総連を代表してあいさつに立った田野辺委員長は、はじめに軽井沢スキーバス転落事故に言及し、あらめて「安全・安心な貸切バスの運行を実現するための総合的な対策の徹底、監査・行政処分の厳格化など、バス事業の安全性の向上をめざしていく」と考えを示したあと、1月28日に召集された第198回通常国会について触れ、「首相は施政方針演説で厚労省の統計不正問題について陳謝をしたが、間違った統計の結果は、様々な形で国内に影響を与え、日本経済にも大きな影響を与える大問題である。言い換えればアベノミクスの経済成長も偽りであったということだ」と痛烈に批判。これまでの財務省の文書改ざん、防衛省の隠蔽問題、文科省の不正入学と天下りなど、国の根幹がおかしくなっていると指摘、そのうえで立憲民主党がまっとうな政治に戻して欲しいと述べ、「そうでなければこの国に未来はない」と強調した。また19春闘について、「私鉄の要求は、早朝から深夜まで、現場で安全を支え、災害が起きれば寝食を忘れ、復旧復興の最前線に立つ組合員の労苦に報いるための要求である。最後まで、月例賃金に拘りを持ち、回答指定日時には従来以上の交渉の追い込みで、回答を引き出さなければならない。さらなる団結で私鉄春闘を構築する決意だ」と意気込みを語った。最後に、「今年は12年に一度の政治決戦の年だ。春闘をしっかり闘い結果を出して、統一自治体議員選挙で地域の地盤を固め、推薦候補者全員の当選を勝ち取り、私たちの代表『もりやたかし組織内候補』を必ず国政に送くる取り組みを強めよう」と参加者に訴えた。
来賓として立憲民主党の福山幹事長から連帯と激励のあいさつを受けたあとそ、各級議員選挙闘争推進方針、19春闘などを提案、質疑・応答のうえ、満場一致で決定した。




























































 >
> >
>