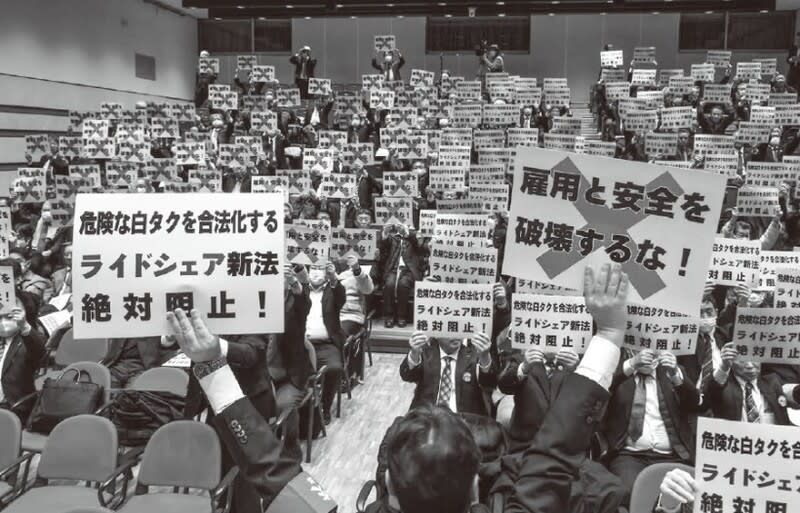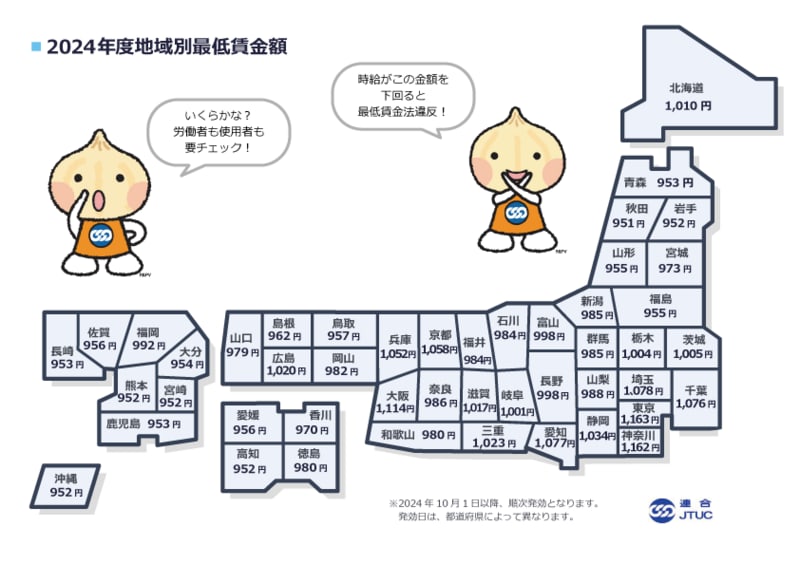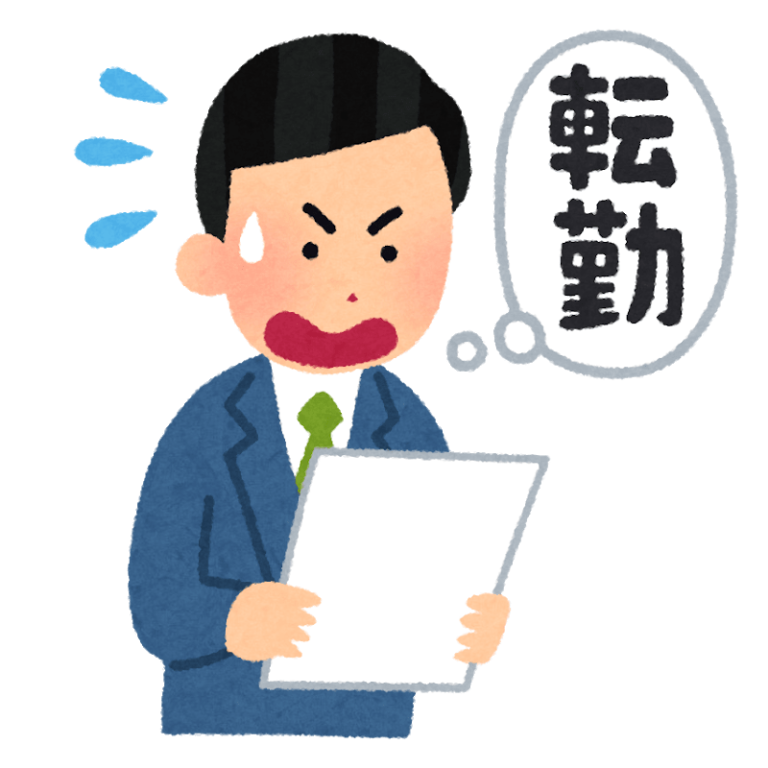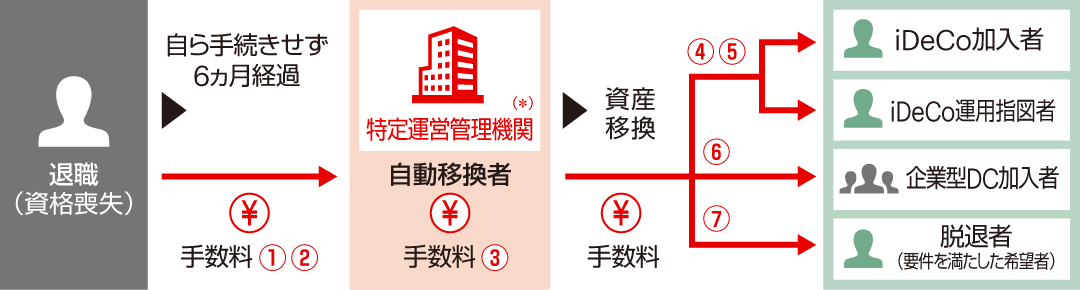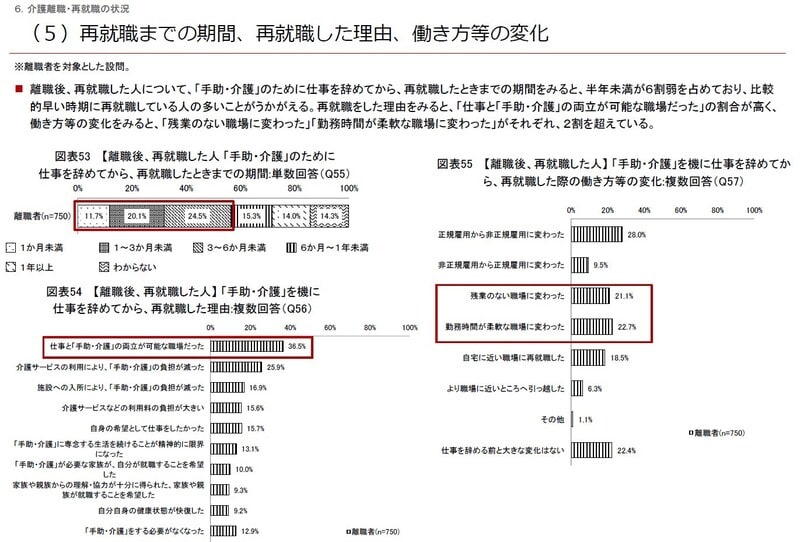双極性障害を負った公務員Xの退職願を受けて栃木県Yが出した免職処分の有効性と、退職勧奨を行った上司の不法行為に基づく国賠法上の責任を争った事案。
裁判所は、免職処分は無効として、Xの公務員としての地位を認めましたが、Yの国賠法上の責任は否定した。
◎判決の要旨
判決は、たとえ上司らに退職勧奨の意図がなかったとしても、原告からすれば、退職を勧められていると受け止めても仕方がない状況であったと認められるところ、原告が面談時にあくまで復職を希望していたことや上記経過からすると、退職は原告の意に反するものであったといえ、面談当時の健康状態及び面談における上司らの説明が相互作用したことにより、熟慮することができないまま退職の選択肢しかないという思考に陥った結果、退職願を提出するに至ったものと認められるから、退職願は自由な意思に基づくものとはいえず、退職願を前提としてなされた辞職承認処分も違法であり取り消されるべきであるとした。
◎自由な意思を否定したポイント
①双極性障害による傷病休暇中で、実際に体調も悪い状態だったこと、②医師や家族の同席もなく、退職以外の選択肢も示されず、面談からわずか2日後に退職願が提出され、③面談は、Xの責任を追及するような比較的厳しい内容だったこと、④面談時にはXが一貫して復職希望を表明していたこと、など。
◎この判例からの留意点
・精神疾患に罹患していることの一事をもって、退職願を提出した者に意思能力がないと判断されるものではない。
・精神疾患に罹患していることの一事をもって、退職願を提出した者の意に反するものと直ちに評価されるものではない。
⇒退職願提出以前の言動から意思能力を有していることに疑念が生ずるような事案であれば、主治医や産業医の意見を聴取しておくべきであろう。
・退職願提出が労働者の自由な意思に基づいてされたものと認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するか否かという観点から判断されるべき。
⇒面談時の記録を取ること、退職することのメリット・デメリットを具体的に記載した書面を交付し、そこに署名を得ておく、なども有用かも。










![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/18bfa755.bb912127.18bfa756.dcb862a9/?me_id=1224379&item_id=10035358&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fdarkangel%2Fcabinet%2F11667147%2F12023446%2F3166-main-250428.jpg%3F_ex%3D400x400&s=400x400&t=picttext)