久しぶりに引き込まれた小説であった。新田次郎の「笛師」(講談社文庫)。
新田次郎はベストセラー作家で作品も多く、どの古書店の棚にもある程度並んでいる。この「笛師」は手に入りにくい文庫本である。笛師というと笛の奏者のことと思っていたが、笛の作り手のことだった。日本の伝統的な雅楽の横笛の作り手。材質は竹である。縦笛である尺八の音はよく聴いたことがあるが、横笛はあまり聴いた記憶がない。高音で遠方まで聞こえるそうである。

(『笛師』の笛:材料は150年経た篠竹、内面には朱漆、紐の桜樺巻き)
この著作、どこがいいかといえば、伝統をテーマにして歴史の深みを感じさせてくれるところだろうか。岡本太郎はどういうかな?「伝統とは創造である」といって一蹴するかもしれない。小説の中で、「かたちができている」というフレーズが何度も出てくる。「かたち」とは、伝統を守っていることである。「かたちができていないと本物ではない」というのだ。
この作品、伝統を背負っていくことの重さ、苦しさを感じさせる悲痛なストーリーである。笛師は長男が継ぎ、次男以下は笛師の下職にしかなれないのだ。時代と場所が急に変化する章立てになっているので少し違和感があったが、解説の所をみると、三つの作品を組み合わせたものであることがわかった。第二章は幕末の頃の尾張藩御土居下同心の市之助のことが興味深く描かれている。藩主の秘密の逃げ道のこと、遠入りの隠密のこと。第四章がヨーロッパアルプスという場所が設定され、絵画の中の横笛のことや笛のおかげで命拾いした笛師の末裔のことが描かれ面白い。いろいろ紆余曲折がありながら伝統が引き継がれていくのである。
久しぶりに一気に読んでしまいたくなる小説であった。新田次郎作品は初めてだった。映画化された「八甲田山死の彷徨」も新田次郎の原作だった。
新田次郎は夫人の藤原ていに触発されて小説を書き始めたという。作家としては藤原ていが先輩だった。息子の藤原正彦氏は数学者だが、本もかなり書いている。
追加;
天候の記述がとても詳しい。新田次郎は、気象庁測候所に勤務していたからであろう。
新田次郎はベストセラー作家で作品も多く、どの古書店の棚にもある程度並んでいる。この「笛師」は手に入りにくい文庫本である。笛師というと笛の奏者のことと思っていたが、笛の作り手のことだった。日本の伝統的な雅楽の横笛の作り手。材質は竹である。縦笛である尺八の音はよく聴いたことがあるが、横笛はあまり聴いた記憶がない。高音で遠方まで聞こえるそうである。

(『笛師』の笛:材料は150年経た篠竹、内面には朱漆、紐の桜樺巻き)
この著作、どこがいいかといえば、伝統をテーマにして歴史の深みを感じさせてくれるところだろうか。岡本太郎はどういうかな?「伝統とは創造である」といって一蹴するかもしれない。小説の中で、「かたちができている」というフレーズが何度も出てくる。「かたち」とは、伝統を守っていることである。「かたちができていないと本物ではない」というのだ。
この作品、伝統を背負っていくことの重さ、苦しさを感じさせる悲痛なストーリーである。笛師は長男が継ぎ、次男以下は笛師の下職にしかなれないのだ。時代と場所が急に変化する章立てになっているので少し違和感があったが、解説の所をみると、三つの作品を組み合わせたものであることがわかった。第二章は幕末の頃の尾張藩御土居下同心の市之助のことが興味深く描かれている。藩主の秘密の逃げ道のこと、遠入りの隠密のこと。第四章がヨーロッパアルプスという場所が設定され、絵画の中の横笛のことや笛のおかげで命拾いした笛師の末裔のことが描かれ面白い。いろいろ紆余曲折がありながら伝統が引き継がれていくのである。
久しぶりに一気に読んでしまいたくなる小説であった。新田次郎作品は初めてだった。映画化された「八甲田山死の彷徨」も新田次郎の原作だった。
新田次郎は夫人の藤原ていに触発されて小説を書き始めたという。作家としては藤原ていが先輩だった。息子の藤原正彦氏は数学者だが、本もかなり書いている。
追加;
天候の記述がとても詳しい。新田次郎は、気象庁測候所に勤務していたからであろう。












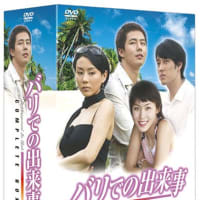
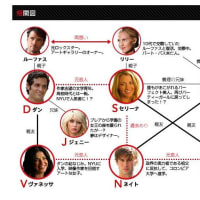
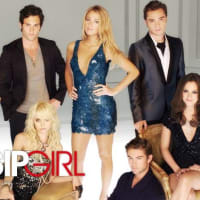

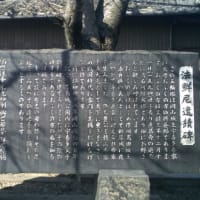



※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます