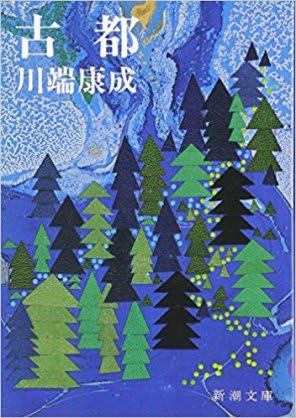
もし、あなたが旅行に行くとしたら、どこに行ってみたいですか?
私は行きたいところはいろいろあるのですが、その中でも歴史と伝統のロマンあふれる京都に行ってみたいです。
そして、それがこの小説を読む動機になりました。
だけど、正直に告白すると、「古都」は以前、三十ページほど読んで、やめてしまったことがありました。
理由は登場人物の会話が京都弁で書かれていて、九州育ちの私には読みづらくて、大変だったからです。
でも、「古都」は川端康成の作品の中でも有名ですし、今なら、何となく読めそうな気がしてきたのです。
そういう訳で、再びチャレンジしてみたのですが、この小説は京都弁が出てくるだけでなく、京都の名所や年中行事が沢山、書いてあり、京都の観光案内というか、京都を知るうえで、とても役に立つ作品だなと思いました。
だから、川端康成はタイトル通り、古き良き京都の面影を、この小説に封じ込めたかったのかも知れません。
そして、それと同時に山里と町なかという境遇のまったく違う双子の姉妹を通して、日本女性ならではのそれぞれの美しさを引き出したかったのではないでしょうか。
そういうふうに、この小説を読むと、実に構成がしっかりしていることに気づかされます。
まず、冒頭にもみじの古木の幹に、すみれの花がひらいたのを、千重子が見つけます。
すみれは上と下の幹に二株あって、一尺ほど離れています。
その二つのすみれを、年ごろになった千重子は「上のすみれと下のすみれとは、会うことがあるのかしら。おたがいに知っているのかしら。」と思うのです。
それに対し、川端は『すみれ花が「会う」とか「知る」とは、どういうことなのか。』と読者に疑問を投げかけるのです。
ここで、すみれを擬人化し、千重子に、自分の知らないところに、苗子という双子の姉妹がいることを暗示させています。
そのあと、今度は桜が出てきます。
千重子の幼なじみの水木真一が電話で、平安神宮の桜見に誘うのです。
そして、父の太吉郎が、千重子がくれたクレーの画集にヒントを得てデザインした帯の図案の一件のあと、親子三人は、町なかのさくらとしては遅咲きの御室の有明ざくらや、八重の桜を見に行きます。
それから車で植物園に向かい、そこのチューリップ畑で、偶然、出会った大友秀男が、千重子は中宮寺や広隆寺の弥勒よりも、どれだけ美しいかしれないと、太吉郎に褒めるのです。
しかし、太吉郎は「秀男さん、娘はすぐにばばあになりまっせ。そら、早いもんどす。」と返します。
ところが、秀男は動ぜず、「そやかいチューリップの花は生きてるて、わたし言うたんどす」と言い、さらに語気を強め、「ほんの短い花どきだけ、いのちいっぱい咲いてるやおへんか。今、その時どっしゃろ。」と言い放つのです。
そして、秀男は自分に言い聞かせるように、太吉郎に自分の胸のうちをこう明かすのです。
「わたしかて、孫子の代までしめやはる帯を織らしてもろてるとは、思わしまへんね。今では・・・。一年でも、しゃんとしめ心地のええように、織らしてもろてるのどす。」
この秀男の言葉は、この小説における川端康成の女性観を見事に言い現しているように思えます。
つまり、花も女性も美しい時は短いかも知れないけれど、与えられた運命を精一杯生きることに価値があるのだと。
このエピソードのあと、千重子は友人の真砂子に、高雄のもみじを見に行かないかと誘われ、北山杉が見たいと言い出します。
「北山杉のまっすぐに、きれいに立ってるのをながめると、うちは心が、すうっとする。」
そこで、真砂子は千重子そっくりの女性を見つけるのです。
それが、千重子の双子の姉妹、苗子との最初の出会いでした。
千重子と苗子
私は、二人の名前に注目しました。
もしかしたら、千重子の名前の由来は年を重ねて、様々な経験を経て、美しくなった姿を現しているのではないのか?
一方、苗子は生まれたばかりの汚れのない純粋な美しさを現しているのではないのか?
そして、苗子が住み、働いているのを、京都の中心部から遠く離れた北山地方にしたのは都を形作るのに必要な木材を重要視したためではなかったのか?
その千重子と苗子のそれぞれの境遇や運命を花に例え、儚いまでの美しさを描きながら、京都の歴史と伝統と年中行事を絡めて書いたのが、「古都」だったように、私は思うのです。
そして、それが「古都」を名作たらしめることになったのでは?
しかし、この小説に問題点がない訳ではないのです。
この小説は、京都にお住まいの方や、京都をよく知る人にはその良さを心行くまで堪能出来るかも知れませんが、京都から遠く離れ、京都をよく知らない人が読むと、ちょっと理解しづらい面も多々あるのです。
この私にしても、冒頭で告白したように京都弁が読みにくくて、一度挫折したのですが、京都のいくつもの名所や年中行事を文章だけで理解するのは難しかったです。
そこで、私は映画化された「古都」も観てみてみることにしました。
一つは、1963年製作の岩下志麻さんが主演したものです。

この頃、川端康成はまだ健在で、京都での撮影も見に行っていて、意見もどしどし発言したらしいです。
それによると、川端康成は本物に非常にこだわる人で、セットで簡単にすませるのを極力嫌っていたとか。
そうしたことから、岩下志麻版は、川端康成の原作にかなり忠実に作ってあり、京都の名所や年中行事も映っているので、「古都」の魅力を知るうえで、とても価値ある映画だなと思いました。
そして、もう一つ観たのが、1980年製作の山口百恵さん主演版です。

この映画は調べてみたら、山口百恵さんの芸能生活の最後を飾る作品として選ばれたそうです。
しかも、山口百恵さんは川端康成とかなり縁があるらしく、映画主演第一作目も、川端康成原作の「伊豆の踊子」だったとか。
こちらは川端康成が亡くなったあとに作られたので、アレンジしているところがいくつも見られました。
例えば、原作では太吉郎が、秀男の頬を叩くところを、映画では秀男の父が叩いていますし、遠く離れた千重子と苗子が同じ日に刃物で手を切ってしまう場面も原作にはありませんでした。
しかし、私がこの山口百恵主演の作品を観て、もっとも気にしたのは、この映画のあと、山口百恵さんと結婚する三浦友和さんがどんな役で出ているのかという点でした。
原作で、千重子に好意を寄せている竜介か、或いは苗子に求婚の意志を示した秀男か?
そして、百恵ちゃんと友和さんのキスシーンはあるのか?
結婚する直前に撮った映画だから、原作にはないキスシーンくらいあって、当然かも?(真っ赤)
ところが、三浦友和さんは秀男でも竜介でも、どっちでもなく、苗子と一緒に働く清作という青年を演じていたのです!

原作には、清作なんて出てこなかったし。(苦笑)
まさか、この清作が苗子と結婚して、ハッピーエンドで終わっちゃうの?
それじゃ、原作への冒涜じゃ?
でも、二人の結婚という第二の人生の門出を祝福するためなら、それもいいかも?
だけど、さすがにそこまでは原作を改竄してなかったです。
しかし、それが名作に対する当然の姿勢かも知れませんね。
原作に忠実な岩下志麻主演版と、アレンジしてある山口百恵主演版、それぞれ好みはあると思いますが、双方とも原作の雰囲気は壊してないので、私はどっちもいいなと思いました。



















