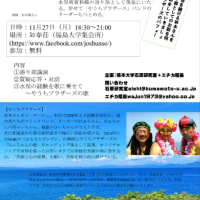10:00
朝から郡山市立美術館『歌川国芳展』を観に来た。
武者絵、面白い。
版画なのだから、基本は線と面によってベタに表現されているはず……なのだが、横に三枚並べて刷られたセットの組み絵は、躍動感に溢れている。
かつまた筋肉の細部までこだわった描写と、時折見せる吹きかけられたようなボカしの「硝煙」の表現、さらにはベタな絵というよりデザイン的な虚構性を孕んだ絵たちの画面は、動き続けている力の表象とでもいうべきものになっている。
不思議な力感の魅力に溢れた作品群。
鯨やら骸骨やらの奇想溢れた前期の展示を見逃したのは残念だが、森アートギャラリーだかで2月までやっている別の展覧会でいくつかは見ることができるだろう。
12:00
昼、山の中のパン屋さんで昼食用のパンを買おうとしたらクルマが縁石に乗り上げ、危うく走行不能状態に。
幸いすんでのところでガリガリ車体とコンクリートの擦れる音を立てながら脱出……。
修理費を考えると凹むなあ。
13:30
そこからアウトレットへ行き、家族は買い物。
私は貴重な読書&ブログタイム。
買い物圏域から離脱することができないため、むしろテキストと向き合うには他に選択の余地が無い分好都合。
かえって仕事が進んだりもする。
というわけで積ん読だった
東浩紀『一般意志2.0』を読み始める。
大震災「前/後」の区切り方についての東のスタンスには疑問があるし、この今読んでいる本の方向性にも同意はしないが、ルソーの「一般意志」に遡って「個人」を超えた政治について論じようとする姿勢には納得。
別に過去の哲学や著作作品群の引用をしなきゃならんわけではないが。
問題はどんな道具を調達し、それによって「今」を分析し、どう使用していくかの姿勢と方向性。
ほのめかされているように多分ネットワーク状の一般意志みたいな落としどころになるのだろう。
『ised-情報社会の思想的視座』
から続くアーキテクチャ優先論でしょう。
ただ、宮台のエリート主義とは違うが、階層的というかネット「地域」代表的匂いがして、今ひとつおじさんはついていけない。
まあ、齋藤純一や大澤真幸、アーレント ハーバーマスを参照してるし、その困難を踏まえてはいて、響き合ってはいないけれど「敢えてする」議論という点では共通しているかも?
私は、たぶんこの方向の議論には相変わらず納得できないかもしれない。
たとえツッコミどころ満載であっても同じ敢えてするなら心情的にはアーレントの議論のほうも拾っておきたい気がしてしまう。
けれど、この東浩紀のお話は、これはこれとしてしっかり聞いて考えねばなるまい……ともかんじるのだ。
というわけで、また本に戻る。
19:30『一般意志2.0』を半分ほど読んだところで佐野出発。
とりあえずルソーについても少し勉強せねば、と思う。
でも、公共性とか一般意志とかについて考えるとなれば、私はやっばり「神」のところから考え直さないとピンとこない。
というわけで、年末、またどうしてもスピノザについて考えねばならなくなっている。
朝から郡山市立美術館『歌川国芳展』を観に来た。
武者絵、面白い。
版画なのだから、基本は線と面によってベタに表現されているはず……なのだが、横に三枚並べて刷られたセットの組み絵は、躍動感に溢れている。
かつまた筋肉の細部までこだわった描写と、時折見せる吹きかけられたようなボカしの「硝煙」の表現、さらにはベタな絵というよりデザイン的な虚構性を孕んだ絵たちの画面は、動き続けている力の表象とでもいうべきものになっている。
不思議な力感の魅力に溢れた作品群。
鯨やら骸骨やらの奇想溢れた前期の展示を見逃したのは残念だが、森アートギャラリーだかで2月までやっている別の展覧会でいくつかは見ることができるだろう。
12:00
昼、山の中のパン屋さんで昼食用のパンを買おうとしたらクルマが縁石に乗り上げ、危うく走行不能状態に。
幸いすんでのところでガリガリ車体とコンクリートの擦れる音を立てながら脱出……。
修理費を考えると凹むなあ。
13:30
そこからアウトレットへ行き、家族は買い物。
私は貴重な読書&ブログタイム。
買い物圏域から離脱することができないため、むしろテキストと向き合うには他に選択の余地が無い分好都合。
かえって仕事が進んだりもする。
というわけで積ん読だった
東浩紀『一般意志2.0』を読み始める。
大震災「前/後」の区切り方についての東のスタンスには疑問があるし、この今読んでいる本の方向性にも同意はしないが、ルソーの「一般意志」に遡って「個人」を超えた政治について論じようとする姿勢には納得。
別に過去の哲学や著作作品群の引用をしなきゃならんわけではないが。
問題はどんな道具を調達し、それによって「今」を分析し、どう使用していくかの姿勢と方向性。
ほのめかされているように多分ネットワーク状の一般意志みたいな落としどころになるのだろう。
『ised-情報社会の思想的視座』
から続くアーキテクチャ優先論でしょう。
ただ、宮台のエリート主義とは違うが、階層的というかネット「地域」代表的匂いがして、今ひとつおじさんはついていけない。
まあ、齋藤純一や大澤真幸、アーレント ハーバーマスを参照してるし、その困難を踏まえてはいて、響き合ってはいないけれど「敢えてする」議論という点では共通しているかも?
私は、たぶんこの方向の議論には相変わらず納得できないかもしれない。
たとえツッコミどころ満載であっても同じ敢えてするなら心情的にはアーレントの議論のほうも拾っておきたい気がしてしまう。
けれど、この東浩紀のお話は、これはこれとしてしっかり聞いて考えねばなるまい……ともかんじるのだ。
というわけで、また本に戻る。
19:30『一般意志2.0』を半分ほど読んだところで佐野出発。
とりあえずルソーについても少し勉強せねば、と思う。
でも、公共性とか一般意志とかについて考えるとなれば、私はやっばり「神」のところから考え直さないとピンとこない。
というわけで、年末、またどうしてもスピノザについて考えねばならなくなっている。