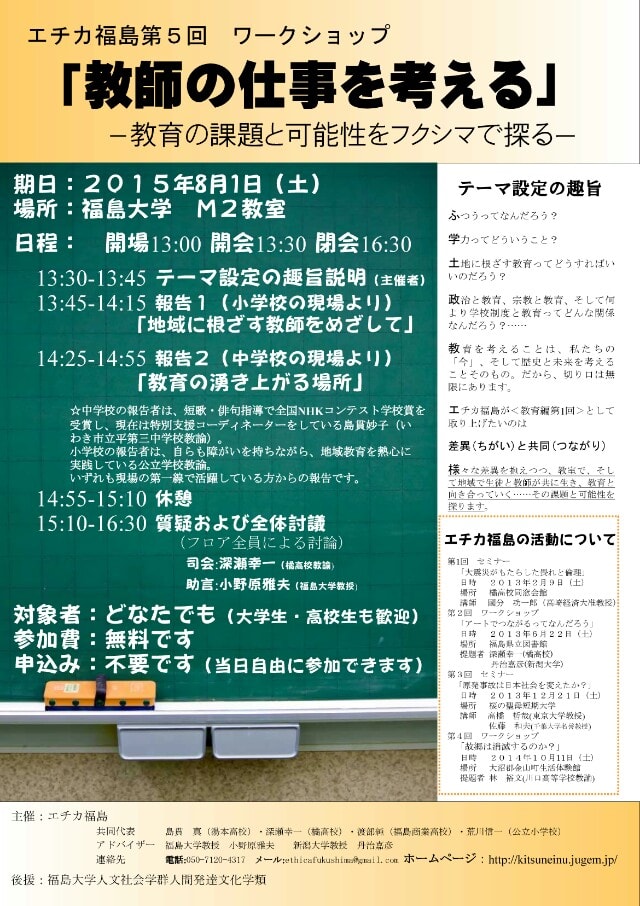福島県いわき市には「日々の新聞」というバイウィークリー(隔週刊)の新聞がある。
2週間に一度の発行で新聞といえるのか?ましてこのネットで瞬時にニュースが世界を駆け巡るご時世なのに……
という声が聞こえてきそうだ。だがもちろん、バイウィークリーの新聞には、それだけの意味がある。なぜなら、ひとつには思考には「遅速度」が必要だからだ。
じっくり粘り強く物事を考え、文字にして世界の片隅に刻んでいくためには、それ相応に時間の「熟成」が必要だろう。
もちろん、毎日紙面を印刷しつづけることも大切だし、世界中のニュースに目をこらして遅滞なく配信することも必要だ。だが同時に、私たちはその「加速度」的に増え続ける情報=記号の海に流されはじめてから、だいぶ長い時間を既に過ごしてきた。
物事を深くかつ広く考えるためには、いったん立ち止まって考えることが大切だ。
そういう意味で「日々の新聞」は私たちにとってとても重要な時間の「溜め」をもたらしてくれる貴重なメディアなのだ。
もう一つ、「日々の新聞」には重要な役割がある。それは、福島県いわき市(私が住む町)に根付いた新聞だ、ということだ。
お店の紹介やイベントの告知が主のタウン誌なら、どこにでもある。
地元がかかえる課題や話題を、2週間のスパンで届けてくれる「日々の新聞」は、きわめて貴重だ。
こういう地元に根ざしたウィークリーやバイウィークリーを持っている町が、日本にはどれほどあるだろうか。
メディアは、自分たちが生活の中でその主張と対話しながら自分たち自身の生活を見直し、考えを深め、あるいは改めつつ「よりよき生」を生きるために必要不可欠なツールだ。いくら文句を言ってみても、テレビのニュースや新聞、ネットの配信抜き、私たちは「世界」と向き合い、自分自身の生活を向上させていく術を知らない。
なるほど私たちの生活はホームセンターに行ってDIYの道具や資材を買うことによっても向上するし、おいしいレストランをタウン情報誌で探し出し、ステキなランチをゲットすることによっても向上するだろう。
では、それ以外に広がっている私たちの社会が抱える課題は、どうすれば向上するのだろうか。
おそらく私たちに今必要なのは「中立」の報道ではなく、開かれた議論のできる「対話の相手」だ。
地域の生活や空気を共有し、その中から課題を見つけだしてくる地域の新聞だからこそ、できることがある。それは毎日あるいは毎時間ごとにニュースを配信するタイプのメディアとは種類が異なるけれど、必要不可欠な知性の道具なのではないか。
「日々の新聞」を持たない地域に住んでいた時には、そんなことを考えもしなかった。
だが、今は違う。
この新聞がなければ、確実に何かを考えるきっかけを失うだろう。そういう実感がある。
最近、「谷口楼」といういわき市平にある料亭の女将さんが、お店の歴史を語るコラムが連載されている
「谷口楼よもやまばなし」
町の歴史を抱えてきたお店だからこそ、その切り口から見えてくることがある。そういえば、銀座にもそういうコミュニティ雑誌があった。銀座百点とかいったかな?
この記事はそんな香りもする。
他方、じっくり足を止めて問題を見据え、闘うべききっかけを教えてくる記事もある。
「むのさんからのメッセージ」
という連載がそれだ。戦争について、民主主義について、落ち着いて考える素材を提供してくれる。
町の新聞を誇りに思うことができる都市に住んでいることを、私は密かに誇りに思っている。できればそんな気持ちをいわき市の他の人にも、いわき市以外の人にもお裾分けしたい。
よろしかったらこちらまで。
日々の新聞サイト
http://www.hibinoshinbun.com/
そして、もし気に入ったらぜひ定期購読をしてみてください。
2週間に一度の発行で新聞といえるのか?ましてこのネットで瞬時にニュースが世界を駆け巡るご時世なのに……
という声が聞こえてきそうだ。だがもちろん、バイウィークリーの新聞には、それだけの意味がある。なぜなら、ひとつには思考には「遅速度」が必要だからだ。
じっくり粘り強く物事を考え、文字にして世界の片隅に刻んでいくためには、それ相応に時間の「熟成」が必要だろう。
もちろん、毎日紙面を印刷しつづけることも大切だし、世界中のニュースに目をこらして遅滞なく配信することも必要だ。だが同時に、私たちはその「加速度」的に増え続ける情報=記号の海に流されはじめてから、だいぶ長い時間を既に過ごしてきた。
物事を深くかつ広く考えるためには、いったん立ち止まって考えることが大切だ。
そういう意味で「日々の新聞」は私たちにとってとても重要な時間の「溜め」をもたらしてくれる貴重なメディアなのだ。
もう一つ、「日々の新聞」には重要な役割がある。それは、福島県いわき市(私が住む町)に根付いた新聞だ、ということだ。
お店の紹介やイベントの告知が主のタウン誌なら、どこにでもある。
地元がかかえる課題や話題を、2週間のスパンで届けてくれる「日々の新聞」は、きわめて貴重だ。
こういう地元に根ざしたウィークリーやバイウィークリーを持っている町が、日本にはどれほどあるだろうか。
メディアは、自分たちが生活の中でその主張と対話しながら自分たち自身の生活を見直し、考えを深め、あるいは改めつつ「よりよき生」を生きるために必要不可欠なツールだ。いくら文句を言ってみても、テレビのニュースや新聞、ネットの配信抜き、私たちは「世界」と向き合い、自分自身の生活を向上させていく術を知らない。
なるほど私たちの生活はホームセンターに行ってDIYの道具や資材を買うことによっても向上するし、おいしいレストランをタウン情報誌で探し出し、ステキなランチをゲットすることによっても向上するだろう。
では、それ以外に広がっている私たちの社会が抱える課題は、どうすれば向上するのだろうか。
おそらく私たちに今必要なのは「中立」の報道ではなく、開かれた議論のできる「対話の相手」だ。
地域の生活や空気を共有し、その中から課題を見つけだしてくる地域の新聞だからこそ、できることがある。それは毎日あるいは毎時間ごとにニュースを配信するタイプのメディアとは種類が異なるけれど、必要不可欠な知性の道具なのではないか。
「日々の新聞」を持たない地域に住んでいた時には、そんなことを考えもしなかった。
だが、今は違う。
この新聞がなければ、確実に何かを考えるきっかけを失うだろう。そういう実感がある。
最近、「谷口楼」といういわき市平にある料亭の女将さんが、お店の歴史を語るコラムが連載されている
「谷口楼よもやまばなし」
町の歴史を抱えてきたお店だからこそ、その切り口から見えてくることがある。そういえば、銀座にもそういうコミュニティ雑誌があった。銀座百点とかいったかな?
この記事はそんな香りもする。
他方、じっくり足を止めて問題を見据え、闘うべききっかけを教えてくる記事もある。
「むのさんからのメッセージ」
という連載がそれだ。戦争について、民主主義について、落ち着いて考える素材を提供してくれる。
町の新聞を誇りに思うことができる都市に住んでいることを、私は密かに誇りに思っている。できればそんな気持ちをいわき市の他の人にも、いわき市以外の人にもお裾分けしたい。
よろしかったらこちらまで。
日々の新聞サイト
http://www.hibinoshinbun.com/
そして、もし気に入ったらぜひ定期購読をしてみてください。