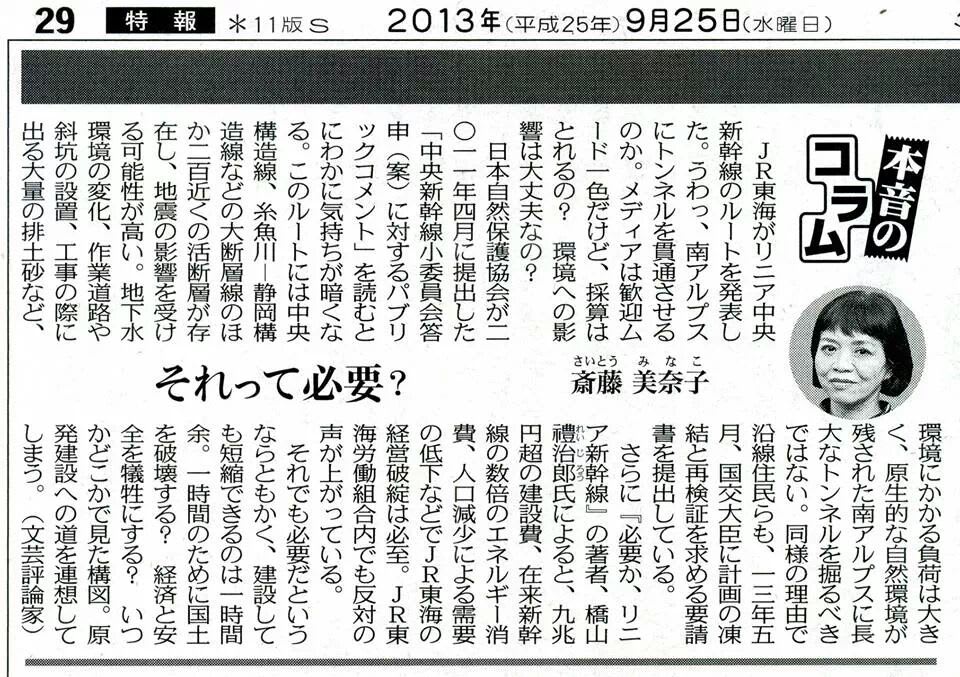出席者の一人桜の聖母短大の二瓶先生に伺ったところ、出席した人全員が特定秘密保護法案に反対だったという。
原発事故だけでは足りず、「守る」ためにはどんなものを失ってもいい、という「縮減」の道を政府はたどり始めたように感じるのは私だけだろうか。
チカラを得て強権を発動しているように見えるけれど(もしかすると主観的にはそうなのかもしれないけれど)、実際は何かを守ろうとしてたちすくみ、縮こまっていく「端緒」に立ち合っているように見えてしまう。
さて、他方、在日中国大使館は、在日中の中国人に対して、緊急事態に備えて連絡先を登録するよう呼びかけたという。
それも含めてブラフかもしれないし、しかし一つ一つの積み重ねで緊張状態は高まりもする。
人は攻める時よりも、何かを守ろうとしたとき、強迫的行動に出ることが多い。
政党・政府・国家レベルでそういう「縮減」が、度を超えて転がり出さないでほしいものだ。
無論、杞憂ならそれに超したことはないのだが。
福島県で改選された地方自治体の首長が、次々に敗北している。
これもまた、新しいものを求める、といえば聞こえはいいが、「閉塞感」を底流に持った「縮減」の一形態ではないか、と本当に心配になる。
つまり、本質的に動くものは、動きすぎない。
守ろうとうする「縮減」の圏域に捕捉された者こそが過剰に動き出してしまう。
政治家さんたち、お願いだからそんな田吾作の下手を打たないでね。
『生成変化を乱したくなければ、動きすぎてはいけない』(ジル・ドゥルーズ)
を全面展開した千葉さんのドゥルーズ論、彼らに読んでほしいなあ。
ま、無理なんだけどさ。
原発事故だけでは足りず、「守る」ためにはどんなものを失ってもいい、という「縮減」の道を政府はたどり始めたように感じるのは私だけだろうか。
チカラを得て強権を発動しているように見えるけれど(もしかすると主観的にはそうなのかもしれないけれど)、実際は何かを守ろうとしてたちすくみ、縮こまっていく「端緒」に立ち合っているように見えてしまう。
さて、他方、在日中国大使館は、在日中の中国人に対して、緊急事態に備えて連絡先を登録するよう呼びかけたという。
それも含めてブラフかもしれないし、しかし一つ一つの積み重ねで緊張状態は高まりもする。
人は攻める時よりも、何かを守ろうとしたとき、強迫的行動に出ることが多い。
政党・政府・国家レベルでそういう「縮減」が、度を超えて転がり出さないでほしいものだ。
無論、杞憂ならそれに超したことはないのだが。
福島県で改選された地方自治体の首長が、次々に敗北している。
これもまた、新しいものを求める、といえば聞こえはいいが、「閉塞感」を底流に持った「縮減」の一形態ではないか、と本当に心配になる。
つまり、本質的に動くものは、動きすぎない。
守ろうとうする「縮減」の圏域に捕捉された者こそが過剰に動き出してしまう。
政治家さんたち、お願いだからそんな田吾作の下手を打たないでね。
『生成変化を乱したくなければ、動きすぎてはいけない』(ジル・ドゥルーズ)
を全面展開した千葉さんのドゥルーズ論、彼らに読んでほしいなあ。
ま、無理なんだけどさ。